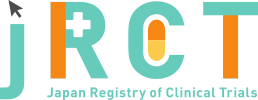臨床研究等提出・公開システム
臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
| 特定臨床研究 | ||
| 令和7年6月27日 | ||
| 令和7年10月29日 | ||
| うつ病に対する機能結合ニューロフィードバック治療法のアクティブコントロール・クロスオーバーデザイン二重盲検ランダム化比較試験 | ||
| うつ病結合ニューロフィードバックのクロスオーバー試験 | ||
| 岡田 剛 | ||
| 広島大学病院 | ||
| うつ病の症状の責任神経回路をターゲットとするニューロフィードバックを行い、症状に対応する機能結合を内発的に変化させることにより、うつ病の多様な症状に対応できる個別的で最適化されたニューロフィードバック治療法を確立することである。そのため二種類の症状にそれぞれ対応する機能結合をターゲットとして、うつ病患者を対象にアクティブコントロール・クロスオーバーデザイン二重盲検ランダム化比較試験を実施する。 | ||
| N/A | ||
| うつ病 | ||
| 募集中 | ||
| 広島大学臨床研究審査委員会 | ||
| CRB6180006 | ||
管理的事項
管理的事項
| 研究の種別 | 特定臨床研究 |
|---|---|
| 届出日 | 令和7年10月28日 |
| 臨床研究実施計画番号 | jRCTs062250026 |
1 特定臨床研究の実施体制に関する事項及び特定臨床研究を行う施設の構造設備に関する事項
1 特定臨床研究の実施体制に関する事項及び特定臨床研究を行う施設の構造設備に関する事項
(1)研究の名称
(1)研究の名称
| うつ病に対する機能結合ニューロフィードバック治療法のアクティブコントロール・クロスオーバーデザイン二重盲検ランダム化比較試験 | A double-blind, randomized, controlled trial of active control crossover design of functional connectivity neurofeedback treatment for depression | ||
| うつ病結合ニューロフィードバックのクロスオーバー試験 | Crossover study of functional connectivity neurofeedback for depression | ||
(2)統括管理者に関する事項等
(2)統括管理者に関する事項等
| 医師又は歯科医師である個人 | |||
|
/
|
|||
| 岡田 剛 | Okada Go | ||
|
|
10457286 | ||
|
/
|
広島大学病院 | Hiroshima University Hospital | |
|
|
精神科 | ||
| 734-8551 | |||
| / | 広島県広島市南区霞1-2-3 | 1-2-3 Kasumi,Minami-ku,Hiroshima City,Hiroshima 734-8551,Japan | |
| 082-257-5814 | |||
| goookada@hiroshima-u.ac.jp | |||
| 岡田 剛 | Okada Go | ||
| 広島大学 | Hiroshima University | ||
| 大学院医系科学研究科精神神経医科学 | |||
| 734-8551 | |||
| 広島県広島市南区霞1-2-3 | 1-2-3 Kasumi,Minami-ku,Hiroshima City,Hiroshima 734-8551,Japan | ||
| 082-257-5814 | |||
| 082-257-5209 | |||
| goookada@hiroshima-u.ac.jp | |||
| 令和7年4月17日 | |||
| 共同で統括管理者の責務を負う者(Secondary Sponsor)該当者の有無 | なし |
|---|
(3)統括管理者及び研究責任医師以外の臨床研究に従事する者に関する事項
(3)統括管理者及び研究責任医師以外の臨床研究に従事する者に関する事項
| 広島大学 | ||
| 森 万有美 | ||
| 大学院医系科学研究科精神神経医科学 | ||
| 広島大学 | ||
| 三宅 典恵 | ||
| 70548990 | ||
| 広島大学保健管理センター | ||
| 広島大学 | ||
| DE SOUZA RODRIGUES ALAN | ||
| 90865031 | ||
| 大学院医系科学研究科精神神経医科学 | ||
(4)多施設共同研究に関する事項
(4)多施設共同研究に関する事項
| 多施設共同研究の該当の有無 | あり |
|---|
(5)研究における研究責任医師に関する事項等
(5)研究における研究責任医師に関する事項等
| / | 岡田 剛 |
Okada Go |
|
|---|---|---|---|
10457286 |
|||
| / | 広島大学病院 |
Hiroshima University Hospital |
|
精神科 |
|||
734-8551 |
|||
広島県 広島市南区霞一丁目2番3号 |
|||
082-257-5814 |
|||
goookada@hiroshima-u.ac.jp |
|||
岡田 剛 |
|||
広島大学 |
|||
大学院医系科学研究科精神神経医科学 |
|||
734-8551 |
|||
| 広島県 広島市南区霞一丁目2番3号 | |||
082-257-5814 |
|||
082-257-5209 |
|||
goookada@hiroshima-u.ac.jp |
|||
| 安達 伸生 | |||
| あり | |||
| 令和7年4月17日 | |||
| 自施設に当該研究で必要な救急医療が整備されている | |||
| / | 吉原 雄二郎 |
Yoshihara Yujiro |
|
|---|---|---|---|
| / | 京都大学 |
Kyoto University |
|
大学院医学研究科脳病態生理学講座(精神医学) |
|||
606-8507 |
|||
京都府 京都市左京区聖護院川原町54 |
|||
075-751-4947 |
|||
yujiroyo@kuhp.kyoto-u.ac.jp |
|||
吉原 雄二郎 |
|||
京都大学 |
|||
大学院医学研究科脳病態生理学講座(精神医学) |
|||
606-8507 |
|||
| 京都府 京都市左京区聖護院川原町54 | |||
075-751-4947 |
|||
yujiroyo@kuhp.kyoto-u.ac.jp |
|||
| 髙折 晃史 | |||
| あり | |||
| 令和7年4月17日 | |||
| 自施設に当該研究で必要な救急医療が整備されている | |||
(6)研究の実施体制に関する事項
(6)研究の実施体制に関する事項
| 効果安全性評価委員会の設置の有無 | なし |
|---|
2 特定臨床研究の目的及び内容並びにこれに用いる医薬品等の概要
2 特定臨床研究の目的及び内容並びにこれに用いる医薬品等の概要
(1)特定臨床研究の目的及び内容
(1)特定臨床研究の目的及び内容
| うつ病の症状の責任神経回路をターゲットとするニューロフィードバックを行い、症状に対応する機能結合を内発的に変化させることにより、うつ病の多様な症状に対応できる個別的で最適化されたニューロフィードバック治療法を確立することである。そのため二種類の症状にそれぞれ対応する機能結合をターゲットとして、うつ病患者を対象にアクティブコントロール・クロスオーバーデザイン二重盲検ランダム化比較試験を実施する。 | |||
| N/A | |||
| 実施計画の公表日 | |||
|
|
2031年03月31日 | ||
|
|
28 | ||
|
|
介入研究 | Interventional | |
|
Study Design |
|
無作為化比較 | randomized controlled trial |
|
|
二重盲検 | double blind | |
|
|
実薬(治療)対照 | active control | |
|
|
交差比較 | crossover assignment | |
|
|
治療 | treatment purpose | |
|
|
なし | ||
|
|
あり | ||
|
|
あり | ||
|
|
|
うつ病患者 (1)18歳以上、60歳以下の患者(外来入院不問) (2)DSM-5の分類でうつ病(現在、抑うつエピソードの診断を満たす)と診断されている。 (3)研究参加について、研究対象者本人から文書による同意が得られていること |
Patients with major depressive (1) Aged 18-60 years old (2)Being diagnosed as depression (currently meeting the criteria for a depressive episode) according to DSM-5 criteria (3)Written consent for participation has been obtained from the participant him/herself |
|
|
(1)研究の趣旨を理解することが困難な精神状態にある者 (2)身体疾患が重篤で、検査及び調査に耐えられない者 (3)MRIの実施が困難な者 ・心臓ペースメーカーを使用している者 ・脳血管のクリップを使用している者 ・神経の電気刺激装置を使用している者 ・埋め込み式ポンプを使用している者 ・金属片が体内に残存している者 ・入れ墨(入れ墨式のアイライン等を含む)がある者 ・妊娠中の者または妊娠している可能性がある者 ・MRI閉所恐怖がある者 (4)過去1年以内にNF, mECT, rTMSを受けたことがある者 (5)その他、研究責任医師又は研究分担医師等が本研究を安全に実施するのに不適当と判断した者 |
(1) Decisionally impaired individuals who has diminished capacity to understand the aim of the research (2) Physically impaired individuals who are not able to complete the experiment (3) Subjects who are contraindicated for the use of MRI Having an implanted heart pace-maker Having implanted cerebral (arteries) clips Having implanted neural/nerve stimulators Having implanted pumps Having work experience in a metal industry or possibility of metal residues remaining in the body Having metal-tattoos (including tattooed eye-lining) Being pregnant, or having possibility of being pregnant MRI claustrophobia (4)Those who have received NF, mECT, or rTMS within the past 1 year (5)Any individuals judged as inappropriate for the experiment by the principal investigator or a collaborating researcher |
|
|
|
18歳 以上 | 18age old over | |
|
|
60歳 以下 | 60age old under | |
|
|
男性・女性 | Both | |
|
|
個々の研究対象者における中止基準 ・ 研究対象者から研究参加の同意の撤回があった場合 ・ 登録後に適格性(選択基準/除外基準)を満たさないことが判明した場合 ・ 修正型電気痙攣療法や反復経頭蓋磁気刺激法が必要となった場合 ・ 原疾患の悪化または合併症の増悪により試験の継続が困難な場合 ・ 有害事象により研究の継続が困難な場合 ・ 妊娠が判明した場合 ・ 著しくコンプライアンス不良の場合(NF中の睡眠、治療意欲の著しい低下等) ・ 原疾患が完治し、継続の必要がなくなった場合 ・ 研究全体が中止された場合 ・ その他の理由により医師が研究を中止することが適当と判断した場合 研究全体の中止 ・ 研究対象者のリクルートが困難で、予定症例を達成することが困難であると判断された時。 ・ 研究機器の品質、安全性、有効性に関する重大な情報が得られた時。 ・ 予定症例数を研究期間内で達成することが困難であると判断された時。 ・ 審査委員会により、実施計画等の変更指示があり、これを受け入れることが困難と判断された時。 ・ 研究の倫理的妥当性もしくは科学的合理性を損なう事実もしくは情報が得られた時。 ・ 研究の実施適正性もしくは研究結果の信頼を損なう事実または情報を得られた時。 ・ 審査委員会により中止の勧告あるいは指示があった場合は、研究を中止する。 |
||
|
|
うつ病 | depression | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
あり | ||
|
|
機能結合ニューロフィードバックは、外部からの刺激を全く使わず、自分の思考や注意を内的にコントロールすることにより、自分の脳活動をリアルタイムにMRIでモニターしながら自己調節し、脳活動パターンを選択的に操作する方法である。本研究では、1日1セッション(約45分)を開始後2週間までの間に計3回行う。 | Functionally connectivity neurofeedback is a method of selectively manipulating brain activity patterns by controlling one's thoughts and attention internally without using any external stimuli, while monitoring one's brain functional connectivity in real time with MRI. In this study, one session per day (about 45 minutes) will be performed a total of three times during the first two weeks. | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
なし | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
① 機能結合Aをターゲットとした機能結合ニューロフィードバックを行った際の症状A(HRSDおよびBDI-IIで評価)のベースラインからの変化 ② 機能結合Bをターゲットとした機能結合ニューロフィードバックを行った際の症状B(HRSDおよびBDI-IIで評価)のベースラインからの変化 |
(1) Change from baseline in symptom A (assessed by HRSD and BDI-II) when neurofeedback targeting functional coupling A (2) Change from baseline in symptom B (assessed by HRSD and BDI-II) when neurofeedback targeting functional coupling B |
|
|
|
① 不安症状:不安症状(STAIで評価)のベースラインからの変化。STAIは不安を状態不安と特性不安の2つの因子に分けて測定する自記式質問紙検査である。 ② 反すう症状:反すう症状(RRSで評価)のベースラインからの変化。RRSは自記式質問紙検査である。 ③ 認知機能:認知機能(Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery : CANTABで評価)のベースラインからの変化。CANTABは認知機能を評価するために開発されたコンピュータベースのテストバッテリーでありタッチパネル式のiPadで施行。 ④社会認知機能:EBT(情動バイアス課題)のベースラインからの変化。EBTはコンピュータベースのテストバッテリーでありタッチパネル式のモバイル端末で施行。 |
(1) Anxiety symptoms: Change from baseline in anxiety symptoms (assessed by STAI). STAI is a self-administered questionnaire test that measures anxiety by dividing it into two factors: state anxiety and trait anxiety. (2) Rumination symptoms: Change from baseline in rumination symptoms (assessed by RRS). RRS is a self-administered questionnaire test. (3) Cognitive function: Change from baseline in cognitive function (as assessed by the Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB). CANTAB is a computer-based test battery developed to evaluate cognitive function, and is performed on a touch-panel iPad. (4) Social cognitive function: Changes from the baseline of EBT (Emotion Bias Task). EBT is a computer-based test battery administered using a touch panel mobile device. |
|
(2)特定臨床研究において有効性又は安全性を明らかにしようとする医薬品等の概要
(2)特定臨床研究において有効性又は安全性を明らかにしようとする医薬品等の概要
|
|
医療機器 | ||
|---|---|---|---|
|
|
未承認 | ||
|
|
|
|
なし |
|
|
未定(機能結合ニューロフィードバックプログラム) | ||
|
|
なし | ||
|
|
|
株式会社XNef | |
|
|
京都府 相楽郡精華町光台2-2-2 | ||
(3)特定臨床研究において著しい負担を与える検査その他の行為に用いる医薬品等の概要
(3)特定臨床研究において著しい負担を与える検査その他の行為に用いる医薬品等の概要
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
3 特定臨床研究の実施状況の確認に関する事項
3 特定臨床研究の実施状況の確認に関する事項
(1)監査の実施予定
(1)監査の実施予定
|
|
なし |
|---|
(2)特定臨床研究の進捗状況
(2)特定臨床研究の進捗状況
|
|
||
|---|---|---|
|
|
実施計画の公表日 |
|
|
|
||
|
|
募集中 |
Recruiting |
|
|
||
4 特定臨床研究の対象者に健康被害が生じた場合の補償及び医療の提供に関する事項
4 特定臨床研究の対象者に健康被害が生じた場合の補償及び医療の提供に関する事項
|
|
あり | |
|---|---|---|
|
|
|
あり |
|
|
死亡、後遺障害1級または2級 | |
|
|
なし | |
5 特定臨床研究に用いる医薬品等の製造販売をし、又はしようとする医薬品等製造販売業者及びその特殊関係者の当該特定臨床研究に対する関与に関する事項等
5 特定臨床研究に用いる医薬品等の製造販売をし、又はしようとする医薬品等製造販売業者及びその特殊関係者の当該特定臨床研究に対する関与に関する事項等
(1)特定臨床研究に用いる医薬品等の医薬品等製造販売業者等からの研究資金等の提供等
(1)特定臨床研究に用いる医薬品等の医薬品等製造販売業者等からの研究資金等の提供等
|
|
株式会社XNef | |
|---|---|---|
|
|
なし | |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
あり | |
|
|
機能結合ニューロフィードバックプログラム | |
|
|
あり | |
|
|
MRIの撮像 | |
(2)特定臨床研究に用いる医薬品等の医薬品等製造販売業者等以外からの研究資金等の提供
(2)特定臨床研究に用いる医薬品等の医薬品等製造販売業者等以外からの研究資金等の提供
|
|
あり | |
|---|---|---|
|
|
国立研究開発法人日本医療研究開発機構 医療研究開発革新基 盤創成事業(AMED) | Japan Agency for Medical Research and Development |
6 審査意見業務を行う認定臨床研究審査委員会の名称等
6 審査意見業務を行う認定臨床研究審査委員会の名称等
|
|
広島大学臨床研究審査委員会 | Hiroshima University Certified Review Board |
|---|---|---|
|
|
CRB6180006 | |
|
|
広島県 広島市南区霞一丁目2番3号 | 1-2-3 Kasumi,Minami-ku,Hiroshima City, 734-8551,Japan, Hiroshima |
|
|
082-257-1551 | |
|
|
iryo-sinsa@office.hiroshima-u.ac.jp | |
|
|
承認 | |
7 その他の事項
7 その他の事項
(1)特定臨床研究の対象者等への説明及び同意に関する事項
(1)特定臨床研究の対象者等への説明及び同意に関する事項
|
|
有 | Yes |
|---|---|---|
|
|
本研究を通して取得されたデータリソースは、将来、新たに計画・実施される研究・医療機器開発などのために長期間保存のうえ、個人情報保護法とその関連法規を遵守して利用する。データベースへの登録の同意が得られた場合、匿名化の作業が行われた後、国際電気通信基礎技術研究所(ATR)脳情報通信総合研究所ないしこれが指定する機関によって管理・運営されるデータベース、脳神経科学統合プログラムの中核拠点のデータベースセンターないしこれが指定する機関によって管理・運営されるデータベース、ならびに東京大学医学部附属病院精神神経科によって管理と運営が実施されるデータベースに登録する。これらのデータベースは、審査によって使用が承認された研究機関研究者の間で共有され、研究の目的で使用される。さらに、研究対象者から非制限公開データとすることについての同意が得られた場合は、新たに付された符号との対応表を残さない匿名化により、完全に個人を識別できないようにした上で、自由に閲覧可能なデータベースに対して提供される。 | The data resources obtained through this research will be stored for a long period for future studies and medical device developments, in compliance with the Personal Information Protection Law and related regulations. If consent for registration in the database is obtained, after anonymization, the data will be managed and operated by the Advanced Telecommunications Research Institute International (ATR) Brain Information Communication Research Laboratory or an institution designated by them, as well as by the database center of the Neuroscience Integration Program or an institution designated by them, and by the Department of Neuropsychiatry at the University of Tokyo Hospital. These databases will be shared among researchers from approved research institutions for research purposes. Furthermore, if consent is obtained from the research subjects for unrestricted public data, the data will be provided to a freely accessible database with complete anonymization, ensuring that individuals cannot be identified without leaving a correspondence table with the newly assigned codes. |
(2)他の臨床研究登録機関への登録
(2)他の臨床研究登録機関への登録
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
(3)特定臨床研究を実施するに当たって留意すべき事項
(3)特定臨床研究を実施するに当たって留意すべき事項
|
|
|
該当しない | |
|---|---|---|---|
|
|
なし | none | |
|
|
なし | ||
|
|
該当しない | ||
|
|
該当しない | ||
|
|
該当しない | ||
(4)全体を通しての補足事項等
(4)全体を通しての補足事項等
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
添付書類(実施計画届出時の添付書類)
添付書類(実施計画届出時の添付書類)
|
|
設定されていません |
|---|---|
|
|
設定されていません |
|
設定されていません |