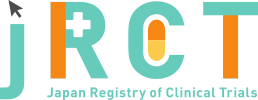臨床研究等提出・公開システム
再生医療等提供計画情報の詳細情報です。
| 第三種 | ||
| 令和2年3月30日 | ||
| 令和4年5月31日 | ||
| 令和3年9月29日 | ||
| 令和4年3月25日 | ||
| 自家非培養表皮細胞移植による白斑治療を目指した臨床研究 | ||
| 自家非培養表皮細胞移植による白斑治療を目指した臨床研究 | ||
| 大阪大学医学部附属病院 | ||
| 竹原 徹郎 | ||
| 白斑を対象とした自己非培養表皮細胞移植の有効性と安全性検証 | ||
| 1-2 | ||
| 非進行性白斑 | ||
| 研究終了 | ||
| 大阪大学第一特定認定再生医療等委員会 | ||
| NA8140001 | ||
総括報告書の概要
総括報告書の概要
臨床研究の名称等
臨床研究の名称等
| 第三種 | |||
| 令和4年5月24日 | |||
| jRCTc050190126 | |||
| 提供しようとする再生医療等の名称 | 自家非培養表皮細胞移植による白斑治療を目指した臨床研究 | ||
| 認定再生医療等委員会の名称(認定番号) | 大阪大学第一特定認定再生医療等委員会 (NA8140001) | ||
| 2022年03月25日 | |||
| 5 | |||
| / | 細胞移植を行った5症例は分節型白斑が1例、汎発型白斑が4例であった。 1) 27才男性 尋常性白斑(分節型白斑) 2) 25才女性 尋常性白斑(汎発型白斑) 3) 76才男性 尋常性白斑(汎発型白斑) 4) 74才男性 尋常性白斑(汎発型白斑) 5) 75才女性 尋常性白斑(汎発型白斑) |
5 cases conducted cell transplantation consisted of one segmental vitiligo and four generalized vitiligo. 1) 27-year-old male segmental 2) 25-year-old female generalized 3) 76-year-old male generalized 4) 74-year-old male generalized 5) 75-year-old female generalized |
|
| / | 目標症例数5例を症例登録し、全例に自家非培養細胞分散液を移植した。術後3ヶ月、6ヶ月で定期観察し安全性、有効性評価を行った。 | The target 5 cases were resistered, and autologous noncultured epidermal cell transplantation was conducted to all cases. The safety and efficacy were evaluated by regular observation 3 months and 6 months after the operation. | |
| / | 本細胞移植を原因とする疾病等の発生は無かった。 | No adverse events caused by this cell transplantation. | |
| / | 主要評価項目 細胞移植病変の白斑改善率(縮小率)に関して下記であった。 H-01:術後3か月2.49%、術後6か月2.88% H-02:術後3か月31.99%、術後6か月32.12% H-03:術後3か月34.19%、術後6か月30.89% H-04:術後3か月/6か月ともに赤味との区別がつかず判定不能 H-05:術後3か月/6か月ともに赤味との区別がつかず判定不能 一方、表皮移植病変の白斑改善率(縮小率)に関して下記であった。 H-01:術後3か月3.28%、術後6か月10.52% H-02:術後3か月20.27%、術後6か月20.96% H-03:術後3か月88.03%、術後6か月81.82% H-04:術後3か月41.21%、術後6か月50.21% H-05:術後3か月/6か月ともに赤味との区別がつかず判定不能 副次評価項目 各症例の色味測定の結果は下記であった(手術前、術後3ヶ月、術後6ヶ月の順に記載)。 <メラニン指標値> 被験者識別コード:H-01 細胞移植部(平均)101.5、86.8、134.3 吸引水疱蓋移植部(平均)102.0、78.0、112.7 対照部位(平均)95.8、65.3、103.3 被験者識別コード:H-02 細胞移植部(平均)61.5、82.3、93.7 吸引水疱蓋移植部(平均)62.7、74.3、91.0 対照部位(平均)100.7、78.5、121.5 被験者識別コード:H-03 細胞移植部(平均)96.3、178.3、172.5 吸引水疱蓋移植部(平均)102.5、194.5、216.5 対照部位(平均)81.5、89.5、83.2 被験者識別コード:H-04 細胞移植部(平均)24.7、35.0、29.5 吸引水疱蓋移植部(平均)10.5、65.3、100.8 対照部位(平均)6.0、23.2、24.3 被験者識別コード:H-05 細胞移植部(平均)64.3、32.3、46.3 吸引水疱蓋移植部(平均)68.7、29.8、46.2 対照部位(平均)64.3、49.0、50.2 <ヘモグロビン指標値> 被験者識別コード:H-01 細胞移植部(平均)354.7、496.5、370.0 吸引水疱蓋移植部(平均)393.2、464.8、384.3 対照部位(平均)525.3、505.3、507.8 被験者識別コード:H-02 細胞移植部(平均)87.0、208.0、168.5 吸引水疱蓋移植部(平均)94.3、134.5、170.7 対照部位(平均)225.0、108.5、219.2 被験者識別コード:H-03 細胞移植部(平均)179.2、286.2、345.2 吸引水疱蓋移植部(平均)228.8、279.7、407.2 対照部位(平均)179.0、133.8、198.5 被験者識別コード:H-04 細胞移植部(平均)153.3、455.7、299.7 吸引水疱蓋移植部(平均)167.7、261.5、211.8 対照部位(平均)176.5、107.7、135.7 被験者識別コード:H-05 細胞移植部(平均)233.3、469.8、367.2 吸引水疱蓋移植部(平均)264.8、485.5、411.5 対照部位(平均)245.5、271.0、180.2 開始前、術後3ヶ月、6ヶ月における感染症、瘢痕、稗粒腫の発生を観察したが、いずれの症例も感染症、瘢痕、稗粒腫の発生は認められなかった。 |
Primary endpoints: repigmentation rate Repigmentation rate on the epidermal cell transplantation sites H-01: 2.49% and 2.88% of repigmentation rate 3 and 6 months after treatment, respectively H-02: 31.99% and 32.12% of repigmentation rate 3 and 6 months after treatment, respectively H-03: 34.19% and 30.89% of repigmentation rate 3 and 6 months after treatment, respectively H-04: Undeterminable because of not differentiating from repigmentation to skin redness 3 and 6 months after treatment H-05: Undeterminable because of not differentiating from repigmentation to skin redness 3 and 6 months after treatment Repigmentation rate on the suction blister epidermal transplantation sites H-01: 3.28% and 10.52% of repigmentation rate 3 and 6 months after treatment, respectively H-02: 20.27% and 20.96% of repigmentation rate 3 and 6 months after treatment, respectively H-03: 88.03% and 81.82% of repigmentation rate 3 and 6 months after treatment, respectively H-04: 41.21% and 50.21% of repigmentation rate 3 and 6 months after treatment, respectively H-05: Undeterminable because of not differentiating from repigmentation to skin redness 3 and 6 months after treatment Secondary endpoints Melanin index (pretreatment/3 months after treatment/6 months after treatment) Case: H-01 Epidermal cell transplantation (mean): 101.5/86.8/134.3 Suction blister epidermal transplantation (mean): 102.0/78.0/112.7 Control(mean): 95.8, 65.3, 103.3 Case: H-02 Epidermal cell transplantation (mean): 61.5/82.3/93.7 Suction blister epidermal transplantation (mean): 62.7/74.3/91.0 Control(mean): 100.7, 78.5, 121.5 Case: H-03 Epidermal cell transplantation (mean): 96.3/178.3/172.5 Suction blister epidermal transplantation (mean): 102.5/194.5/216.5 Control(mean): 81.5, 89.5, 83.2 Case: H-04 Epidermal cell transplantation (mean): 24.7/35.0/29.5 Suction blister epidermal transplantation (mean): 10.5/65.3/100.8 Control(mean): 6.0, 23.2, 24.3 Case: H-05 Epidermal cell transplantation (mean): 64.3/32.3/46.3 Suction blister epidermal transplantation (mean): 68.7/29.8/46.2 Control(mean): 64.3, 49.0, 50.2 Hemoglobin index (pretreatment/3 months after treatment/6 months after treatment) Case: H-01 Epidermal cell transplantation (mean): 354.7/496.5/370.0 Suction blister epidermal transplantation (mean): 393.2/464.8/384.3 Control(mean): 525.3, 505.3, 507.8 Case: H-02 Epidermal cell transplantation (mean): 87.0/208.0/168.5 Suction blister epidermal transplantation (mean): 94.3/134.5/170.7 Control(mean): 225.0, 108.5, 219.2 Case: H-03 Epidermal cell transplantation (mean): 179.2/286.2/345.2 Suction blister epidermal transplantation (mean): 228.8/279.7/407.2 Control(mean): 179.0, 133.8, 198.5 Case: H-04 Epidermal cell transplantation (mean): 153.3/455.7/299.7 Suction blister epidermal transplantation (mean): 167.7/261.5/211.8 Control(mean): 176.5, 107.7, 135.7 Case: H-05 Epidermal cell transplantation (mean): 233.3/469.8/367.2 Suction blister epidermal transplantation (mean): 264.8/485.5/411.5 Control(mean): 245.5, 271.0, 180.2 Brief summary Since the number of 5 cases analyzed here was quite small, it is required to increase the sample size to evaluate the usefulness of epidermal cell transplantation properly. We did not encounter severe adverse event which indicated a safety of epidermal cell transplantation. While in case H-02 and -3, 25% or more of vitiliginous area reduction was found, other 3 cases might not have sufficient improvement of the treated lesions due to the remaining disease activity and loss of transplanted epidermal cells from the recipient sites. In order to provide the more efficient treatment, we suppose the importance to enroll the stable state patients and fix the translanted epidermal cells properly. |
|
| / | 今回は症例数5例で検討したため、再生医療の提供が有効であったかどうかは判断できず、もう少し症例を増やして検討する必要がある。ただし、全症例で重篤な有害事象はみられず安全に施行できることが示唆された。 H-02、H-03では25%以上の面積縮小がみられたが、残り3例では改善がみられなかった。3例においては白斑の活動性が残存していた可能性、細胞分散に用いた血清の粘度が低く細胞溶出によるロスが生じたため、改善が認められなかったと考えられる。本再生医療の提供が有効なのは、病勢がないもしくは低く十分細胞の固定が得られた症例であると考えられる。 |
(See the Outcome measures.) | |
| 2022年05月31日 | |||
IPDシェアリング
IPDシェアリング
| / | 無 | No | |
|---|---|---|---|
| / | |||
1 提供しようとする再生医療等及びその内容
1 提供しようとする再生医療等及びその内容
申請者情報
申請者情報
| 令和4年5月24日 | |||
| jRCTc050190126 | |||
| 大阪大学医学部附属病院 | |||
| 大阪府吹田市山田丘2ー15 | |||
| 竹原 徹郎 | Takehara Tetsuo | ||
(1)再生医療等の名称及び分類
(1)再生医療等の名称及び分類
| 自家非培養表皮細胞移植による白斑治療を目指した臨床研究 | Clinical study of autologous noncultured epidermal cell transplantation for leucodelma treatment | ||
| 自家非培養表皮細胞移植による白斑治療を目指した臨床研究 | Clinical study of autologous noncultured epidermal cell transplantation for leucodelma treatment | ||
| 第三種 | |||
| 提供する再生医療に用いる特定細胞加工物は、再生医療を受ける者の健常部皮膚に形成した吸引水疱蓋を切除し、酵素処理して得られるケラチノサイト、メラノサイトを含む細胞分散液である。本特定細胞加工物は、人の胚性幹細胞/人工多能性幹細胞/人工多能性幹細胞様細胞を用いず、遺伝子導入操作を行わず、特定細胞加工物の製造時に異種動物細胞は用いない患者自身の表皮由来細胞であり、幹細胞の分離や濃縮などの工程は含まない。本特定細胞加工物は非培養で製造し、表皮を剥削した白斑患部に移植して色素形成の回復を目的とする相同利用である。以上より、本再生医療は第三種再生医療と判断した。 | |||
(2)再生医療等の内容
(2)再生医療等の内容
| 白斑を対象とした自己非培養表皮細胞移植の有効性と安全性検証 | |||
| 1-2 | |||
| 2019年10月02日 | |||
| 2022年05月31日 | |||
| 5 | |||
| 介入研究 | Interventional | ||
| 単一群 | single arm study | ||
| 非盲検 | open(masking not used) | ||
| 非対照 | uncontrolled control | ||
| 単群比較 | single assignment | ||
| 治療 | treatment purpose | ||
| 大阪大学医学部附属病院を受診した非進行性白斑と診断された患者 | Men and women aged over 20 years old with a diagonosis of stable vitiligo who visited the department of dermatology Osaka University Hospital and who signed a written informed consent by themselves after receiving the explanation of clinical study. | ||
| 過去12か月以内に白斑の進行がみられる者 被験者登録の4週間以内にステロイド剤、活性型ビタミD3外用剤、カルシニューリン阻害外用剤、光線照射療法を行った者 肥厚性瘢痕やケロイド形成歴のある者やケブネル現象を呈する者 抗生物質や局所麻酔薬アレルギーのある者 テープかぶれする者 妊娠、授乳婦、研究期間中に妊娠を希望する者 感染症(HBV、HCV、HIV、HTLV-1)を有する者 他の臨床研究に参加している者 研究分担医師、研究責任医師が不適格と判断した者 |
Apparently unstable patients defined as new areas of depigmentation or enlarging areas of depigmentation within the last 12 months. Patients with treatment of steroid, active vitamin D3, calcineurin inhibitor and light radiation therapy within the 4 weeks befor registration. History of hypertrophic scar, keloid scars or presence of Koebner's phenomenon Patients with allergies to antibiotics and local anaesthetics Patients with tape rash Pregnant women, lactating women and patients who deaire pregnancy during clinical studies. Positive serology of Hepatitis B and C, HIV, HTLV-1 Patients who are participating in other clinical studies including interventions or non-interventions such as observation studies. Investigators judge the patiens should not paticipate in the study for any reason |
||
| 20歳 以上 | 20age old over | ||
| 上限なし | No limit | ||
| 男性・女性 | Both | ||
| 個々の症例の中止基準 研究責任医師は以下に示す理由で研究継続が不可能と判断した場合には、研究を中止し、中止・脱落の日付・時期、中止・脱落の理由、経過をカルテに明記するとともに、中止・脱落時点で必要な検査を行い有効性・安全性の評価を行う。 (1) 対象者から研究参加の辞退の申し出や同意の撤回があった場合 (2) 水疱蓋が形成されないまたは形成が極めて困難と医師が判断した場合 (3) 登録後に適格性を満足しないことが判明した場合 (4) 白斑症状の悪化のため、継続が好ましくないと判断された場合 (5) 合併症などの増悪により研究の継続が困難な場合 (6) 有害事象により研究の継続が困難な場合 (7) 著しくコンプライアンス不良の場合(処方された抗生物質の使用が守られない等) (8) 研究全体が中止された場合 (9) その他の理由により医師が研究を中止することが適当と判断した場合 研究全体としての中止基準 本臨床研究において、患者登録ペースが計画時より著しく不良で登録不良による研究の早期中止勧告やその他の理由により研究の継続が困難と判断 される場合は、研究責任医師は研究の早期中止を行うか決定する。研究を中止する場合は、病院長が中止の日から10日以内に、その旨を認定再生医療等員会に通知するとともに、様式第四(第三十一条関係 再生医療等提供中止届書)を厚生局長に届け出る。 |
|||
| 非進行性白斑 | stable vitiligo | ||
| 有 | |||
| 非培養表皮細胞移植 | noncultured epidermal cell transplantation | ||
| 特定細胞加工物を移植した部位(試験部位)、吸引水疱蓋を移植した部位(比較部位)、および無治療部(対照部位)の色素再生率をデジタルカメラで撮影した画像から算出して評価する。写真撮影は開始前、術後3ヶ月、術後6ヶ月で行う。安全性評価として、採皮部および細胞移植部位、吸引水疱蓋移植部位の創部、対照部位を観察する。 | Evaluation of repigmentation rate of cell transplantation area (test site), suction blister transplantation area (comparison site), non-treated area (control site) by calculating the area of images taken by digital camera.Photographs are taken before, 3 months after and 6 months after the operation. Observation of the wound areas of donor site, test site, comparison site and control site as a safety evaluation. | ||
| 試験部、比較部、および対象部と周辺健常部との色味(メラニン、ヘモグロビン)をメグザメーターで数値化する。安全性評価は再生医療等の提供に起因する副作用である感染症、瘢痕、稗粒腫の発生率とする。色味測定、安全性評価は開始前、術後3ヶ月、術後6ヶ月で行う。 | Evaluation of color matching (melanin and hemoglobin) on the test site, comparison site, control site and peripheral healthy site by the Mexameter. Incidence of adverse effects like infection, scarring and hemorrhoids resulting from the regenerative medicine as a safety evaluation. Color matching and safety evaluation are performed before, 3 months after and 6 months after the operation. | ||
| 提供する再生医療は、非進行性の白斑患者を対象とする。再生医療を受ける者の選択基準は以下である。(1)大阪大学医学部附属病院皮膚科を受診し、非進行性の白斑と診断された満年齢20歳以上の男女であり、臨床研究内容を説明の上、本人から文書による同意が得られた者、(2)手術適応があり、これまでの外科治療で十分な整容的満足を得ることが出来ない、もしくはこれまでの外科治療を拒否した症例。除外基準は以下である。(1)過去12ヶ月以内に白斑部位の拡大や新たな部位の出現など、明らかに白斑症状が進行している者、(2)被験者登録前の4週間以内にステロイド剤、活性型ビタミンD3剤、カルシニューリン阻害剤の外用薬治療や光線照射治療を行った者、(3)肥厚性瘢痕やケロイド形成歴のある者やケブネル現象を呈する者、(4)抗生物質や局所麻酔薬に対するアレルギー既往がある者、(5)テープかぶれする者、(6) 妊婦、授乳婦(子どもに母乳を与えている者)、試験期間中に妊娠を希望する者、(7)感染症(HBV、HCV、HIV、HTLV-1)を有する者、(8)他の臨床研究(介入および観察研究などの非介入を含む)に参加している者、(9)研究分担医師、研究責任医師が不適格と判断した者。 再生医療に用いる細胞(特定細胞加工物の構成細胞となる細胞)及び血清は、再生医療を受ける者の健常部皮膚より得られる吸引水疱蓋から調製したケラチノサイトとメラノサイト及び採血した血液から遠心分離して得られる血清よりなる。再生医療等を受ける者の健常部皮膚(例えば大腿内側など)を1%キシロカインによる局所麻酔下、10ml滅菌ディスポシリンジを用いて吸引減圧下で吸引水疱蓋を形成する。吸引水疱蓋を滅菌鋏で切除分離する。採取する吸引水疱蓋は、移植先の白斑患部面積の1/5~1/10を目安とする。吸引水疱蓋の形成時間短縮のため、赤外線ランプを皮膚表面温度が約40℃を維持できるように適切な距離を保って照射する。細胞培養調製施設(CPC)にて吸引水疱蓋をDPBSで洗浄、Trypsin処理に加え、スクレーパー、ペアン鉗子、ピンセット等により吸引水疱蓋から細胞を分離する。また、血清の調製もCPCにて行う。細胞をDPBSで洗浄し、細胞を培養せずに患者の自己血清に分散したものを特定細胞加工物とする。特定細胞加工物の投与方法は、予め炭酸ガスレーザーで表皮を剥削した白斑患部にディスポスポイトもしくは滅菌ディスポシリンジで滴下移植する。同一白斑患部に、特定細胞加工物の移植部、無治療の対照部、吸引水疱蓋法を適応する比較部を設けて実施する。移植後、各部位は抗生物質を配合した軟膏を塗布した非固着性ガーゼ及びドレッシング材等で被覆する。 再生医療等の有効性の判定は、主要評価項目を特定細胞加工物を移植した部位の色素再生率(もしくは白斑縮小率)をデジタルカメラで撮影した画像から算出して評価する。測定は開始前、術後3ヶ月、術後6ヶ月で行う。副次評価項目は改善した移植部と周辺健常部との色味(メラニン、ヘモグロビン)をメグザメーターで数値化する。安全性評価は再生医療等の提供に起因する副作用である感染症、瘢痕、脾粒腫の発生率とする。色味測定、安全性評価は開始前、術後3ヶ月、術後6ヶ月で行う。研究期間は委員会審査後、厚生局に届出を行い受理された日以降~2021年9月の間に有効症例に達した時点で終了とする。大阪大学医学部附属病院皮膚科に受診し外科的治療を行う患者数から概算した。2013年度5例、2014年度6例、2015年度5例、2016年度6例、2017年度9例、2018年度8例の手術実績があり、目標症例数を5例とした。 |
|||
2 人員及び構造設備その他の施設等
2 人員及び構造設備その他の施設等
(1)人員及び構造設備その他の施設に関する事項
(1)人員及び構造設備その他の施設に関する事項
| 医師 | |||||
| 種村 篤 | Tanemura Atsushi | ||||
| 大阪大学医学部附属病院 | Osaka University Hospital | ||||
| 皮膚科 | |||||
| 565-0871 | |||||
| 大阪府吹田市山田丘2-2 | 2-2 Yamadaoka, Suita, Osaka Japan | ||||
| 06-6879-3031 | |||||
| tanemura@derma.med.osaka-u.ac.jp | |||||
| 自施設 | |||||
| 大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター 病床数:集中治療室20床 設備:2管球ヘルカルCT、XperCT機能付き透視装 置、超音波検査装置、心電図装置、臨床検査室、ドクターヘリを常時運行 | |||||
(2)その他研究の実施体制に関する事項
(2)その他研究の実施体制に関する事項
| 吉永 美緒 | Yoshinaga Mio | ||||
| 大阪大学大学院医学系研究科 | Osaka University Graduate School of Medicine | ||||
| 皮膚科 | |||||
| 565-0871 | |||||
| 大阪府吹田市山田丘2-2 | 2-2 Yamadaoka, Suita, Osaka Japan | ||||
| 06-6879-3031 | |||||
| 06-6879-3039 | |||||
| 166yoshinaga@derma.med.osaka-u.ac.jp | |||||
| 医師 | ||
| 種村 篤 | ||
| 大阪大学医学部附属病院 | ||
| 皮膚科 |
| 医師 | ||
| 花岡 佑真 | ||
| 大阪大学医学部附属病院 | ||
| 皮膚科 |
| 大阪大学医学部附属病院 | ||
| 樽井 弥穂 | ||
| 大阪大学医学部附属病院 | ||
| 未来医療開発部 臨床研究センター モニタリンググループ | ||
| 大阪大学医学部附属病院 | ||
| 種村 篤 | ||
| 大阪大学医学部附属病院 | ||
| 皮膚科 | ||
(3)多施設共同研究に関する事項
(3)多施設共同研究に関する事項
| 無 |
3 再生医療等に用いる細胞の入手の方法並びに特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法等
3 再生医療等に用いる細胞の入手の方法並びに特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法等
(1)再生医療等に用いる細胞の入手の方法(特定細胞加工物を用いる場合のみ記載)
(1)再生医療等に用いる細胞の入手の方法(特定細胞加工物を用いる場合のみ記載)
| 再生医療等の提供を受ける者の健常部表より製造されるケラチノサイトとメラノサイトを含む細胞分散液 | |
| 再生医療等の提供を行う医療機関と同じ | |
| 再生医療等を受けるものと同じ | |
| 再生医療等を行う研究責任医師は、再生医療等に用いる細胞が以下を満たすことを確認する。(1) 細胞提供者(本臨床研究では再生医療等を受ける者と同一)から提供される細胞の採取が行われる医療機関が、細胞の採取や保管にあたり必要な管理が行われていること、十分な知識及び技術を有する者を有していることを確認する。 (2) 細胞提供者の健康状態、年齢その他の事情を考慮した上で、細胞提供者を選定する。 (3) 細胞提供者の適格性の判定に際し、既往歴の確認、診察、必要があれば検査等を行う。本臨床研究では自己細胞を用いるため、細胞提供者の選定に際しての詳細な検査は必要としないが、特定細胞加工物の製造工程での交さ汚染の防止や製造を行う者への安全性対策等の観点から、以下の項目について問診及び検査(血清学的試験、核酸増殖法等を含む)を実施する。 ①B型肝炎ウイルス(HBV) ② C型肝炎ウイルス(HCV) ③ヒト免疫不全ウイルス(HIV) ④ ヒトT細胞白血病ウイルスⅠ型(HTLV-1)(4)細胞提供者より採取される細胞が、医学的処置、手術及びその他の治療方針を変更することにより採取された細胞でないことを確認する。(5)特定細胞加工物の製造に用いる細胞の提供は無償で行う。 | |
| 再生医療等を受ける者の健常部皮膚(例えば大腿内側など)を1%キシロカインによる局所麻酔下、10ml滅菌ディスポシリンジを用いて吸引減圧下で吸引水疱蓋を形成する。吸引水疱蓋を滅菌鋏で切除分離する。採取する吸引水疱蓋は、移植先の白斑患部面積の1/5~1/10を目安とする。吸引水疱蓋の形成時間短縮のため、赤外線ランプを皮膚表面温度が約40℃を維持できるように適切な距離を保って照射する。細胞培養調製施設(CPC)にて吸引水疱蓋をDPBSで洗浄、Trypsin処理に加え、スクレーパー、ペアン鉗子、ピンセット等により吸引水疱蓋から細胞を分離する。また、血清の調製もCPCにて行う。細胞をDPBSで洗浄し、細胞を培養せずに患者の自己血清に分散したものを特定細胞加工物とする。 |
(2)特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法(特定細胞加工物等を用いる場合のみ記載)
(2)特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法(特定細胞加工物等を用いる場合のみ記載)
| 自家非培養表皮細胞分散液 | ||
| 特定細胞加工物は細胞提供者の健常部皮膚(例えば大腿内側など)を1%キシロカインによる局所麻酔下、10ml滅菌ディスポシリンジを用いて吸引減圧下で吸引水疱蓋を形成する。吸引水疱蓋の形成時間短縮のため、赤外線ランプを皮膚表面温度が約40℃を維持できるように適切な距離を保って照射する。形成した吸引水疱蓋を滅菌鋏で切除分離し、DPBSが入った密閉容器で細胞培養調製施設に輸送する。また、特定細胞加工物を分散させる自己血清を調製するために細胞提供者から血液を採取し、細胞培養調製施設に輸送する。細胞培養調製施設で吸引水疱蓋をトリプシン処理し、自己血清に分散した細胞分散液を製造する。特定細胞加工物は1次容器(クライオチューブ)に入れ、予め冷蔵した2次容器(バイセル)、蓄冷剤入り3次容器(搬送容器)に入れて出荷判定後、低温で手術室に搬送する。特定細胞加工物は以下の規格で管理する。1)総細胞数1.0x10E4個以上、2)生存率60%以上、3)感染症検査で陰性。3)は特定細胞加工物の最終洗浄液を用いて感染症検査(日本薬局方に準じたグラム染色)を行い陰性であること。製造工程内での特定細胞加工物への微生物感染がないことを判定する試験として、以下の感染症検査を実施する。無菌試験:日本薬局方に準じた無菌試験を実施し、その結果が陰性であることを判断基準とする。マイコプラズマ否定試験:特定細胞加工物へのマイコプラズマ感染を高感度かつ特異的に判定可能な試験として、日本薬局方に準じたPCR法によるマイコプラズマ否定試験を実施し、陰性であることを判断基準とする。エンドトキシン試験:特定細胞加工物へ混入するエンドトキシン量が定量可能な試験として日本薬局方に準じたエンドトキシン試験を実施し、1.0 EU/mL以下であることを判断基準とする。特定細胞加工物に対する感染症検査サンプルは移植当日に得られるため、その試験結果は投与後に判明することに留意する。特定細胞加工物の感染症検査で基準を満たさない結果が報告された場合は、直ちに適切な対応を講じる。 | ||
| 特定細胞加工物の投与方法は、予め炭酸ガスレーザーで表皮を剥削した白斑患部にディスポスポイトもしくは滅菌ディスポシリンジで滴下移植する。 | ||
| 有 | ||
| 国立大学法人大阪大学 | ||
| FC5150030 | ||
| 大阪大学医学部附属病院細胞培養調製施設 | ||
| 表皮細胞分散液の調製 | ||
(3)再生医療等製品等に関する事項(再生医療等製品を用いる場合のみ記載)
(3)再生医療等製品等に関する事項(再生医療等製品を用いる場合のみ記載)
(4)再生医療等に用いる未承認又は適応外の医薬品又は医療機器に関する事項(未承認又は適応外の医薬品又は医療機器を用いる場合のみ記載)
(4)再生医療等に用いる未承認又は適応外の医薬品又は医療機器に関する事項(未承認又は適応外の医薬品又は医療機器を用いる場合のみ記載)
4 再生医療等技術の安全性の確保等に関す措置
4 再生医療等技術の安全性の確保等に関す措置
(1)利益相反管理に関する事項
(1)利益相反管理に関する事項
① 再生医療等に対する特定細胞加工物等製造事業者からの研究資金等の提供その他の関与
① 再生医療等に対する特定細胞加工物等製造事業者からの研究資金等の提供その他の関与
| 無 | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
② 再生医療等に対する医療薬品等製造販売業者等からの研究資金等の提供その他の関与
② 再生医療等に対する医療薬品等製造販売業者等からの研究資金等の提供その他の関与
| 花王株式会社 | ||
| 無 | ||
| 有 | ||
| 2018年11月22日 | ||
| 有 | ||
| 電動式可搬型吸引機器 ミニックW-Ⅱ(花王株式会社より) メグザメーターMDD4(花王株式会社より) |
||
| 無 | ||
③ 再生医療等に対する特定細胞加工物等製造事業者又は医療品等製造販売業者等以外からの研究資金
③ 再生医療等に対する特定細胞加工物等製造事業者又は医療品等製造販売業者等以外からの研究資金
| 有 | ||
| 花王株式会社が大阪市立大学に設置した共同研究部門 色素異常症治療開発共同研究部門 | Osaka City University, Department of Pigmentation Research and Therapeutics established by Kao Corporation | |
| 非該当 | ||
(2)その他再生医療等技術の安全性の確保等に関する措置
(2)その他再生医療等技術の安全性の確保等に関する措置
| 安全性についての検討内容 1)特定細胞加工物製造工程における無菌性試験 3ロットの健常ヒト皮膚をポピドンヨードで十分に消毒した後、表皮シートを採取し非培養表皮細胞分散液を調製した。すなわち、0.25%Trypsin/DPBSで消化し、得られた表皮細胞をDPBSで2回洗浄し、2回目の洗浄液中の一般細菌、酵母およびカビについて一般財団法人日本食品分析センターにて検査を行った。方法は寒天培養法を用いた。 その結果、3ロットの健常ヒト皮膚からの一般細菌、酵母およびカビの混入は検出されなかった。 2)特定細胞加工物製造工程におけるトリプシン残存否定試験 3ロットの健常ヒト皮膚をポピドンヨードで十分に消毒した後、表皮シートを採取し非培養表皮細胞分散液を調製した。すなわち、0.25%Trypsin/DPBSで消化し、得られた表皮細胞をDPBSで2回洗浄し、洗浄液中のトリプシン残存量をTrypsin ELISA Kit(検出限界1.56ng/mL、Cloud-Clone Corp社)にて測定した。 その結果、表皮細胞分散液の2回目の洗浄液中のトリプシンの残存量は3ロットすべて検出限界以下であった。本特定細胞加工物と同様に自家非培養細胞分散液を用いた白斑治療の実施状況は、国内では実施前例はないが、海外では広く行われている。細胞加工物を製造する細胞調製法や移植する白斑患部の剥削方法や術後の追加処置(紫外線照射など)が異なるため、一概に比較はできないが、トリプシンを用いて細胞を分散し、移植した患部に低色素沈着や瘢痕などの副作用は認められず(文献1-4)、アレルギー症状や感染に関する副作用は報告されていない。 1) Lommerts JE. Br J Dermatol. 2017 Apr 12. doi: 10.1111/bjd.15569. 2) Komen L. J Am Acad Dermatol. 2015 Jul;73(1):170-2. 3) Singh C. Br J Dermatol. 2013 Aug;169(2):287-93. 4) Budania A. Br J Dermatol. 2012 Dec;167(6):1295-301. |
||||||
| 提供する再生医療等の妥当性を支持する報告 提供する再生医療は自家非培養表皮細胞移植である。自家非培養表皮細胞移植は、1992年にGauthier ら(文献1)の報告以降、海外では広くその有効性と安全性が検証されている。本再生医療のメリットは、既存の外科的手法の課題である移植後のムラや瘢痕化などの副作用が少なく、整容的に優れることである(文献2)。また、既手法では移植先の白斑患部と同等面積の健常部皮膚が必要だが、本再生医療は白斑患部面積の1/10と採皮面積を低減でき(文献3)、患者の負担を軽減できる。さらに、患者のQOL評価も高く(文献4)治療満足度が高い外科的治療法である(文献5)。デメリットとしては、既手法と比較して細胞製造に要する時間を拘束される点である。 1) Gauthier Y. J Am Acad Dermatol. 1992 Feb;26(2 Pt1):191-4. 2) Budania A. Br J Dermatol. 2012 Dec;167(6):1295-301. 3) Jeong HS. Dermatol Surg. 2016 May;42(5):688-91. 4) Singh C. Br J Dermatol. 2013 Aug;169(2):287-93. 5) Adotama P. J Am Acad Dermatol. 2015 Apr;72(4):732-3. 褐色モルモット(Kwl:A-1)への自家非培養表皮細胞移植による上皮化の確認 表皮細胞分散液の調整 移植前日に移植個体からイソフルラン麻酔下で毛刈りし、70%エタノールで採皮部皮膚滅菌後、直径4mmの生検トレパンにて背部皮膚を回収して切除部位を縫合しイソジンで消毒した。回収した皮膚はDPBSで3回洗浄した後、60mmシャーレに表皮側が下になるように配置し、ディスパーゼに4℃で一晩浸漬した。翌日、滅菌済ピンセットを用いて表皮層と真皮層を分離し、表皮層のみをDPBSで洗浄した。洗浄後、37℃に加温した0.25%トリプシン溶液中に5分間浸漬処理した後、100μmのセルストレイナーで残渣を除去し、表皮細胞を得た。得られた表皮細胞はDPBSで3回洗浄し、最終的に500μLのDPBSに再分散した。表皮細胞はPKH26 Red Fluorescent Cell Linker Mini Kit for General Cell Membrane Labeling(Sigma-Aldrich)を用いて標識・洗 浄後、DPBSで1x10E5細胞/mLの表皮細胞分散液を作製した。 表皮細胞の移植 イソフルラン麻酔下で移植部位を毛刈りし、5mm×5mmの区画を確保した。超音波メス(日本ストライカー)を用い、確保した区画の表皮組織を剥削した。その後、表皮細胞分散液を20μL滴下し、5分間静置した後に、ウルゴチュール(ニトムズ)で被覆し、その上にDPBSで湿らせたガーゼ、乾燥したガーゼを重ね、エラストポア(ニチバン)で 固定した。 自家非培養表皮細胞の上皮化の確認 表皮細胞移植部の皮膚は移植8日後に採材した。イソフルラン麻酔下で直径2mmの生検トレパンにより回収した。回収した皮膚はDPBSで2回洗浄した後、O.C.T.コンパウンドに包埋し、クリオスタットを用いて薄切切片を作成し、蛍光顕微鏡で観察した。 その結果、移植した自家非培養表皮細胞が基底層直上に生着し、上皮化した。 |
||||||
| 特定細胞加工物の投与の可否の決定は、研究責任医師が行う。特定細胞加工物概要書に基づいて吸引水疱蓋から製造した最終製造物の品質が以下の規格を満たすことで決定する。ただし、無菌試験の結果は最終製造物の投与後の確認となる。 1) 総細胞数:1x10E4個以上 2) 生細胞率:60%以上 3) 感染症検査:陰性 |
||||||
| 研究分担医師、研究責任医師は、細胞提供者の遅発性感染症の発症の疑い、その他の当該細胞の安全性に関する疑義が生じたことを知った場合、状況に応じて提供の中止や再生医療等を受けた者への必要な検査、治療を行う。 | ||||||
| 再生医療等を受ける者由来原料や製造した特定細胞加工物は微量であり、製造日に投与するため保存しない。参考品として製造工程での最終洗浄液を保管する、保管期間は5年とする。 | ||||||
| 製造された細胞の洗浄液は5年間保存され、細胞製造工程における品質管理を目的とした試験に用いる。臨床研究、品質管理試験などの全ての試験が終了後、検体は施設の管理及び処理に関する規定に則って適切に廃棄する | ||||||
| 再生医療等の提供によるものと疑われる疾病、傷害、若しくは死亡または感染症を有害事象と定義し、その発生を知ったときは、病院長に速やかにその旨を報告する。報告を受けた病院長、研究責任医師は再生医療等を行う医師に対し、再生医療等の中止、その他の必要な措置(疾病などの発生の原因分析や発生した事態が細胞加工物に起因するものであるかの検討)を講ずるよう指示する。病院長、研究責任医師は発生した事態及び講じた措置について、特定細胞加工物を製造した大阪大学医学部附属病院細胞培養調製施設および認定再生医療等委員会に速やかに通知する。病院長は、再生医療等の提供について、次に掲げる事項を知ったときは、それぞれに定める期間内に当該事項を別紙様式第一(省令第三十五条関係、疾病等報告書)により認定再生医療等委員会に報告する。報告を受けた認定再生医療等委員会は、必要があると認めるときは、病院長に対し、その原因究明および講ずべき措置について意見を述べた上で、提供機関が認定再生医療等委員会の意見を添えて別紙様式第二(省令第三十六条関係、疾病等報告書)により厚生局長に報告する。但し、厚生局長への報告は(1)、(2)のみ該当する。 (1)次に掲げる疾病等の発生のうち、再生医療等の提供によるものと疑われるもの又は再生医療の提供によるものと疑われる感染症によるもの:7日 (ア) 死亡 (イ)死亡につながるおそれのある症例 (2)次に掲げる疾病等の発生のうち、再生医療等の提供によるものと疑われるもの又は再生医療等の提供によるものと疑われる感染症によるもの:15日 (ア) 治療のために医療機関への入院又は入院期間の延長が必要とされる症状(イ) 障害(ウ) 障害につながるおそれのある症例(エ) 重篤である症例 ※「重篤」は(ア)~(ウ)までに掲げる症状に準ずるもの(オ)後世代における先天性の疾病または異常 (3)再生医療等の提供によるものと疑われるもの又は再生医療等の提供によるものと疑われる感染症による疾病等の発生((1)及び(2)に掲げるものを除く): 再生医療等提供計画を厚生局長に提出した日から起算して60日ごとに期間満了後10日以内。 |
||||||
| 疾病等の発生について追跡調査 再生医療の提供終了後、再生医療の提供による疾病などの発生については、研究期間(術後6ヶ月間)に加えて6ヶ月の追跡期間を設ける。再生医療の提供による疾病等の発生については、病院長に報告する。 |
||||||
| 再生医療等の提供に起因するものと疑われる疾病等の発生の場合に当該疾病等の情報を把握できるよう、及び細胞加工物に問題が生じた場合に再生医療を受けた者の健康状態が把握できるよう、臨床研究終了後6ヶ月の経過観察期間を設け、経過観察期間終了後でも適切な措置を講じることができるよう、再生医療等を受けた者の連絡先を把握する。 | ||||||
| 無 | ||||||
| 2019年06月03日 | ||||||
| 2019年10月02日 | ||||||
| 研究終了 | Complete | |||||
5 細胞提供者及び再生医療等を受ける者に対する健康被害の補償の方法
5 細胞提供者及び再生医療等を受ける者に対する健康被害の補償の方法
細胞提供者について(特定細胞加工物を用いる場合のみ記載)
細胞提供者について(特定細胞加工物を用いる場合のみ記載)
| 有 |
再生医療等を受ける者について
再生医療等を受ける者について
| 有 |
6 審査等業務を行う認定再生医療等委員会に関する事項
6 審査等業務を行う認定再生医療等委員会に関する事項
| 大阪大学第一特定認定再生医療等委員会 | The First Certified Special Committee for Regenerative Medicine, Osaka University | |
| NA8140001 | ||
| 大阪府吹田市山田丘2-2 | 4F Center of Medical Innovation and Translational Research 2-2 Yamadaoka, Suita, Osaka, Osaka | |
| 06-6210-8293 | ||
| nintei@dmi.med.osaka-u.ac.jp | ||
| 第一種再生医療等又は第二種再生医療等を審査することができる構成 | ||
| 適 | ||
| 2019年03月07日 | ||
7 その他
7 その他
| 個人情報の取り扱いについて 再生医療等を受ける者に関する個人情報を保有する者は、当該個人情報について匿名化を行う場合にあっては、連結可能匿名化(必要な場合に特定の個人を識別できる情報を保有しつつ行う匿名化をいう)した上で、当該個人情報を取り扱う。 個人情報の保護について 病院長は、個人情報の適正な取り扱いの方法を具体的に定めた実施規定(個人情報取扱実施規定)を定める。個人情報取扱規定は次に掲げる事項を含むものであること① 個人情報の適正な取得に関する事項② 保有する個人情報の漏洩、紛失又はき損の防止その他の安全管理に関する事項③ 保有する個人情報を取り扱う者に対する指導及び管理に関する事項④ 保有する個人情報の開示等に関する事項 研究として再生医療等を行う場合には、臨床研究に関する倫理指針の個人情報の保護に係る責務を参考にする。本臨床研究に関わる個人情報を『独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律』に基づき作成された『大阪大学個人情報管理規程』及び『人を対象とする医学系研究に関する試料・情報の利用及び学外機関への提供に係る業務手順書』にしたがって、臨床研究の中止または終了後5年間適切に保管する。個人情報は『大阪大学個人情報管理規程』及び『人を対象とする医学系研究に関する試料・情報の利用及び学外機関への提供に係る業務手順書』にしたがって適切に廃棄する。すなわち、紙又は記録媒体等の有体物に記録されている場合には裁断・廃棄をおこない、情報の取出しができない状態にする。また、コンピュータ・データとして保管されている場合には初期化する等情報の取出しができない状態にする。 | ||
| 病院長又は研究責任医師は、再生医療等を適正に実施するために定期的に教育又は研修の機会を確保する。医師や再生医療等の提供に係る関係者は再生医療等を適正に実施するために定期的に適切な教育又は研修を受け、情報収集に努める。 再生医療等の提供に携わる関係者は、大阪大学医学部附属病院が実施する講習会への受講(年1回以上)及び臨床研究e-learningシステム(CROCO)にて、再生医療等研究者コースを受講することが義務付けられている。 | ||
| 本研究に関する問い合わせ・苦情の窓口、個人情報の取扱い等に関する問い合わせ、及び緊急時の連絡先は以下のとおりである。 大阪大学医学部附属病院皮膚科学教室 〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2-15 研究責任医師: 種村 篤(准教授) TEL: 06-6879-3031 FAX: 06-6879-3039 E-mail: tanemura@derma.med.osaka-u.ac.jp |
||
| 非該当 | ||
| なし | none | |
| 無 | ||
| 非該当 | ||
| 非該当 | ||
| 非該当 | ||
| UMIN000037612 | ||
| UMIN臨床試験登録システム | University hospital Medical Information Network | |
添付資料
添付資料
| 4 再生医療等を受ける者に対する説明文書及び同意文書の様式 | 【最新】4.同意説明文書_第7版(種村先生職名変更).pdf |
|---|