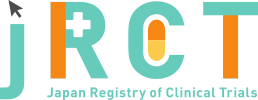臨床研究等提出・公開システム
再生医療等提供計画情報の詳細情報です。
| 第三種 | ||
| 令和2年3月2日 | ||
| 令和3年12月20日 | ||
| 令和3年2月3日 | ||
| 令和2年12月1日 | ||
| 多血小板血漿(PRP)を用いた難治性皮膚潰瘍の研究 | ||
| PRPを用いた難治性皮膚潰瘍の研究 | ||
| 金沢医科大学病院 | ||
| 伊藤 透 | ||
| 糖尿病、膠原病などに伴う重度血流障害等に起因する皮膚潰瘍、褥瘡などの中には従来の治療に対して抵抗性の難治性症例(難治性皮膚潰瘍)は国内では約130万人の患者がいるとされている。本研究は従来の方法では治療が困難であった症例に対し、PRPを用いて低侵襲かつ組織再生を期待できる方法を行うことができると考える。創傷面積を縮小させることが難治性皮膚潰瘍治療の第一目標となるため、面積縮小割合の評価指標は、褥瘡・皮膚潰瘍治療の既承認製剤の情報を参照して設定し、潰瘍面積縮小率も併せて算出し評価を行う。 | ||
| 1-2 | ||
| 難治性潰瘍 | ||
| 研究終了 | ||
| 金沢医科大学認定再生医療等委員会 | ||
| NB4150006 | ||
総括報告書の概要
総括報告書の概要
臨床研究の名称等
臨床研究の名称等
| 第三種 | |||
| 令和3年11月29日 | |||
| jRCTc040190121 | |||
| 提供しようとする再生医療等の名称 | 多血小板血漿(PRP)を用いた難治性皮膚潰瘍の研究 | ||
| 認定再生医療等委員会の名称(認定番号) | 金沢医科大学認定再生医療等委員会 (NB4150006) | ||
| 2020年12月01日 | |||
| 1 | |||
| / | 40代 女性 病名:難治性潰瘍(左下腿) 《経緯》 左下腿の開放性骨折、下肢末梢神経障害を受傷し、通常の治療を施行しても難治であった。 対象者は本研究の選択基準を満たし、治療に関する十分な説明と理解のうえ患者本人の自由意思による文書同意を得たうえで本治療を実施した。 |
40s, Female, Disease name: Refractory ulcer (left lower leg) Background:Injured open fracture of left lower leg, peripheral neuropathy of lower limbs, it was intractable even after the usual treatment. Patient meets the selection criteria of this study and is related to the treatment with sufficient explanation and understanding. This treatment was performed after obtaining written consent. |
|
| / | 対象患者自身の血液を採取し、オートメーション化された自己血小板遠心分離機(Magellan; Artetiocyte Medical Systems,Inc.,Cleveland,USA)によりPRPを得る。採血量の目途は、一般成人において 潰瘍10×10㎝に対し30〜60mLの採血で、ここから およそ3〜6mLの多血小板血漿(PRP)が得られる。 局所処置としては、潰瘍面の壊死組織を可能な範囲 で除去し、創面の新鮮化を図った後、PRPを創部に塗 布もしくは、創傷被覆材に浸漬貼付する。壊死組織除去に際して強い疼痛を伴う場合には、局所麻酔下で行う。PRP 2回目以降は、凍結保存したPRPを使用した。凍結したPRPを自然解凍して同様に投与した。 | The patient's own blood is collected and PRP is obtained by an automated autologous platelet centrifuge (Magellan; Artetiocyte Medical Systems, Inc., Cleveland, USA). The area of ulcer and the amount of blood collected are 30 to 60 mL of blood collected for 10 x 10 cm of ulcer in general adults, and about 3 to 6 mL of platelet-rich plasma (PRP) can be obtained from this. As a local treatment, the necrotic tissue on the ulcer surface is removed to the extent possible to refresh the wound surface, and then PRP is applied to the wound or immersed in a wound dressing. If there is severe pain when removing necrotic tissue, it is performed under local anesthesia. Cryopreserved PRP was used from the second PRP onward. Frozen PRP was naturally thawed and administered in the same manner. | |
| / | 症状増悪につながるような所見は見られなかった。 | No findings that could lead to exacerbation of symptoms were identified. | |
| / | 2019年3月6日から2020年3月5日までの1年間に 女性1名(40代)の難治性潰瘍(左下腿)に対して、多 血小板血漿(PRP)の投与を実施した。患者背景や症状などを含めた本療法の選択基準などを遵守して行った。逸脱は認められなかった。PRP投与に伴う、発赤、滲出液の量、出血、疼痛などの有害事象は認めず、投与後の経過観察においても、初回投与時から最終投与6カ月までの面積縮小割合は70%以上であった。症状増悪につながるような所見は認めなかった。 潰瘍は徐々に縮小し、最終投与の6カ月後には線状潰瘍を残すのみとなった。 以上を総括すると当該再生医療の安全性は十分高いものと考えられる。難治性潰瘍における本再生医療研究において、画像所見や症状の改善傾向から科学的な妥当性があると考えられる。引き続き可能な限り経過観察を行う。 | Platelet-rich plasma (PRP) was administered to one female (40s) intractable ulcer (left thigh) during the year from March 6, 2019 to March 5, 2020. The selection criteria for this therapy, including patient background and symptoms, were observed. No deviation was found. No adverse events such as redness, exudate volume, bleeding, or pain associated with PRP administration were observed, and the area reduction rate from the first administration to 6 months after the final administration was 70% or more even in the follow-up after administration. No findings leading to exacerbation of symptoms were found. The ulcer gradually shrank, leaving only a linear ulcer 6 months after the final dose. Summarizing the above, it is considered that the safety of the regenerative medicine is sufficiently high. In this regenerative medicine study for refractory ulcers, it is considered to be scientifically valid from the image findings and the tendency of improvement of symptoms. Follow up observation will be continued as much as possible. |
|
| / | 40代 女性 病名:難治性潰瘍(左下腿) 《経緯》 左下腿の開放性骨折、下肢末梢神経障害を受傷し、 通常の治療を施行しても難治であった。 《多血小板血漿(PRP)投与》 2019/3/26にプロトコールに従い 末梢血を採取し3ccのPRPを作成し人工真皮(テルダーミス)に浸漬して潰瘍部に貼付した。同様の手技 を2019/5/8にも行った。 《投与後の経過》 潰瘍は徐々に縮小し、最終投与の6ヵ月後には線状潰瘍を残すのみとなった。 《奏効率》 初回投与時から最終投与6ヵ月までの面積縮小割合 は70%以上であった。 【まとめ】 多血小板血漿(PRP)は難治性潰瘍の治療に有効であった。 |
40s, Female, Disease name: Refractory ulcer (left lower leg)Injured open fracture of left lower leg, peripheral neuropathy of lower limbs, intractable even after the usual treatment. On March 26, 2019, according to the protocol, PRP was prepared, immersed in artificial dermis (terdermis), and attached to the ulcer. A linear ulcer left 6 months after the final dose. The area reduction rate was 70% or more. PRP was effective in treating intractable ulcers. | |
| 2021年11月29日 | |||
IPDシェアリング
IPDシェアリング
| / | 無 | No | |
|---|---|---|---|
| / | |||
1 提供しようとする再生医療等及びその内容
1 提供しようとする再生医療等及びその内容
申請者情報
申請者情報
| 令和3年11月29日 | |||
| jRCTc040190121 | |||
| 金沢医科大学病院 | |||
| 石川県河北郡内灘町大学1-1 | |||
| 伊藤 透 | Ito Tohru | ||
(1)再生医療等の名称及び分類
(1)再生医療等の名称及び分類
| 多血小板血漿(PRP)を用いた難治性皮膚潰瘍の研究 | A study of Platelet rich plasma(PRP) therapy for refractory ulcer( A study of Platelet rich plasma(PRP) therapy for refractory ulcer ) | ||
| PRPを用いた難治性皮膚潰瘍の研究 | A study of PRP therapy( A study of PRP therapy ) | ||
| 第三種 | |||
| 法令で除外した技術→No→人の胚性幹細胞等→No→遺伝子導入→No→動物の細胞→No→投与を受ける者以外の細胞→No→幹細胞を利用している→No→人の身体の修復目的→Yes→培養→No→相同利用→Yes→第3種 | |||
(2)再生医療等の内容
(2)再生医療等の内容
| 糖尿病、膠原病などに伴う重度血流障害等に起因する皮膚潰瘍、褥瘡などの中には従来の治療に対して抵抗性の難治性症例(難治性皮膚潰瘍)は国内では約130万人の患者がいるとされている。本研究は従来の方法では治療が困難であった症例に対し、PRPを用いて低侵襲かつ組織再生を期待できる方法を行うことができると考える。創傷面積を縮小させることが難治性皮膚潰瘍治療の第一目標となるため、面積縮小割合の評価指標は、褥瘡・皮膚潰瘍治療の既承認製剤の情報を参照して設定し、潰瘍面積縮小率も併せて算出し評価を行う。 | |||
| 1-2 | |||
| 実施計画の公表日 | |||
| 2021年03月31日 | |||
| 30 | |||
| 介入研究 | Interventional | ||
| 単一群 | single arm study | ||
| 非盲検 | open(masking not used) | ||
| 非対照 | uncontrolled control | ||
| 単群比較 | single assignment | ||
| 治療 | treatment purpose | ||
| 従来の治療法で改善を認めない、または増悪傾向を示す難治性皮膚潰瘍例で、身体の 状態などにより手術による治療が困難な患者のうち、本研究参加にあたり十分な説明 をうけた後、十分な理解の上、患者本人の自由意思による文書同意が得られた 20 歳 以上の患者 ①通常の保存的加療に抵抗性を有する難治性潰瘍 ②切断・植皮術等の外科的処置を患者自身が拒否する症例もしくは麻酔科医が手術不適応と 判断する程度の全身状態不良患者 ③PRP の調製のための採血が可能な患者 ④20 歳以上の成人であること ⑤PRP 調製のための採血を行うまでに被験者本人(または代諾者)から書面による同意が得られ ている患者 |
Patients with refractory skin ulcers that are not improved or are exacerbated by conventional treatments, and who are difficult to treat by surgery due to physical condition, etc. Patients over 20 years of age who have obtained a written consent of their own free will (1)Refractory ulcer resistant to conservative treatment (2)Patients who refuse to undergo surgical procedures such as amputation and skin grafting, or patients whose general condition is poor enough for the anesthesiologist to determine that the surgery is inappropriate (3)Patients who can collect blood for PRP preparation (4)Being an adult over 20 years old (5)Patients who have obtained written consent from the subject (or surrogate) before collecting blood for PRP preparation |
||
| 高度な貧血や血小板減少、その他、試験責任(分担)医師が被験者として不適当と判 断した患者 ①創傷面の感染を制御できない患者(創部の色、膿汁の色、臭いで感染が疑われる場合に、 菌培養を行い感染の有無を判定) ②創傷面(潰瘍部)に悪性腫瘍を合併している患者 ③著しい貧血症例(男女ともHb 7g/dL未満) ④白血病 ⑤再生不良性貧血 ⑥血小板減少症 ⑦血液凝固異常と診断された患者 ⑧医師の指示に従うことができない患者 ⑨PRP療法に同意が得られない患者 |
Patients with advanced anemia, thrombocytopenia, etc., who are judged inappropriate as subjects by the investigator (1)Patients who have wound surface with uncontrollable infection (if the infection is suspected due to the color of the wound, the color of the pus, or the smell, the presence of infection is determined by culturing the bacteria) (2)Patients with malignant tumor on the wound surface (ulcer) (3)Significant anemia (Hb <7g / dL for both men and women) (4)leukemia (5)Aplastic anemia (6)Thrombocytopenia (7)Patients diagnosed with abnormal blood coagulation |
||
| 20歳 以上 | 20age old over | ||
| 上限なし | No limit | ||
| 男性・女性 | Both | ||
| 研究者は、以下に示す理由で試験継続が不可能と判断した場合には、試験を中止し、中 止・脱落の日付・時期、中止・脱落の理由、経過をカルテに明記するとともに、中止・ 脱落時点で必要な検査を行い有効性・安全性の評価を行う。 1) 被験者から試験参加の辞退の申し出や同意の撤回があった場合 2) 登録後に適格性を満足しないことが判明した場合 3) 合併症の増悪により試験の継続が困難な場合 4) 有害事象により試験の継続が困難な場合 5) 試験全体が中止された場合 6) その他の理由により、医師が試験を中止することが適当と判断した場合 |
|||
| 難治性潰瘍 | refractory ulcer | ||
| 難治性潰瘍、PRP | refractory ulcer, Platelet rich plasma | ||
| 有 | |||
| 対象患者自身の血液を採取し、オートメーション化された自己血小板遠心分離機 (Magellan® ;Arteriocyte Medical Systems,Inc.,Cleveland,USA)によりPRP を得る。対象潰瘍面積と採血量の目途は、一般成人において潰瘍10×10cmに対し30 ~60mLの採血で、ここからおよそ3~6mLの多血小板血漿(PRP)が得られる。 局所処置としては、潰瘍面の壊死組織除去を可能な範囲で除去し、創面の新鮮化 を図った後、PRPを創部に塗布もしくは、創傷被覆材に浸漬貼付する。壊死組織除 去に際して強い疼痛を伴う場合には、局所麻酔下に壊死組織除去を行う。実施場所 については、血液採取およびPRP分離、局所処置までの一連の操作を中央手術室で 行う。 壊死組織除去のために局所麻酔薬を使用することがあるが、従来の皮膚移植術や 皮弁形成術に比較して、患者への負担は小さく、ほとんどの症例において施行可能 な処置である。 PRP投与2回目以降は、凍結保存したPRPを使用する。凍結したPRPを自然解凍し て、同様に投与する。 |
The patient's own blood is collected and PRP is obtained by an automated autologous platelet centrifuge (Magellan; Arteriocyte Medical Systems, Inc., Cleveland, USA). In general adults, for 10 x 10 cm target ulcer, blood collection volume is 30-60 mL, and approximately 3-6 mL of platelet-rich plasma (PRP) is obtained. As a local treatment, after removing the necrotic tissue on the ulcer surface as much as possible and renewing the wound surface, PRP is applied to the wound part or immersed and applied to the wound dressing. If patient complains severe pain in removing the necrotic tissue, the necrotic tissue is removed under local anesthesia. The series of operations from blood collection, PRP separation, and local treatment will be performed in the central operating room. Although local anesthetics are sometimes used to remove necrotic tissue, the burden on the patient is small compared to conventional skin transplantation and flap arthroplasty, and this is a treatment that can be performed in most cases. For the second and subsequent doses of PRP, use cryopreserved PRP. Frozen PRP is naturally thawed and administered in the same manner. |
||
| 奏効率:本研究開始前から PRP 実施期間の最終来院時の面積縮小割合が 50%を超 えた症例を奏功と定義し奏功率を算出する。 ※創傷面積を縮小させることが難治性皮膚潰瘍治療の第一目標となるため、面積縮 小割合の評価指標は、褥瘡・皮膚潰瘍治療の既承認製剤の情報を参照して設定し た。また、潰瘍面積縮小率も併せて算出し評価を行う。 潰瘍の面積および性状の変化について、各々の観察時点での評価(投与時、最終投 与時以降は 1 週、4 週、3 ヵ月、6 カ月後を目安に診察)を行う。 |
Response rate: The response rate is calculated by defining a case where the area reduction rate at the final visit during the PRP implementation period exceeds 50% before the start of this study as a response. * Since the reduction of the wound area is the primary goal for treatment of intractable skin ulcers, the evaluation index for the area reduction rate was set with reference to information on the approved preparations for treatment of pressure ulcers and skin ulcers. The ulcer area reduction rate is also calculated and evaluated. Evaluate changes in ulcer area and properties at the time of each observation (diagnosis after 1 week, 4 weeks, 3 months, and 6 months after administration). |
||
| PRP 療法の安全性(有害事象、重篤な有害事象、不具合の発生頻度)を評価する。 | Evaluate the safety of PRP therapy (adverse events, serious adverse events, frequency of failures). |
||
| 別添のとおり | |||
2 人員及び構造設備その他の施設等
2 人員及び構造設備その他の施設等
(1)人員及び構造設備その他の施設に関する事項
(1)人員及び構造設備その他の施設に関する事項
| 医師 | |||||
| 島田 賢一 | Shimada Kenichi | ||||
| 金沢医科大学病院 | Kanazawa Medical University Hospital | ||||
| 形成外科 | |||||
| 920-0293 | |||||
| 石川県河北郡内灘町大学1-1 | 1-1 Daigaku, Uchinada, Kahoku, Ishikawa 920-0293, JAPAN | ||||
| 076-286-2211 | |||||
| shimaken@kanazawa-med.ac.jp | |||||
| 自施設 | |||||
| 金沢医科大学病院 病床数:一般病床835床 診療科目:内科、循環器内科、外科、脳神経外科、整形外科、等 設備:MRI・CT・X線TV撮影装置・外科用イメージ 血管造影装置・手術顕微鏡・脳血流測定装置・脳波計・心電図・超音波診断装置 | |||||
(2)その他研究の実施体制に関する事項
(2)その他研究の実施体制に関する事項
| 桝田 直美 | Masuda Naomi | ||||
| 金沢医科大学病院 | Kanazawa Medical University Hospital | ||||
| 再生医療センター | |||||
| 920-0293 | |||||
| 石川県河北郡内灘町大学1-1 | 1-1 Daigaku, Uchinada, Kahoku, Ishikawa 920-0293, JAPAN | ||||
| 076-218-8200 | |||||
| 076-218-8210 | |||||
| regene@kanazawa-med.ac.jp | |||||
| 医師 | ||
| 岸邊 美幸 | ||
| 金沢医科大学病院 | ||
| 形成外科 |
| 医師 | ||
| 山下 昌信 | ||
| 金沢医科大学病院 | ||
| 形成外科 |
| 医師 | ||
| 宮永 亨 | ||
| 金沢医科大学病院 | ||
| 形成外科 |
| 医師 | ||
| 金子 貴芳 | ||
| 金沢医科大学病院 | ||
| 形成外科 |
| 医師 | ||
| 柳下 幹男 | ||
| 金沢医科大学病院 | ||
| 形成外科 |
| 医師 | ||
| 坂上 陽彦 | ||
| 金沢医科大学病院 | ||
| 形成外科 |
| 医師 | ||
| 牧本 和彦 | ||
| 金沢医科大学病院 | ||
| 形成外科 |
| 医師 | ||
| 東山 麻伊子 | ||
| 金沢医科大学病院 | ||
| 形成外科 |
| 医師 | ||
| 黒田 友美 | ||
| 金沢医科大学病院 | ||
| 形成外科 |
| 金沢医科大学病院 | ||
| 真田 亮子 | ||
| 金沢医科大学病院 | ||
| 臨床試験治験センター | ||
| 金沢医科大学総合医学研究所 | ||
| 丹羽 修 | ||
| 金沢医科大学総合医学研究所 | ||
| 臨床試験支援室 | ||
(3)多施設共同研究に関する事項
(3)多施設共同研究に関する事項
| 無 |
3 再生医療等に用いる細胞の入手の方法並びに特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法等
3 再生医療等に用いる細胞の入手の方法並びに特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法等
(1)再生医療等に用いる細胞の入手の方法(特定細胞加工物を用いる場合のみ記載)
(1)再生医療等に用いる細胞の入手の方法(特定細胞加工物を用いる場合のみ記載)
| 多血小板血漿(自家) | |
| 再生医療等提供機関と同じ | |
| 細胞提供者と投与を受ける者が同一のため、再生医療等を受ける者の基準と同一である。 <選択基準> 従来の治療でも改善を認めない、または増悪傾向を示す難治性皮膚潰瘍例で、身体の状態などにより手術による治療が困難な患者のうち、本研究参加にあたり十分な説明を受けた後、十分な理解の上、患者本人の自由意思による文書同意が得られた20歳以上の患者 ①通常の保守的加療に抵抗性を有する難治性潰瘍 ②切断・植皮術等の外科的処置を患者自身が拒否する症例もしくは麻酔科医が手術不適応と判断する程度の全身状態不良患者 ③PRPの調製のための採血が可能な患者 ④20以上の成人であること ⑤PRP調製のための採血を行うまでに被験者本人(または代諾者)から書面による同意が得られている患者 <除外基準> 高度な貧血や血小板減少、その他、試験責任(分担)医師が被験者として不適当と判断した患者 ①創傷面の感染を制御できない患者(層部の色、膿汁の色、臭いで感染が疑われる場合に、菌培養を行い感染の有無を判定) ②創傷面(潰瘍部)に悪性腫瘍を合併している患者 ③著しい貧血症例(男女ともHb 7g/dL未満) ④白血病 ⑤不良性貧血 ⑥血小板減少症 ⑦血液凝固異常と診断された患者 ⑧医師の指示に従うことができない患者 ⑨PRP療法に同意が得られない患者 |
|
| 細胞提供者と投与を受ける者が同一のため、再生医療等を受ける者の基準と同一である。 選択及び除外基準を確認した患者のうち、治療に問題となる事項がなければ、末梢血採取しPRP作製し投与が可能であることを実施医師が判断する。 | |
| 当院の手術室にて、患者本人から30~最大60mLの末梢血を採取し、オートメーション化された自己血小板遠心分離機(Magellan®;Arteriocyte Medical Systems, Inc.,Cleveland,USA)により遠心分離を行うことで自己多血小板血漿を分取する。 |
(2)特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法(特定細胞加工物等を用いる場合のみ記載)
(2)特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法(特定細胞加工物等を用いる場合のみ記載)
| 多血小板血漿(自家) | ||
| 【採取した細胞の加工方法】 【PRP調製方法】 1.採血 50mLシリンジに抗凝固剤(輸血用10%クエン酸Na注射液)を体積あたり10%含有 する注射器で、21G翼 状針を用いて最大60mL採血を行う。 2.PRP分離容器を用いたPRP調製 PRP調製技術員は別途定める手順書に従いPRP調製を行う。 オートメーション化された自己血小板遠心分離機(Magellan® ;Arteriocyte Medical Systems,Inc.,Clevel and,USA)によりPRPを得る。 ※品質管理について 本研究で用いる自己血小板遠心分離機は、医療機器として薬事承認(承認番号:23 100BZX00024000)を受けていること、また採血からPRPを得るまで閉鎖的に調整 されることにより、特段の品質試験は行わない。 【PRP保存・管理】 1.保存 初回投与後、余剰PRPは、滅菌保管容器に封入し、患者識別コードを付け(ラベ ル貼付)、-80℃の冷凍庫で保存・保管する 2.管理 PRP調製技術員は、PRPの冷凍庫(鍵付)への入・出庫をPRP分離容器の入出管 理台帳に記入し管理する。なお、保管期間は4週間とし、保管されたPRPが不足 している場合は、改めて採血を行い調整する。 3.PRPの廃棄 投与終了、中止等の事象により未使用のPRPについては、医療用廃棄物として適 切に処理する。なお、医療用廃棄物として適切に処理する際は、その旨を記載し た書類を医師が作成し記録を残す。 |
||
| 当院手術室にて、作製したPRPを潰瘍面の壊死組織除去を可能な範囲で除去し、創面の新鮮化を図った後、PRPを創部に塗布もしくは、創傷被覆材に浸漬貼付する。 | ||
| 無 | ||
| 金沢医科大学病院 | ||
| FC4150042 | ||
| 金沢医科大学病院 手術室 | ||
| 該当なし | ||
(3)再生医療等製品等に関する事項(再生医療等製品を用いる場合のみ記載)
(3)再生医療等製品等に関する事項(再生医療等製品を用いる場合のみ記載)
(4)再生医療等に用いる未承認又は適応外の医薬品又は医療機器に関する事項(未承認又は適応外の医薬品又は医療機器を用いる場合のみ記載)
(4)再生医療等に用いる未承認又は適応外の医薬品又は医療機器に関する事項(未承認又は適応外の医薬品又は医療機器を用いる場合のみ記載)
4 再生医療等技術の安全性の確保等に関す措置
4 再生医療等技術の安全性の確保等に関す措置
(1)利益相反管理に関する事項
(1)利益相反管理に関する事項
① 再生医療等に対する特定細胞加工物等製造事業者からの研究資金等の提供その他の関与
① 再生医療等に対する特定細胞加工物等製造事業者からの研究資金等の提供その他の関与
| 無 | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
② 再生医療等に対する医療薬品等製造販売業者等からの研究資金等の提供その他の関与
② 再生医療等に対する医療薬品等製造販売業者等からの研究資金等の提供その他の関与
| 無 | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
③ 再生医療等に対する特定細胞加工物等製造事業者又は医療品等製造販売業者等以外からの研究資金
③ 再生医療等に対する特定細胞加工物等製造事業者又は医療品等製造販売業者等以外からの研究資金
| 無 | ||
(2)その他再生医療等技術の安全性の確保等に関する措置
(2)その他再生医療等技術の安全性の確保等に関する措置
| 血小板は創傷治癒の第一段階に出現し、創傷治癒を開始する働きをする。さらに血小板内に多く含まれるα顆粒中には、組織再生や創傷治癒に効果的であるPDGF(血小板由来増殖因子)、TGF-β(形質転換成長因子)、EGF(上皮細胞成長因子)、IGF(インスリン様増殖因子)などの成長因子が豊富に存在し、脱顆粒によりこれら成長因子が放出される。PRPは、この血小板を濃縮した血漿であり、これを治療に応用した最初の報告は、骨移植の際にPRPを添加し、骨再生が促進されるというものであった。その後、外傷性、糖尿病性など様々な難治性潰瘍の局所治療にも用いられ、安全かつ組織再生や創傷治癒に極めて有効性が高いとする報告がなされている。 本治療は、日本国内においても、先進医療として承認され、当院でも先進医療(多施設共同)として6例の難治性潰瘍症例に対して臨床応用がなされ、良好な結果を得ている。 |
||||||
| PRPを用いて治療を行うことにより、利益としては潰瘍治癒の促進、肉芽形成促進、上皮化促進効果が期待される。起こりうる不利益としては自己PRPを難治性潰瘍の肉芽組織形成促進の目的で用いる技術であり、採血からPRP作成過程及び保存時の無菌操作において感染の可能性は極めて低いものの皆無ではない。ただし、過去に本治療により深刻な感染を合併したとの報告はない。 | ||||||
| 細胞提供者の選定方法、品質確認事項等に従い、細胞提供者の健康状態を十分に把握して問題ないと実施医師が判断した際に投与可とする。 | ||||||
| 患者に疑義の内容に応じた説明や検査を実施すると共に、必要に応じて適切な処置を行う。また、必要に応じて、他の医療機関を紹介する(セカンドオピニオン)等の適切な対応を行う。疑義の内容については実施責任者および管理者へ報告し、疾病等における規定に沿い速やかに報告を行う。 | ||||||
| 細胞加工物の一部の保存については、無菌操作が閉鎖式操作のみで行われ、培養工程を伴わず、短時間の操作で人体への特定細胞加工物の投与が行われる場合であって操作の無菌性が確保されていることから保存の必要性はないと考える。 | ||||||
| 該当なし | ||||||
| (1)有害事象発生時の被験者の対応 研究責任者又は分担者は有害事象を認めたときは、直ちに適切な処置を行うとともに、カルテ並びに症例報告書に齟齬なく記載する。また介入対象の治療を中止した場合や、有害事象に対する治療が必要となった場合には、被験者にその旨を伝える。 (2)重篤な有害事象の報告 認定再生医療等委員会および厚生労働省へ報告義務のある疾病等 【7日以内に報告義務のある症例】 明らかに本療法によるものと疑われるもの、本療法によるものと疑われる感染症によるもののうち、以下のいずれかに該当する疾病等については、管理者は当該疾病等の発生を知ってから7日以内に、指定された「疾病等報告書」を作成し、認定再生医療等委員会および厚生労働省へ提出する。 1)死亡例 2)死亡につながる恐れのある症例(生命を脅かすもの) 【15日以内に報告義務のある症例】 明らかに本療法によるものと疑われるもの、本療法によるものと疑われる感染症によるもののうち、以下のいずれかに該当する疾病等については、管理者は当該疾病等の発生を知ってから15日以内に、指定された「疾病等報告書」を作成し、認定再生医療等委員会および厚生労働省へ提出する。 1)治療のために医療機関への入院または入院期間の延長が必要とされる症例 2)障害 3)障害につながるおそれのある症例 4)重篤である症例 5)後世代における先天性の疾病または異常 その他の認定再生医療等委員会への報告義務のある疾病等 「認定再生医療等委員会および厚生労働省へ報告義務のある疾病等」に記載された症例以外で、明らかに本療法によるものと疑われるもの、本療法によるものと疑われる感染症によるもののうち、上記のいずれにも該当しない疾病等の発生については、管理者は本再生医療等提供計画を厚生大臣に提出した日から起算して、60日ごとに当該期間満了後10日以内に指定された「疾病等報告書」を作成し、認定再生医療等委員会へ提出する。 また、不適合(重大な不適合を含む)を認めた場合は、速やかに研究代表者等に報告し、報告を受けた者は認定再生医療等委員会へ報告を行い適切な措置を講ずる。 研究責任者は、試験期間中の全ての重篤な有害事象、試験終了(中止)後に本研究との関連性が疑われる重篤な有害事象について、速やかに病院長に報告する。 |
||||||
| <他覚所見の確認> PRP療法の効果は、下記の観察評価項目を設定し、PRP療法期間中、投与時、投与後は投与後1週、4週、3ヵ月、6ヵ月を目安に評価する。創部の状態に応じて開始後1週ごとに、対象者の同意を得た上で、追加のPRP療法を施行する。観察および実施期間は4週とするが、効果を認め、対象者が本研究の継続を希望する場合には、8週を限度にこの期間を延長する。 <治療観察評価項目> ①赤み ⑥肉芽形成 ②浮腫性 ⑦上皮形成 ③浸出液の量 ⑧潰瘍面積 ④出血 ⑤疼痛 *上記①-⑦の評価項目は、肉眼的観察およびデジタルカメラでの記録により定性的に評価する。これらをもとに総合的に評価し効果判定を行う。 *創部の汚染や、感染を疑う所見を認めた場合には、細菌検査を行う。 <有害事象の確認> 有害事象には、各種検査値異常も含める。内容、発現時期・消失時期、程度、処置、転帰、重篤性評価、試験薬との関連性等をカルテに記載する。必要があれば追跡調査する。程度については、副作用評価基準によるグレード1〜4によるか、あるいは、1)軽度:無処置で投与継続可能な状態、2)中等度:何らかの処置により投与継続可能な状態、3)重度:投与を中止あるいは中止すべき状態などと定義する。 重篤性評価は、「14.有害事象の取り扱い(2)重篤な有害事象の報告)で定義し、該当する場合は速やかに報告することを記載する。有害事象の評価には、MedDRA/J (Medical Dictionary for Regulatory Activities/J:ICH国際医薬用語集日本語版、厚生労働省の副作用症例報告書に使用する副作用等用語として採用されている、有料会員制、http://www.sjp.or.jp/08/01.htm)、あるいは米国National Cancer Institute の有害事象共通用語規準(Common Terminology Criteria for Adverse Events, CTCAE)日本語版(JCOG版、http://plaza.umin.ac.jp/thymus/JART01/jcog.pdf)を用いることも考慮する。 なお、有害事象等の発生による中止症例等については、継続的に最善の措置を講ずるよう努める。 |
||||||
| PRP療法期間中、投与時、投与後は投与後1週、4週、3ヵ月、6ヵ月を目安に通院にて経過観察を行う。創部の状態に応じて開始後1週ごとに、対象者の同意を得た上で、追加のPRP療法を施行する。観察および実施期間は4週とするが、効果を認め、対象者が本研究の継続を希望する場合には、8週を限度にこの期間を延長する。研究終了後も被験者が研究の結果により得られた最善の予防、診断及び治療を受けるよう努める。なお、再生医療等を受けた者の連絡先については複数把握し、来院がない場合には連絡を行い、可能な限り情報の把握に努める。 | ||||||
| 有 | ||||||
| 実施計画の公表日 | ||||||
| 2019年03月19日 | ||||||
| 研究終了 | Complete | |||||
5 細胞提供者及び再生医療等を受ける者に対する健康被害の補償の方法
5 細胞提供者及び再生医療等を受ける者に対する健康被害の補償の方法
細胞提供者について(特定細胞加工物を用いる場合のみ記載)
細胞提供者について(特定細胞加工物を用いる場合のみ記載)
| 有 |
再生医療等を受ける者について
再生医療等を受ける者について
| 有 |
6 審査等業務を行う認定再生医療等委員会に関する事項
6 審査等業務を行う認定再生医療等委員会に関する事項
| 金沢医科大学認定再生医療等委員会 | Kanazawa Medical University Certified Committee for Regenerative Medicine | |
| NB4150006 | ||
| 石川県河北郡内灘町字大学一丁目1番地 | 1-1 Daigaku, Uchinada, Kahoku, Ishikawa JAPAN, Ishikawa | |
| 076-218-8200 | ||
| regene@kanazawa-med.ac.jp | ||
| 第三種再生医療等のみを審査することができる構成 | ||
| 適 | ||
| 2017年02月24日 | ||
7 その他
7 その他
| 診療情報は通常診療と同様に電子カルテに保管される。また、治療実施に係る資料等を取り扱う際は、患者の個人情報等は無関係の番号を付して管理し、被験者の秘密保持に十分配慮する。治療の結果を公表する際は、被験者を特定できる情報を含まないようにする。また、治療の目的以外に、治療で得られた患者の試料等を使用しない。 | ||
| 再生医療等の提供に係る関係者は年数回程度の学術集会への参加により情報収集および情報交換を行う。 | ||
| 本研究の苦情及び問い合わせ窓口は以下の通りとし、受付者は速やかに代表管理者等に連絡し、適切な対応を検討する。 【苦情及び問い合わせ窓口】 金沢医科大学形成外科 外来076-286-3511 (内線)4168 受付時間:月~金 9:00~17:00(開学記念日・土・祝祭日は除く) 【委員会への問い合わせ窓口】 金沢医科大学認定再生医療等委員会 事務局 076-218-8200 受付時間:月~金 9:00~17:00(開学記念日・土・祝祭日は除く) |
||
| 非該当 | ||
| なし | none | |
| 無 | ||
| 非該当 | ||
| 非該当 | ||
| 非該当 | ||
添付資料
添付資料
| 4 再生医療等を受ける者に対する説明文書及び同意文書の様式 | ⑦PRP説明・同意文書‗第4版‗20200108.pdf |
|---|