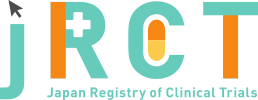臨床研究等提出・公開システム
再生医療等提供計画情報の詳細情報です。
| 第三種 | ||
| 令和4年6月24日 | ||
| 令和7年4月11日 | ||
| 慢性膵炎等に対する膵全摘術に伴う自家膵島移植の臨床試験 | ||
| 自家膵島移植臨床試験 | ||
| 国立健康危機管理研究機構国立国際医療センター | ||
| 宮嵜 英世 | ||
| 疼痛コントロール困難な慢性膵炎および膵動静脈奇形に対して膵全摘術を行うとともに、併せて膵島の自家移植を行い、従来膵全摘を行うと必然的に生じる膵性糖尿病を、移植膵島から分泌する内因性インスリンにより軽減する。対象である慢性膵炎患者は日本に6-7万人とされる。 | ||
| 2 | ||
| 慢性膵炎(遺伝性膵炎含む)および膵動静脈奇形 | ||
| 募集中 | ||
| 国立健康危機管理研究機構認定再生医療等委員会 | ||
| NB3150046 | ||
変更内容
変更内容
| 再生医療等提供機関(再生医療等の提供を行う医療機関) | ||
| 名称:国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院 | ||
| 名称:国立健康危機管理研究機構国立国際医療センター | ||
| 令和7年4月1日 | ||
| 実施責任者の連絡先 | ||
| 所属機関:国立国際医療研究センター病院 | ||
| 所属機関:国立国際医療センター | ||
| 令和7年4月1日 | ||
| 実施責任者の連絡先 | ||
| Affiliation:Center Hospital of National Center for Global Health and Medicine | ||
| Affiliation:National Center for Global Health and Medicine | ||
| 令和7年4月1日 | ||
| 実施責任者の連絡先 | ||
| 電子メールアドレス:mshimoda@hosp.ncgm.go.jp | ||
| 電子メールアドレス:shimoda.m@jihs.go.jp | ||
| 令和7年4月1日 | ||
| 事務担当者の連絡先 | ||
| 所属機関:国立国際医療研究センター | ||
| 所属機関:国立国際医療センター | ||
| 令和7年4月1日 | ||
| 事務担当者の連絡先 | ||
| Affiliation:Center Hospital of National Center for Global Health and Medicine | ||
| Affiliation:National Center for Global Health and Medicine | ||
| 令和7年4月1日 | ||
| 事務担当者の連絡先 | ||
| 電子メールアドレス:mtsuchida@hosp.ncgm.go.jp | ||
| 電子メールアドレス:tsuchida.m@jihs.go.jp | ||
| 令和7年4月1日 | ||
| 再生医療等を行う医師又は歯科医師 | ||
| 所属機関:国立国際医療研究センター | ||
| 所属機関:国立国際医療センター | ||
| 令和7年4月1日 | ||
| 再生医療等を行う医師又は歯科医師 | ||
| 所属機関:国立国際医療研究センター | ||
| 所属機関:国立国際医療センター | ||
| 令和7年4月1日 | ||
| 再生医療等を行う医師又は歯科医師 | ||
| 所属機関:国立国際医療研究センター | ||
| 所属機関:国立国際医療センター | ||
| 令和7年4月1日 | ||
| 再生医療等を行う医師又は歯科医師 | ||
| 所属機関:国立国際医療研究センター | ||
| 所属機関:国立国際医療センター | ||
| 令和7年4月1日 | ||
| 再生医療等を行う医師又は歯科医師 | ||
| 所属機関:国立国際医療研究センター | ||
| 所属機関:国立国際医療センター | ||
| 令和7年4月1日 | ||
| 再生医療等を行う医師又は歯科医師 | ||
| 所属機関:国立国際医療研究センター | ||
| 所属機関:国立国際医療センター | ||
| 令和7年4月1日 | ||
| 統計解析担当機関 | ||
| 国立国際医療研究センター | ||
| 国立健康危機管理研究機構 | ||
| 令和7年4月1日 | ||
| 統計解析担当機関 | ||
| 所属機関:国立国際医療研究センター | ||
| 所属機関:国立健康危機管理研究機構 | ||
| 令和7年4月1日 | ||
| 細胞培養加工施設 | ||
| 細胞培養加工施設の名称:国立国際医療研究センター病院細胞調整管理室 | ||
| 細胞培養加工施設の名称:国立国際医療センター細胞調整管理室 | ||
| 令和7年4月1日 | ||
| 6 審査等業務を行う認定再生医療等委員会に関する事項 | ||
| 当該再生医療等について審査等業務を行う認定再生医療等委員会の名称:国立国際医療研究センター認定再生医療等委員会 | ||
| 当該再生医療等について審査等業務を行う認定再生医療等委員会の名称:国立健康危機管理研究機構認定再生医療等委員会 | ||
| 令和7年4月1日 | ||
| 6 審査等業務を行う認定再生医療等委員会に関する事項 | ||
| Name of Certified Review Board:Certified Committee for Regenerative Medicine of National Center for Global Health and Medicine | ||
| Name of Certified Review Board:Certified Committee for Regenerative Medicine of Japan Institute for Health Security | ||
| 令和7年4月1日 | ||
| 6 審査等業務を行う認定再生医療等委員会に関する事項 | ||
| 電子メールアドレス:saisei@hosp.ncgm.go.jp | ||
| 電子メールアドレス:saisei@jihs.go.jp | ||
| 令和7年4月1日 | ||
| 7 その他 | ||
| 個人情報の取扱いの方法:本研究で知り得た個人情報および臨床情報などのプライバシーに関する情報は、個人の人格尊重の理念の下、厳重に保護 され慎重に扱われるべきものと認識し、プライバシー保護に努める。本研究により得られたデータは、連結可能匿名化され「個人情報の保護に関する法律」(平成15年 5月)に 準拠し、「国立研究開発法人国立国際医療研究センターの保有する個人情報の保護に関する規程」により運用する。 | ||
| 個人情報の取扱いの方法:本研究で知り得た個人情報および臨床情報などのプライバシーに関する情報は、個人の人格尊重の理念の下、厳重に保護 され慎重に扱われるべきものと認識し、プライバシー保護に努める。本研究により得られたデータは、連結可能匿名化され「個人情報の保護に関する法律」(平成15年 5月)に 準拠し、「国立健康危機管理研究機構国立国際医療センターの保有する個人情報の保護に関する規程」により運用する。 | ||
| 令和7年4月1日 | ||
| 7 その他 | ||
| 苦情及び問合せへの対応に関する体制の整備状況:研究責任者、コーディネーター等が対応する。電話メールによる 受け付けも可能。 日中:問い合わせ窓口:国立国際医療研 究センター膵島移植プロジェクト: 03-3202-7181 内線2776 休日・ 夜間:緊急連絡先:国立国際医療研究センター夜間休日受付03-3202-7181 | ||
| 苦情及び問合せへの対応に関する体制の整備状況:研究責任者、コーディネーター等が対応する。電話メールによる 受け付けも可能。 日中:問い合わせ窓口:国立国際医療センター膵島移植プロジェクト: 03-3202-7181 内線2776 休日・ 夜間:緊急連絡先:国立国際医療センター夜間休日受付03-3202-7181 | ||
| 令和7年4月1日 | ||
| 47 その他(本文中に掲載しきれない説明書類等) | ||
| 開設許可事項事項一部変更届_202504.pdf | ||
| 令和7年4月1日 | ||
1 提供しようとする再生医療等及びその内容
1 提供しようとする再生医療等及びその内容
申請者情報
申請者情報
| 令和7年4月10日 | |||
| jRCTc030220161 | |||
| 国立健康危機管理研究機構国立国際医療センター | |||
| 東京都新宿区戸山1-21-1 | |||
| 宮嵜 英世 | Miyazaki Hideyo | ||
(1)再生医療等の名称及び分類
(1)再生医療等の名称及び分類
| 慢性膵炎等に対する膵全摘術に伴う自家膵島移植の臨床試験 | A Study of Pancreatectomy with Autologous Islet Transplantation for Treatment of Chronic Pancreatitis( Auto-I ) | ||
| 自家膵島移植臨床試験 | A Study of Pancreatectomy with Autologous Islet Transplantation for Treatment of Chronic Pancreatitis( Auto-I ) | ||
| 第三種 | |||
| 患者自身の細胞であり、幹細胞でなく、遺伝子導入せず、培養せず、相同利用である細胞加工物を用いた再生医療等技術 の範囲であると判断されるため。 | |||
(2)再生医療等の内容
(2)再生医療等の内容
| 疼痛コントロール困難な慢性膵炎および膵動静脈奇形に対して膵全摘術を行うとともに、併せて膵島の自家移植を行い、従来膵全摘を行うと必然的に生じる膵性糖尿病を、移植膵島から分泌する内因性インスリンにより軽減する。対象である慢性膵炎患者は日本に6-7万人とされる。 | |||
| 2 | |||
| 2022年06月24日 | |||
| 2029年03月31日 | |||
| 10 | |||
| 介入研究 | Interventional | ||
| 単一群 | single arm study | ||
| 非盲検 | open(masking not used) | ||
| 非対照 | uncontrolled control | ||
| 単群比較 | single assignment | ||
| 治療 | treatment purpose | ||
| 1.研究参加に関して文書による同意が得られた者 2.同意取得時の年齢が18歳以上、70歳以下の男女 3.膵全摘術が適応となりうる良性膵疾患のうち疼痛を伴う慢性膵炎(遺伝性膵炎含む)および膵動静脈奇形と診断されている者 4.前治療として保存的治療、神経ブロック、内視鏡的治療または外科的治療を受けているが、無効または不十分な効果または一時的な効果に過ぎなかった者 | 1. A written consent can be obtained. 2. Age is between 18 and 70 years old. 3. Diagnosis of chronic pancreatitis or pancreatic arteriovenous malformation 4.Previous conservative treatment, celiac plexus block, endoscopic treatment or surgical treatment were ineffective. | ||
| 1. 体重が100kgを超えている。もしくは、BMIが30kg/m2 を超えている。 2. インスリン必要量が0.8IU/kg/日以上、あるいは 55U/日以上。 3. 1型糖尿病と診断されている患者。 4. 過去1年間に複数回測定したHbA1c値(NGSP値)の平均値が10%以上。 5. 血圧:収縮期血圧が160mmHgあるいは拡張期血圧が100mmHg超えている(治療後は除外項目としない)。 6. eGFR 30ml/min/1.73㎡以下。 7. 妊娠中または授乳中である者。 8. 以下の活動性感染症がある。B型肝炎、C型肝炎あるいは結核を含む抗酸菌症。具体的にはキャリアを含むHBs抗原あるいはHBV-DNAの陽性者、HCV抗体陽性者あるいはHCV-RNA陽性者。結核を含む抗酸菌症に関しては、クオンティフェロン検査が陽性の場合、あるいは胸部CTにて潜在性結核感染症(Latent tuberculosis infection: LTBI)や非定型抗酸菌症が疑われる場合、抗酸菌症を疑って薬物治療が行われている場合をもって活動性感染症とみなす。ツベルクリン反応は特に参考としない。 9. 担癌患者。ただし、治療後で無再発と診断されている者は除外しない。 10. 現在アルコール依存症あるいは薬物依存症を有している(治療後は除外項目としない)。アルコールに関しては、久里浜式アルコール依存症スクリーニングテスト(※)で0.0以上を除外基準とする。また、登録前3ヶ月は禁酒していることが必要で、禁酒できていない場合は除外とする。 11. 血中ヘモグロビン値<10 g/dL。ただし、術中に輸血を予定している場合は除外しない。 12. 凝固障害がある、もしくは移植した後も長期にわたって抗凝固剤(ワーファリンなど)の投与が必要となる医学上の状態を有する患者(低用量のアスピリン治療の場合には許容できる)、またはプロトロンビン時間のINR(International Normalized Ratio)値が1.5を超えている者。 13. 重度の併存する心疾患を有する場合。以下のいずれかの状態: ① 最近(過去6ヶ月以内に)発症した心筋梗塞。 ② 過去6ヶ月以内に心機能検査において診断された虚血障害。 ③ 左心室のejection fractionが30%未満。 14. 臨床試験参加時に肝機能検査値が持続的に高値を示すもの。すなわちSGOT(AST),SGPT(ALT),あるいは総ビリルビン値が、正常値上限の2倍以上の高値が持続している。ただし、肝機能検査値の上昇が、他の基質的疾患がなく、膵炎の症状抑制目的の食事制限や消化吸収障害などに起因した脂肪肝が原因と考えられる場合には、本治療により改善が見込まれるため、除外しない。 15. 門脈圧亢進症または肝線維症と診断されている者。 16. 膵腫瘍を認める者。 17. 重度の頻回な下痢、嘔吐あるいは潜在的に経口薬剤の吸収を障害する可能性のある胃腸障害を有する(治療後は除外項目としない)。 18. 臨床試験参加の4週間以内に何らかの臨床試験中の薬剤の投与を受けた者。 19. 臨床試験遂行に必要な検査のための入院、定期的な外来通院が不可能である者。 20. 臨床試験遂行に問題となる精神的異常を有している者。 21. 研究責任者または分担者が研究への組み入れを不適切と判断した者。 | 1. BW >100kg or BMI >30 kg/m2. 2. Insulin requirement >0.8IU/kg/day or >55U/day. 3. Type 1 diabetes. 4. HbA1c>10%. 5. Systolic blood pressure >160 mmHg or diastolic blood pressure >100 mmHg. 6. eGFR >30ml/min/1.73m2. 7. Pregnancy or breastfeeding. 8. Active infections, Hepatitis B, hepatitis C or mycobacteriosis including tuberculosis. 9. Malignant tumor. However, those who have been diagnosed as recurrence-free after treatment are not excluded. 10. Alcoholism or drug dependency 11. Hb<10 g/dL. However, this does not exclude cases where blood transfusion is planned during surgery. 12. Coagulopathy. 13. Severe heart disease. 14. Liver dysfunction. 15. Portal vein hypertension or liver fibrosis. 16. Pancreatic tumor. 17. Gastrointestinal disorders with impair oral drug absorption. 18. Participant in another clinical trial. 19. Patients who are unable to make regular outpatient visits. 20. Mental illness. 21. Patients who are judged to be inappropriate by clinical trial investigators. | ||
| 18歳 以上 | 18age old over | ||
| 70歳 以下 | 70age old under | ||
| 男性・女性 | Both | ||
| ・被験者が同意を撤回した場合 ・被験者が妊娠した場合 ・原疾患の増悪の場合 ・その他にリスクが利益を上回ると研究責任者が判断した場合 | |||
| 慢性膵炎(遺伝性膵炎含む)および膵動静脈奇形 | Chronic pancreatitis and pancreatic arteriovenous malformation | ||
| 慢性膵炎 膵動静脈奇形 | Chronic pancreatitis and pancreatic arteriovenous malformation | ||
| 有 | |||
| 膵臓を摘出後定められた手順書に基づいて膵島分離を行い、その調整膵島を膵臓を摘出した被験者本人の門脈内へ注入し、膵島移植を行う。 | After pancreatectomy, islets are isolated and injected into the portal vein of the subject. | ||
| 治療半年後(180日±14(日後)評価において血糖コントロールが良好な患者の割合とする。血糖コントロール良好とは、以下の①、②、③のすべてを満たした場合と定義する。 ①空腹時血中c-ぺプチド≧0.1ng/mL ②HbA1c値(NGSP値) <7.4%もしくは術前から糖尿病を合併する場合はHbA1c値(NGSP値)が術前値プラス1.0%未満 ③術後30日後から半年後まで重症低血糖発作を起こさなかった | The ratio of patients with good glycemic control 6 months after treatment (180 +/- 14 days). blood glucose control is defined as satisfying all of the following 1, 2 and 3. 1. Fasting blood c-peptide >= 0.1 ng / mL. 2. HbA1c value <7.4% or HbA1c value <preoperative value + 1.0% in case of diabetes before treatment 3. No severe hypoglycemic attack from 30 days to 6 months after treatment | ||
| 1) 膵臓に起因する疼痛が改善した(Izbicki pain scoreが術前値より減少またはペインスコアが術前値より減少)患者の割合 2) 重症低血糖発作を起こさず血糖コントロールが良好な患者の割合。すなわち、HbA1c値(NGSP値) <7.4%もしくは術前から糖尿病を合併する場合はHbA1c値(NGSP値)が術前値プラス1.0%未満で、かつ術後30日後から半年後まで重症低血糖発作を起こさなかった患者の割合である。 3) 鎮痛薬の使用が不要となった患者の割合 4) 鎮痛薬の種類と投与量 5) SF-36およびQLQ30-PAN26(CP)によるQOLの評価 6) 数値的評価スケールによるペインスコア(直前7日間の平均) 7) 体重、BMI 8) 消化酵素薬の投与量 9) インスリン導入症例の割合 10) インスリン使用量 11) HbA1c値(NGSP値) 12) 空腹時血糖値と血中C-peptide値 13) 混合食負荷試験刺激時血中C-peptide値および血中グルカゴン値 14) β-score 15) SUITO Index 16) OGTT2時間値 17) Insulinogenic Indexの値 18) 無自覚低血糖の回数 19) 重症低血糖発作の回数 20) 栄養評価 (血清総蛋白、アルブミン、プレアルブミン、総コレステロール、トランスフェリン、レチノール結合蛋白、ビタミンE、利き手握力) 21) 一次登録症例のうち二次登録した症例の割合 安全性評価項目: • 安全性評価項目として、有害事象を評価する。 |
1) Percentage of patients with improved pancreatic pain (Izbicki pain score lower than preoperative value or Pain score lower than preoperative value) 2) Percentage of patients with good glycemic control without severe hypoglycemia. 3) Percentage of patients who do not need analgesics 4) Types and doses of analgesics 5) Evaluation of QOL by SF36 and QLQPAN28 (CP) 6) Pain score by numerical rating scale (average of last 7 days) 7) Body weight and BMI 8) Dosage of digestive enzymes 9) Percentage of insulin depencent cases 10) Insulin dose 11) HbA1c value (NGSP value) 12) Fasting blood glucose level and C-peptide level 13) stimulated serum C-peptide and glucagon level 14) beta-score 15 SUITO Index 16) OGTT 120 minutes value 17) Insulinogenic Index value 18) Presence of hypoglycemia unawareness 19) Presence of severe hypoglycema 20) Nutritional evaluation (serum total protein, albumin, prealbumin, total cholesterol, transferrin, retinol binding protein, vitamin E, hand grip strength) 21) Proportion of secondary registration cases among primary registration cases Adverse event rate | ||
| 摘出された膵臓を速やかにバックテーブルへ運び、原則十二指腸および脾臓を除去した後に主膵管へカニューレを挿入し臓器保護液を注入する。その後、 臓器保存液の入ったコンテナを使用して膵臓を細胞調整施設(CPC)へ搬送する。CPC にて膵島分離を行う。分離された膵島を点滴バッ グに封入し、手術室へ搬送する。腸間膜静脈等にカテーテルを挿入し、先端を門脈本管に留置して門脈圧をモニターしながら点滴にて膵島を肝臓内に移植する。 | |||
2 人員及び構造設備その他の施設等
2 人員及び構造設備その他の施設等
(1)人員及び構造設備その他の施設に関する事項
(1)人員及び構造設備その他の施設に関する事項
| 医師 | |||||
| 霜田 雅之 | Shimoda Masayuki | ||||
| 国立国際医療センター | National Center for Global Health and Medicine | ||||
| 病院肝胆膵外科/研究所膵島移植企業連携プロジェクト | |||||
| 162-8655 | |||||
| 東京都新宿区戸山1-21-1 | 1-21-1 Toyama Shinjyuku-ku,Tokyo | ||||
| 03-3202-7181 | |||||
| shimoda.m@jihs.go.jp | |||||
| 自施設 | |||||
| 救急医療に必要な施設又は設備の内容(他の医療機関の場合はそ の医療機関の名称及び施設又は設備の内容) 救急科医師が常勤しており、救急科・救命救急センター(3 0床)を有する。X線装置、CT、心電計、輸血・輸液のため の設備、その他救急医療を行うために必要な設備を有する。 また、救急医療を要する傷病者のための専用病床を有する。 | |||||
(2)その他研究の実施体制に関する事項
(2)その他研究の実施体制に関する事項
| 土田 みゆき | Tsuchida Miyuki | ||||
| 国立国際医療センター | National Center for Global Health and Medicine | ||||
| 研究所膵島移植企業連携プロジェクト | |||||
| 162-8655 | |||||
| 東京都新宿区戸山1-21-1 | 1-21-1 Toyama Shinjyuku-ku,Tokyo | ||||
| 03-3202-7181 | |||||
| 03-5273-6885 | |||||
| tsuchida.m@jihs.go.jp | |||||
| 医師 | ||
| 稲垣 冬樹 | ||
| 国立国際医療センター | ||
| 病院肝胆膵外科 |
| 医師 | ||
| 栁瀨 幹雄 | ||
| 国立国際医療センター | ||
| 病院消化器内科 |
| 医師 | ||
| 小谷 紀子 | ||
| 国立国際医療センター | ||
| 病院糖尿病内分泌代謝科 |
| 医師 | ||
| 中條 大輔 | ||
| 国立国際医療センター | ||
| 病院糖尿病内分泌代謝科 |
| 医師 | ||
| 山本 夏代 | ||
| 国立国際医療センター | ||
| 病院消化器内科 |
| 医師 | ||
| 霜田 雅之 | ||
| 国立国際医療センター | ||
| 肝胆膵外科/研究所膵島移植企業連携プロジェクト |
| 国立国際医療研究センター | ||
| 大栁 一 | ||
| 国立国際医療研究センター | ||
| 臨床研究センター JCRACデータセンター | ||
| 国立国際医療研究センター | ||
| 矢野 里奈 | ||
| 国立国際医療研究センター | ||
| 臨床研究センター臨床研究推進部 | ||
| 国立国際医療研究センター | ||
| 久保田 晴久 | ||
| 国立国際医療研究センター | ||
| 臨床研究センター臨床研究品質保証グループ | ||
| 国立健康危機管理研究機構 | ||
| 上村 夕香理 | ||
| 国立健康危機管理研究機構 | ||
| 臨床研究センター データサイエンス部 生物統計研究室 | ||
| 非該当 | |||
(3)多施設共同研究に関する事項
(3)多施設共同研究に関する事項
| 有 |
| 京都大学医学部附属病院 | ||||||
| 京都府京都市左京区聖護院川原町54 | ||||||
| 075-751-3111 | ||||||
| 髙折 晃史 | ||||||
| 波多野 悦朗 | Hatano Etsuro | |||||
| 京都大学医学部附属病院 | Kyoto Univercity Hospital | |||||
| 肝胆膵・移植外科 | ||||||
| 606-8507 | ||||||
| 京都府京都市左京区聖護院川原町54 | ||||||
| 075-751-3111 | ||||||
| etsu@kuhp.kyoto-u.ac.jp | ||||||
| 穴澤 貴行 | ||||||
| 京都大学医学部附属病院 | ||||||
| 肝胆膵・移植外科 | ||||||
| 606-8507 | ||||||
| 京都府京都市左京区聖護院川原町54 | ||||||
| 075-751-4323 | ||||||
| 075-751-4348 | ||||||
| anazawa@kuhp.kyoto-u.ac.jp | ||||||
| 波多野 悦朗 | ||||||
| 京都大学医学部附属病院 | ||||||
| 肝胆膵・移植外科 | ||||||
| 自施設 | ||||||
| 救急科医師が常勤しており、救急外来を有する。救急外来にはX線装置、CT、心電図計、輸血・輸液のための設備、その他救急医療を行うために必要な設備を有する。また、救急医療を要する傷病者のための専用病床を有する。病床数1141床のうち当該診療科として48床を有し、再生医療等の提供によるものと疑われる疾病、傷害、もしくは生命の危機的状況、感染症の発症などが発生した際に、再生医療等を受けた者が優先的に使用できる病床数は十分確保されており、緊急の手術実施も可能である。 | ||||||
| 福岡大学病院 | ||||||
| 福岡県福岡市城南区七隈7丁目45−1 | ||||||
| 092-801-1011 | ||||||
| 三浦 伸一郎 | ||||||
| 小玉 正太 | Kodama Shota | |||||
| 福岡大学病院 | Fukuoka Univercity Hospital | |||||
| 再生医療センター、消化器外科 、医学部再生・移植医学講座 | ||||||
| 814-0180 | ||||||
| 福岡県福岡市城南区七隈7丁目45−1 | ||||||
| 092-801-1011 | ||||||
| skodama@adm.fukuoka-u.ac.jp | ||||||
| 田村 弓恵 | ||||||
| 福岡大学病院 | ||||||
| 医学部再生・移植医学 | ||||||
| 814-0180 | ||||||
| 福岡県福岡市城南区七隈7丁目45−1 | ||||||
| 092-801-1011 | ||||||
| 092-801-1019 | ||||||
| yumietamura@fukuoka-u.ac.jp | ||||||
| 小玉 正太 | ||||||
| 福岡大学病院 | ||||||
| 再生医療センター、消化器外科、医学部再生・移植医学講座 | ||||||
| 自施設 | ||||||
| 福岡大学病院の救急医療設備(自施設)について】 名称:救命救急センター 説明:センターとして病棟に救命病床34床を有し、そのうち10床はICU(集中治療室)となっている。 設備としては、救命救急センター救急搬入口と直結した2つの救急初療室、救急初療室に直結したCTスキャン、人工呼吸器、ECMO、血液浄化機器、人工膵臓、熱傷用特殊ベット、ECMOカー、ドクターカー、 災害用各種備品臨床訓練室(シムマン・ハートシム・マイクロシム)等を備えている。 |
||||||
| 東北大学病院 | ||||||
| 宮城県仙台市青葉区星陵町1番1号 | ||||||
| 022-717-7000 | ||||||
| 張替 秀郎 | ||||||
| 後藤 昌史 | Goto Masafumi | |||||
| 東北大学病院 | National University Corporation Tohoku University | |||||
| 大学院医学系研究科 移植再生医学分野 | ||||||
| 980-0872 | ||||||
| 宮城県仙台市青葉区星陵町2-1 | ||||||
| 022-717-7205 | ||||||
| masafumi.goto.c6@tohoku.ac.jp | ||||||
| 吉川 真木子 | ||||||
| 東北大学病院 | ||||||
| 医学系研究科移植再生医学分野 | ||||||
| 980-0872 | ||||||
| 宮城県仙台市青葉区星陵町2番1号 | ||||||
| 022-717-7895 | ||||||
| 022-717-7899 | ||||||
| m.kikkawa@med.tohoku.ac.jp | ||||||
| 後藤 昌史 | ||||||
| 東北大学病院 | ||||||
| 大学院医学系研究科 移植再生医学分野 | ||||||
| 自施設 | ||||||
| 救急科医師が常勤しており、救急外来を有する。救急外来にはX線装置、CT、心電図計、輸血・輸液のための設備、その他救急医療を行うために必要な設備を有する。また、救急医療を要する傷病者のための専用病床を有する。再生医療等の提供によるものと疑われる疾病、傷害、もしくは生命の危機的状況、感染症の発症などが発生した際に、再生医療等を受けた者が優先的に使用できる病床数は十分確保されており、緊急の手術実施も可能である。 |
||||||
| 京都大学医学部附属病院 | ||||||
| 京都府京都市左京区聖護院川原町5 4 | ||||||
| 075-751-3111 | ||||||
| 髙折 晃史 | ||||||
| 波多野 悦朗 | Hatano Etsuro | |||||
| 京都大学医学部附属病院 | Kyoto Univercity Hospital | |||||
| 肝胆膵・移植外科 | ||||||
| 606-8507 | ||||||
| 京都府京都市左京区聖護院川原町5 4 | ||||||
| 075-751-3111 | ||||||
| etsu@kuhp.kyoto-u.ac.jp | ||||||
| 穴澤 貴行 | ||||||
| 京都大学医学部附属病院 | ||||||
| 肝胆膵・移植外科 | ||||||
| 606-8507 | ||||||
| 京都府京都市左京区聖護院川原町5 4 | ||||||
| 075-751-4323 | ||||||
| 075-751-4348 | ||||||
| anazawa@kuhp.kyoto-u.ac.jp | ||||||
| 穴澤 貴行 | ||||||
| 京都大学医学部付属病院 | ||||||
| 肝胆膵・移植外科 | ||||||
| 自施設 | ||||||
| 救急科医師が常勤しており、救急外来を有する。救急外来にはX線装置、CT、心電図計、輸血・輸液のための設備、その他救急医療を行うために必要な設備を有する。また、救急医療を要する傷病者のための専用病床を有する。病床数1141床のうち当該診療科として48床を有し、再生医療等の提供によるものと疑われる疾病、傷害、もしくは生命の危機的状況、感染症の発症などが発生した際に、再生医療等を受けた者が優先的に使用できる病床数は十分確保されており、緊急の手術実施も可能である。 | ||||||
| 京都大学医学部附属病院 | ||||||
| 京都府京都市左京区聖護院川原町5 4 | ||||||
| 0757513111 | ||||||
| 髙折 晃史 | ||||||
| 波多野 悦朗 | Hatano Etsuro | |||||
| 京都大学医学部附属病院 | Kyoto Univercity Hospital | |||||
| 肝胆膵・移植外科 | ||||||
| 606-8507 | ||||||
| 京都府京都市左京区聖護院川原町5 4 | ||||||
| 0757513111 | ||||||
| etsu@kuhp.kyoto-u.ac.jp | ||||||
| 穴澤 貴行 | ||||||
| 京都大学医学部附属病院 | ||||||
| 肝胆膵・移植外科 | ||||||
| 606-8507 | ||||||
| 京都府京都市左京区聖護院川原町5 4 | ||||||
| 075-751-4323 | ||||||
| 075-751-4348 | ||||||
| anazawa@kuhp.kyoto-u.ac.jp | ||||||
| 長井 和之 | ||||||
| 京都大学医学部附属病院 | ||||||
| 肝胆膵・移植外科 | ||||||
| 自施設 | ||||||
| 救急科医師が常勤しており、救急外来を有する。救急外来にはX線装置、CT、心電図計、輸血・輸液のための設備、その他救急医療を行うために必要な設備を有する。また、救急医療を要する傷病者のための専用病床を有する。病床数1141床のうち当該診療科として48床を有し、再生医療等の提供によるものと疑われる疾病、傷害、もしくは生命の危機的状況、感染症の発症などが発生した際に、再生医療等を受けた者が優先的に使用できる病床数は十分確保されており、緊急の手術実施も可能である。 | ||||||
| 福岡大学病院 | ||||||
| 福岡県福岡市城南区七隈7丁目45−1 | ||||||
| 092-801-1011 | ||||||
| 三浦 伸一郎 | ||||||
| 小玉 正太 | Kodama Shota | |||||
| 福岡大学病院 | Fukuoka Univercity Hospital | |||||
| 再生医療センター、消化器外科 、医学 部再生・移植医学講座 | ||||||
| 814-0180 | ||||||
| 福岡県福岡市城南区七隈7丁目45−1 | ||||||
| 092-801-1011 | ||||||
| skodama@adm.fukuoka-u.ac.jp | ||||||
| 田村 弓恵 | ||||||
| 福岡大学病院 | ||||||
| 医学部再生・移植医学 | ||||||
| 814-0180 | ||||||
| 福岡県福岡市城南区七隈7丁目45−1 | ||||||
| 092-801-1011 | ||||||
| 092-801-1019 | ||||||
| yumietamura@fukuoka-u.ac.jp | ||||||
| 坂田 直昭 | ||||||
| 福岡大学病院 | ||||||
| 医学部再生・移植医学講座 | ||||||
| 自施設 | ||||||
| 福岡大学病院の救急医療設備(自施設)について】 名称:救命救急センター 説明:センターとして病棟に救命病床34床を有し、そのうち10床はICU(集中治療室)となっている。 設備としては、救命救急センター救急搬入口と直結した2つの救急初療室、救急初療室に直結したCTスキャン、人工呼吸器、ECMO、血液浄化機器、人工膵臓、熱傷用特殊ベット、ECMOカー、ドクターカー、災害用各種備品臨床訓練室(シムマン・ハートシム・マイクロシム)等を備えている。 |
||||||
| 福岡大学病院 | ||||||
| 福岡県福岡市城南区七隈7丁目45−1 | ||||||
| 092-801-1011 | ||||||
| 三浦 伸一郎 | ||||||
| 小玉 正太 | Kodama Shota | |||||
| 福岡大学病院 | Fukuoka Univercity Hospital | |||||
| 再生医療センター、消化器外科 、医学 部再生・移植医学講座 | ||||||
| 814-0180 | ||||||
| 福岡県福岡市城南区七隈7丁目45−1 | ||||||
| 092-801-1011 | ||||||
| skodama@adm.fukuoka-u.ac.jp | ||||||
| 田村 弓恵 | ||||||
| 福岡大学病院 | ||||||
| 医学部再生・移植医学 | ||||||
| 814-0180 | ||||||
| 福岡県福岡市城南区七隈7丁目45−1 | ||||||
| 092-801-1011 | ||||||
| 092-801-1019 | ||||||
| yumietamura@fukuoka-u.ac.jp | ||||||
| 吉松 軍平 | ||||||
| 福岡大学病院 | ||||||
| 再生医療センター | ||||||
| 自施設 | ||||||
| 福岡大学病院の救急医療設備(自施設)について】 名称:救命救急センター 説明:センターとして病棟に救命病床34床を有し、そのうち10床はICU(集中治療室)となっている。 設備としては、救命救急センター救急搬入口と直結した2つの救急初療室、救急初療室に直結したCTスキャン、人工呼吸器、ECMO、血液浄化機器、人工膵臓、熱傷用特殊ベット、ECMOカー、ドクターカー、災害用各種備品臨床訓練室(シムマン・ハートシム・マイクロシム)等を備えている。 |
||||||
| 福岡大学病院 | ||||||
| 福岡県福岡市城南区七隈7丁目45−1 | ||||||
| 092-801-1011 | ||||||
| 三浦 伸一郎 | ||||||
| 小玉 正太 | Kodama Shota | |||||
| 福岡大学病院 | Fukuoka Univercity Hospital | |||||
| 再生医療センター、消化器外科 、医学部再生・移植医学講座 | ||||||
| 814-0180 | ||||||
| 福岡県福岡市城南区七隈7丁目45−1 | ||||||
| 092-801-1011 | ||||||
| skodama@adm.fukuoka-u.ac.jp | ||||||
| 田村 弓恵 | ||||||
| 福岡大学病院 | ||||||
| 医学部再生・移植医学 | ||||||
| 814-0180 | ||||||
| 福岡県福岡市城南区七隈7丁目45−1 | ||||||
| 092-801-1011 | ||||||
| 092-801-1019 | ||||||
| yumietamura@fukuoka-u.ac.jp | ||||||
| 川浪 大治 | ||||||
| 福岡大学病院 | ||||||
| 医学部内分泌・糖尿病内科学講座 | ||||||
| 自施設 | ||||||
| 福岡大学病院の救急医療設備(自施設)について】 名称:救命救急センター 説明:センターとして病棟に救命病床34床を有し、そのうち10床はICU(集中治療室)となっている。 設備としては、救命救急センター救急搬入口と直結した2つの救急初療室、救急初療室に直結したCTスキャン、人工呼吸器、ECMO、血液浄化機器、人工膵臓、熱傷用特殊ベット、ECMOカー、ドクターカー、災害用各種備品臨床訓練室(シムマン・ハートシム・マイクロシム)等を備えている。 |
||||||
| 福岡大学病院 | ||||||
| 福岡県福岡市城南区七隈7丁目45−1 | ||||||
| 092-801-1011 | ||||||
| 三浦 伸一郎 | ||||||
| 小玉 正太 | Kodama Shota | |||||
| 福岡大学病院 | Fukuoka Univercity Hospital | |||||
| 再生医療センター、消化器外科 、医学 部再生・移植医学講座 | ||||||
| 814-0180 | ||||||
| 福岡県福岡市城南区七隈7丁目45−1 | ||||||
| 092-801-1011 | ||||||
| skodama@adm.fukuoka-u.ac.jp | ||||||
| 田村 弓恵 | ||||||
| 福岡大学病院 | ||||||
| 医学部再生・移植医学 | ||||||
| 814-0180 | ||||||
| 福岡県福岡市城南区七隈7丁目45−1 | ||||||
| 092-801-1011 | ||||||
| 092-801-1019 | ||||||
| yumietamura@fukuoka-u.ac.jp | ||||||
| 長谷川 傑 | ||||||
| 福岡大学病院 | ||||||
| 医学部 消化器外科学講座 | ||||||
| 自施設 | ||||||
| 福岡大学病院の救急医療設備(自施設)について】 名称:救命救急センター 説明:センターとして病棟に救命病床34床を有し、そのうち10床はICU(集中治療室)となっている。 設備としては、救命救急センター救急搬入口と直結した2つの救急初療室、救急初療室に直結したCTスキャン、人工呼吸器、ECMO、血液浄化機器、人工膵臓、熱傷用特殊ベット、ECMOカー、ドクターカー、災害用各種備品臨床訓練室(シムマン・ハートシム・マイクロシム)等を備えている。 |
||||||
| 福岡大学病院 | ||||||
| 福岡県福岡市城南区七隈7丁目45−1 | ||||||
| 092-801-1011 | ||||||
| 三浦 伸一郎 | ||||||
| 小玉 正太 | Kodama Shota | |||||
| 福岡大学病院 | Fukuoka Univercity Hospital | |||||
| 再生医療センター、消化器外科 、医学 部再生・移植医学講座 | ||||||
| 814-0180 | ||||||
| 福岡県福岡市城南区七隈7丁目45−1 | ||||||
| 092-801-1011 | ||||||
| skodama@adm.fukuoka-u.ac.jp | ||||||
| 田村 弓恵 | ||||||
| 福岡大学病院 | ||||||
| 医学部再生・移植医学 | ||||||
| 814-0180 | ||||||
| 福岡県福岡市城南区七隈7丁目45−1 | ||||||
| 092-801-1011 | ||||||
| 092-801-1019 | ||||||
| yumietamura@fukuoka-u.ac.jp | ||||||
| 梶原 正俊 | ||||||
| 福岡大学病院 | ||||||
| 消化器外科 | ||||||
| 自施設 | ||||||
| 福岡大学病院の救急医療設備(自施設)について】 名称:救命救急センター 説明:センターとして病棟に救命病床34床を有し、そのうち10床はICU(集中治療室)となっている。 設備としては、救命救急センター救急搬入口と直結した2つの救急初療室、救急初療室に直結したCTスキャン、人工呼吸器、ECMO、血液浄化機器、人工膵臓、熱傷用特殊ベット、ECMOカー、ドクターカー、災害用各種備品臨床訓練室(シムマン・ハートシム・マイクロシム)等を備えている。 |
||||||
| 福岡大学病院 | ||||||
| 福岡県福岡市城南区七隈7丁目45−1 | ||||||
| 092-801-1011 | ||||||
| 三浦 伸一郎 | ||||||
| 小玉 正太 | Kodama Shota | |||||
| 福岡大学病院 | Fukuoka Univercity Hospital | |||||
| 再生医療センター、消化器外科 、医学 部再生・移植医学講座 | ||||||
| 814-0180 | ||||||
| 福岡県福岡市城南区七隈7丁目45−1 | ||||||
| 092-801-1011 | ||||||
| skodama@adm.fukuoka-u.ac.jp | ||||||
| 田村 弓恵 | ||||||
| 福岡大学病院 | ||||||
| 医学部再生・移植医学 | ||||||
| 814-0180 | ||||||
| 福岡県福岡市城南区七隈7丁目45−1 | ||||||
| 092-801-1011 | ||||||
| 092-801-1019 | ||||||
| yumietamura@fukuoka-u.ac.jp | ||||||
| 平井 郁仁 | ||||||
| 福岡大学病院 | ||||||
| 消化器内科学講座 | ||||||
| 自施設 | ||||||
| 福岡大学病院の救急医療設備(自施設)について】 名称:救命救急センター 説明:センターとして病棟に救命病床34床を有し、そのうち10床はICU(集中治療室)となっている。 設備としては、救命救急センター救急搬入口と直結した2つの救急初療室、救急初療室に直結したCTスキャン、人工呼吸器、ECMO、血液浄化機器、人工膵臓、熱傷用特殊ベット、ECMOカー、ドクターカー、災害用各種備品臨床訓練室(シムマン・ハートシム・マイクロシム)等を備えている。 |
||||||
| 東北大学病院 | ||||||
| 宮城県仙台市青葉区星陵町1番1号 | ||||||
| 022-717-7000 | ||||||
| 張替 秀郎 | ||||||
| 後藤 昌史 | Goto Masafumi | |||||
| 東北大学病院 | National University Corporation Tohoku University | |||||
| 大学院医学系研究科 移植再生医学分野 | ||||||
| 980-0872 | ||||||
| 宮城県宮城県仙台市青葉区星陵町2-1 | ||||||
| 022-717-7205 | ||||||
| masafumi.goto.c6@tohoku.ac.jp | ||||||
| 吉川 真木子 | ||||||
| 東北大学病院 | ||||||
| 医学系研究科移植再生医学分野 | ||||||
| 980-0872 | ||||||
| 宮城県宮城県仙台市青葉区星陵町2-1 | ||||||
| 022-717-7895 | ||||||
| 022-717-7899 | ||||||
| m.kikkawa@med.tohoku.ac.jp | ||||||
| 海野 倫明 | ||||||
| 東北大学病院 | ||||||
| 東北大学大学院医学系研究科 消化器外科学分野 | ||||||
| 自施設 | ||||||
| 救急科医師が常勤しており、救急外来を有する。救急外来にはX線装置、CT、心電図計、輸血・輸液のための設備、その他救急医療を行うために必要な設備を有する。また、救急医療を要する傷病者のための専用病床を有する。再生医療等の提供によるものと疑われる疾病、傷害、もしくは生命の危機的状況、感染症の発症などが発生した際に、再生医療等を受けた者が優先的に使用できる病床数は十分確保されており、緊急の手術実施も可能である。 | ||||||
| 東北大学病院 | ||||||
| 宮城県仙台市青葉区星陵町1番1号 | ||||||
| 022-717-7000 | ||||||
| 張替 秀郎 | ||||||
| 後藤 昌史 | Goto Masafumi | |||||
| 東北大学病院 | National University Corporation Tohoku University | |||||
| 大学院医学系研究科 移植再生医学分野 | ||||||
| 980-0872 | ||||||
| 宮城県宮城県仙台市青葉区星陵町2-1 | ||||||
| 022-717-7205 | ||||||
| masafumi.goto.c6@tohoku.ac.jp | ||||||
| 吉川 真木子 | ||||||
| 東北大学病院 | ||||||
| 医学系研究科移植再生医学分野 | ||||||
| 980-0872 | ||||||
| 宮城県宮城県仙台市青葉区星陵町2-1 | ||||||
| 022-717-7895 | ||||||
| 022-717-7899 | ||||||
| m.kikkawa@med.tohoku.ac.jp | ||||||
| 戸子台 和哲 | ||||||
| 東北大学病院 | ||||||
| 総合外科 | ||||||
| 自施設 | ||||||
| 救急科医師が常勤しており、救急外来を有する。救急外来にはX線装置、CT、心電図計、輸血・輸液のための設備、その他救急医療を行うために必要な設備を有する。また、救急医療を要する傷病者のための専用病床を有する。再生医療等の提供によるものと疑われる疾病、傷害、もしくは生命の危機的状況、感染症の発症などが発生した際に、再生医療等を受けた者が優先的に使用できる病床数は十分確保されており、緊急の手術実施も可能である。 | ||||||
| 東北大学病院 | ||||||
| 宮城県仙台市青葉区星陵町1番1号 | ||||||
| 022-717-7000 | ||||||
| 張替 秀郎 | ||||||
| 後藤 昌史 | Goto Masafumi | |||||
| 東北大学病院 | National University Corporation Tohoku University | |||||
| 大学院医学系研究科 移植再生医学分野 | ||||||
| 980-0872 | ||||||
| 宮城県宮城県仙台市青葉区星陵町2-1 | ||||||
| 022-717-7205 | ||||||
| masafumi.goto.c6@tohoku.ac.jp | ||||||
| 吉川 真木子 | ||||||
| 東北大学病院 | ||||||
| 医学系研究科移植再生医学分野 | ||||||
| 980-0872 | ||||||
| 宮城県宮城県仙台市青葉区星陵町2-1 | ||||||
| 022-717-7895 | ||||||
| 022-717-7899 | ||||||
| m.kikkawa@med.tohoku.ac.jp | ||||||
| 藤尾 淳 | ||||||
| 東北大学病院 | ||||||
| 総合外科 | ||||||
| 自施設 | ||||||
| 救急科医師が常勤しており、救急外来を有する。救急外来にはX線装置、CT、心電図計、輸血・輸液のための設備、その他救急医療を行うために必要な設備を有する。また、救急医療を要する傷病者のための専用病床を有する。再生医療等の提供によるものと疑われる疾病、傷害、もしくは生命の危機的状況、感染症の発症などが発生した際に、再生医療等を受けた者が優先的に使用できる病床数は十分確保されており、緊急の手術実施も可能である。 | ||||||
| 東北大学病院 | ||||||
| 宮城県仙台市青葉区星陵町1番1号 | ||||||
| 022-717-7000 | ||||||
| 張替 秀郎 | ||||||
| 後藤 昌史 | Goto Masafumi | |||||
| 東北大学病院 | National University Corporation Tohoku University | |||||
| 大学院医学系研究科 移植再生医学分野 | ||||||
| 980-0872 | ||||||
| 宮城県宮城県仙台市青葉区星陵町2-1 | ||||||
| 022-717-7205 | ||||||
| masafumi.goto.c6@tohoku.ac.jp | ||||||
| 吉川 真木子 | ||||||
| 東北大学病院 | ||||||
| 医学系研究科移植再生医学分野 | ||||||
| 980-0872 | ||||||
| 宮城県宮城県仙台市青葉区星陵町2-1 | ||||||
| 022-717-7895 | ||||||
| 022-717-7899 | ||||||
| m.kikkawa@med.tohoku.ac.jp | ||||||
| 中川 圭 | ||||||
| 東北大学病院 | ||||||
| 東北大学大学院医学系研究科 消化器外科学分野 | ||||||
| 自施設 | ||||||
| 救急科医師が常勤しており、救急外来を有する。救急外来にはX線装置、CT、心電図計、輸血・輸液のための設備、その他救急医療を行うために必要な設備を有する。また、救急医療を要する傷病者のための専用病床を有する。再生医療等の提供によるものと疑われる疾病、傷害、もしくは生命の危機的状況、感染症の発症などが発生した際に、再生医療等を受けた者が優先的に使用できる病床数は十分確保されており、緊急の手術実施も可能である。 | ||||||
3 再生医療等に用いる細胞の入手の方法並びに特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法等
3 再生医療等に用いる細胞の入手の方法並びに特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法等
(1)再生医療等に用いる細胞の入手の方法(特定細胞加工物を用いる場合のみ記載)
(1)再生医療等に用いる細胞の入手の方法(特定細胞加工物を用いる場合のみ記載)
| 膵臓内にある内分泌細胞塊である膵島(Islet) | |
| 再生医療等提供機関と同じ | |
| 自家移植であり、細胞提供者は被験者自身である。細胞提供者の選定方法は「 再生医療等を受ける者の適格基準」に明記しているように以下の通りである。 1.研究参加に関して文書による同意が得られた者 2.同意取得時の年齢が18歳以上、70歳以下の男女 3.膵全摘術が適応となりうる良性膵疾患のうち疼痛を伴う慢性膵炎(遺伝性膵炎含む)および膵動静脈奇形と診断されている者 4.前治療として保存的治療、神経ブロック、内視鏡的治療または外科的治療を受けているが、無効または不十分な効果または一時的な効果に過ぎなかった者 |
|
| 自家移植であり、細胞提供者は被験者自身である。細胞提供者の適格性の確認方法は、実施計画書による規定の検査を実施した後、再生医療等提供機関の膵臓外科(または肝胆膵手術担当科)および消化器内科の合議に基づき(必要があればその他の診療科の担当医も含む)、適格性を研究責任者が最終決定する。ただし、術中に外科医の判断で術式の変更や中止をすることができる。 | |
| 全身麻酔科下に膵臓外科医により通常の手術手順に則り膵全摘術あるいは残膵全摘術を行う。ただし、膵島のviabilityを保つため膵を栄養する主要血管の処理は摘出直前に行う。手術室内に用意した清潔なバックテーブルにて摘出した膵を速やかに無菌的に処理した後、臓器保存容器に入れる。手術室から細胞調製施設(CPC)へ膵臓を運搬し、以後の細胞加工工程に全量を供する。 |
(2)特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法(特定細胞加工物等を用いる場合のみ記載)
(2)特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法(特定細胞加工物等を用いる場合のみ記載)
| 膵島 | ||
| 【採取の方法】 摘出された膵臓を用いる。バックテーブルにて摘出膵を処理した後、臓器保存容器に入れ当病院内の細胞調整施設(CPC)へ膵臓を運搬する。【加工の方法】 膵島分離すなわち膵島の製造工程は、CPC内で行う。膵島は摘出した膵から分離され膵β細胞を含む無菌な組織であり、CPC内で無菌的に製造する。膵臓を消毒薬、抗菌剤を用いて、除菌する。工程中汚染が起こらないよう留意し、最終的に製造された膵島は定められた無菌検査を行う。汚染されていた場合は移植に 用いられない。製造における品質管理は「再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号)第四十四 条」に示される厚生労働省令第110号(平成26年 9月26日)で定められた「特定細胞加工物製造事業者がその業務に関し遵守するべき事項」を遵守して実施する。膵島製造の品質に 関する作業については手順書を定め、その実施内容を記載した記録書を所定の期間保管する。膵島の製造管理および品質 管理の責任者を置く。 【保管の方法】 製造された膵島は原則24時間以内に移植される。移植まではCPC内の保冷庫内で2℃〜8℃で保管される 。 【試験検査の方法】 製造された膵島は以下の基準を満たすこ とを確認する。 1) 膵島量 ≧ 50,000IE 2) 純度 ≧ 30%(ただし、純化前の組織量が12mL以下で 純化を行わなかった場合は純度30%未満でも移植を行う) 3) 組織量 ≦ 12mL 4) Viability ≧ 70% 5) Endotoxin ≦ 5EU/kg (患者体重) 6) グラム染色陰性 |
||
| 手術室にて、開腹下に腸間膜静脈経由で門脈内にカテーテルをを留置する。 門脈圧を測定し正常であることを確認した後、カテーテルを通して分離膵島を注入、移植する。 | ||
| 無 | ||
| 非該当 | ||
| FC3140024 | ||
| 国立国際医療センター細胞調整管理室 | ||
| 該当なし | ||
| 膵島 | ||
| 【採取の方法】 摘出された膵臓を用いる。バックテーブルにて摘出膵を処理した後、臓器保存容器に入れ当病院内の細胞調整施設(CPC)へ膵臓を運搬する。【加工の方法】 膵島分離すなわち膵島の製造工程は、CPC内で行う。膵島は摘出した膵から分離され膵β細胞を含む無菌な組織であり、CPC内で無菌的に製造する。膵臓を消毒薬、抗菌剤を用いて、除菌する。工程中汚染が起こらないよう留意し、最終的に製造された膵島は定められた無菌検査を行う。汚染されていた場合は移植に 用いられない。製造における品質管理は「再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号)第四十四 条」に示される厚生労働省令第110号(平成26年 9月26日)で定められた「特定細胞加工物製造事業者がその業務に関し遵守するべき事項」を遵守して実施する。膵島製造の品質に 関する作業については手順書を定め、その実施内容を記載した記録書を所定の期間保管する。膵島の製造管理および品質 管理の責任者を置く。 【保管の方法】 製造された膵島は原則24時間以内に移植される。移植まではCPC内の保冷庫内で2℃〜8℃で保管される 。 【試験検査の方法】 製造された膵島は以下の基準を満たすこ とを確認する。 1) 膵島量 ≧ 50,000IE 2) 純度 ≧ 30%(ただし、純化前の組織量が12mL以下で 純化を行わなかった場合は純度30%未満でも移植を行う) 3) 組織量 ≦ 12mL 4) Viability ≧ 70% 5) Endotoxin ≦ 5EU/kg (患者体重) 6) グラム染色陰性 |
||
| 開腹下に腸間膜静脈等を経由して門脈内にカテーテルをを留置する。 門脈圧を測定し正常であることを確認した後、カテーテルを通して分離膵島を注入、移植する。 | ||
| 無 | ||
| 非該当 | ||
| FC5210050 | ||
| 京都大学医学部附属病院 細胞療法センター 分子細胞治療センター | ||
| 該当なし | ||
| 膵島 | ||
| 【採取の方法】 摘出された膵臓を用いる。バックテーブルにて摘出膵を処理した後、臓器保存容器に入れ当病院内の細胞調整施設(CPC)へ膵臓を運搬する。【加工の方法】 膵島分離すなわち膵島の製造工程は、CPC内で行う。膵島は摘出した膵から分離され膵β細胞を含む無菌な組織であり、CPC内で無菌的に製造する。膵臓を消毒薬、抗菌剤を用いて、除菌する。工程中汚染が起こらないよう留意し、最終的に製造された膵島は定められた無菌検査を行う。汚染されていた場合は移植に 用いられない。製造における品質管理は「再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号)第四十四 条」に示される厚生労働省令第110号(平成26年 9月26日)で定められた「特定細胞加工物製造事業者がその業務に関し遵守するべき事項」を遵守して実施する。膵島製造の品質に 関する作業については手順書を定め、その実施内容を記載した記録書を所定の期間保管する。膵島の製造管理および品質 管理の責任者を置く。 【保管の方法】 製造された膵島は原則24時間以内に移植される。移植まではCPC内の保冷庫内で2℃〜8℃で保管される 。 【試験検査の方法】 製造された膵島は以下の基準を満たすこ とを確認する。 1) 膵島量 ≧ 50,000IE 2) 純度 ≧ 30%(ただし、純化前の組織量が12mL以下で 純化を行わなかった場合は純度30%未満でも移植を行う) 3) 組織量 ≦ 12mL 4) Viability ≧ 70% 5) Endotoxin ≦ 5EU/kg (患者体重) 6) グラム染色陰性 | ||
| 開腹下に腸間膜静脈等を経由して門脈内にカテーテルをを留置する。 門脈圧を測定し正常であることを確認した後、カテーテルを通して分離膵島を注入、移植する。 | ||
| 無 | ||
| 非該当 | ||
| FC7150005 | ||
| 学校法人 福岡大学病院 細胞調製室 | ||
| 該当なし | ||
| 膵島 | ||
| 【採取の方法】 摘出された膵臓を用いる。バックテーブルにて摘出膵を処理した後、臓器保存容器に入れ当病院内の細胞調整施設(CPC)へ膵臓を運搬する。【加工の方法】 膵島分離すなわち膵島の製造工程は、CPC内で行う。膵島は摘出した膵から分離され膵β細胞を含む無菌な組織であり、CPC内で無菌的に製造する。膵臓を消毒薬、抗菌剤を用いて、除菌する。工程中汚染が起こらないよう留意し、最終的に製造された膵島は定められた無菌検査を行う。汚染されていた場合は移植に 用いられない。製造における品質管理は「再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号)第四十四 条」に示される厚生労働省令第110号(平成26年 9月26日)で定められた「特定細胞加工物製造事業者がその業務に関し遵守するべき事項」を遵守して実施する。膵島製造の品質に 関する作業については手順書を定め、その実施内容を記載した記録書を所定の期間保管する。膵島の製造管理および品質 管理の責任者を置く。 【保管の方法】 製造された膵島は原則24時間以内に移植される。移植まではCPC内の保冷庫内で2℃〜8℃で保管される 。 【試験検査の方法】 製造された膵島は以下の基準を満たすこ とを確認する。 1) 膵島量 ≧ 50,000IE 2) 純度 ≧ 30%(ただし、純化前の組織量が12mL以下で 純化を行わなかった場合は純度30%未満でも移植を行う) 3) 組織量 ≦ 12mL 4) Viability ≧ 70% 5) Endotoxin ≦ 5EU/kg (患者体重) 6) グラム染色陰性 | ||
| 開腹下に腸間膜静脈等を経由して門脈内にカテーテルをを留置する。 門脈圧を測定し正常であることを確認した後、カテーテルを通して分離膵島を注入、移植する。 | ||
| 無 | ||
| 非該当 | ||
| FC2150002 | ||
| 東北大学病院細胞プロセッシングセンター | ||
| 該当なし | ||
(3)再生医療等製品等に関する事項(再生医療等製品を用いる場合のみ記載)
(3)再生医療等製品等に関する事項(再生医療等製品を用いる場合のみ記載)
(4)再生医療等に用いる未承認又は適応外の医薬品又は医療機器に関する事項(未承認又は適応外の医薬品又は医療機器を用いる場合のみ記載)
(4)再生医療等に用いる未承認又は適応外の医薬品又は医療機器に関する事項(未承認又は適応外の医薬品又は医療機器を用いる場合のみ記載)
4 再生医療等技術の安全性の確保等に関す措置
4 再生医療等技術の安全性の確保等に関す措置
(1)利益相反管理に関する事項
(1)利益相反管理に関する事項
① 再生医療等に対する特定細胞加工物等製造事業者からの研究資金等の提供その他の関与
① 再生医療等に対する特定細胞加工物等製造事業者からの研究資金等の提供その他の関与
| 該当なし | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
② 再生医療等に対する医療薬品等製造販売業者等からの研究資金等の提供その他の関与
② 再生医療等に対する医療薬品等製造販売業者等からの研究資金等の提供その他の関与
| 無 | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
③ 再生医療等に対する特定細胞加工物等製造事業者又は医療品等製造販売業者等以外からの研究資金
③ 再生医療等に対する特定細胞加工物等製造事業者又は医療品等製造販売業者等以外からの研究資金
| 無 | ||
(2)その他再生医療等技術の安全性の確保等に関する措置
(2)その他再生医療等技術の安全性の確保等に関する措置
| 本研究で使用する膵島は、被験者から摘出された膵臓より、 膵島分離の手順書に則って分離された膵内分泌細胞組織と定義する。また、分離の最終段階で以下の条件を満たすことを 確認し移植に使用する。 1) 膵島量 ≧ 50,000IE 2) 純度 ≧ 30% (ただし、純化前の組織量が12mL以下で 純化を行わなかった場合は純度30%未満でも移植を行う。 3) 組織量 ≦ 12mL 4) Viability ≧ 70% 5) Endotoxin ≦ 5EU/kg (患者体重) 6) グラム染色陰性 自家移植であるため、拒絶反応はなく免疫抑制剤は不要である。移植膵島による内因性感染の可能性はない。移植手技そのものにともなう死に至るような重篤な合併症は報告されていない。同種膵島移植においては、外分泌組織を含めて大量に門脈内投与した際に急性肝不全、DICを発症して死亡した症例の報告があるが、総移植量を10mL以下としたエドモ ントン・プロトコール以降においてはこのような合併症の報告はない。また、血管内への組織の移植であるため、移植組織による動脈塞栓、それに続く梗塞の可能性があるが、現在まで脳梗塞、肺梗塞、心筋梗塞などの報告はない。以上より移植膵島の安全性は極めて高いと考えられる 。なお、膵全摘術および移植を終了するまですべて施設の手術室で行う。 ミネソタ大学における48例の検討では重度の合併症は報告されず、一時的な肝酵素上昇が見られた症例でも退院までには正常化していた(Wahoff DC, et al. Ann Surg. 1995; 222(4):562-75)。他の報告と併せても、膵切除術および自家膵島移植は安全性の高い治療法と考えられる( White SA, et al. Ann Surg. 2001; 233(3):423-431、Berney T, et al. Transplant Proc. 2004;36(4):1123-1124)。 | ||||||
| 難治性の疼痛を伴う慢性膵炎に対する膵全摘+自家膵島移植は欧米を中心に行われており、疼痛の抑制と2次性糖尿病の緩和に効果的とされている。しかし、日本では未だ探索的治療の位置づけである。 研究責任者は、2016年より国立国際医療研究センターにおいて先行研究「慢性膵炎患者を対象とした 膵切除術および自家膵島移植の有効性と安全性に関 する臨床試験」を実施した。2019年までに予定症例数の5例を実施し、良好な成績を示した。 本臨床試験においても高度な膵島分離技術、適切な患者選択を用いた、膵全摘術および自家膵島移植を行い、疼痛コントロール困難な慢性膵炎などの膵全摘術が適応となる膵疾患患者に対する自家膵島移植の標準治療化を目指す。治療前後の膵島機能(低血糖の有無、血中CペプチドやHbA1cなど)を評価し、さらに副次評価としてQOL、疼痛、鎮痛剤使用などについても評価する。このように、今回我々は慢性膵炎などに対する膵全摘術に伴う自家膵島移植が二次性糖尿病を軽減することにより代謝的好影響をもたらすものと考え、本治療を標準治療とすることを目標として本臨床試験を実施するものである。 *添付資料「提供する再生医療等の妥当性についての検討内容.pdf」に詳細を記載。 |
||||||
| 本研究において再生医療等を行う医師は、特定細胞加工物製造部門に特定細胞加工物の製造を行わせる際に、特定細胞加工物概要書に従った製造が行われるよう必要な指示を行う。膵島分離工程が終了した段階で、以下の項目について確認し、基準を満たし、かつ品質に問題が無いと判定された細胞加工物について使用可能と医師である品質管理責任者または出荷判定者が判定する。 1) 膵島量 ≧ 50,000IE 2) 純 度 ≧ 30%(ただし、純化前の組織量が12mL以下 で純化を行わなかった場合は純度30%未満でも移植を行う ) 3) 組織量 ≦ 12mL 4) Viability ≧ 70% 5) Endotoxin ≦ 5EU/kg (患者体重) 6) グラム染色陰性 | ||||||
| 特定細胞加工物の安全性の確保に重大な影響を及ぼすおそれがある事態が生じた場合には、必要な措置等を講ずるとともに、その旨を速やかに厚生労働大臣(地方厚生局長経由)及び認定再生医療等委員会に提出する。 必要な措置として、万一自家膵島移植後に膵島がウイルスや細菌などに侵されていることが判明した場合等 に、速やかに被験者に対しその旨を伝え、必要な検査および治療を行う。被験者のフォローアップ後も連絡が取れるよう、被験者の連絡先は常に把握しておくようにする。 | ||||||
| 分離に使用されない膵組織の一部または細胞を含む臓器保存液の一部を採取して凍結し、少なくとも10年間保存する。また、 細胞加工物として分離した膵島の一部もしくは細胞を含む膵島移植溶液の一部を試料として凍結し、少なくとも10年間保存する。 |
||||||
| 被験者が同意撤回した場合、試料に付した被験者識別コード(研究用ID)を削除した上で、廃棄物管理規程に従って感染性廃棄物として廃棄する。同意撤回の際には匿名化対応表は廃棄しない。 研究終了後、研究計画書に規定された保管期間10年が経過した場合、試料は廃棄する。廃棄の際は、試料に付した被験者識別コード(研究用ID)を削除し、匿名化対応表を破棄して特定の個人が識別できないよう措置を行った上で、廃棄物管理規程に従って感染性廃棄物として廃棄する。 | ||||||
| 有害事象の報告 全ての有害事象について、発現日、事象の経過、重症度、因果関係、転帰の判断日を記録する。ただし、治療行為による検査値異常(ヘパリン投与によるAPTT延長など)は有害事象としての収集と記録は不要とする。また、手術の侵襲による術直後の一時的な、且つ一般的で重篤でない検査値異常値については経過観察し、有害事象として取り上げるか否かを研究責任者が判断する。 重篤な有害事象の報告 重篤な有害事象が発現した場合、情報を知り得た研究者は速やかに研究責任者に報告する。研究責任者は、重篤な有害事象について及び対応状況について速やかに把握し、必要な対応を行う。規定に従って報告書を作成し、当該再生医療等提供機関の管理者と研究代表者に報告を行う。重篤な有害事象は発現後、転帰が軽快または回復するまで追跡する。研究代表者は、代表管理者、独立データモニタリング委員会(国立国際医療研究センターの場合は臨床研究安全管理室と理事長にも報告)に報告する。 研究代表者および研究責任者は、報告内容の緊急性、重要性、影響の程度などを判断し、必要に応じて登録の一時停止(データセンターへ連絡)や、施設内の担当医への周知事項の決定事項などの対策を講じる。データセンターへの連絡においては緊急度に応じて電話連絡も可能であるが、追って速やかに文書(FAX・郵送・電子メール)による連絡を行う。 認定再生医療等委員会および厚生労働大臣への報告 当該再生医療等の提供によるものと疑われる疾病、障害、若しくは死亡又は当該再生医療等の提供によるものと疑われる感染症の発生を知った場合および定期報告時、研究責任者は研究代表者へ「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」に基づき以下の報告を行う。研究代表者は代表管理者(国立国際医療研究センターについては理事長にも報告)に報告を行う。代表管理者は当該報告を受け、認定再生医療等委員会にこれを報告し、当該委員会の意見を添えて必要な事項を厚生労働大臣へ報告する。また、再生医療等技術の適正な提供のために必要な際に、代表管理者に対しその原因と究明および講ずべき措置について意見が述べられた場合は、当該意見を受けて講じた計画の変更やその他の措置について当該認定再生医療等委員会に報告を行う。 1) 死亡または死亡につながるおそれのある場合: 7日以内に認定再生医療等委員会および厚生労働大臣に報告 2) 治療のために医療機関への入院又は入院期間の延長が必要とされる場合、障害又はそのおそれのある場合、重篤な場合、後世代における先天性の疾病又は異常: 15日以内に認定再生医療等委員会および厚生労働大臣に報告 3) 上記以外の疾病の発生等: 再生医療等提供計画を厚生労働大臣に提出した日から起算して60日ごとに、当該期間満了後10日以内に認定再生医療等委員会および厚生労働大臣に報告 4) その他の定期報告等:当該再生医療等の研究責任者は、再生医療等提供計画及び再生医療等 提供基準に従い適正に実施されていることを随時確認し、提供機関の管理者と、研究代表者へ報告する。また、当該提供計画を厚生労働大臣に提出した日から起算して1年ごと当該期間満了後30日以内に、その状況を必要に応じて提供機関の管理者と、研究代表者へ報告する。 研究代表者は代表管理者に遅滞なく報告し、代表管理者は認定再生医療等委員会へ報告しその意見を聴く。代表管理者は、認定再生医療等委員会の意見を添えて、必要な事項を厚生労働大臣へ報告する。 代表管理者、研究代表者は報告を受けて、あるいは報告に対する認定再生医療等委員会の意見を受けて、必要な措置を講ずる。 |
||||||
| 移植終了以降は、プロトコールに従って観察期間中 (移植後半年)効果と有害事象の確認を行い、定期的、および重篤な有害事象が発現した場合に、定められたとおり報告する。ただしプロトコール中止後に発生した有害事象が、膵島移植あるいは治療手順との因果関係が否定される場合には報告する必要はない。 | ||||||
| 観察期間終了後も原則当院外来にてフォローアップし、状態の把握と適切な処置を行う。 そのために被験者が拒否しない限り被験者の連絡先は常に把握しておくようにする。 | ||||||
| 有 | ||||||
| 2022年06月24日 | ||||||
| 2022年10月26日 | ||||||
| 募集中 | Recruiting | |||||
5 細胞提供者及び再生医療等を受ける者に対する健康被害の補償の方法
5 細胞提供者及び再生医療等を受ける者に対する健康被害の補償の方法
細胞提供者について(特定細胞加工物を用いる場合のみ記載)
細胞提供者について(特定細胞加工物を用いる場合のみ記載)
| 無 |
再生医療等を受ける者について
再生医療等を受ける者について
| 有 |
6 審査等業務を行う認定再生医療等委員会に関する事項
6 審査等業務を行う認定再生医療等委員会に関する事項
| 国立健康危機管理研究機構認定再生医療等委員会 | Certified Committee for Regenerative Medicine of Japan Institute for Health Security | |
| NB3150046 | ||
| 東京都新宿区戸山1-21-1 | 1-21-1 Toyama Shinjyuku-ku,Tokyo, Tokyo | |
| 03-3202-7181 | ||
| saisei@jihs.go.jp | ||
| 第三種再生医療等のみを審査することができる構成 | ||
| 適 | ||
| 2020年10月19日 | ||
7 その他
7 その他
| 本研究で知り得た個人情報および臨床情報などのプライバシーに関する情報は、個人の人格尊重の理念の下、厳重に保護 され慎重に扱われるべきものと認識し、プライバシー保護に努める。本研究により得られたデータは、連結可能匿名化され「個人情報の保護に関する法律」(平成15年 5月)に 準拠し、「国立健康危機管理研究機構国立国際医療センターの保有する個人情報の保護に関する規程」により運用する。 | ||
| 無 | No | |
| 提供機関の管理者または研究責任者は教育研修の機会を確保する。また、当該再生医療等の提供に係る関係者は再生医療等を適切に実施するために定期的に教育又は研修に参加し、情報収集に努めることとする。 また、製造従事者に対し次に掲げる教育訓練を行う。教育訓練については、定期的に実施する。 1. 製品に関する知識 2. 製造に用いる細胞・組織の安全な取扱いに関する知識及び技術 3. 設備・装置に関する知識及び技術 4. 製造工程の安全性に関する知識及び技術 5. 事故発生時の措置に関する知識及び技術 | ||
| 研究責任者、コーディネーター等が対応する。電話メールによる 受け付けも可能。 日中:問い合わせ窓口:国立国際医療センター膵島移植プロジェクト: 03-3202-7181 内線2776 休日・ 夜間:緊急連絡先:国立国際医療センター夜間休日受付03-3202-7181 | ||
| 非該当 | ||
| なし | none | |
| 有 | ||
| 非該当 | ||
| 非該当 | ||
| 非該当 | ||
添付資料
添付資料
| 4 再生医療等を受ける者に対する説明文書及び同意文書の様式 | 05_Auto-I 説明同意文書_多機関版 v.4.0_20240722.pdf |
|---|