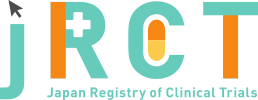臨床研究等提出・公開システム
再生医療等提供計画情報の詳細情報です。
| 第二種 | ||
| 令和2年3月31日 | ||
| 令和4年2月9日 | ||
| 令和4年1月31日 | ||
| 非培養自己脂肪組織由来幹細胞を用いた歯槽骨再生(増生)療法の検討(第一相臨床試験) | ||
| 非培養脂肪幹・前駆細胞を応用した歯槽骨再生 | ||
| 国立大学法人 長崎大学病院 | ||
| 中尾 一彦 | ||
| 本研究の目的は、骨移植を必要とする重度の歯槽骨萎縮症患者に対して、脂肪組織由来幹細胞を組織から単離後に即時移植に応用することで、効果的かつ侵襲の少ない骨再生治療を提供することにある。顆粒状のリン酸カルシウム製の人工骨材料に、低用量化された骨形成蛋白質(Bone Morphogenetic Protein-2;BMP2)と非培養自己脂肪組織由来幹細胞を混合した移植材料(以下、「移植骨」)による歯槽骨再生能及びその安全性を評価する。従来自家骨移植が必要とされた患者に対して、デンタルインプラントの埋入に必要な歯槽骨を再生させ、最終的にインプラント義歯による咬合回復の実現を目指す。自家骨移植は、採骨部に対する2次的な外科侵襲が大きく、採取量にも限界がある。そのため、それ以外の選択肢を拡げることで、患者負担の軽減を図る。 | ||
| 1 | ||
| 重度歯槽骨萎縮症 | ||
| 募集中断 | ||
| 再生医療普及協会 認定再生医療等委員会 | ||
| NA8180001 | ||
中止内容
中止内容
| 令和4年1月31日 | ||
1 提供しようとする再生医療等及びその内容
1 提供しようとする再生医療等及びその内容
申請者情報
申請者情報
| 令和4年2月1日 | |||
| jRCTb070190059 | |||
| 国立大学法人 長崎大学病院 | |||
| 長崎県長崎県長崎市坂本1-7-1 | |||
| 中尾 一彦 | Nakao Kazuhiko | ||
(1)再生医療等の名称及び分類
(1)再生医療等の名称及び分類
| 非培養自己脂肪組織由来幹細胞を用いた歯槽骨再生(増生)療法の検討(第一相臨床試験) | Alveolar bone regeneration with non-cultured autologous adipose tissue-derived stem/progenitor cells -Phase I clinical study-( Bone regeneration with ADSCs ) | ||
| 非培養脂肪幹・前駆細胞を応用した歯槽骨再生 | Alveolar bone regeneration with fresh isolated adipose stem/progenitor cells( Bone regeneration with ADSCs ) | ||
| 第二種 | |||
| 自己細胞を利用するが、非培養組織から単離した細胞を使用し、相同利用に該当しないので、第二種と判断した。 | |||
(2)再生医療等の内容
(2)再生医療等の内容
| 本研究の目的は、骨移植を必要とする重度の歯槽骨萎縮症患者に対して、脂肪組織由来幹細胞を組織から単離後に即時移植に応用することで、効果的かつ侵襲の少ない骨再生治療を提供することにある。顆粒状のリン酸カルシウム製の人工骨材料に、低用量化された骨形成蛋白質(Bone Morphogenetic Protein-2;BMP2)と非培養自己脂肪組織由来幹細胞を混合した移植材料(以下、「移植骨」)による歯槽骨再生能及びその安全性を評価する。従来自家骨移植が必要とされた患者に対して、デンタルインプラントの埋入に必要な歯槽骨を再生させ、最終的にインプラント義歯による咬合回復の実現を目指す。自家骨移植は、採骨部に対する2次的な外科侵襲が大きく、採取量にも限界がある。そのため、それ以外の選択肢を拡げることで、患者負担の軽減を図る。 | |||
| 1 | |||
| 実施計画の公表日 | |||
| 2024年03月31日 | |||
| 15 | |||
| その他 | Other | ||
| 単一群 | single arm study | ||
| 非盲検 | open(masking not used) | ||
| 非対照 | uncontrolled control | ||
| 単群比較 | single assignment | ||
| 治療 | treatment purpose | ||
| 上顎洞底挙上術および歯槽骨増生術に限った症例とする。 ① 1歯以上の欠損を認め、固定式架橋義歯(いわゆるブリッジ)による補綴処置によって機能回復が望めないもの ② 可撤式義歯(入れ歯)ではなくデンタルインプラントを用いた補綴処置を希望するもの ③ デンタルインプラント埋入のための充分な骨量が存在せず、埋入したインプラントの外側面のスレッドが露出し、露出部位に骨移植を必要とするもの ④ 治療前処置として、歯石除去と歯ブラシ指導を受けており、良好なプラークコントロールが維持されているもの ⑤ 年齢は20歳以上、70歳以下であるもの |
1. Patients who are partially or fully edentulous, and are required to treat by dental implants for prosthetic rehabilitation. 2. Patients who have insufficient bone height and/or width to place the dental implant 3. Patients who received the oral health care and maintain the good condition of Plaque Control. 4. The age of the patients: 20- to 70-years old |
||
| ① 重篤な代謝内分泌疾患または自己免疫疾患に罹患しているもの ② 悪性腫瘍、敗血症及びその疑いのあるもの ③ 血液凝固異常を有しているもので以下の値を外れる場合: PT (プロトロンビン時間):50%以上 APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間):23.5~42.5秒 あるいは抗血小板薬や抗凝固薬を使用しているもので服薬の中止が困難であるもの ④ 梅毒、HBV抗原, HCV抗体, HTLV-1抗体, HIV抗体のいずれかが陽性であるもの。 ⑤ 肝疾患、肝臓機能障害のあるもの(以下の値を外れる場合)。 GOT(AST):10~40 IU/L GPT(ALT):5~45 IUI/L ⑥ 骨粗鬆症など骨代謝疾患のものやビスフォスフォネート製剤を使用しているもの ⑦ 妊娠しているもの、あるいは妊娠の疑いのあるもの ⑧ 伝達性海綿状脳症及びその疑い並びに認知症があるもの ⑩ 骨硬化性病変等遺伝性疾患及びその疑いのあるもの ⑪ 喫煙者 ⑫ 代諾者が必要なもの |
1. All patients are required to be nonsmokers. 2. Patients who have systemic disease, malignances, chronic infections, immune system abnormalities, septicemia, syphilis, HBV, HCV, HTLV-1, HIV, pregnancy, dementia. 3. Patients who have disorder of blood coagulation. 4. Patients who have hepatitis function disorders, metabolic bone disease or skeletal dysplasia. 5. Patients who needs the legal representative. |
||
| 20歳 以上 | 20age old over | ||
| 70歳 以下 | 70age old under | ||
| 男性・女性 | Both | ||
| 下記(1)から(3)のいずれかの事項に該当し、責任歯科医師が臨床試験継続を困難と判断した場合、責任歯科医師はその時点で臨床試験の一部または全体を中断する。その上で、臨床試験の一部または全体を中止するか否かを決定し、その旨を文書に記録する。 (1)臨床試験に関する新たな安全性情報または重篤な有害事象の情報が得られた場合。 (2)責任歯科医師または長崎大学病院のいずれかが、再生医療等安全性確保法、臨床試験実施計画書から重大な逸脱を行った場合。 (3)その他、本試験実施中に試験の中止・中断が必要と考えられる新たな情報が得られた場合。責任歯科医師は、長崎大学病院臨床研究倫理委員会などとの協議により本試験の一部または全体の中止を決定した場合、速やかにその旨を理由とともに、長崎大学病院に文書で通知する。長崎大学病院長は、速やかにその旨を理由とともに、特定認定再生医療等委員会に文書で通知する。責任医師は、理由の如何を問わず本試験が中止または中断された場合、本試験に参加中の被験者に速やかにその旨を通知し、適切な処置ならびに被験者の安全性を確認するための検査などを実施する。 |
|||
| 重度歯槽骨萎縮症 | Severe alveolar bone atrophy | ||
| 有 | |||
| β-TCPをBMP2溶液に15分間浸した後、メッシュ(セルストレイナー)にて余剰の水分を除いた上で、1x10^7個程度の非培養脂肪幹・前駆細胞とガラス皿上で混和して、移植に用いる。 | 1x10^7 non-cultured fresh isolated adipose cells are mixed to TCP and rhBMP2 as implants. | ||
| 安全性 | Safety | ||
| 骨生検における骨形態計測量、および頭部CT撮影画像から得られた骨形成量 | Analyses of new bone formation by bone biopsy and CT imaging. | ||
| 別添えの通り | |||
2 人員及び構造設備その他の施設等
2 人員及び構造設備その他の施設等
(1)人員及び構造設備その他の施設に関する事項
(1)人員及び構造設備その他の施設に関する事項
| 歯科医師 | |||||
| 朝比奈 泉 | Asahina Izumi | ||||
| 長崎大学 | Nagasaki University | ||||
| 生命医科学域 顎口腔再生外科学分野 | |||||
| 852-8588 | |||||
| 長崎県長崎市坂本1-7-1 | 1-7-1 Sakamoto, Nagasaki | ||||
| 095-819-7704 | |||||
| asahina@nagasaki-u.ac.jp | |||||
| 自施設 | |||||
| 自施設に当該研究で必要な救急医療が整備されている。 | |||||
(2)その他研究の実施体制に関する事項
(2)その他研究の実施体制に関する事項
| 住田 吉慶 | Sumita Yoshinori | ||||
| 長崎大学 | Nagasaki University | ||||
| 生命医科学域 硬組織疾患基盤研究センター | |||||
| 852-8511 | |||||
| 長崎県長崎市坂本1-7-1 | 1-7-1 Sakamoto, Nagasaki | ||||
| 095-819-7706 | |||||
| 095-819-7718 | |||||
| y-sumita@nagasaki-u.ac.jp | |||||
| 歯科医師 | ||
| 住田 吉慶 | ||
| 長崎大学 | ||
| 生命医科学域 硬組織疾患基盤研究センター |
| 歯科医師 | ||
| 澤瀬 隆 | ||
| 長崎大学 | ||
| 生命医科学域 口腔インプラント学分野 |
| 医師 | ||
| 江口 晋 | ||
| 長崎大学 | ||
| 生命医科学域 移植消化器外科学分野 |
| 医師 | ||
| 田中 克己 | ||
| 長崎大学 | ||
| 生命医科学域 形成再建外科学分野 |
| 医師 | ||
| 吉本 浩 | ||
| 長崎大学 | ||
| 生命医科学域 形成再建外科学分野 |
| 医師 | ||
| 長井 一浩 | ||
| 長崎大学病院 | ||
| 細胞療法部 |
| 歯科医師 | ||
| 大場 誠悟 | ||
| 長崎大学 | ||
| 生命医科学域 顎口腔再生外科学分野 |
| 歯科医師 | ||
| 黒嶋 伸一郎 | ||
| 長崎大学 | ||
| 生命医科学域 口腔インプラント学分野 |
| 歯科医師 | ||
| 江頭 寿洋 | ||
| 長崎大学 | ||
| 生命医科学域 顎口腔再生外科学分野 |
| 医師 | ||
| 傍島 聡 | ||
| そばじまクリニック | ||
| 再生医療センター |
| 医師 | ||
| 岩畔 英樹 | ||
| そばじまクリニック | ||
| 再生医療センター |
| なし | ||
| 長崎大学 | ||
| 緒方 絹子 | ||
| 長崎大学 | ||
| 生命医科学域 顎口腔再生外科学分野 | ||
| なし | ||
| なし | ||
| なし | ||
| 長崎大学 | ||
| 住田 吉慶 | ||
| 長崎大学 | ||
| 生命医科学域 硬組織疾患基盤研究センター | ||
| 非該当 | |||
(3)多施設共同研究に関する事項
(3)多施設共同研究に関する事項
| 無 |
3 再生医療等に用いる細胞の入手の方法並びに特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法等
3 再生医療等に用いる細胞の入手の方法並びに特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法等
(1)再生医療等に用いる細胞の入手の方法(特定細胞加工物を用いる場合のみ記載)
(1)再生医療等に用いる細胞の入手の方法(特定細胞加工物を用いる場合のみ記載)
| 自家脂肪組織由来幹・前駆細胞 | |
| 長崎大学病院 | |
| 被験者 | |
| 被験者の選択基準により確認 | |
| 【自己脂肪組織の採取】 1)採取場所 脂肪組織採取は長崎大学病院手術室にて行う。 2)組織採取 採取者は、当院形成外科医師もしくは移植・消化器外科医師とする。 3)採取方法 脂肪組織の採取は、全身麻酔下もしくは局所および腰椎麻酔下(症例による)に患者自身の腹壁、又は臀部や大腿部の皮下より、通常形成・美容外科で行われているシリンジおよびカニューラを用いた用手的な手技で行う。無菌的に最大300ml程度の脂肪組織を採取する。液採取部に局所麻酔(1%キシロカイン アストラゼネカ(株))を行った後、腹部または臀部皮下脂肪組織に混合液【成分:生理食塩水1000ml+1%リドカイン2ml+0.1%アドレナリン1.5ml+炭酸水素ナトリウム10ml】を適量注入し膨満させ、皮膚に小切開を加える。陰圧ポンプとカニューラ(吸引管)、シリンジ(注射筒)を用いて、脂肪組織を含む懸濁液を吸引する。吸引した脂肪組織は、そのままシリンジにてCelution装置に移される。 4)脂肪組織の採取回数 原則として1回とする。しかし、細胞数確認後、移植骨作製開始が困難であることが判明した場合には、直ちに被験者の意思を確認後、別部位より再採取を行う。この場合に備え、予め被験者 の意思を確認しておく。被験者が複数回の組織採取を拒否する場合は、その時点でプロトコル治療を中止す 【自己脂肪組織由来幹細胞(F-ADSCs)の抽出】 1)抽出場所 F-ADSCsの抽出は、長崎大学病院の手術室でon-siteにて行う。 2)細胞抽出 抽出者は、当院口腔外科医師もしくは形成外科医師とする。 3)抽出方法 ① Celution®800/CRS自動細胞処理装置(Cytori Therapeutics社製)を用いて、採取した脂肪組織の洗浄、細胞の分離、濃縮処理までの行程を無菌的かつ自動的に行い、濃縮細胞液を抽出する(2-5ml)。脂肪分離装置による濃縮細胞液の調整時間は約1時間である。 ② 術室内で、濃縮細胞液の調整後、確認検査用検体(50μl)を採取し、細胞数、細胞生存率を算出する。細胞数1x107個以上、細胞生存率60%以上であることを確認の上、治療に用いる。又、細胞組成(脂肪組織由来間葉系幹/前駆細胞の割合)も計測し、算出しておく。通常本装置を使用して、300gの脂肪組織から1x108個以上/5mlで細胞を分離・濃縮できる。移植に使用しなかった残りの検体は、口腔外科において10年間保管する。 ③ 最後に、Celution®800/CRS自動細胞処理装置の最終工程で得られる最終洗浄液を用いて細菌検査を実施し、品質管理責任者は無菌性を確認しておく。 |
(2)特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法(特定細胞加工物等を用いる場合のみ記載)
(2)特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法(特定細胞加工物等を用いる場合のみ記載)
| 自家脂肪組織由来幹・前駆細胞 | ||
| 【本試験で用いる移植骨】 非培養脂肪組織由来幹細胞(Fresh-adipose derived stem cells、F-ADSCs)を、低用量rhBMP2(骨形成誘導因子)を吸着させたリン酸カルシウム顆粒(足場)に播種し、自己血清を添加することでゲル化させた、細胞と顆粒が一塊なった移植材料を移植骨と称する。 【非培養脂肪組織由来幹細胞】 1.概要 患者の腹部などより採取した脂肪組織から細胞単離用の専用遠心器(Celution)を使用して、閉鎖系において単離・抽出された細胞群(F-ADSCs)をいう。 2.成分・構造・特性・製造方法など 脂肪組織の採取は、手術室において、全身麻酔下に患者自身の腹壁、又は臀部から大腿部の皮下より、通常美容外科で行われているシリンジおよびカニューラを用いた用手的な手技で行う。最大100mlの脂肪組織を採取する。Celution®800/CRS自動細胞処理装置(Cytori Therapeutics社製)を用いて、採取した脂肪組織の洗浄、細胞の分離、濃縮処理までの行程を無菌的かつ自動的に行い、濃縮細胞液を抽出する(2-5ml)。脂肪分離装置による濃縮細胞液の調整時間は約1時間である。手術室内で、濃縮細胞液の調整後、確認検査用検体を採取し、細胞数、細胞生存率を算出する。細胞数1x107個以上、細胞生存率60%以上であることを確認の上、治療に用いる。 3.品質管理 厚生労働省通知「ヒト又は動物由来成分を原料として製造される医薬品等の品質及び安全性確保について(平成12年12月26日医薬発第1314号)」及び「第3回厚生科学審議会科学技術部会ヒト幹細胞を用いた臨床研究の在り方に関する専門委員会(平成14年5月2日開催)」議事録などを参考にして試験項目を決定した。又、特定細胞加工物に係る品質リスクマネジメントについては、「品質リスクマネジメントに関するガイドライン」(平成18年9月1日付け薬食審査次第0901004号/薬食審査発第第0901005号)に則り、その運用は製造管理基準書および品質管理基準書に従い、製造、試験検査を行う。 1)試験検査に関する設備及び器具の点検整備、計器の校正等に関する事項: 専用遠心器は、設置時に設備の適格性の確認を行い、また、定期的(機器により設定する)に再点検・整備(必要と判断された場合は計測機器の校正を含む)を行って、適切に作動していることを確認しておく。点検整備に関しては機器メーカーの取扱説明書等を遵守する。不適切な場合は、修理を行い適切な作動を確保する。 2)特定細胞加工物等及び資材の試験検査における検体の採取等に関する事項: 患者毎に採取年月日、採取量が明記し、その手順を特定細胞加工物標準書に則って記載する。 3)検体の識別及び区分の方法に関する事項: 患者の手術時にon-siteで作製して使用するため、他の患者の検体との混同や交さ汚染が起きる可能性は低いが、防止策としてシリンジや採血管のラベル貼付等によりそれぞれの検体間を混同しない様適切に区別する。 4)採取した検体の試験検査に関する事項: 無菌的に処理された濃縮細胞液をディスポーザルシリンジで無菌的に採取し、手術室の患者の患部に直接移植する。従って、F-ADSCsは、分取後直ちに移植に用いるので、移植前の試験検査等は実施しない。 また、包装、保存は行わない。 5)交付・搬送: 移植骨は手術室において採取されたF-ADSCsを使用して、手術室内で調整する。調整終了後は、手術室内で対象病変部位に使用する。従って、交付・搬送は行わない。 6)管理・保管: 移植骨は手術室で調整後、直ちに患者に移植する。ただし、その一部を確認検査用検体として分取する。確認検査用検体を用いて細胞数、細胞生存率、細胞組成(脂肪組織由来間葉系幹/前駆細胞の割合)を算出する。残りの検体は口腔外科において10年間は保管する。また、Celution®800/CRS自動細胞処理装置の最終工程で得られる最終洗浄液を用いて細菌検査を行う。 |
||
| 非培養脂肪組織由来幹・前駆細胞を低用量rhBMP2を吸着させたリン酸カルシウム顆粒に播種して移植する。 | ||
| 無 | ||
| 国立大学法人 長崎大学 | ||
| FC7160017 | ||
| 長崎大学病院 手術室14 | ||
| なし | ||
(3)再生医療等製品等に関する事項(再生医療等製品を用いる場合のみ記載)
(3)再生医療等製品等に関する事項(再生医療等製品を用いる場合のみ記載)
(4)再生医療等に用いる未承認又は適応外の医薬品又は医療機器に関する事項(未承認又は適応外の医薬品又は医療機器を用いる場合のみ記載)
(4)再生医療等に用いる未承認又は適応外の医薬品又は医療機器に関する事項(未承認又は適応外の医薬品又は医療機器を用いる場合のみ記載)
4 再生医療等技術の安全性の確保等に関す措置
4 再生医療等技術の安全性の確保等に関す措置
(1)利益相反管理に関する事項
(1)利益相反管理に関する事項
① 再生医療等に対する特定細胞加工物等製造事業者からの研究資金等の提供その他の関与
① 再生医療等に対する特定細胞加工物等製造事業者からの研究資金等の提供その他の関与
| 該当なし | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
② 再生医療等に対する医療薬品等製造販売業者等からの研究資金等の提供その他の関与
② 再生医療等に対する医療薬品等製造販売業者等からの研究資金等の提供その他の関与
| 該当なし | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
③ 再生医療等に対する特定細胞加工物等製造事業者又は医療品等製造販売業者等以外からの研究資金
③ 再生医療等に対する特定細胞加工物等製造事業者又は医療品等製造販売業者等以外からの研究資金
| 無 | ||
(2)その他再生医療等技術の安全性の確保等に関する措置
(2)その他再生医療等技術の安全性の確保等に関する措置
| 【脂肪組織由来間葉系幹細胞に関するこれまでの知見】 2006年にHederickらが脂肪組織に間葉系幹細胞が存在することを見出し、その数は骨髄中の100~1000倍であることを明らかにした。脂肪組織は骨髄と比較して、余剰組織として細胞培養に十分な量の回収が可能であり、それから抽出された間葉系幹細胞は、骨髄由来のそれと同等の多分化能を持っているばかりか、増殖能に優れ、大量培養が容易であることが知られている。現在、脂肪組織由来間葉系幹細胞は、基礎研究では骨再生はもとより様々な分野で応用が試されており、臨床においても難治性皮膚疾患や乳房再建、歯周組織などで臨床研究が実施されている。しかしながら、高度に萎縮・欠損した歯槽骨の再生に臨床応用された報告は少なく、国内では例をみない。脂肪組織からの幹細胞の回収に関しては、Cytori Therapeutics Inc.(San Diego, CA, USA)より、高精度脂肪組織由来幹細胞抽出システム(Celution システム)が既に開発されおり、回収された幹細胞を用いた組織再生治療が期待されている。例えば、腹圧性尿失禁治療においては、回収された細胞を障害された尿道の括約筋および尿道粘膜下に移植することで、括約筋機能を回復させ得ることが報告されている。又、Celutionシステムにより分離された脂肪組織由来幹細胞からの骨芽細胞様細胞への分化誘導も既に確認されている。現在までに、脂肪組織由来幹細胞を用いた臨床研究は国内8施設(8課題)実施されており、これまでこの細胞と因果関係の否定できない重篤な有害事象は報告されていない。さらに直近では、本研究と同様にCelutionシステムを使用して単離した非培養脂肪組織由来細胞を歯槽骨再生(上顎洞挙上術)に応用した臨床研究例が報告されており、安全性とその有効性が一部示唆されている(Prins HJ et al. Bone regeneration using the freshly isolated autologous stromal vascular fraction of adipose tissue in combination with calcium phosphate ceramics, Stem Cells Transl Med, 2016)。 【歯槽骨再に対するBMP適用に関する知見】 歯槽骨の領域では、従来から骨形成蛋白質(Bone Morphogenetic Protein;BMP)の応用が進められてきたのは周知の通りだが、そのBMPは足場材料と共に動物に移植すると、本来骨組織のない部位に異所性に骨を形成させる強い骨誘導作用を持つ。また、骨欠損部においてもBMPが骨組織を再生させることは、数多くの動物実験モデルにて明らかにされている。しかしながら、高等な動物になるに従って、骨組織を誘導するために必要なBMPの用量は増加することも明らかになっている。これは、より高等な動物になるに従って、BMPの作用に対する様々な負のフィードバック機構が強力に働いていると思われる。さらに、受容者の加齢に伴い、BMPの骨誘導作用は減弱することも明らかになっており、これは加齢に伴いBMPに応答する細胞が減少するためと考えられる。われわれも人工代用骨に骨誘導能を付与するため、BMPを応用したTissue Engineeringによる骨再生を基礎実験から前臨床段階にて試みてきたが、その結果においても、BMPの移植にはそれに応答する細胞の添加が有効であることが明らかになっている(Seto I et al. Plast Reconstr Surg, 2006)。 一方で、BMPに関しては、既に幾つか臨床研究が行なわれている。わが国ではBMPの臨床応用は厚生労働省による認可は得られていないが、欧米やオーストラリアでは、Ⅰ型アテロコラーゲンスポンジを担体としたrecombinant human(rh)BMP2が、Infuse Bone Graft(Medtronic社)として認可され、既に販売されている。rhBMP2(BMP2)は、米国食品医薬品局(FDA)から歯科・口腔外科領域において、上顎洞底挙上術における自家骨に変わる移植術、あるいは抜歯窩保全用の移植材としての使用が認可されており、多施設ランダム化臨床試験の結果、上顎洞と抜歯窩のいずれにおいても自家骨移植と同等の治療成果が得られたと報告されている。また、rhBMP-7も牛脱灰骨基質やメチルセルロースなどを担体とした商品(OP-1 ImplantやOP-1 Putty: Olympus社)が販売されている。しかしながら、BMPについては、動物実験の結果から劇的な骨組織の再生が期待されたものの、実際のところは期待されたほどの臨床成果が得られていない。これは、先に述べたように、動物実験が比較的若い動物で行なわれたのに対し、臨床研究の多くが高齢者を対象として行なわれたため、局所の応答細胞ばかりでなく、加齢によって血中を循環している前駆細胞も減少しているためと考えられる。ヒトへの臨床応用を考えた場合、BMPは上顎洞底の挙上や抜歯窩のような小さな歯槽骨欠損に対しては効果が期待出来るが、比較的大きな骨欠損に対しては、骨膜のような骨芽細胞の供給源がある場合を除いて、応答する細胞と共に移植する必要があると思われる(Seto I et al. Plast Reconstr Surg, 2006)。 又、腫脹を惹起させる強い副作用もあることから、適応の拡大については、効果が期待できる適切な用量を十分に検討する必要がある。比較的炎症による副反応の危険性が低い上顎洞底挙上術においては、Loma Linda大学のBoyneらがrhBMP2を応用した時の主な副反応について詳細な報告を行なっている(Boyne PJ et al. J Oral Maxillofac Surg, 2005)。即ち、0.75~1.5 mg/mlの用量において、術後の顔部浮腫が35例中21例、口腔内の紅斑35例中7例、皮膚発疹35例中3例、上顎洞炎の発現が35例中3例とある。この中で最も発現率の高い顔部浮腫については、1.5 mg/mlの用量時に17例中14例と有意に高い発現率であったものの、その半量である0.75 mg/mlの用量では18例中7例の発現と、その発現率はBMP非使用のコントロール群と同等であり、その他の副反応もコントロール群と有意差は認めていない。このことから、低用量化により副反応の発現を制御できることが示唆されている。 【本研究の実施】 以上に本研究にて提供する再生医療の安全性に関する検討内容を記したが、これらの知見をもとに計画された再生医療等提供計画書および再生医療等提供基準に従い、適正に再生医療が実施されていることを実施責任者は随時確認を行うと共に、適正な実施を担保するための必要な指示を行う。詳細は、別添え実施計画書42-49頁に記載。 |
||||||
| 【小型実験動物を用いた研究】 ① 培養ヒト脂肪由来間葉系幹細胞の応用 ヒト脂肪(頬脂肪体)組織由来間葉系幹細胞をハイドロキシアパタイト(HA)の担体に播種し、デキサメタゾン、アスコルビン酸とβ-グリセロリン酸、およびBMP2の存在下の3次元培養下で骨芽細胞様細胞に分化誘導し、とヌードマウス背部皮下に移植することによって、骨組織形成の有無を確認した。その結果、脂肪組織由来間葉系幹細胞を骨芽細胞様細胞に分化誘導後に移植したもののみ異所性の骨形成が見られた。なかでもデキサメタゾンとBMP2の両因子の添加培養後に移植したものに顕著な骨形成が観察され、これらの骨形成因子を有効に使うことで、ヒト脂肪組織由来間葉系幹細胞から有効に骨組織を再生できることを確認した(Shiraishi T et al. J Dent Res, 2012)。 ② BMPと骨髄多血小板血漿の応用 BMP2と末梢血多血小板血漿(PRP)を応用した骨再生について、下記中型動物実験において、それらの相乗効果による骨誘導性の亢進を認めた。そこで、骨髄液から抽出したPRP分画に着目して実験を行った。骨髄液には数は多くないものの間葉系幹細胞を含むことから、末梢血PRPと比較して、このような幹細胞成分も濃縮される。そして、このような幹細胞成分は、BMP2に応答することで骨形成を促進すると考えられる。 骨髄PRPと低用量BMP2の相乗効果について、それらを人工骨(β-リン酸三カルシウム:β-TCP)に組み込んだ移植骨をマウスの頭蓋骨上に移植することで、評価を行った(江頭寿洋ほか 第13回日本再生医療学会総会O-36-4; 論文作成中)。その結果、骨、髄PRPを組み込んだ材料において、それが組み込まれてない試料と比較して早期に骨形成が認められ、頭蓋骨に連続しない異所性の骨形成も人工骨の周囲に有意に認められた。細胞成分と低用量BMP2との相乗効果の有用性が示唆された。 ③ 非培養ヒト脂肪組織由来幹細胞の応用 ヒト脂肪(頬脂肪体)組織から遠心操作と酵素処理にて単離した細胞群を、予め低用量BMP2(通常量の半量)を吸着させたリン酸カルシウム(β-TCP)の担体に播種し、ヌードマウス頭蓋骨上に移植を行うことで、骨組織形成の促進の程度を確認した。その結果、非培養脂肪組織由来幹細胞を応用すると、半用量のBMP2による骨誘導を通常用量のBMP2を使用した時と同レベルに増幅させることが可能であることが分かった(Egashira K et al. PLoS ONE 2018)。 【中型実験動物を用いた研究】 ① 間葉系幹細胞と末梢血PRPの応用 移植動物としてイヌを用い、骨髄由来間葉系幹細胞と多血小板血漿(PRP)の有用性を検討した。イヌの顎骨に形成した骨欠損に間葉系幹細胞とPRPを移植すると、自家海綿骨細片移植と同程度の骨形成が見られることが分かった(Ito K et al. Clin Oral Implants Res, 2006)。さらに、再生された骨組織にデンタルインプラントを埋入することにより咬合機能の回復が可能であることや、PRPとMSCの移植が歯槽骨の再生にも有用であることも過去に示されているYamada Y et al. Tissue Eng, 2004; Yamada Y et al, Clin Oral Implants Res, 2004)。 ② BMPと末梢血PRPの応用 末梢血PRPとBMP2を吸着させた人工骨(Bisphasic Calcium Phophate: 75%TCP+25%HA)を混和して作製した移植骨を家兎頭蓋骨欠損に移植することで、PRPとBMPの併用効果を評価した(Yoshida K et al. Biomed Mater Eng, 2013)。その結果、PRPを併用することで、BMPによる骨形成が早期に促進されることが示され、BMPに細胞を併用することの有用性が示された。 【非培養脂肪組織由来幹細胞の抽出】 非培養脂肪組織由来幹細胞は、遠心操作と酵素処理にて頬脂肪体組織から単離・抽出した。抽出した細胞群は、CD34、90、105陽性細胞をそれぞれ10、25、1%程度含有していた(Egashira K et al. PLoS ONE 2018.)。高精度脂肪組織由来幹細胞抽出システム(Celution遠心分離装置)では、脂肪組織1ml当たり平均3.0x105個の細胞が得られ、細胞生存率は86.6%程度と報告されており(Lin K et al. Cytotherapy, 2008)、2gのβ-TCPを片側上顎洞へ移植する場合、3x107個の細胞を移植に用いるとすると、100ml程度の脂肪組織が必要となる。本研究では、両側上顎洞へ移植する場合を考えると、脂肪組織採取の侵襲や安全性などを考慮し、200~100mlまでの採取とすることが妥当と考えられる。 【移植骨の調整】 移植骨は、上記の非臨床試験において、低用量0.5μg (12.5μg/ml)[小型動物実験における通常使用量1.0μg(25μg/ml)の半量]のBMP2を吸着させた20mg人工骨β-TCP顆粒(Osferion)に3x105個の非培養脂肪組織由来幹細胞を混和した後、トロンビン/塩化カルシウム混合液にてゲル化させて作製した。臨床におけるBMP2の用量については、前述したように通常用量は1.5mg/mlとされているが、それを半量の0.75mg/mlに減じると、顔部浮腫などの副作用がBMP非使用時と同程度までに軽減されることが報告されている(Boyne PJ et al. J Oral Maxillofac Surg, 2005)。本研究では、その安全性を考慮し、1/3量である0.5mg/mlの用量にて移植骨を作製する。具体的には、2gのβ-TCP を片側上顎洞への移植に使用する場合、Infuseに付属の溶解液(蒸留水)4.2mlにより0.5mg/mlに調整したBMP2溶液(2.1mg BMP/4.2ml)に2g β-TCPを浸すことで、BMP2をβ-TCPに吸着させる。この場合、片側の上顎洞に使用するBMP2の総量は、2.1mgとなり、下顎で報告されている通常濃度での総用量4.2mgの半量である(Herford AS et al. J Oral Maxillofac Surg, 2007)。また、前述のLoma Linda大学のBoyneらの報告では、片側の上顎洞に8~20mg程度のrhBMP2を使用しており、その使用量と比較すればさらに低用量であると言え、安全に使用できる条件であると考える。 非培養脂肪組織由来幹細胞とBMP吸着人工骨の混和については、上記の条件でβ-TCPをBMP2溶液に15分間浸した後、セルストレイナーにて余剰の水分を除いた上で、1x107個程度の細胞とガラス皿上で混和する。その後、0.3~0.5mlの自己血清を添加・混和しゲル化させ、ゲル化後にこれを直ちに移植に用いる。自己血清は、術前に静脈から5ml程度採血し、そのままプラスチック製真空採血管を専用の遠心分離器に設置して遠心分離(3600回転、8分)後に上清の血清部分を1ml程度分取する。 移植骨の作製には、以上のベッドサイドにおける用事調整が、操作ステップと各材料の汚染の機会を最小限にする妥当な方法であると判断する。 【本研究の実施】 これらの知見をもとに計画された再生医療等提供計画書および再生医療等提供基準に従い、適正に再生医療が実施されていることを実施責任者は随時確認を行うと共に、適正な実施を担保するための必要な指示を行う。詳細は、別添え実施計画書42-49頁に記載。 |
||||||
| 【可否の決定方法】 臨床研究への参加希望者に対して、治療開始予定日の3ヶ月以内に以下の「検査項目」を全て実施する。ただし、血液検査、尿検査については治療開始1ヶ月以内のデータが必要である。登録前検査の結果に基づいて症例検討会にて検討を行なう。被験者として適格であると判断された場合には、本臨床研究の説明を行ない、同意の得られた症例については、脂肪組織採取および採血が計画される。 (検査項目) ① 臨床所見 ・主訴、既往歴、家族歴、現病歴 ・血圧、脈拍数 ・自覚症状、口腔内診査 ② 血液検査 ・末梢血液検査: 白血球(WBC)及び白血球分画(WBC分画)、赤血球数(RBC)、ヘモグロビン(Hb)、ヘマトクリット(Ht)、血小板数(PLT)、PT、APTT、フィブリノゲン(Fib) ・血液生化学検査: TP、GOT(AST)、GPT(ALT)、γGTP、アルブミン(Alb)、総ビリルビン(T-Bil)、直接ビリ ルビン(D-Bil)、ALP、LDH、BUN、クレアチニン、尿酸、電解質(Ca、Na、K、Cl)、総コレステロール(T-CHO)、グルコース、HbA1c、CPK、CRP ・免疫血清学検査 (被験者に対して事前に本検査実施に関する承諾をとり、結果の報告については、被験者の意思に任せる。また、結果については一切公表しない): ABO式血液型、Rh式血液型、梅毒定性(TPHA法、梅毒凝集反応定性)、HCV抗体、HBs抗原、HTLV-Ⅰ抗体、HIV抗体 ③ 尿検査 ・尿一般検査(定性・定量) ④ X線撮影 ・頭部CT撮影 ・パノラマX線撮影(院内あるいは紹介医師による) ・胸部X線撮影 ⑤ 心電図 【決定を行う者:症例検討会】 個々の症例について、本移植骨による歯槽骨再生療法が適応となるかを症例検討会を開催して決定する。 ① 症例検討会の委員長は責任歯科医師とする。 ② 症例検討会委員長は複数の委員を、副責任歯科医師、分担医師・歯科医師、研究協力者以外の当施設の医師・歯科医師を含めて複数名指名する。また必要に応じて、外部機関に所属する者を指名することもできる。 ③ 症例検討会は委員の2/3以上の出席で成立し、適応の決定については出席委員全員の賛成が必要である。 |
||||||
| 下記(1)から(3)のいずれかの事項に該当し、責任歯科医師が臨床試験継続を困難と判断した場合、責任歯科医師はその時点で臨床試験の一部または全体を中断する。その上で、臨床試験の一部または全体を中止するか否かを決定し、その旨を文書に記録する。 (1)臨床試験に関する新たな安全性情報または重篤な有害事象の情報が得られた場合。 (2) 責任歯科医師または長崎大学病院のいずれかが、再生医療等安全性確保法、臨床試験実施計画書から重大な逸脱を行った場合。 (3) その他、本試験実施中に試験の中止・中断が必要と考えられる新たな情報が得られた場合。責任歯科医師は、長崎大学病院臨床研究倫理委員会などとの協議により本試験の一部または全体の中止を決定した場合、速やかにその旨を理由とともに、長崎大学病院に文書で通知する。長崎大学病院長は、速やかにその旨を理由とともに、特定認定再生医療等委員会に文書で通知する。責任医師は、理由の如何を問わず本試験が中止または中断された場合、本試験に参加中の被験者に速やかにその旨を通知し、適切な処置ならびに被験者の安全性を確認するための検査などを実施する。 |
||||||
| 【採取した細胞の保管方法・期間】 移植骨は手術室で調整後、直ちに患者に移植する。ただし、その一部を確認検査用検体として分取する。確認検査用検体を用いて細胞数、細胞生存率、細胞組成(脂肪組織由来間葉系幹/前駆細胞の割合)を算出する。残りの検体がある場合は口腔外科において10年間保管する。 (研究機関中の保管の方法)研究室内(病院本館8階・共同実験室13)の施錠可能なディープフリーザにて保管される。 |
||||||
| 試料は施錠可能なディープフリーザにて総括報告書提出日より10年間保管され、その後オートクレーブの後廃棄される。また、組織バンクへの寄託は予定しない。 | ||||||
| 【有害事象の報告と対応】 ① 報告義務のある有害事象:報告義務のある有害事象は「有害事象の定義」で規定した重篤な有害事象(SAE)のうち、プロトコル治療期(自己血清作製用末梢血採血ないしは骨髄穿刺から手術後2年以内)に発生したもので、本治療との因果関係が否定出来ないものとする。 ② 報告手順: 1)一次報告(24時間以内) 報告義務のある有害事象あるいは重大な事態 が発生した場合、責任歯科医師は、本プロトコル治療との因果関係の有無に関わらず、発生を知った時点から速やかに長崎大学病院長および臨床研究医療センター長に口頭または電話にて連絡し、報告義務のある有害事象の場合には「重篤な有害事象に関する報告書」(様式第6号)にその時点までに把握できている情報を記載して、24時間以内に提出する。 2)二次報告(7日以内) 責任歯科医師は、死亡もしくは死亡につながるおそれのある症例については、事態を知った時点から、7日以内に、治療のために医療機関への入院又は入院期間の延長が必要とされる症例、障害、障害につながるおそれのある症例、重篤である症例、後世代における先天性の疾病又は異常については事態を知った時点から15日以内に「重篤な有害事象に関する報告書」を完成させ、長崎大学病院長および長崎大学病院臨床研究倫理委員会、再生医療等提供計画に記載された特定認定再生医療等委員会に提出する。 3)詳細調査報告 長崎大学病院臨床研究倫理委員会および特定認定再生医療等委員会から詳細な情報の提供を要請された場合、責任歯科医師は長崎大学病院臨床研究倫理委員会および特定認定再生医療等委員会の指示に従って調査を行い、報告書を提出する。 4)最終報告 責任歯科医師は、重篤な有害事象の転帰が確定した後、二次報告後の経過及び転帰に関する報告書を作成し、長崎大学病院長および長崎大学病院臨床研究倫理委員会と、特定認定再生医療等委員会に提出する。 ③ 対応手順 1)一次報告後の対応 責任歯科医師は、登録中断等の緊急対策の必要性を判断し、必要な場合その内容を長崎大学病院長に報告し、病院長が決定する。 2)二次報告後の対応 担当医師(副責任歯科医師、分担医師・歯科医師、研究協力者)は、責任歯科医師に「重篤な有害事象に関する報告書」を送付し、評価を依頼する。 3)責任歯科医師による評価・勧告 評価を依頼された責任歯科医師は、「重篤な有害事象に関する報告書」の内容を検討し、必要な場合に担当歯科医師に詳細な情報の提供を要請する。 責任歯科医師は、提供された全ての情報に基づき評価を行い、それを基に病院長が、試験の中止、登録の中断・再開、プロトコルの変更等の決定を行う。病院長および責任歯科医師は、速やかに上記を行った上で、「特定認定再生医療等委員会」による審査を通して、九州厚生局に報告する。 4)対策の決定 責任歯科医師は、長崎大学病院長の勧告を踏まえて、対策の必要性及びその内容について決定を行う。責任歯科医師は、決定事項を病院長に連絡する。病院長は、九州厚生局から意見があった場合には、それに従い対応を行う。 【有害事象の定義】 1) 有害事象(AE: Adverse Events) 本臨床試験中に起こる、あらゆる好ましくない、あるいは意図しない徴候(臨床検査値の異常を含む)、症状または病気のことであり、当該治療方法と因果関係の有無は問わない。有害事象のなかには放射線障害や手術による損傷も含まれる。 2) 有害反応(AR: Adverse Reaction) 有害事象のうち、当該治療との因果関係が否定できないものをいう。 3) 予測できない有害反応(UAR:Unexpected Adverse Reaction) 有害反応のうち、本臨床試験で使用される薬剤等の添付文書(被験製剤概要書に記載)、および本プロトコル15.3予想される有害事象に記載されていないもの、あるいは記載されていてもその性質や重症度が記載内容と一致しないものをいう。 4) 重症度(判定)(Grading) 有害事象の重症度についてはNCI CTCAE ver.4.0による。 Grade 1 軽度のAE Grade 2 中等度のAE Grade 3 高度のAE Grade 4 生命を脅かすまたは活動不能とするAE Grade 5 AEによる死亡 5) 重篤な有害事象(SAE: Serious Adverse Event) 重篤な有害事象を以下の通りに定義するが、これは「ヒト幹細胞を用いた臨床研究指針」中における「重大な事態」に相当するものとする。 ① 死亡 ② 死亡につながる恐れのあるもの ③ 治療のために入院または入院期間の延長が必要となるもの ④ 永続する障害 ⑤ 永続する障害につながる恐れのあるもの ⑥ その他、①~⑤に準じて重篤であるもの ⑦ 後世代における先天性の疾病または異常 【有害事象の評価】 有害事象は定めた検査項目に基づき、指定された時期に評価するほか、それ以外の発現時にも適切に評価する。このとき、その症状または疾患、他覚所見の内容、発現日、程度、重篤度、処置の有無及びその内容、転帰及びその判定日、本治療との関連性及びその理由を症例報告書の有害事象欄に記入する。 プロトコル治療期間中に観察された症状または疾患、他覚所見において、本治療との因果関係が否定できない有害事象が認められた場合は、正常化または有害事象として捉えないレベルに回復するまで、あるいは症状として固定化し変化が期待できず 臨床的に問題が無くなる状態となるまで追跡調査を行う。 有害事象の転帰は、以下の基準で分類する。 ① 回復:正常化または有害事象として捉えないレベルまでに回復したもの ② 継続:その時点で回復に至っていないもの ③ 死亡:被験者が死亡に至ったもの 【予想される有害事象】 ① 感染(脂肪組織採取後および移植移植後) ② 疼痛(脂肪組織採取後および移植移植後) ③ 出血(脂肪組織採取後および移植移植後) ④ 腫脹(脂肪組織採取後および移植移植後) ⑤ 発熱(脂肪組織採取後および移植移植後) ⑥ ショック(脂肪組織採取後および移植移植後) ⑦ 歯肉の哆開(移植骨移植後) 東京大学医科学研究所での先行臨床試験(15例)においては、上記の有害事象の中で、②と④は培養骨移植手術後に全例手術部位で発生している。これは骨および骨膜、歯肉を対象とした手術であることから反応性に発生するものと考えられる。それ以外は発生していない。しかしながら、観血的な処置においては起こる可能性があるものとして、記載する。 |
||||||
| 【提供終了後の措置の内容】 ① 手術後1日目および1、2,4,6,8,16,20、28週目 臨床所見の自覚症状の確認及び口腔内診査を実施する。これに加え、パノラマX線撮影を治療後6週、12週、24週目に実施する。頭部CT撮影は手術後16週、および28週目に実施する。 ② 手術後16週目の検査項目 「臨床所見」(ア)主訴、既往歴、家族歴、現病歴、「血液検査」(ウ)ABO式血液型、Rh式血液型、「尿検査」 尿一般検査、「X線撮影」 (ア)頭部CT撮影(イ)パノラマX線撮影(ウ)胸部X線撮影を全て実施する。 責任歯科医師、分担歯科医師との協議によりデンタルインプラント埋入可能と判断された被験者に関しては、術後16週目を目途にインプラント1次手術を行ない、その際に移植部からの骨生検を行う。 ③ 手術後28週目または手術後27週以内におけるプロトコル治療中止時 臨床所見の自覚症状の確認及び口腔内診査を実施する。また、パノラマX線撮影と頭部CT撮影を実施する。 ④ 手術後9ヶ月から24ヶ月までの検査項目 臨床所見の自覚症状の確認及び口腔内診査を3ヶ月毎に実施する。ただし、治療12ヶ月及び24ヶ月後は、パノラマX線撮影と頭部CT撮影を実施する。 【エンドポイントの定義】 第Ⅰ相試験のエンドポイント 1)主要エンドポイント 「安全性」:本臨床研究期間中に発現した有害事象の種類別の有無。 2)副次エンドポイント 「骨生検における骨形態計測量」:骨生検で得られた組織から非脱灰標本を作製しVillanueva-Goldner染色を施した後、任意の10視野における単位面積あたりの新生骨面積、残留β-TCP面積、骨髄腔面積、繊維性結合組織面積を算定したものを平均し、それぞれ新生骨量、残留β-TCP量、骨髄腔量、繊維性結合組織量とする。 【総括報告書の提出について】 試験期間中は、少なくとも1年に1回、「臨床研究実施状況報告書(年次報告書)(臨研様式第7号)」を研究助成係を通じて病院長に提出し、試験継続の可否についてヒト幹細胞臨床研究審査委員会特定・認定再生医療等委員会の審査を受け、厚生労働省への定期報告を届出る。試験の中止時または終了後には研究結果に関する総括報告書を作成・提出する。 |
||||||
| 研究参加期間として、移植手術後2年まで追跡する。追跡期間終了後は、紹介医にて6ヶ月ごとの定期検診が継続的に行われるため、紹介医との連携のもと患者状況の把握に努める。また、追跡期間終了後においても責任医師を通じて、患者からの相談を受け付けるものとする。 | ||||||
| 無 | ||||||
| 実施計画の公表日 | ||||||
| 2018年02月21日 | ||||||
| 募集中断 | Suspended | |||||
5 細胞提供者及び再生医療等を受ける者に対する健康被害の補償の方法
5 細胞提供者及び再生医療等を受ける者に対する健康被害の補償の方法
細胞提供者について(特定細胞加工物を用いる場合のみ記載)
細胞提供者について(特定細胞加工物を用いる場合のみ記載)
| 無 |
再生医療等を受ける者について
再生医療等を受ける者について
| 有 |
6 審査等業務を行う認定再生医療等委員会に関する事項
6 審査等業務を行う認定再生医療等委員会に関する事項
| 再生医療普及協会 認定再生医療等委員会 | none | |
| NA8180001 | ||
| 東京都中央区勝どき1-13-1 イヌイビル・カチドキ3階 | 1-13-1 Kachidoki Cyuo-ku, Tokyo | |
| 03-5547-0203 | ||
| office@rdclinic.jp | ||
| 第一種再生医療等又は第二種再生医療等を審査することができる構成 | ||
| 適 | ||
| 2017年01月11日 | ||
7 その他
7 その他
| 再生医療に関する記録は、下記の事項に則り、医療を受けた患者毎に記録し保存する。 【個人情報事項】 1.再生医療等を受けた者の住所、氏名、性別及び生年月日 2.病名及び主要症状 3.使用した特定細胞加工物又は再生医療等製品の種類、投与方法その他の再生医療等の内容及び評価 4.再生医療等に用いる細胞に関する情報 5.特定細胞加工物の製造を委託した場合は委託先及び委託業務の内容 6.再生医療等を行った年月日 7.再生医療等を行った医師又は歯科医師の氏名 【匿名化の方針】 患者試料は施設内では匿名化されないが、外部への検査委託、検体の保管時、本試験の結果解析時には連結可能匿名化を行う。匿名化及び対照表の管理は個人情報保護管理者が行う。 【匿名化の方法】 試料を採取した段階でそれぞれ番号付けされる。匿名化および番号は紙台帳およびPCにて管理される。尚、PCはネット接続のない専用ものを使用する。検査等を外部へ発注する場合には番号のみでやり取りされるため、検査等によって得られた結果と特定の個人とが第3者により結び付けられることはない。 【情報管理体制】 責任歯科医師が保管する同意書のコピーなど個人情報は施錠可能な研究室内の鍵のかかる保管庫にて管理される。対照表は個人情報保護管理者により管理される。資料は匿名化されているが、研究データについても施錠による管理を行う。 症例報告書の作成・取り扱い、医学雑誌等への発表においては被験者の秘密は保全する。被験者の秘密保持の立場から、診療録、検査データ、被験者の同意に関する記録は当院において、また、症例報告書及びそれに準ずる書類は責任歯科医師の所属する研究室において、それぞれ保存する。これらの記録等は監督官庁の監査あるいは他機関からの相互監査の請求があれば開示されるが、その秘密は保持される。研究責任者は、これらの記録等を総括報告書提出日より10年間保存し、必要に応じて検索できるように保存する。 |
||
| 本研究の実施責任者・分担医師・歯科医師、研究協力者は、研究の実施・参加に際し、全員CITI JAPANプロジェクトによるe-ランニングプログラムの受講は必須でである。また、継続研修として、 長崎大学病院臨床研究センター主催の「臨床研究に関する研修会」及び「臨床研究・治験推進セミナー」を対象に年に1度以上の受講が義務付けられる。さらに、厚生局や日本再生医療学会など外部機関が実施する教育・研修又は学術集会へ参加し、再生医療等の提供に係る倫理や具体的な実施方法などについて常に情報収集に努める。 | ||
| 相談、苦情の窓口について 本臨床試験に関する相談、苦情、あるいは個人情報に関する相談、苦情については以下を窓口とする。 ・長崎大学病院 医療安全 TEL: 095–819–7616(代表) 安全・広報課にて受けた苦情や問い合わせについては、速やかに内容を実施責任者に報告される。実施責任者は、内容を検討し、必要な場合に担当医師・歯科医師に詳細な情報の提供を要請する。その上で、分担医師・歯科医師および研究協力者と協議のもと、対策の必要性とその内容について決定を行う。実施責任者は、苦情や相談の内容と対策の内容について長崎大学病院長に報告を行う。 |
||
| 非該当 | ||
| なし | none | |
| 無 | ||
| 非該当 | ||
| 非該当 | ||
| 非該当 | ||
添付資料
添付資料
| 4 再生医療等を受ける者に対する説明文書及び同意文書の様式 | 2020年3月27日修正 2020年1月経過措置変更 5. 非培養脂肪細胞 説明同意文書(手術室).pdf |
|---|