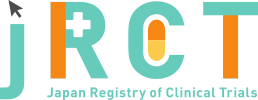臨床研究等提出・公開システム
再生医療等提供計画情報の詳細情報です。
| 第二種 | ||
| 令和2年3月11日 | ||
| 令和4年10月24日 | ||
| 令和3年6月13日 | ||
| 令和3年6月13日 | ||
| 「小児脳性麻痺など脳障害に対する自家臍帯血単核球細胞輸血」-細胞バンクで保管されている自家臍帯血単核球細胞を用いた輸血の安全性研究- | ||
| 脳性麻痺など脳障害に対する自家臍帯血細胞輸血の安全性について | ||
| 高知大学医学部附属病院 | ||
| 執印 太郎 | ||
| 小児脳性麻痺など脳障害を有する小児に対して、自家臍帯血幹細胞輸血を行い、損傷した脳神経細胞の再生をはかり、患児の身体・知的障害の改善、発達を促すことを目標にしている。本研究の目的は、国内でも初めてとなる細胞バンクにて保管・管理された自家臍帯血細胞の輸血投与における安全性を確認することにある。副次的に脳性麻痺などの脳障害に対する効果を確認する。 | ||
| 1 | ||
| 脳性麻痺 | ||
| 研究終了 | ||
| 大阪大学第一特定認定再生医療等委員会 | ||
| NA8140001 | ||
総括報告書の概要
総括報告書の概要
臨床研究の名称等
臨床研究の名称等
| 第二種 | |||
| 令和3年12月3日 | |||
| jRCTb060190039 | |||
| 提供しようとする再生医療等の名称 | 「小児脳性麻痺など脳障害に対する自家臍帯血単核球細胞輸血」-細胞バンクで保管されている自家臍帯血単核球細胞を用いた輸血の安全性研究- | ||
| 認定再生医療等委員会の名称(認定番号) | 大阪大学第一特定認定再生医療等委員会 (NA8140001) | ||
| 2021年06月13日 | |||
| 6 | |||
| / | 症例1 1.7歳男児、痙性四肢麻痺、粗大運動尺度分類(GMFCS level)V 症例2 6.7歳男児、痙性対麻痺、粗大運動尺度分類(GMFCS level)Ⅲ 症例3 2.3歳男児、痙性右片麻痺、粗大運動尺度分類(GMFCS level)Ⅲ 症例4 3.2歳男児、痙性右片麻痺、粗大運動尺度分類(GMFCS level)I 症例5 2.2歳女児、痙性左方麻痺、粗大運動尺度分類(GMFCS level)I 症例6 4.0歳男児、弛緩性麻痺、粗大運動尺度分類(GMFCS level)IV |
Six children with cerebral palsy aged 1.7 to 6.7 years old. Gross Motor Function Classification System (GMFCS) levels were 2 (Cases 4 and 5) as grade I, 2 (Cases 2 and 3) as grade III, 1 (Case 6) as grade IV, and 1 (Case 1) as grade V. | |
| / | 上記6名に自家臍帯血単核球細胞を輸血した。全員に輸血後6、12、24および36か月の後観察で、粗大運動能力尺度(GMFM)、知能検査(新版K式発達検査またはWISC-IV)、脳波、頭部MRIおよび血液・尿検査を行った。 | Autologous umbilical cord mononuclear cells (ACBMC) were administered intravenously in 6 children with cerebral palsy. Evaluation was performed at 6, 12, 24, and 36 months after treatment. Gross Motor Function Measure (GMFM), Kyoto Scale Psychological Development (KSPD), WISCIV, electroencephalography (EEG), brain MRI, and examinations including blood and urine were tested in all patients. All 6 patients were followed completely by 36 months after treatment. | |
| / | 疾病等は発生しなかった。 | No diseases were developed in all patients. | |
| / | 1. 観察期間を通じて認められた有害事象は以下の通りであるが、自家臍帯血単核球細胞輸血に関連すると思われる副事象や有害事象は認められなかった。 ・症例2(2017年6月6日臍帯血輸血)において、2017年6月14日の血中NSE(32.5ng/ml)と小児の正常上限(25ng/ml)を超えたが同年7月25日に正常値となった。 ・症例3(2017年8月16日臍帯血輸血)において、2018年2月21日に顕微鏡的血尿が認められたがその後は消失した。 ・症例4(2017年10月17日臍帯血輸血)は、輸血前に熱性けいれんの既往が2回あり、2018年7月13日に無熱性けいれんが 1 回認められた。その後、けいれんは認めていない。 ・症例6(2018年4月17日臍帯血輸血)は、輸血前に1度のみ熱性けいれんを認めたが、その後、けいれんは認めていない。2年後の定期観察時に脳波で棘波を認めたため、かりつけ医に定期的観察を依頼した。3年後の最終観察では棘波は残存したが、2年目観察時よりも頻度は減少していた。以後もかかりつけ医で定期観察を実施している。頭部MRIでも、輸血前後で変化を認めなかった。 なお、疾病ではないが、輸血後の後観察で一部、時期が許容範囲を超え不適合となった。 症例1 輸血後36か月が41か月後(COVID-19感染拡大防止による移動自粛のため) 症例2 輸血後36か月が41か月後(COVID-19感染拡大防止による移動自粛のため) 症例3 輸血後36か月が44か月後(COVID-19感染拡大防止による移動自粛のため) 症例6 輸血後24か月が28か月後(学校行事参加のため) 2.88項目にわたる粗大運動能力尺度(GMFM-88)は、3年間の観察で4ポイント以上の上昇が全例に 認められた。さらにRussellらの障害度別・年齢別の改善度(66項目にわたるGMFM:GMFA-66)では、6例中4例(症例2、3、5、6)が治療としてリハビリテーションのみを行った場合よりもポイントが上昇していた(Russell DJ et al. Gross Motor Function Measure (GMFM-66 &GMFM-88) User’s Manual,2nd Ed. 2013, Mac Keith Press, UK)。 3.5歳未満に実施した新版K式発達検査では5例中3例(症例3、5、6)で+6~+30とばらつきがあるものの言語社会のポイントの上昇が見られ、5歳以上で実施した1例(症例2)のWISC-IVではすべての面でポイントの上昇が得られた。一方、新版K式で全般と言語社会の両面でポイントの上昇のない例(症例1、4)も認められた。前述の3例(症例3、5、6)は、上記2に示すように運動能力のポイントも上昇した。 4. 以上から、自家臍帯血輸血は、一部の脳性麻痺患児に対して、運動面のみでなく言語面のポイントも上昇する可能性がうかがえた。 5.脳波、頭部MRIおよび血液尿検査では輸血前後で変化は認められなかった。 6.運動能力や言語社会の改善と投与細胞数の間には相関は認められなかった。 |
1.No adverse health change and serious adverse event were observed in all patients. No unfavorable changes in terms of health or serious adverse events were seen in all patients. Case 2 Transient high value of serum NES (32.5ng/ml) was observed 8 days after transfusion. Case 3 Transient microhematuria was observed 4 months after transfusion. Case 4 This case had past illness of febrile convulsion twice. Afebrile convulsion was observed once 8 months after transfusion, but thereafter no convulsion was recognized during observed periods. Case 6 This case had past illness of febrile convulsion. Spikes in EEG were recognized 2 years after transfusion. But spikes in EEG decreased 3 years after transfusion and no convulsion and change of brain MRI findings were observed during observed periods. Although not a disease, in the post-transfusion course, there were cases of nonconformity with timing beyond the permissible range. Case 1 Post-transfusion duration of 36 months was extended to 41 months (because of travel restrictions to prevent the spread of COVID-19). Case 2 Post-transfusion duration of 36 months was extended to 41 months (because of travel restrictions to prevent the spread of COVID-19). Case 3 Post-transfusion duration of 36 months was extended to 44 months (because of travel restrictions to prevent the spread of COVID-19). Case 6 Post-transfusion duration of 24 months was extended to 28 months (because of participation in a school event). 2.GMFM-88 scores were increased in all of 6 patients after infusion of ACBMC. In addition, GMFM-66 scores by the method of Russell DJ et al were increased than that of controls in 4 (Cases 2, 3, 5, and 6) of 6 patients (Russell DJ et al. Gross Motor Function Measure (GMFM-66 & GMFM-88), 2nd Ed. 2013, Mac Keith Press, UK). 3.Language-social scales assessed by KSPD improved in 3 (Cases 3, 5, and 6) of 5 patients. Case 2 improved on the overall of WISCV-IV after infusion of ACBMC. On the other hand, Both Cases 1 and 4 did not improved on total and language-social scales assessed by KSPD. Three cases (Case 3, 5, and 6) had greater changes in their GMFM scores than the other cases after treatment. 4.From the above, infusion of ACBMC might improve both motor and language in some patients with cerebral palsy. 5.No significant change was recognized in EEG, brain MRI, and laboratory tests, and there was no significant correlation between the changes of GMFM scores and infused ACBMC counts. |
|
| / | 本研究を実施した6例全例で、再生医療提供から36か月後の観察終了まで血尿や熱性けいれんなどの症状は認められたが、重篤な有害事象は認められなかったことから小児の脳性麻痺に対する自家臍帯血単核球細胞輸血は安全であると考えられる。また副次項目の解析結果から粗大運動能力尺度のポイントの上昇は全例に認められ、運動能力のポイントがより上昇した3例では言語理解ポイントの上昇も認められた。 | No adverse events were recognized in all of 6 children with cerebral palsy who had ACBMC infusion during 36 months periods.Autologous cord blood mononuclear cell infusion was safe. In addition, GMFM scores were increased in all of 6 patients and in 3 cases who had great change in their GMFM scores, improvement on language-social scores was recognized after ACBMC infusion. | |
| 2022年10月24日 | |||
IPDシェアリング
IPDシェアリング
| / | 無 | No | |
|---|---|---|---|
| / | |||
1 提供しようとする再生医療等及びその内容
1 提供しようとする再生医療等及びその内容
申請者情報
申請者情報
| 令和3年12月3日 | |||
| jRCTb060190039 | |||
| 高知大学医学部附属病院 | |||
| 高知県南国市岡豊町小蓮185番地1 | |||
| 執印 太郎 | Shuin Tarou | ||
(1)再生医療等の名称及び分類
(1)再生医療等の名称及び分類
| 「小児脳性麻痺など脳障害に対する自家臍帯血単核球細胞輸血」-細胞バンクで保管されている自家臍帯血単核球細胞を用いた輸血の安全性研究- | Assessment of the safety of autologous umbilical cord blood cells infusions for children with cerebral palsy or cerebral disorder in Kochi ( CBReK ) | ||
| 脳性麻痺など脳障害に対する自家臍帯血細胞輸血の安全性について | Assessement of the safety of autologous umbilical cord blood cells infusions for cerebral palsy in Kochi( CBRek ) | ||
| 第二種 | |||
| 臍帯血は従来から造血幹細胞移植の細胞ソースとして臨床的に利用されており、その範疇での医療は法の対象外である 。当該研究において利用する特定細胞加工物は、臍帯血より分離した単核球細胞であるが、臍帯血を採取した本人への利用であり、また、iPS細胞への誘導や遺伝子導入等は実施しないことから第一種の再生医療ではないと判断した。当該再生医療で利用する単核球細胞の大部分は幹細胞ではないが、造血幹細胞や間葉系幹細胞を含んでおり、それらが病変部位に作用することが機序の一つと考えられているため 、幹細胞を利用していると判断した。実際に投与する特定細胞加工物に施す主な操作は、加工の定義に該当しない遠心、凍結、融解であり培養工程に起因するリスクはないが、当該研究の対象は脳神経疾患であり、本来の細胞と異なる機能を発揮することを目的として使用すること、また、対象となる部位の細胞と同様の機能を持たない細胞の投与であることから相同利用の定義に該当しないものと判断した。上述より、当該研究は第二種再生医療等技術であると判断した。 | |||
(2)再生医療等の内容
(2)再生医療等の内容
| 小児脳性麻痺など脳障害を有する小児に対して、自家臍帯血幹細胞輸血を行い、損傷した脳神経細胞の再生をはかり、患児の身体・知的障害の改善、発達を促すことを目標にしている。本研究の目的は、国内でも初めてとなる細胞バンクにて保管・管理された自家臍帯血細胞の輸血投与における安全性を確認することにある。副次的に脳性麻痺などの脳障害に対する効果を確認する。 | |||
| 1 | |||
| 2016年12月16日 | |||
| 2023年03月31日 | |||
| 6 | |||
| 介入研究 | Interventional | ||
| 単一群 | single arm study | ||
| 非盲検 | open(masking not used) | ||
| 非対照 | uncontrolled control | ||
| 単群比較 | single assignment | ||
| その他 | other | ||
| 対象患者は、本研究の計画が厚生労働省に提出された日までにステムセル研究所に臍帯血を保管している症例とし、以下の1)、2)の両方を満たすこととする。 1)以下のいずれかの診断をうけている7歳未満の症例 ①小児脳性麻痺の診断をうけている症例 ②中等症以上の低酸素性虚血性脳症の診断を受けている症例 ③脳性麻痺への移行が確実視されている脳室周囲白質軟化症(PVL)を画像上認められる症例 2)特定細胞加工物が「最終特定細胞加工物に対する試験および判定基準」に適合していること。 |
1. Age under 7 years at the autologous umbilical cord blood cells (Auto-CB) infusion. 2. Recipients with cerebral palsy, or maderate and severe hypoxic ischemic encephalopathy, or periventricular leukomalacia 3. Total cell count of Auto-CB is over 1.2E+06 cells with cell viability >60%. |
||
| 以下の基準に1つでも抵触する場合は除外とする。 1)遺伝子疾患が確認された症例 2)悪性腫瘍が確認された症例。ただし、頭蓋内腫瘍は悪性良性問わず除外とする。 3)母親での感染症(B型肝炎、C型肝炎、HIV、HTLV-1、梅毒)が陽性と確認された症例 4)ステロイドにアレルギー反応のある症例 5)特定細胞加工物の無菌検査(好気性菌、嫌気性菌、真菌)で陽性が認められた症例 6)医師が不適格と判断した症例 7)同意の得られない症例 |
1. Recipients with genetic disorder. 2. Recipients with malignant disease or brain tumor. 3. Mothers are positive for HBV, HCV, HIV, HTLV-1, and syphilus at the pregnancy. 4. Recipients with steroid allergy. 5. Auto-CB are positive for bacterial culture. 6. Recipients who are decided to be ineligible by doctors. 7. No principal or parental consent. |
||
| 下限なし | No limit | ||
| 7歳 未満 | 7age old not | ||
| 男性・女性 | Both | ||
| <研究対象個々の研究の中止基準> 実施責任者または研究分担者は、被験者が下記の中止基準に該当すると判明した場合には、その旨を被験者および親権者に説明し、当該被験者の研究継続を中止する。なお中止の場合には、可能な範囲で安全性を確認し、その後の被験者の治療については、被験者の不利益とならないよう、誠意を持って対応する。有害事象により中止した被験者については、 必要に応じ適切に処置を実施し、その有害事象の転帰が定まるまで、出来る限り追跡を実施する。 また、中止の場合にはそれまでに提供していただいた検体やデータは引き続き使用をさせていただく場合があることも 同意取得の際に説明する。 ※1)の場合は、同意撤回書をいただく際にデータ等の使用について、意思の確認を行う。 1)同意の撤回があった場合 2)研究への継続参加の辞退があった場合(その後の全ての観察の拒否) 3)選択/除外基準への不適合が発覚した場合 4)死亡(原因を記録する)や、重篤な有害事象が生じた場合 5)被験者フォローアップが不可能となった場合 6)担当医師により中止が妥当的と判断した場合 7)本臨床研究全体が中止となった場合 <研究全体の中止基準> 実施責任者は、以下の事項に該当する場合は研究実施継続の可否を検討する。 1)当該特定細胞加工物の品質、安全性、有効性に関する重大な情報が得られたとき。 2)対象者の募集が困難で予定症例を達成することが困難と判断されたとき。 3)予定症例数または予定期間に達する前に研究の目的が達成されたとき。 4)特定認定再生医療等委員会が中止すべき意見を述べ、医療機関の管理者が中止を決定した時や厚生労働省大臣から停止を命ぜられたとき。 |
|||
| 脳性麻痺 | Cerebral palsy | ||
| 有 | |||
| 1.調製した自家臍帯血は4時間以内に研究対象者に1時間以上かけて輸血する。 2.臍帯血輸血30分前に、プレドニゾロン1mg/kgを30分かけて点滴静注する。 |
1. Auto-CB mixed with normal salline (total volume 100ml) are administered intravenously over 1hour. 2. Prednisolone is given 30 minutes before Auto-CB administration over 30 minutes. |
||
| 安全性評価:有害事象の有無、有害事象の種類、出現頻度及び時期 | Safety which will be evaluated by assessing the incidence of acute infusion reactions, infections, any other adverse events for 36 months. | ||
| 1) 発達障害(新版K式発達指数またはWISC-IV知能検査)と運動障害(粗大運動能力尺度)の輸血前(入院後から輸血当日まで)、輸血後(退院日、輸血6、12、24か月後)の変化 2) 脳波の輸血前(入院後から輸血当日まで)、輸血後(退院日、輸血6、12、24か月後)の変化 3) 頭部MRI画像の輸血前(入院後から輸血当日まで)、輸血後(退院日、輸血6、12、24か月後)の変化(但し、金属の埋め込み等の理由でMRI撮影ができない症例のみCT画像を代用する。) 4) 上記1) - 3) と顆粒球を除いたCD45陽性細胞数との関連性 5) 上記1) - 3) とHLA(A、B、DRB1)一致数との関連性 |
1. Assessment of improvement in gross mot or function using gross motor function meas ure(GMFM) at the day before transfusion (from admission to one day before trasfusion), on discharge, 6 months later, 12 months later, and 24 months later. 2. Assessment of mental, speech, and social development using new edition k type devel opmental examination or WISC-IV at the day before transfusion (from admission to one day before trasfusion), on discharge, 6 months later, 12 months later, and 24 months later. 3. Serial change of EEG and brain MRI findin gs(CT findings in cases with contraindication of MRI) at the day before transfusion (from admission to one day before trasfusion), on discharge, 6 months later, 12 months later, and 24 months later. 4. Relationship among clinical improvement, total CD45 positive cell numbers of sibling A llo-CB excluding granulocytes, and HLA-match rate. |
||
| 別添の通り | |||
2 人員及び構造設備その他の施設等
2 人員及び構造設備その他の施設等
(1)人員及び構造設備その他の施設に関する事項
(1)人員及び構造設備その他の施設に関する事項
| 医師 | |||||
| 藤枝 幹也 | Fujieda Mikiya | ||||
| 高知大学医学部附属病院 | Kochi Medical School Hospital | ||||
| 小児科 | |||||
| 783-8505 | |||||
| 高知県南国市岡豊町小蓮185番地1 | 185-1Kohasu, Oko-cho, Nankoku, Kochi 783-8505, Japan | ||||
| 088-880-2355 | |||||
| fujiedam@kochi-u.ac.jp | |||||
| 自施設 | |||||
| 小児医療救急が可能な小児病棟33床、集中治療室(ICU)12床、X線装置、MRI、CT、人工呼吸器、心拍呼吸モニターなど救急医療に対応できる施設・設備を有する。 | |||||
(2)その他研究の実施体制に関する事項
(2)その他研究の実施体制に関する事項
| 菊地 広朗 | Kikuchi Hiroaki | ||||
| 高知大学医学部附属病院 | Kochi Medical School Hospital | ||||
| 小児科 | |||||
| 783-8505 | |||||
| 高知県南国市岡豊町小蓮185番地1 | 185-1 Kohasu, Oko-cho, Nankoku, Kochi 783-8505, Japan | ||||
| 088-880-2355 | |||||
| 088-880-2356 | |||||
| kikuchi@kochi-u.ac.jp | |||||
| 医師 | ||
| 藤枝 幹也 | ||
| 高知大学医学部附属病院 | ||
| 小児科 |
| 高知大学医学部附属病院次世代医療創造センターデータマネジメント部門 | ||
| 西本 博之 | ||
| 高知大学医学部附属病院 | ||
| 次世代医療創造センターデータマネジメント部門 | ||
| 高知大学医学部附属病院次世代医療創造センターデータマネジメント部門 | ||
| 田井 麻美 | ||
| 高知大学医学部附属病院 | ||
| 次世代医療創造センターデータマネジメント部門 | ||
| 高知大学医学部附属病院次世代医療創造センターデータマネジメント部門 | ||
| 黒岩 朝 | ||
| 高知大学医学部附属病院 | ||
| 次世代医療創造センターデータマネジメント部門 | ||
| 高知大学医学部附属病院 | ||
| 藤枝 幹也 | ||
| 高知大学医学部附属病院 | ||
| 小児科 | ||
(3)多施設共同研究に関する事項
(3)多施設共同研究に関する事項
| 無 |
3 再生医療等に用いる細胞の入手の方法並びに特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法等
3 再生医療等に用いる細胞の入手の方法並びに特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法等
(1)再生医療等に用いる細胞の入手の方法(特定細胞加工物を用いる場合のみ記載)
(1)再生医療等に用いる細胞の入手の方法(特定細胞加工物を用いる場合のみ記載)
| 自家臍帯血単核球細胞 | |
| 当院を含む産科施設で出産した児の臍帯血を採取し、ステムセル研究所と児の母親等との契約に基づき、同研究所で加工・保管する。当該児が本研究へ参加決定後、同研究所から当院に加工物を輸送する。 | |
| 被験者自身の自家臍帯血単核球を用いる。 |
|
| 研究責任者は、以下の内容についてステムセル研究所から「 臍帯血関連情報書」として入手する。以下の項目について、 全て確認できることを必須とする。 ① 臍帯血採取時に、親権者より採取の依頼が得られている こと。 ② 母親の感染症(B型肝炎、C型肝炎、HIV、HTLV-1、梅毒 )検査(妊婦健診)の検査結果。ただし確認できない場合は 「前診察時」に感染症検査を実施する。 ③ 当該細胞加工物HLAの結果 |
|
| 臍帯血の採取は、新生児と臍帯を切り離し、胎盤娩出前、又は胎盤娩出直後に胎盤をのう盆にのせた状態で実施する。穿刺予定個所の臍帯表面を消毒した後に、薬事承認を得ている200ml用血液バックの針を臍帯静脈に穿刺する。この際、血液バックを下位に位置させ高低差を利用した自然落下により臍帯血の流入を待つ。採血量は多い方がよいが、臍帯血が血液バックに流入するまでには一定の時間(数分間)を要するため産後処置に支障をきたさない範囲で行うものとしている。 |
(2)特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法(特定細胞加工物等を用いる場合のみ記載)
(2)特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法(特定細胞加工物等を用いる場合のみ記載)
| 自家臍帯血単核球細胞 | ||
| 【加工方法】 臍帯血に比重液(Ficoll)を加え、遠心分離し、単核球細胞層を回収する。 【保管方法】 製造を委託する細胞培養加工施設の細胞保管場所で管理された液体窒素タンクで保管する。 *保管場所:東京都港区または神奈川県横浜市のステムセル研究所内加工物保管施設 *保管期間:採取日から7年未満 当該特定細胞加工物の製造工程①〜⑥と品質管理の方法の概要については以下の通りとする。 ① 原料(臍帯血)について(細胞培養加工施設) ・臍帯血採取手技の適切性の確認 ・核染色による細胞カウントにより、分離後細胞数の品質規格への適合性を確認 ② 特定細胞加工物製造事業所への原料の運搬搬入(細胞培養加工施設) ・温度管理(-150℃以下)、容器外観の品質規格への適合性の確認 ③ 単核球細胞の分離抽出および凍結保管(細胞培養加工施設) ・分離前および後の品質規格への適合性の確認 ④ 特定細胞加工物の払出し(細胞培養加工施設) ・保管から払出しまでの温度管理状況(-150℃以下)の確認 ・被験者および当該加工物の生物学的同一性の確認のため、 特定細胞加工物のHLA型判別検査を実施 ⑤ 当院への特定細胞加工物の輸送(細胞培養加工施設) ・輸送状況(輸送経路、禁忌事項の遵守等)の確認 ・輸送中の温度管理状況(温度モニタリングにより-150℃以下を維持)の確認 ⑥ 最終調整物について(高知大) ・無菌性の確認(好気性菌/嫌気性菌/真菌培養) ・有核細胞数検査(フローサイトメトリ解析)による品質確認 ・母体血の感染症検査の付帯情報による適切性の確認 |
||
| 小児病棟で、調整後4時間以内に生理食塩水と混合した100mlの特定細胞加工物を1時間以上かけ輸血を行う。 | ||
| 有 | ||
| 株式会社ステムセル研究所 東京CPC 代表取締役社長 清水崇文 | ||
| FA3150022 | ||
| ステムセル研究所 東京CPC | ||
| 本院が作成した特定細胞加工物概要書に基づく特定細胞加工物の製造及び品質管理(本院までの輸送を含む) | ||
(3)再生医療等製品等に関する事項(再生医療等製品を用いる場合のみ記載)
(3)再生医療等製品等に関する事項(再生医療等製品を用いる場合のみ記載)
(4)再生医療等に用いる未承認又は適応外の医薬品又は医療機器に関する事項(未承認又は適応外の医薬品又は医療機器を用いる場合のみ記載)
(4)再生医療等に用いる未承認又は適応外の医薬品又は医療機器に関する事項(未承認又は適応外の医薬品又は医療機器を用いる場合のみ記載)
4 再生医療等技術の安全性の確保等に関す措置
4 再生医療等技術の安全性の確保等に関す措置
(1)利益相反管理に関する事項
(1)利益相反管理に関する事項
① 再生医療等に対する特定細胞加工物等製造事業者からの研究資金等の提供その他の関与
① 再生医療等に対する特定細胞加工物等製造事業者からの研究資金等の提供その他の関与
| 無 | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
② 再生医療等に対する医療薬品等製造販売業者等からの研究資金等の提供その他の関与
② 再生医療等に対する医療薬品等製造販売業者等からの研究資金等の提供その他の関与
| 無 | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
③ 再生医療等に対する特定細胞加工物等製造事業者又は医療品等製造販売業者等以外からの研究資金
③ 再生医療等に対する特定細胞加工物等製造事業者又は医療品等製造販売業者等以外からの研究資金
| 無 | ||
(2)その他再生医療等技術の安全性の確保等に関する措置
(2)その他再生医療等技術の安全性の確保等に関する措置
| アメリカDuke大学Kurtzberg教授らは、2005年から脳性麻痺患者に対する自家臍帯血輸血の臨床試験を実施している。 その臨床試験に用いられる自家臍帯血は、民間バンクで長期保管されているものであることから、臍帯血の品質に関する論文(Sun et al. Transfusion 2010)を報告し、途中経過も報告している(Englandr et al. NeuroImage 2015、Kurt zberg. 2016)。輸血関連死等の重大事故は起きていない。 同様に、メキシコのRamirez医師らの研究グループにおいても、脳性麻痺患児8例を対象としたパイロットスタディーで 安全性を確認している。さらに、Kurtzberg医師と同じDuke大学のCotten医師らは、脳性麻痺の主な原因疾患である低酸素性虚血性脳症の患児(在胎35週以上)に対して、低体温療法と自家臍帯血投与を行い(23名)、その安全性を確認し報告した(J Pediatr 2014)。 この他に、Georgia医科大学においても、脳性麻痺児に対する自家臍帯血を利用した臨床試験がFDAの認可の下実施されている(Clinical Trials. gov Identifier : NCT01072370)。 このような海外の状況に加え、国内においても臍帯血を用いた二つの臨床研究が、ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針に準じ開始されている。(当学(高知大学)の前田医師らの研究グループ:脳性麻痺を対象とした凍結自家臍帯血細胞の投与、大阪市立大学の新宅医師らの研究グループ:新生児低酸素性虚血性脳症を対象とした自家臍帯血細胞の投与 。)両者共に症例が未だ少なく未報告であるが、当学では前述した前田医師らが進める臨床研究を安全に実施するために必要な医療体制がすでに整っており、当然のことながら前田医師らの経験を踏まえ、また連携をとり、当該臨床研究を万全の体制で実施することができる環境にある。加えて、小児血液疾患に対する臍帯血幹細胞移植はすでに一般化された治療法であり、輸血の手法に関しても臨床の場でも検証済である。 我々の施設でも、血液疾患に対する臍帯血幹細胞移植は、研究分担者の菊地を中心に経験済である。 本臨床研究は、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」下において特定細胞加工物の製造許可を得た適切な施設に、臍帯血の入手・調製・保管を委託することに特徴がある 。委託する工程については、あらかじめ定める「特定細胞加工物に対する試験および判定基準」に適合する臍帯血を使用することは言うまでも無く、保管場所から当学への輸送についても複数名で確実性をもって実施することとしている。委託する工程で使用する資材や試薬については、無菌性が保証されたものを使用する。投与する細胞調製液に含まれる(残存するものも含む)自己に由来しない成分、すなわち、特定細胞加工物(自家臍帯血単核球細胞)の製造に使用されている試薬については、研究用試薬として扱われているものが含まれるが、そのすべてのロットについて、製造国の薬局法に定められた無菌試験に合格したものが使用される。それらのうち、DMSOについては軽度の皮膚刺激、眼刺激、長期または反復ばく露による皮膚、肝臓、血液への毒性が知られているが、投与する細胞調製液中のDMSO残存量は、細胞液の洗浄工程を経ることで0.2g未満となることが確認されており 、DMSOによる有害事象のリスクは限りなく低いことが推察される。 加えて、当該プロトコールよりも高濃度のDMSOを投与することになる臍帯血幹細胞移植でも当施設において実施経験があることを踏まえると、DMSOに起因するリスクは十分に対処可能である。当院での凍結臍帯血細胞の解凍・調整作業については再生医療技術の教育訓練を受け、研究責任者が認めた者が行うこととしている。 本研究の自家臍帯血輸液投与療法は、細胞調製液(最大100ml)を1回、1時間以上かけて輸血を行う。低酸素性虚血性脳症の新生児は通常の新生児より少なめの1日水分量は40-60ml/kgである。今回、対象となる被験者は、新生児ではなく多くが生後2か月以降の児であり、体重は最低でも約3kg(120-180ml/日の最低水分量)と推測されるため、今回の投与量は水分過多にならない輸液量である。 以上の状況すなわち、類似の臨床試験で自家臍帯血投与の安全性が高いことが十分に推察されること、考え得る有害事象に対し迅速かつ慎重に対応することができる救急医療体制が整っていること、臍帯血幹細胞移植の経験があること、適切な環境下で細胞調製作業がなされること、調製に使用される資材や試薬はすべて無菌保証があるものであること、熟練した技術者が投与細胞の調製作業にあたることなどから、安全性を十分に確保した上で当該臨床研究は十分に実施可能であると言える。 |
||||||
| アメリカDuke大学Kurtzberg教授らは、脳障害を伴う先天性代謝異常や脳性麻痺に臍帯血幹細胞輸血を行い、有効性を報告1)-7)した。2010年時点で、184人に対して治療を行っている。同様に、メキシコのグループからも8例中6例に症状の改善を報告8)し、台湾Chang Gung Children病院からも2例の臨床症状改善例が示されている。さらに、Georgia医科大学では、脳性麻痺児へ自家臍帯血を利用した臨床医研究が2010年FDAの認可の下、実施されている9)。Duke大学のCotten医師らは、在胎35週以上の新生児の虚血性脳症に対して、自家臍帯血輸血を行い、23名に細胞投与を行い、その安全性とともに、低体温療法以上の有効性を報告した10)。これを受けて、我が国では、大阪市立大学小児科を中心に厚生労働省研究として、新生児における中等度以上の低酸素性虚血性脳症に対する自家臍帯血輸血が開始され、今日までに3例に投与した。なお、上述の自家臍帯血輸血において、全例、特段の有害事象は報告されていない。 一方、虚血性あるいは外傷性脳損傷動物モデルでも自家臍帯血輸血の効果が報告され11-16)、その作用機序として、 「臍帯血中細胞は、損傷部位に遊走し、CD34陽性細胞が血管新生因子を分泌し血管新生を促す。次に、臍帯血中の神経前駆細胞が、分化し神経再生修復に寄与するとともに、自家の神経幹細胞も刺激され分化し再生修復に当たる。」ことが推測されている。 高知大学医学部先端医療学推進センターの臍帯血幹細胞研究班は、新規脳性麻痺モデルとして、新生仔脳虚血再灌流障害モデルマウスを確立した。同種同系マウスの血液幹細胞を モデルマウスに投与すると、ドナー細胞はレシピエントマウスの脳障害部位に遊走し、長期間生着した。そして、モデルマウス脳障害側における血管新生関連因子の発現を上昇させていることを明らかにした17)。さらにこのモデルを用いて、臍帯血投与前後における血中各種サイトカインの動態から、ドナー細胞の局所への誘導と内在性神経幹細胞の動きについても検討している。 以上、動物実験と臨床研究から脳障害児への自家臍帯血輸血は安全で神経学的・機能学的にも改善がえられる可能性があり、同療法は意義のある医療行為と考えられる。 なお、利益・不利益として予想されるものとしては以下のものがあり、被験者への同意説明文書にも記載し、十分説明を行う。 <予測される利益> この研究における臍帯血輸血の安全性の確認ができれば、 将来の治療選択が広がる可能性がある。脳性麻痺など脳障害に対する改善効果の可能性がある。 <予測される不利益> 特定細胞加工物の無菌検査では、全てのバイアルの検査を行うことは出来ない。そのため、汚染については完全に否定が出来ない。 また、2.5%ヒトアルブミンが混合された溶液を用いるためにヒト血液を材料にしていることによる感染症伝播のリスクも完全に排除できない。 そのほか、臍帯血輸血によるアレルギー反応が起こる可能性がある。被験者をアレルギー反応から回避させるため、臍帯血輸血30分前に水溶性プレドニン1mg/kgの投与を行う。 これら感染やアレルギー等のリスクに対応するため、臍帯血輸血中の厳重なバイタル等の観察はじめ、輸血終了後も、 被験者の状態には留意し、不調・異変を来した場合には、感染症等の検査を適宜行い、適切な治療を行う。 また、この研究ではステムセル社に保管している当該被験者の臍帯血細胞を全て使用するため、臍帯血細胞の保管は無くなる。 参考文献 1)〜17)は別紙参照 |
||||||
| <前診察後> 当院での被験者情報およびステムセル研究所からの細胞に関わる情報をもって、症例検討委員会(高知大学医学部附属病院 病院長:執印太郎、産科婦人科教授:前田長正、医学部附属先端医療学推進センター名誉センター長・名誉教授:相良祐輔、医学部附属病院輸血・細胞治療部部長 松村敬久) にて臍帯血輸血の実施の可否を検討し、実施責任者はその結果に基づき可否を決定する。 <臍帯血輸血前日まで> 症例検討委員会は、使用する特定細胞加工物の適格性の確認結果に基づき、当該細胞加工物投与について検討を行い、実施責任者は検討結果に基づき被験者への臍帯血輸血可否の決定を行う。 <臍帯血輸血当日> 午前10時までの診察およびバイタルサインの結果を踏まえ 、実施責任者が投与を決定する。 |
||||||
| 「特定細胞加工物に対する試験及び判定基準」に従い、細胞の安全性には十分留意を行うが、研究対象者の症状の観察を行い、細胞の安全性に関する疑義が生じた場合は、疾病等の取り扱いに準じ適切に対応を行う。 〈疾病等の取り扱い〉 1) 再生医療等を行う医師は疾病等の発生を知ったときは、医療機関の管理者及び実施責任者に対し、速やかに報告する。 2) 医療機関の管理者又は実施責任者は、再生医療等を行う医師に対し、当該再生医療等の中止その他の必要な措置を講ずるよう指示する。 3) 医療機関の管理者又は実施責任者は、特定細胞加工物を製造した特定細胞加工物製造事業者に速やかに通知する。 ・安全性に疑義が生じた場合の報告体制 本再生医療等計画で、細胞の安全性に疑義が生じるのは、①ステムセル研究所での管理不十分、②検体の輸送中の事故、③当院で行う無菌検査(好気性菌、嫌気性菌、真菌)が陽性、④母体血の感染症検査結果が異常値の場合が考えられる。①は、ステムセル研究所が、使用予定の臍帯血細胞の温度管理、容器外観の適合性を「臍帯血の回収運搬作業手順書」とその記録により確認を行い臍帯血関連情報書により当院に提供される。②は、輸送者(ステムセル研究所)と受領者(当院輸血・細胞治療部)にてダブルチェックで「検体引き渡し確認書」と検体の照合を行う。③は、ステムセル研究所が保管する母体血の感染症検査(B型肝炎検査、C型肝炎検査、HTLV-1検査、HIV検査、梅毒検査)の付帯情報による収集する場合は、臍帯血関連情報書により当院に報告されるが、情報がない場合は当院で実施する感染症検査の結果をもって判断する。④は当院輸血・細胞治療部が特定細胞加工物受理後、実施する。いずれの結果も速やかに実施責任者に報告され、細胞の安全性に関する疑義が生じた場合は、安全性について確認を行い研究への参加の可否を決定する。 ・再生医療等の提供の可否決定の手段(誰がどの時点で判断するか) 前診察終了後、臍帯血輸血前日までに当院の実施責任者を除く4名の医師による症例検討委員会を開催し、①~④を含むチェック項目の確認結果に基づき、当該細胞加工物の投与について検討を行う。実施責任者はその検討結果及び臍帯血輸血当日の診察/検温の結果により被験者への臍帯血輸血の可否を決定する。 ・既に当該再生医療等が提供された患者の状態把握の手段 被験者の連絡先を把握し、併せて当院の24時間対応の連絡先を伝えておく。 ・必要な経過観察等の対応(投与した場合の経過観察期間) 投与1週間後以後、6か月後、12か月後、24か月後、36か月後に、当院小児科で基本的には1泊入院の上、以下の項目について実施する。ただし、⑤⑧は可能であれば実施する。 ①発達・運動検査 年齢に応じて下記のいずれかを行う 発達検査(新版K式発達指数)5歳未満 知能検査(WISK-IV知能検査)5歳以上 ②運動障害程度(粗大運動能力尺度) ③血液検査:合計3-5ml採取する。内容は、血算、血糖、CRP、総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、直接ビリルビン、AST、ALT、アルカリフォスファ ターゼ、CK、CK-BB、クレアチニン、BUN、BNP、NSE、Na、K、Cl、Ca、P、Mg ※検体量に余裕があるなら 各種サイトカイン(IL-1、IL-6、TNF-α、SDF-1α、MCP-1、GRO-α、MIP-1α、EGF、VEGF) ④尿検査:合計5-10ml採取する。内容は、蛋白、糖、潜血、沈渣、尿中クレアチニン、採取量に余裕あれば尿中β2ミクログロブリン、尿中NAG ⑤髄液検査:(医師が可能と判断した場合実施する)合計1-2ml採取する。 検体量により、可能な範囲で検討する。内容は、細胞数、総蛋白、糖、NSEおよび、各種サイトカイン(IL-1、IL-6、TNF-α、SDF-1α、MCP-1、GRO-α、MIP-1α、EGF、VEGF) ⑥脳波 ⑦頭部MRI ⑧SPECT(医師が可能と判断した場合実施する。) なお、⑤~⑧については被験者の安全性の確保のためや適切な検査が実施できるように静脈麻酔による鎮静を行うことがある。その場合には当院で定めている『処置説明書』を用いて説明し、同意を得てから行う。手順についても当院の手順に準じて行う。 |
||||||
| 細胞培養加工施設で30年間保存する。 なお、「採取した細胞の一部」は、臍帯ではなく臍帯血血漿 (細胞ではありませんが)を指し、「再生医療等に用いた細胞加工物」は、自家臍帯血単核球細胞を指す。 |
||||||
| 細胞培養加工施設が適切に廃棄する。 | ||||||
| 疾病等の発生の場合の措置 1) 担当医師は疾病等の発生を知ったときは、病院長又は 実施責任者に対し、速やかに報告する。 2) 病院長又は実施責任者は、担当医師に対し、当該再生医療等の中止その他の必要な措置を講ずるよう指示する。 3) 病院長又は実施責任者は、特定細胞加工物を製造した特定細胞加工物製造事業者(ステムセル研究所)に速やかに通知する。 特定認定再生医療等委員会及び厚生労働大臣への疾病等の報告 病院長は、再生医療等提供計画に記載された再生医療等の提供について、次に掲げる事項を知ったときは、それぞれに定める期間内に当該事項を、特定認定再生医療等委員会を介して厚生労働大臣に報告する。 1) 次に掲げる疾病等の発生のうち、当該再生医療等の提供によるものと疑われるもの又は当該再生医療等の提供によるものと疑われる感染症によるものに関しては、発生後7日以内に報告する。 ① 死亡 ② 死亡につながるおそれのある症例 2) 次に掲げる疾病等の発生のうち、当該再生医療等の提供によるものと疑われるもの又は当該再生医療等の提供によるものと疑われる感染症によるものに関しては、発生後1 5日以内に報告する。 ① 治療のために医療機関への入院又は入院期間の延長が必要とされる症例 ② 障害 ③ 障害につながるおそれのある症例 ④ ①〜③に掲げる症例に準ずる重篤な症例 ⑤ 後世代における先天性の疾病又は異常 3) 再生医療等の提供によるものと疑われる又は当該再生医療等の提供によるものと疑われる感染症による疾病等の発生(1)及び2)に掲げるものを除く。)に関しては再生医療等提供計画を厚生労働大臣に提出した日から起算して60日ごとに当該期間満了後10日以内に報告する。 有害事象発生時の被験者への対応 研究担当者は、有害事象を認めたときは、直ちに適切な処置を行うとともに、診療録に記載する。 重篤な有害事象発生時の対応 上述の「疾病等」に該当しない重篤な有害事象については、当院における「人を対象とする医学系研究に係る安全性情報等の取り扱いに関する手順書」に従う。 |
||||||
| 投与後の観察 投与1週間後(退院日)、6ヵ月後、12ヵ月後、24ヵ月後 、36ヵ月後に当院小児科で基本的には1泊入院の上、所定の検査を行い観察を継続する。 研究の終了 すべての観察が完了し、追跡の必要な異常所見がみられない事を確認した時点を、その被験者における研究の終了とする。研究終了後、実施責任者または研究分担者は、被験者と 相談の上、最も適切と考えられる医療を提供する。 中止基準 実施責任者または研究分担者は、被験者が下記の中止基準に該当すると判明した場合には、その旨を被験者および親権者に説明し、当該被験者の研究継続を中止する。なお中止の場合には、可能な範囲で安全性を確認し、その後の被験者の治療については、被験者の不利益とならないよう、誠意を持って対応する。有害事象により中止した被験者については、 必要に応じ適切に処置を実施し、その有害事象の転帰が定まるまで、出来る限り追跡を実施する。 また、中止の場合にはそれまでに提供していただいた検体やデータは引き続き使用をさせていただく場合があることも 同意取得の際に説明する。 ※1)の場合は、同意撤回書をいただく際にデータ等の使用について、意思の確認を行う。 1) 同意の撤回があった場合 2) 研究への継続参加の辞退があった場合(その後の全ての観察の拒否) 3) 選択/除外基準への不適合が発覚した場合 4) 死亡(原因を記録する)や、重篤な有害事象が生じた場合 5) 被験者フォローアップが不可能となった場合 6) 担当医師により中止が妥当的と判断した場合 7) 本臨床研究全体が中止となった場合 有害事象の収集 本研究における有害事象の情報収集対象期間は投与後から 投与後36ヵ月までとする。 有害事象は直接の観察(検査を含む)、被験者の自発的報告または各来院時の被験者への質問で確認する。研究開始前に存在した合併症は、それらが研究開始後に悪化した場合のみ有害事象と見なす。臨床検査値又はその他の検査結果の異常は、それらが臨床的兆候又は症状を惹起した場合、治療を必要とした場合、又は臨床的に重要と実施責任者および研究担当者が判断した場合のみ有害事象とみなす。有害事象と判断された事象に関しては、適切に診療録および症例報告書に記載し、評価をおこなう。 本研究の有害事象の収集については、規定来院での確認の他、被験者の主治医からの情報提供も収集の対象とする。 |
||||||
| 〈有害事象の収集〉 本研究における有害事象の情報収集対象期間は輸血直後から輸血36か月後までとする。 有害事象は輸血6,12,24,36か月後の直接の観察(検査を含む)、研究対象者等の自発的報告又は各来院時の研究対象者等への質問での聞き取りで確認する。研究開始前に存在した合併症は、それらが研究開始後に悪化した場合のみ有害事象とみなす。臨床検査値又はその他の検査結果の異常は、それらが臨床的兆候または症状を惹起した場合、治療を必要とした場合、又は臨床的に重要と実施責任者及び再生医療等を行う医師が判断した場合のみ有害事象とみなす。有害事象と判断された事象に関しては、適切に診療録及び症例報告書に記載し、評価を行う。 本研究の有害事象の収集については、規定来院での確認の他、研究対象者のかかりつけの主治医からの情報提供も収集の対象とする。 効果を検証するため下記について評価を行う。 1) 発達障害(新版K式発達指数またはWISC-IV知能検査)と運動障害(粗大運動能力尺度)の輸血前(入院後から輸血当日まで)、輸血後(退院日、輸血6、12、24か月後)の変化 2) 脳波の輸血前(入院後から輸血当日まで)、輸血後(退院日、輸血6、12、24か月後)の変化 3) 頭部MRI画像の輸血前(入院後から輸血当日まで)、輸血後(退院日、輸血6、12、24か月後)の変化(但し、金属の埋め込み等の理由でMRI撮影ができない症例のみCT画像を代用する。) 4) 上記1) - 3) と顆粒球を除いたCD45陽性細胞数との関連性 5) 上記1) - 3) とHLA(A,B、DRB1)一致数との関連性 |
||||||
| 無 | ||||||
| 2016年12月16日 | ||||||
| 2017年03月14日 | ||||||
| 研究終了 | Complete | |||||
5 細胞提供者及び再生医療等を受ける者に対する健康被害の補償の方法
5 細胞提供者及び再生医療等を受ける者に対する健康被害の補償の方法
細胞提供者について(特定細胞加工物を用いる場合のみ記載)
細胞提供者について(特定細胞加工物を用いる場合のみ記載)
| 有 |
再生医療等を受ける者について
再生医療等を受ける者について
| 有 |
6 審査等業務を行う認定再生医療等委員会に関する事項
6 審査等業務を行う認定再生医療等委員会に関する事項
| 大阪大学第一特定認定再生医療等委員会 | The First Certified Special Committee for Regenerative Medicine, Osaka University | |
| NA8140001 | ||
| 大阪府吹田市山田丘2-2 | Yamada 2-2, Suita, Osaka | |
| 06-6210-8293 | ||
| nintei@dmi.med.osaka-u.ac.jp | ||
| 第一種再生医療等又は第二種再生医療等を審査することができる構成 | ||
| 適 | ||
| 2016年12月05日 | ||
7 その他
7 その他
| 研究者等は本研究に参加する被験者の個人情報保護を、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)他関連法令法規に準拠して実施する。被験者の氏名・住所は CRF(症例報告書)には一切記入せず、被験者識別コードリストを用いて被験者を識別する。なお、被験者識別コードリストは実施責任者が施錠できる場所に厳重に保管する。本研究の実施に係る原資料の直接閲覧、医学雑誌への発表などの場合でも被験者の個人情報は保全される。 | ||
| 本研究に携わる者は再生医療等を行う医療機関の管理者が開催する再生医療に係る教育講習又は同等の研修の受講を必須とする。又、本研究の再生医療等に係るもののうち細胞調製実務者は、細胞を用いた再生医療を行うために必要な細胞調製、保管、品質管理(検査)が行える技術についての研修を受ける。再生医療等に係る研修、又は関連する学会等への参加によって継続講習としている。その他の者については実施責任者等が「教育訓練の記録」からその適格性の判断を行う。 | ||
| 苦情及び問い合わせ先 医学部小児思春期医学教室 088-880-2355 附属病院小児病棟 088-880-2494 実施責任者 藤枝幹也 下記のとおり24時間対応を行う。 平日9:00~17:00 実施責任者→(実施責任者が不在の場合)再生医療等を行う医師 平日17:00~9:00、及び休日 携帯電話に連絡する 実施責任者→(実施責任者が応答できない場合)再生医療等を行う医師あるいは当直医 |
||
| 非該当 | ||
| なし | none | |
| 無 | ||
| 非該当 | ||
| 非該当 | ||
| 非該当 | ||
| UMIN試験ID 000024852 | ||
| UMIN臨床試験登録システム | UMIN Clinical Trials Registry | |
添付資料
添付資料
| 4 再生医療等を受ける者に対する説明文書及び同意文書の様式 | 4.マスキングあり_同意説明文書.pdf |
|---|