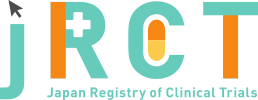臨床研究等提出・公開システム
再生医療等提供計画情報の詳細情報です。
| 第二種 | ||
| 令和2年4月14日 | ||
| 令和3年12月20日 | ||
| 令和3年5月28日 | ||
| 令和3年4月9日 | ||
| インプラント型再生軟骨を用いた気管支塞栓の臨床研究 | ||
| 再生軟骨を用いた気管支塞栓治療 | ||
| 帝京大学医学部附属病院 | ||
| 坂本 哲也 | ||
| 本研究の目的は、気管支瘻に対し、インプラント型再生軟骨による気管支充填の有効性と安全性について評価する。 | ||
| N/A | ||
| 気管支瘻 | ||
| 研究終了 | ||
| CONCIDE特定認定再生医療等委員会 | ||
| NA8160002 | ||
総括報告書の概要
総括報告書の概要
臨床研究の名称等
臨床研究の名称等
| 第二種 | |||
| 令和3年12月9日 | |||
| jRCTb032200013 | |||
| 提供しようとする再生医療等の名称 | インプラント型再生軟骨を用いた気管支塞栓の臨床研究 | ||
| 認定再生医療等委員会の名称(認定番号) | CONCIDE特定認定再生医療等委員会 (NA8160002) | ||
| 2021年04月09日 | |||
| 1 | |||
| / | 症例1 性別:男性 年齢:66歳 初期症状:2018年1月に膿胸・気管支瘻に対して開窓術を実施、以降経過観察中であったが、気管支瘻の残存に伴い膿胸腔の清浄化が得られない状況が続いており、気管支瘻の閉鎖実施が必要であった。 基礎疾患:うつ病、高血圧症 |
Case 1 Gender:Male Age:66 years old Initial symptoms:In January 2018, he underwent an open window operation for pyothorax and bronchopleural fistula, and had been under observation since then. However, the pyothorax cavity continued to be difficult to clean due to residual bronchopleural fistula, thus requiring the closure of the bronchopleural fistula. Comorbidities: Depression, Hypertension |
|
| / | 症例1 2020/10/23 説明・同意取得 2020/10/30 登録前検査① 2020/11/13 登録前検査結果確認①、登録前検査② 2020/11/27 登録前検査結果確認②、登録 2020/12/01 採血① 2020/12/11 採血② 2021/01/19 耳介軟骨組織採取 2021/03/09 手術(再生軟骨の投与) 2021/03/22-26 術後2週の検査 2021/03/26 検査の結果、気管支内に移植した再生軟骨が生着せずに脱落していることを確認。研究中止判定。 2021/04/05-09 中止時検査。胸部X線検査、気管支鏡検査、CT撮影、血液検査を実施し、術後の全身状態について異常がないことを確認。 |
Case 1 2020/10/23 Informed consent obtained 2020/10/30 Pre-Registration Examination (1) 2020/11/13 Pre-Registration Test (2) 2020/11/27 Registration 2020/12/01 Blood Collection (1) 2020/12/11 Blood Collection (2) 2021/01/19 Collection of auricular cartilage tissue 2021/03/09 Procedure (administration of regenerated cartilage) 2021/03/22-26 Postoperative 2-week examination 2021/03/26 Examination results showed that the regenerated cartilage implanted in the bronchus did not graft and had dropped out. The decision to discontinue this study was made. 2021/04/05-09 Examination at discontinuation. Chest X-ray, bronchoscopy, CT imaging, and blood tests were performed, and it was confirmed that there were no abnormalities in the postoperative general condition. |
|
| / | <プロトコルの逸脱> 操作中に、既に挿入されていたシリコン3本の中の1本が脱落したため、脱落部の追加塞栓のために再生軟骨2本(予定外に1本追加)を使用した。 <疾病等> 気管支内に移植した再生軟骨が生着せずに脱落した。健康被害は発生していない。 上記2事象が発生した。 |
<Deviation event> During the operation, one of the three pieces of silicone that had already been inserted fell out, so a total of two pieces of regenerated cartilage were used, including the additional embolization of the fallen part. <Adverse events> The regenerated cartilage implanted in the bronchus did not graft and dropped out. No health damage occurred. The above two events occurred. |
|
| / | 症例1における疾病等の発生を踏まえ、評価前に研究全体を中止したため、主要評価項目及び副次評価項目のデータ解析は実施できなかった。 | The data analysis for the primary and secondary endpoints could not be performed because the entire study was stopped before evaluation based on the occurrence of dropout in case 1. | |
| / | 再生軟骨は気管支塞栓子として活用できる可能性はあるが、長期にわたる固定方法に課題が残った。 | Regenerated cartilage could be useful and utilized as a bronchial embolization device,however, the long-term fixation method remained challenging. | |
| 2021年12月20日 | |||
IPDシェアリング
IPDシェアリング
| / | 無 | No | |
|---|---|---|---|
| / | |||
1 提供しようとする再生医療等及びその内容
1 提供しようとする再生医療等及びその内容
申請者情報
申請者情報
| 令和3年12月9日 | |||
| jRCTb032200013 | |||
| 帝京大学医学部附属病院 | |||
| 東京都板橋区加賀二丁目11番1号 | |||
| 坂本 哲也 | Sakamoto Tetsuya | ||
(1)再生医療等の名称及び分類
(1)再生医療等の名称及び分類
| インプラント型再生軟骨を用いた気管支塞栓の臨床研究 | Clinical study of bronchial embolization using implant-type regenerated cartilage( BEITRC ) | ||
| 再生軟骨を用いた気管支塞栓治療 | Bronchial embolization using regenerated cartilage( ERC ) | ||
| 第二種 | |||
| インプラント型再生軟骨を用いた気管支塞栓の臨床研究は患者自身の耳介軟骨組織から採取した軟骨細胞を用いてインプラント型再生軟骨を作製し、難治性気胸、もしくは術後気管支断端瘻患者に対して、気管支の空気漏れの箇所にインプラント型再生軟骨を詰め、アテロコラーゲンで固定する医療技術であり、胚性幹細胞/人工多能性幹細胞/人工多能性幹細胞様細胞の利用、遺伝子導入操作、投与を受ける者以外の細胞の利用、動物細胞の利用、幹細胞の利用の一切を行わない。インプラント型再生軟骨を作製する際には軟骨細胞を培養する操作を行い、耳介軟骨を気管支へ充填し、再建の材料とすることから相同利用ではない。そして人の身体の構造又は機能の再建、修復又は形成を目的としている。 「「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」及び「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」の取扱いについて(平成26 年10 月31 日付け医政研発1031 第1号厚生労働省医政局研究開発振興課長通知)」の図2(第一種・第二種・第三種再生医療等技術のリスク分類)に基づき、インプラント型再生軟骨を用いた気管支塞栓の臨床研究を第二種再生医療等技術と判断した。 | |||
(2)再生医療等の内容
(2)再生医療等の内容
| 本研究の目的は、気管支瘻に対し、インプラント型再生軟骨による気管支充填の有効性と安全性について評価する。 | |||
| N/A | |||
| 実施計画の公表日 | |||
| 2025年12月31日 | |||
| 2 | |||
| 介入研究 | Interventional | ||
| 単一群 | single arm study | ||
| 非盲検 | open(masking not used) | ||
| 非対照 | uncontrolled control | ||
| 単群比較 | single assignment | ||
| 治療 | treatment purpose | ||
| 以下の条件を全て満たすこと。 1) 本臨床研究への参加について、患者本人による書面での同意が得られる患者 2) 20歳以上の患者(男、女) 3) 画像診断などにより気管支瘻と診断される患者 4) 手術による根治的治療が困難と判断される患者 5) 膿胸のため開窓術後の患者 ※長期治療の患者を対象とする。 6) 活動性の悪性腫瘍がない患者 ※肺癌治療後の場合、臨床的判断として再発所見がない症例は対象とする。 |
Patients who meet all of the following conditions: 1) Patients who obtain written consent for participation in this clinical study 2) Patients over 20 years old (male, female) 3) Patients who are clinically diagnosed as bronchopleural fistula (BPF) 4) Patients who are judged to be difficult for surgical treatment 5) Patient after fenestration for empyema 6) Patients without malignant tumor. Regarding lung cancer patients after treatment, patients without any clinical recurrence are included |
||
| 以下のいずれかの項目に該当する患者。 1) 事前に気管支瘻の責任気管支が同定できない患者 2) 気管支鏡による責任気管支へのアプローチが困難な患者 3) コントロール不良の糖尿病の患者 4) 循環器、呼吸器、肝臓、腎臓、血液に重度の疾患を有する患者 5) 重度のアレルギー性疾患の患者 6) 薬物アレルギーのため術後感染予防の抗生剤投与が十分に行えない患者 7) 内臓・血液等の悪性腫瘍(加療中を含む、治癒例は含まない)がある患者 8) 違法薬物(麻薬など)、アルコール等の中毒者の患者 9) 他の易感染性をもたらす可能性がある併存疾患がある患者 10) 他の臨床研究・治験等に参加中、又は同意取得前24週以内にこれらに参加した患者 11) 現在妊娠中又は授乳中の方および、手術後24週までの間適切に避妊を行うことに同意できない女性患者 12) 梅毒、B型肝炎、C型肝炎、ヒト免疫不全ウイルス感染症、ヒトT細胞白血病ウイルス感染症の可能性があると判断された患者 13) 本人又は家族にリウマチ性関節炎、乾癬関節炎、全身性又は円板状エリテマトーデス、皮膚筋炎、多発性筋炎、慢性甲状腺炎、バセドウ病、多発性動脈炎、強皮症、潰瘍性大腸炎、クローン病、シェーグレン症候群、ライター症候群、混合結合組織病、再発性多発軟骨炎等の自己免疫疾患を有するか、あるいはその既往歴のある患者 14) コラーゲン製剤あるいは乳酸系ポリマー製剤、線維芽細胞成長因子(FGF)製剤、インスリン製剤、ペニシリン、ストレプトマイシン、アムホテリシンB、デキサメタゾンに過敏症あるいはアレルギーの既往のある方及びその恐れを有する患者 15) アテロコラーゲン皮内テスト陽性の患者 16) その他、本研究を担当する医師が不適格と判断した患者 |
Patients who meet any of the following conditions: 1) Patients whose bronchus responsible to BPF cannot be identified in advance 2) Patients who have difficulty in approaching the responsible bronchus with bronchoscope 3) Poor-controlled diabetes 4) Patients with severe disease in the circulatory system, respiratory system, liver, kidney, blood 5) Patients with severe allergic diseases 6) Patients who are unable to administer antibiotics sufficiently due to drug allergies 7) Patients with visceral / blood malignant tumors (including during treatment, excluding cured cases) 8) Patients who are addicted to illegal drugs (such as narcotics) and alcohol 9) Compromised host with other comorbidities 10) Patients who participate in other clinical studies / clinical trials or participate in these within 24 weeks before obtaining consent 11) Female patients who are currently pregnant or breastfeeding and who do not agree with appropriate contraception for up to 24 weeks after surgery 12) Patients with syphilis, hepatitis B, hepatitis C, human immunodeficiency virus infection, human T cell leukemia virus infection 13) Patients with a history of autoimmune diseases such as Rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, systemic or discoid lupus erythematosus, dermatomyositis, polymyositis, chronic thyroiditis, Graves' disease, polyarteritis, scleroderma, ulcerative colitis, Crohn's disease, Sjogren's syndrome, Reiter syndrome, mixed connective tissue disease, or relapsing polychondritis 14) Patients with a history of hypersensitivity or allergy to collagen or lactic acid-based polymer drugs, fibroblast growth factor (FGF), insulin, penicillin, streptomycin, amphotericin B, dexamethasone 15) Patients with positive intradermal test against atelocollagen 16) Patients who are clinically judged to be ineligible for this study due to other factors |
||
| 20歳 以上 | 20age old over | ||
| 上限なし | No limit | ||
| 男性・女性 | Both | ||
| 臨床研究の終了 目標症例数が登録され、全ての症例についての評価が終了したことをもって臨床研究終了とする。また、本臨床研究中に対象患者に対する治療が不可能となった場合は、従来のEWSを用いた気管支塞栓術をおこなうこととする。 臨床研究の中止 臨床研究の中止とは、以下のいずれかの理由により予定より早く臨床研究全体又は一部が中止されることをいう。 「一部中止」条件 ① 登録後に適格基準等の参加条件を満たさなくなった場合 ② 本品移植前に妊娠が発覚した場合 ③ 患者に起因して規定どおりのインプラント型再生軟骨の作製が出来なかった場合 ④ 患者に起因して規定どおりの手術が行えなかった場合 ⑤ 転居などの理由により、患者が来院しない等の事情で研究が完了できなくなった場合 ⑥ 患者から研究継続の中止の申し出があった場合 患者個人の理由から臨床研究の継続が出来ない場合に一部中止とする。 ⑦ 臨床研究が継続不可能と医師が判断した場合 「臨床研究全体の中止」条件 ① 重篤な有害事象の発生により、臨床研究実施検討委員会より中止勧告があった場合 ② 症例登録の遅延やプロトコール逸脱の頻発により、臨床研究実施検討委員会より研究の完遂が困難と判断された場合 ③ 効果安全評価委員より中止勧告があった場合 ④ 実施責任者が研究の中止を必要と認めた場合 臨床研究全体の中止決定後は、実施責任者は可及的速やかに研究中の対象患者に対する対応方法を決定し、臨床研究実施検討委員会に中止とその理由を報告し、対象患者に対して適切な対応をとる。情報・試料は1年間保管の後に廃棄する。なお、中止時検査は特段実施しないものとする。 |
|||
| 気管支瘻 | bronchopleural fistula (BPF) | ||
| 有 | |||
| 1)細胞培養時に使用する自己血清を製造するための採血及び検査のための採血 2)耳介軟骨組織採取のための切開及び組織切除 3)責任気管支への成形したインプラント型再生軟骨の投与。 |
1) Blood collection to produce autologous serum for cell culture 2) Auricular cartilage tissue collection 3) Administration of implant-type regenerated cartilage to the responsible bronchus |
||
| CTスキャンによる気管支の閉塞確認 CTスキャンにより画像を撮影する。空気のCT値および気管支壁のCT値を確認し、閉塞区間の気管支壁内側周囲に空気と同じCT値の部位が連続して存在しているかどうかを確認する。連続して存在していれば非閉塞、存在しなければ閉塞と判断する。 |
Confirmation of bronchial embolization using CT scan | ||
| 気管支鏡による病変部の感染の有無および気管支の閉塞確認 ・ 病変部の感染の有無については気管支鏡により病変部周囲の白苔付着など感染を疑う兆候がないか判断する。 ・ 気管支鏡による閉塞確認は、閉塞部位を中枢側から確認し、塞栓子の周囲に空気の出入りなどが無いか確認する。 ・ 有害事象の確認については、研究終了時までに発生した全ての有害事象を収集し、研究に起因するものか確認する。 |
Confirmation of bronchial obstruction using bronchoscopy Check for the infection in the treated site Adverse events |
||
| 細胞の採取の方法: 軟骨細胞培養用に複数回採血を実施する。採血は当院輸血部の処置室で実施し、血液バックに1日最大200mL採取する。富士ソフト・ティッシュエンジニアリング株式会社に血液を搬送後、血清調製を行い、細胞培養に必要な血清量を得るまで、最大で600mLの採血を実施する。 手術の7週前に患者の耳介軟骨組織を局所麻酔下で約10✕10mm採取し、富士ソフト・ティッシュエンジニアリング株式会社に組織検体を搬送する。 製造及び品質管理の方法の概要: 細胞プロセッシングセンター(CPC)で自己血清を用いて軟骨細胞を分離・培養して必要量まで増殖させる。増えた軟骨細胞とアテロコラーゲンの混合液をPLLA足場素材へ投与し、ゲル化させて振とう培養する事で、インプラント型再生軟骨が完成する。 完成品検査として、細胞数検査、生存率検査、マイコプラズマ否定試験、無菌試験、エンドトキシン試験、特性試験、力学的強度検査等を実施する。 特定細胞加工物の投与の方法: 気管支のサイズを参考にして、メスを用いて成形したインプラント型再生軟骨を気管支鏡やX線透視などを利用して責任気管支にアテロコラーゲン(ゲルおよびシート)と共に投与する。 再生医療等の内容をできる限り平易な表現を用いて記載したもの 別紙の通り |
|||
2 人員及び構造設備その他の施設等
2 人員及び構造設備その他の施設等
(1)人員及び構造設備その他の施設に関する事項
(1)人員及び構造設備その他の施設に関する事項
| 医師 | |||||
| 坂尾 幸則 | Sakao Yukinori | ||||
| 00274605 | |||||
| 帝京大学医学部 | Teikyo University School of Medicine | ||||
| 外科学講座 | |||||
| 173-0003 | |||||
| 東京都板橋区加賀2丁目11−1 | 2-11-1 Kaga Itabashi-ku Tokyo 173-8605 | ||||
| 03-3964-1211 | |||||
| ysakao@med.teikyo-u.ac.jp | |||||
| 自施設 | |||||
| 救命救急センター(第三次救急医療施設) 救命センター専用病床数30床 ICU 16床、HCU 14床、後方病棟 42床、関連病床 22床 救命センター設備概要 大動脈バルーンパンピング、心肺補助装置、頭蓋内圧測定装置、小児蘇生用マット(脊髄針)、水治療室、血漿交換用装置、急速輸血装置、圧迫止血用装置、血液透析装置、血漿交換用装置、血液ろ過透析装置 | |||||
(2)その他研究の実施体制に関する事項
(2)その他研究の実施体制に関する事項
| 坂尾 幸則 | Sakao Yukinori | ||||
| 帝京大学医学部 | Teikyo University School of Medicine | ||||
| 外科学講座 | |||||
| 173-0003 | |||||
| 東京都板橋区加賀2丁目11−1 | 2-11-1 Kaga Itabashi-ku Tokyo 173-8605 | ||||
| 03-3964-1211 | |||||
| ysakao@med.teikyo-u.ac.jp | |||||
| 医師 | ||
| 川村 雅文 | ||
| 70169770 | ||
| 帝京大学医学部 | ||
| 外科学講座 |
| 医師 | ||
| 坂尾 幸則 | ||
| 00274605 | ||
| 帝京大学医学部 | ||
| 外科学講座 |
| 医師 | ||
| 齋藤 雄一 | ||
| 帝京大学医学部 | ||
| 外科学講座 |
| 医師 | ||
| 山内 良兼 | ||
| 30445390 | ||
| 帝京大学医学部 | ||
| 外科学講座 |
| 医師 | ||
| 小室 裕造 | ||
| 90306928 | ||
| 帝京大学医学部 | ||
| 形成・口腔顎顔面外科学講座 |
| 株式会社化合物安全性研究所 | ||
| 寺垣 純 | ||
| 株式会社化合物安全性研究所 | ||
| 臨床事業部 札幌分室 | ||
| 株式会社化合物安全性研究所 | ||
| 山田 朝清 | ||
| 株式会社化合物安全性研究所 | ||
| 監査室 | ||
| 富士ソフト株式会社 | ||
| 原井 基博 | ||
| 富士ソフト株式会社 | ||
| 再生医療研究部 | ||
| 富士ソフト株式会社 | ||
| 矢島 彩子 | ||
| 00287773 | ||
| 富士ソフト株式会社 | ||
| 再生医療研究部 | ||
(3)多施設共同研究に関する事項
(3)多施設共同研究に関する事項
| 無 |
3 再生医療等に用いる細胞の入手の方法並びに特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法等
3 再生医療等に用いる細胞の入手の方法並びに特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法等
(1)再生医療等に用いる細胞の入手の方法(特定細胞加工物を用いる場合のみ記載)
(1)再生医療等に用いる細胞の入手の方法(特定細胞加工物を用いる場合のみ記載)
| 耳介軟骨細胞 | |
| 再生医療等の提供を行う医療機関と同じ。 | |
| ① 細胞提供者の健康状態 患者自身の細胞を用いるため、細胞提供者の選定方法における健康状態についての排除基準は再生医療等を受けようとする者と同じである。 ② 細胞提供者の年齢 20歳以上 |
|
| ・ 登録前の観察項目 ① 併用薬・併用療法 ② 患者背景確認 生年月日、性別、臨床診断名、併存疾患、アレルギー歴、既往歴(過去5年)、喫煙歴、 飲酒歴、アスベスト暴露の有無 ③ アテロコラーゲン皮内テスト アテロコラーゲンの添付文書に従い、皮内反応検査を2週に1度、計2回実施する。 反応確認日については±3日間を許容範囲とする。 ④ 感染症検査 (※同意取得3ヶ月以内に行っていれば、その結果で代用する。) エイズ検査(HIVAb)、成人性T細胞白血病検査(HTLV-1Ab)、梅毒検査(STS)、 B型肝炎検査(HBsAg、HBsAb、HBcrAg)、C型肝炎検査(HCVAb) ⑤ 心電図 ⑥ 血液学的検査 白血球数、赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板数、白血球像 ⑦ 血液生化学的検査 総蛋白、アルブミン、尿素窒素、クレアチニン、Na・K・Cl、グルコース、 PT、APTT、HbA1c、総ビリルビン、AST、ALT、LDH、ALP、γ-GTP、CRP ⑧ 尿検査(尿定性、沈渣) ⑨ 妊娠検査 (妊娠能を有する患者に限る) ・ 血清調製用採血時の観察項目 ① 併用薬、併用療法 ② 一般的身体所見(体温、心拍、血圧) ・ 耳介軟骨組織採取時の観察項目 ① 一般的身体所見(体温、心拍、血圧) ② 軟骨組織採取部位所見 |
|
| 帝京大学医学部附属病院にて軟骨細胞培養用に複数回採血を実施する。採血は当院輸血部の処置室で実施し、血液バックに1日最大200mL採取する。富士ソフト・ティッシュエンジニアリング株式会社に血液を搬送後、血清調製を行い、細胞培養に必要な血清量を得るまで、最大で600mLの採血を実施する。 同様に、帝京大学医学部附属病院にて手術の7週前に患者の耳介軟骨組織を局所麻酔下で約10✕10mm採取し、富士ソフト・ティッシュエンジニアリング株式会社に組織検体を搬送する。 |
(2)特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法(特定細胞加工物等を用いる場合のみ記載)
(2)特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法(特定細胞加工物等を用いる場合のみ記載)
| インプラント型再生軟骨 | ||
| 詳細は「特定細胞加工物概要書」及び「特定細胞加工物標準書」を参照。 細胞プロセッシングセンター(CPC)で自己血清を用いて軟骨細胞を分離・培養して必要量まで増殖させる。増えた軟骨細胞とアテロコラーゲンの混合液をPLLA足場素材へ投与し、ゲル化させて振とう培養する事で、インプラント型再生軟骨が完成する。 完成品検査として、細胞数検査、生存率検査、マイコプラズマ否定試験、無菌試験、エンドトキシン試験、特性試験、力学的強度検査等を実施する。 |
||
| 気管支のサイズを参考にして成形したインプラント型再生軟骨を気管支鏡やX線透視などを利用して責任気管支にアテロコラーゲン(ゲルおよびシート)と共に投与する。 | ||
| 有 | ||
| 富士ソフト・ティッシュエンジニアリング株式会社 | ||
| FA3150002 | ||
| FSTEC 細胞プロセシングセンター | ||
| 自己血液、耳介軟骨組織の搬入から提供における当院への輸送までと、特定細胞加工物等の保管におけるインプラント型再生軟骨の保管および全ての試験検査を委託する。 | ||
(3)再生医療等製品等に関する事項(再生医療等製品を用いる場合のみ記載)
(3)再生医療等製品等に関する事項(再生医療等製品を用いる場合のみ記載)
(4)再生医療等に用いる未承認又は適応外の医薬品又は医療機器に関する事項(未承認又は適応外の医薬品又は医療機器を用いる場合のみ記載)
(4)再生医療等に用いる未承認又は適応外の医薬品又は医療機器に関する事項(未承認又は適応外の医薬品又は医療機器を用いる場合のみ記載)
| 医療機器 | |||
| 適応外 | |||
| 医療用品 4 整形用品 | |||
| コラーゲン使用軟組織注入材 | |||
| 16100BZZ01355000 | |||
| 株式会社 高研 | |||
| 東京都文京区後楽1-4-14 | |||
| 医療機器 | |||
| 適応外 | |||
| 医療用品 4 整形用品 | |||
| コラーゲン使用吸収性局所止血剤 | |||
| 20700BZZ00468000 | |||
| 株式会社 高研 | |||
| 東京都文京区後楽1-4-14 | |||
4 再生医療等技術の安全性の確保等に関す措置
4 再生医療等技術の安全性の確保等に関す措置
(1)利益相反管理に関する事項
(1)利益相反管理に関する事項
① 再生医療等に対する特定細胞加工物等製造事業者からの研究資金等の提供その他の関与
① 再生医療等に対する特定細胞加工物等製造事業者からの研究資金等の提供その他の関与
| 富士ソフト・ティッシュエンジニアリング株式会社 | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
| 株式会社 高研 | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
② 再生医療等に対する医療薬品等製造販売業者等からの研究資金等の提供その他の関与
② 再生医療等に対する医療薬品等製造販売業者等からの研究資金等の提供その他の関与
| 無 | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
③ 再生医療等に対する特定細胞加工物等製造事業者又は医療品等製造販売業者等以外からの研究資金
③ 再生医療等に対する特定細胞加工物等製造事業者又は医療品等製造販売業者等以外からの研究資金
| 無 | ||
(2)その他再生医療等技術の安全性の確保等に関する措置
(2)その他再生医療等技術の安全性の確保等に関する措置
| 【非臨床安全性評価に関する情報】 インプラント型再生軟骨は富士ソフト株式会社で開発された口唇口蓋裂患者の鼻修正術に用いる材料である。作製方法、原材料及び品質管理の方法は本臨床研究で用いるインプラント型再生軟骨と同等、同技術である。現在、富士ソフト株式会社では臨床治験を開始しており、非臨床安全性試験は評価が終了している。 【ヒトへの使用経験、臨床試験成績に関する報告等】 ① 国内/試験名:Generative surgery of cultured autologous auricular chondrocytes for nasal augmentation.;Yanaga H, Imai K, Yanaga K.;Aesthetic Plast Surg. 2009 Nov;33(6):795-802. doi: 10.1007/s00266-009-9399-8. 試験デザイン:単群 被験者数:75例 結果の要約:耳介軟骨組織から単離した軟骨細胞を培養し、鼻背に注入した。注入後2~3週間で柔らかいゲルから硬い軟骨組織に変わり、安定する様子を観察した。 ② 国内/試験名:口唇口蓋裂における鼻変形に対するインプラント型再生軟骨の開発 -アテロコラーゲンハイドロゲルとポリ乳酸(PLLA)多孔体によって構成される足場素材に自家耳介軟骨細胞を投与して作製するインプラント型再生軟骨;ヒト幹細胞臨床研究、東京大学医学部附属病院 試験デザイン:単群オープン、非ランダム化 被験者数:3例 結果の要約:患者耳介軟骨から軟骨細胞を単離後、東京大学医学部附属病院細胞プロセッシングセンターで1ヶ月間培養され、再生軟骨(50×6×3 mmのドーム状)が作製された。いずれの患者も細胞増殖は良好で、規定どおり再生軟骨が移植された。 結果は現在解析中であるが、術後1年の観察期間で再生軟骨抜去に至る例はなかった。そのうち1例において術後1年6ヶ月で再生軟骨の小片を生検し、良好な再生軟骨が確認されている。別の1例において移植物に術後石灰化が見られたが、術後1年以降に進行は認められていない。痛みなどはなく、経過観察が行われている。尚、この他の予期せぬ重篤な有害事象は認められていない。 |
||||||
| 呼吸器外科領域では下記の複数分野において安全で確実な気管支充填術が求められている。国内では、シリコーン製の「Endobronchial Watanabe Spigot(以下、EWS)」が、医療機器として製造販売承認されているものの下記に示すとおり十分な治療効果を得られていない現状がある。 (1) 難治性気胸 細気管支瘻による難治性気胸の場合、手術による縫合閉鎖を要することが多い。しかし、気管支拡張症、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、肺癌、間質性肺炎などの基礎疾患が存在する続発性気胸であることが多く、原疾患のため既に呼吸予備能が減少していることが多い。肺機能の低下に加えて心機能低下や他の合併症などにより手術施行が困難である場合も多く、手術よりも保存的に早期治癒が得られ、かつ再発が少ない治療法が求められている。学会ガイドラインでは、胸膜癒着剤を胸腔に注入する胸膜癒着術や気管支鏡下気管支塞栓術などの対象とされている1)。ただし、国内では、「外科手術による治療が困難な続発性難治性気胸」に対して胸膜癒着剤として製造販売承認されているものはない。また、EWSは経気道的に挿入できるものの、シリコーン製で表面が気管支粘膜との間に接着しないことから移動しやすく、咳嗽などで喀出されてしまうだけでなく、気道内の別の場所に移動してしまうことも経験される。さらに、責任気管支を同定できEWSによる気管支充填術を施行したとしても、責任気管支とEWSの間に隙間が生まれてしまい完全な瘻孔閉鎖ができない事が多い2)。 (2) 気管支断端瘻 呼吸器外科領域における肺切除術において、重篤で治療に難渋する合併症の一つとして気管支断端瘻(気管支を縫い合わせた後、穴があいてしまうこと)が挙げられる。Vesterらは2,243例の肺切除で術後気管支断端瘻の発生は35例(1.6%)に認められたと報告している3)。肺癌登録合同委員会による2004年肺癌外科切除例の全国集計では,11,663例のうち気管支胸膜瘻は66例(0.5%)(主治医判断)であった4)。術後気管支断端瘻に対する治療として、断端瘻に伴う膿胸に対する開窓術の後に大網や広背筋弁などの生体組織を遊離させて瘻孔被覆術が行われることが多いが、その侵襲は非常に大きいため断端瘻を経気管支鏡的に閉鎖できる素材が求められている。これまでフィブリノゲン製剤とポリグリコール酸シートを用いた被覆やn-ブチル-2-シアノアクリレートによる閉鎖術なども報告はあるが確実性に乏しく治療法として確立されていない。術後気管支断端瘻は当院でも1-2例/年の症例を経験する。 当研究に用いる特定細胞加工物であるインプラント型再生軟骨は、富士ソフト株式会社により開発された鼻変形を有する口唇口蓋裂患者の鼻修正術に用いる再生医療等製品である(2018年6月14日に、再生医療等製品として製造販売承認申請された)。臨床での使用実績としては、鼻変形を有する口唇口蓋裂患者を対象とした臨床試験が実施されているが、現在までに9名の被験者に対し移植後2年の観察が終了しており、いずれも重篤な有害事象は報告されていない。さらに、帝京大学医学部耳鼻咽喉科学講座では、真珠腫の治療を目的とし、外耳道後壁を削ったところに、目的のサイズにメスで切ったインプラント型再生軟骨を再建材料として用いる臨床研究が実施されている。2名の被験者で再建の手術が実施され、これまでに術後6ヶ月が経過しているが、重篤な有害事象もなく、また主要評価項目である外耳道後壁の内陥率は術後3ヶ月からほぼ100%維持していることが確認された。5) 外科学講座では気管支充填の新規治療材料として、免疫拒絶が少なく気管支瘻を恒久的に閉鎖でき得る生体材料を模索していた。気管支閉鎖のために用いていたEWSは生着しないため強い気流などで脱落することをしばしば経験しており、生体材料による生着が安定した密閉につながると考えられたためである。インプラント型再生軟骨は、ヒト自家移植組織であり免疫拒絶が少ないこと、生体内では軟骨組織様となり一定の弾力性を有すると考えられることから気管支充填にも応用できる可能性が考えられた。 また、耳鼻咽喉科の臨床研究でも行われている通り、自由な大きさに切って使用できるため患者によって異なる欠損部位の大きさに応じた充填が可能であることや、PLLA(ポリ-L-乳酸)足場素材を用いていることから、ある程度滑り止めの作用があり充填箇所から移動しにくいことも想定された。従来用いられているEWSについては気管支鏡所見などから、閉塞部位の形状などからサイズを決めて挿入していたが、今回の再生軟骨では小さく切離することが可能なため、HRCT画像上で閉塞ターゲットの3Dモデルを作成し、適切な塞栓子の形状をシミュレーションしたうえで挿入することを想定している。そのため今回の方法でより確実に密閉されることが期待される。 以上のことから、気管支充填の新規治療材料として、患者自身の耳介軟骨から作製したインプラント型再生軟骨を用い、本臨床研究を行う。 【参考資料一覧】 1) 日本気胸・嚢胞性肺疾患学会編. 気胸・嚢胞性肺疾患 規約・用語・ガイドライン 2009年度版, 金原出版, 2009;43-7) 2) 本間崇浩, 他. 難治性気胸に対する治療戦略-気管支充填術と50cm H2O陰圧下に行う胸膜癒着療法の併用-. 日呼外会誌2009;23:114-9 3) Vester S, et al. Ann Thorac Surg. 52(6):1253-7. 4) 澤端 章好ら、日呼吸会誌 49(4):327-42. 5)Ken Ito, MD, et al. Successful Posterior Canal Wall Reconstruction with Tissue-Engineered Cartilage. OTO Open. 2019 Jan-Mar; 3(1) |
||||||
| ① 決定を行う時期 細胞加工施設で製造を開始後、全ての製造工程、品質検査が終了した時(細胞採取から約7週間後) ② 決定を行う者 インプラント型再生軟骨の投与の可否判断の決定は再生医療等を行う医師が行う。 ③ その他 無し。 |
||||||
| 細胞加工施設は当院からの組織輸送中及び細胞加工施設から当院への試料の輸送中を含め、細胞の安全性に関する疑義が生じた場合、遅滞なく当院に報告を行い、今後の対策(組織の再採取、研究の修正変更、中止等)を検討する。 当院においても組織採取時及び特定細胞加工物投与時において細胞の安全性に疑義が生じる事象を発見した場合、採取または投与を中止し、有害事象として適切な処置を施し、最善の策を講じると共に、CRFに記載する。 |
||||||
| 採取した組織の一部及び製造した特定細胞加工物の一部を臨床研究終了後より1年間、富士ソフト・ティッシュエンジニアリング株式会社の規定に基づきCPC内の鍵のかかる冷凍庫に保管する。 |
||||||
| 臨床研究終了後より1年経過後は、耳介軟骨試料および血液試料を廃棄処分とする。廃棄方法は保管施設である富士ソフト・ティッシュエンジニアリング株式会社の規定に基づき、感染性廃棄物として適切に廃棄する。 |
||||||
| 実施責任者は、細胞を採取時または投与時において、有害事象が認められた場合は、適切な処置を施し、最善の策を講じると共に、下記の内容を調査しCRFに記載する。 ・発現日 ・症状・疾患名 ・施した処置 ・インプラント型再生軟骨との因果関係、手技との因果関係 ・程度 ・重篤度 ・コメント(因果関係の判定理由など) 有害事象の経過観察期間 患者の転帰を確認し、回復した場合は回復時まで経過観察する。また、回復したが後遺症がある場合や未回復の場合は、有害事象発生後5年間経過観察するものとする。 重篤な有害事象の報告 重篤と思われる有害事象が発生した場合には、担当医師がインプラント型再生軟骨との因果関係の有無にかかわらず、直ちに(知り得てから24時間以内)に実施責任者に口頭、電話又はFAX等で連絡する(下記 緊急連絡先参照)。その後、実施責任者は、帝京大学にて定められた「臨床研究における重篤な有害事象報告に関する標準業務手順書」に準じて報告を行う。 |
||||||
| 本臨床研究は特定細胞加工物の投与後3年間の経過観察期間を設定している。経過観察期間中に実施される検査項目は下記の通りである。 ① 併用薬・併用療法 ② 一般的身体所見(体温、心拍、血圧、SpO2) ③ 血液学的検査(白血球数、赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板数、白血球像) ④ 血液生化学的検査(総蛋白、アルブミン、尿素窒素、クレアチニン、Na・K・Cl、グルコース、PT、APTT、HbA1c、総ビリルビン、AST、ALT、LDH、ALP、γ-GTP、CRP) ⑤ 気管支鏡検査 ⑥ 胸部CTスキャン また、臨床研究終了後(経過観察終了後)は概ね1年に1度、胸部CT撮像を行う。フォローアップする期間は、術後の経過に応じ医師の判断に委ねる。 当院は再生医療等の提供中止の旨を、その中止の日から10日以内に認定再生医療等委員会に通知するとともに、地方厚生局長に再生医療等提供中止届を提出する。再生医療等提供計画を厚生労働大臣に提出した日から起算して、一年ごとに、当該期間満了後90日以内に再生医療等の提供を終了した旨および提供を終了した日を報告する。 |
||||||
| 再生医療等の提供に起因するものと疑われる疾病等の発生の場合に当該疾病等の情報を把握できるよう、及び細胞加工物に問題が生じた場合に患者の健康状態等が把握できるよう、あらかじめ患者の同意を得た上で連絡先等の情報を収集し管理する。収集した情報は「臨床研究における記録の保管に関する標準業務手順書」に従い、適切に保管する。 |
||||||
| 有 | ||||||
| 実施計画の公表日 | ||||||
| 2020年11月27日 | ||||||
| 研究終了 | Complete | |||||
5 細胞提供者及び再生医療等を受ける者に対する健康被害の補償の方法
5 細胞提供者及び再生医療等を受ける者に対する健康被害の補償の方法
細胞提供者について(特定細胞加工物を用いる場合のみ記載)
細胞提供者について(特定細胞加工物を用いる場合のみ記載)
| 有 |
再生医療等を受ける者について
再生医療等を受ける者について
| 有 |
6 審査等業務を行う認定再生医療等委員会に関する事項
6 審査等業務を行う認定再生医療等委員会に関する事項
| CONCIDE特定認定再生医療等委員会 | CONSIDE Specified Certified Regenerative Medicine Committee | |
| NA8160002 | ||
| 東京都千代田区麹町2-3-3 FDC麹町ビル3F | 2-3-3,FDCkozimachi Bld.3F, Kojimachi, Chiyoda Ku, Tokyo, 102-0083, Tokyo | |
| 03-5772-7584 | ||
| concide_jimukyoku@concide.or.jp | ||
| 第一種再生医療等又は第二種再生医療等を審査することができる構成 | ||
| 適 | ||
| 2020年03月25日 | ||
7 その他
7 その他
| 「臨床研究における記録の保管に関する標準業務手順書」に従い、研究中の情報は、研究責任者の管理の下、帝京大学医学部外科学講座にて保管の対象となる記録類一式を適切に保管する。情報管理責任者は、記録類一式が適切に保管されるよう必要な監督を行う。研究終了後にデータセット等を臨床研究実施検討委員会事務局に提出し、臨床研究センター(TARC)にて10年間の保管の後に廃棄する。 (1) 情報の匿名化 匿名化を行う。匿名化は、登録時に発行される11桁の数字アルファベットである患者識別コードを用いて行う。外科外来にて患者識別コード発行時に、研究を担当する医師は登録日、登録番号、カルテID、患者氏名を記入した患者個人対応表を作成する。対応表は下記、情報の保管方法に従い保管する。 (2) 情報の保管方法 患者の身元を明らかにする記録及び医療情報に関する機密の保全に留意する。患者識別コードと患者個人情報の対応表および研究期間中の個人情報のデータは、帝京大学医学部外科学講座にて研究室内の鍵で施錠された場所に適切に保管される。データの閲覧は情報取扱者と情報管理責任者のみが可能となっており、管理権限のある職員以外はデータの持ち出しは不可能となっている。登録患者の同定や照会は、患者識別コードを用いて行い、患者名や生年月日など第三者が直接患者を識別出来る情報は使用しない。研究の目的以外に、研究で得られた患者のデータを使用する場合があるが、研究の結果を公表する際は、患者を特定できる情報を含まないようにする。また、あらかじめ患者の同意を得ないで、説明文書で特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱わない。患者の秘密が保全されることを前提として、研究が適正に行われていることを確保するために行うモニタリング及び監査に従事する株式会社化合物安全性研究所、並びに臨床研究実施検討委員会及び高難度新規医療技術評価委員会に従事する者、認定再生医療等委員会及び規制当局が、必要な範囲内において患者に関する資料・情報を閲覧する。 |
||
| (教育訓練) 提供機関管理者および実施責任者が、医師及び職員に対して以下について定期的に教育及び研修を行い、記録し、保管する。(外部団体の研修含む) 1 医師及び製造管理・品質管理業務に従事する職員に対して製造及び品質管理に関する必要な教育訓練 2 医師及び製造又は検査に従事する職員に対して、特定細胞加工物の製造のために必要な衛生管理、微生物学、医学その他必要な教育訓練 3 清浄度管理区域及び無菌操作等区域等での作業に従事する職員並びに特定細胞加工物の加工等に係る作業に従事する職員に対して、微生物等による汚染を防止するために必要な措置に関する教育訓練 4 必要に応じて、実施責任者からの指示に基づき教育訓練製造及び品質管理に関する必要な教育訓練 5. 医師及び製造管理・品質管理業務に従事する職員に対して被験者保護及び研究倫理に関する必要な教育訓練 (情報の収集) 医師は、専門誌などからの情報収集をはじめ、日本再生医療学会等に出席をして、常に最新の情報の収集につとめる。 |
||
| 苦情及び問合せは下記連絡先に集約し、有害事象への該当性、緊急措置の必要性等を適切に判断し、対応する体制を整備する。 帝京大学医学部附属病院 実施責任者 外科学講座 教授 坂尾 幸則 TEL:03-3964-1211(代表) 住所:〒173-0003 東京都板橋区加賀2丁目11−1 |
||
| 非該当 | ||
| なし | none | |
| 無 | ||
| 非該当 | ||
| 非該当 | ||
| 該当 | ||
添付資料
添付資料
| 4 再生医療等を受ける者に対する説明文書及び同意文書の様式 | 4.説明文書 ver.2.1_同意文書 v1.0_同意撤回書 v1.0.pdf |
|---|