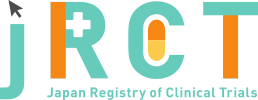臨床研究等提出・公開システム
再生医療等提供計画情報の詳細情報です。
| 第二種 | ||
| 令和5年6月8日 | ||
| 令和6年3月5日 | ||
| 令和5年10月15日 | ||
| 令和5年10月30日 | ||
| 放射線照射された乳房温存療法後の乳房変形に対する自己培養脂肪組織由来間葉系幹細胞を用いた治療の臨床研究 | ||
| 脂肪組織由来間葉系幹細胞を用いた乳房再建治療 | ||
| 帝京大学医学部附属病院 | ||
| 澤村 成史 | ||
| 乳がんは女性のがんの中では最も多いがんであり、手術療法、放射線療法、薬物療法を組み合わせた集学的治療が行われる。乳房温存療法(乳房部分切除術+術後放射線照射)は、乳房全切除術と同等の治療成績が得られることが示され、手術全体の約60%を占めている。一方で、乳がん術後の乳房変形は、患者のQOLを低下させることが問題となっているものの治療法が確立していない。さらには術後放射線照射により組織の変性をきたすため、手術による修正は非常に困難である。脂肪注入移植を用いた再建術が期待されているが、放射線照射後の脂肪の生着率は低く、幹細胞付加による生着率の改善が期待されている。 本臨床研究は、術後放射線照射を行なった乳房温存療法後の皮膚萎縮線維化に対して、組織リモデリングの改善、柔軟性の回復および移植脂肪によるボリュームの改善効果に期待し、ASC注入移植による再建術の安全性と有効性の評価を行うものである。 | ||
| N/A | ||
| 乳房温存療法(乳房部分切除+術後放射線照射)後の乳房変形 | ||
| 研究終了 | ||
| CONCIDE特定認定再生医療等委員会 | ||
| NA8160002 | ||
総括報告書の概要
総括報告書の概要
臨床研究の名称等
臨床研究の名称等
| 第二種 | |||
| 令和6年3月5日 | |||
| jRCTb030230126 | |||
| 提供しようとする再生医療等の名称 | 放射線照射された乳房温存療法後の乳房変形に対する自己培養脂肪組織由来間葉系幹細胞を用いた治療の臨床研究 | ||
| 認定再生医療等委員会の名称(認定番号) | CONCIDE特定認定再生医療等委員会 (NA8160002) | ||
| 2023年10月30日 | |||
| 0 | |||
| / | 本研究において再生医療を受けたものはいなかった。 | No patients received the regenerative medice with this study protocol. | |
| / | 本研究計画は患者登録前に中止終了となり、データは収集されていない。 | This study has been terminated before the patient registration and no data were collected. | |
| / | 本研究計画は患者登録前に中止終了となり、データは収集されていない。 | This study has been terminated before the patient registration and no data were collected. | |
| / | 本研究計画は患者登録前に中止終了となり、データは収集されていない。 | This study has been terminated before the patient registration and no data were collected. | |
| / | 本研究は乳房温存療法後の乳房変形に対するASC注入移植による再生術の安全性及び有効性の評価を行うことを目的とし計画されたが、患者登録前に中止終了となり、データは終了されていない。 | This study was planned to assess safety and efficacy of cultured adipose-redived stem cells for breast-reconstruction after breast conserving surgery with radiation; however, the study has been terminated before the patient registration and no data were collected. | |
IPDシェアリング
IPDシェアリング
| / | 無 | No | |
|---|---|---|---|
| / | |||
1 提供しようとする再生医療等及びその内容
1 提供しようとする再生医療等及びその内容
申請者情報
申請者情報
| 令和6年3月5日 | |||
| jRCTb030230126 | |||
| 帝京大学医学部附属病院 | |||
| 東京都板橋区加賀二丁目11番1号 | |||
| 澤村 成史 | Sawamura Shigehito | ||
(1)再生医療等の名称及び分類
(1)再生医療等の名称及び分類
| 放射線照射された乳房温存療法後の乳房変形に対する自己培養脂肪組織由来間葉系幹細胞を用いた治療の臨床研究 | Safety and efficacy of cultured adipose-derived stem cells for breast-reconstruction after breast conserving surgery with radiation( CABCR ) | ||
| 脂肪組織由来間葉系幹細胞を用いた乳房再建治療 | Cultured adipose-derived stem cells for breast reconstruction( CAB ) | ||
| 第二種 | |||
| 当該臨床研究は患者自身の脂肪組織から採取した脂肪組織由来間葉系幹細胞(Adipose-derived Stem Cell、以下、ASC)を培養して増殖させ、初回及び2回目投与時は培養細胞のみを、3回目、4回目の投与時は自己脂肪組織と培養細胞の混合物を放射線照射後の皮膚萎縮線維化に対して投与する医療技術であり、胚性幹細胞/人工多能性幹細胞/人工多能性幹細胞様細胞の利用、遺伝子導入操作、投与を受ける者以外の細胞の利用、動物細胞の利用、幹細胞の利用の一切を行わない。 「「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」及び「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」の取扱いについて(平成26 年10 月31 日付医政研発1031 第1号厚生労働省医政局研究開発振興課長通知)」の図2(第一種・第二種・第三種再生医療等技術のリスク分類)に基づき、自己培養脂肪組織由来間葉系幹細胞を用いた放射線照射された乳房温存療法後の乳房変形に対する治療の臨床研究を第二種再生医療等技術と判断した。 | |||
(2)再生医療等の内容
(2)再生医療等の内容
| 乳がんは女性のがんの中では最も多いがんであり、手術療法、放射線療法、薬物療法を組み合わせた集学的治療が行われる。乳房温存療法(乳房部分切除術+術後放射線照射)は、乳房全切除術と同等の治療成績が得られることが示され、手術全体の約60%を占めている。一方で、乳がん術後の乳房変形は、患者のQOLを低下させることが問題となっているものの治療法が確立していない。さらには術後放射線照射により組織の変性をきたすため、手術による修正は非常に困難である。脂肪注入移植を用いた再建術が期待されているが、放射線照射後の脂肪の生着率は低く、幹細胞付加による生着率の改善が期待されている。 本臨床研究は、術後放射線照射を行なった乳房温存療法後の皮膚萎縮線維化に対して、組織リモデリングの改善、柔軟性の回復および移植脂肪によるボリュームの改善効果に期待し、ASC注入移植による再建術の安全性と有効性の評価を行うものである。 | |||
| N/A | |||
| 実施計画の公表日 | |||
| 2027年03月31日 | |||
| 5 | |||
| 介入研究 | Interventional | ||
| 単一群 | single arm study | ||
| 非盲検 | open(masking not used) | ||
| 非対照 | uncontrolled control | ||
| 単群比較 | single assignment | ||
| 治療 | treatment purpose | ||
| 以下の条件を全て満たすこと。 1) 20歳以上の女性 2) 片側の初発乳がん患者 3) 乳房温存療法(乳房部分切除+術後放射線照射)後の乳房変形が認められ、再建術を希望する患者 4) 直近の乳がん手術から1年以上経過している患者 5) 乳がんが制御され、転移や局所に残存・再発のない患者 6) 吸引による脂肪採取が可能な患者 7) 本研究への参加について、患者本人が理解し書面での同意が得られる患者 |
Patients who meet all of the following conditions: 1) Female, age 20 years and older 2) Primary breast cancer in one side 3) Anticipate reconstruction for breast deformity after breast-conserving surgery followed by radiation therapy 4) Last surgery for breast cancer more than 1 year prior to enrollment 5) No metastasis, residual or local recurrence, and no evidence of recurrence of cancer 6) Available adipose tissue collection with inhalation technique 7) Signed written informed consent |
||
| 以下のいずれかの項目に該当する患者。 1) 痩身等により治療に必要十分な脂肪組織の採取が困難な患者 2) 活動性の感染がある患者 3) 治療部位あるいは脂肪採取部位に感染がある患者 4) 患側の乳房に豊胸術を行った既往がある患者 5) 制御されていない悪性腫瘍あるいはその転移がある患者 6) 本研究起点日の1ヶ月前から本研究終了(18ヶ月間)までの期間に抗がん剤、免疫抑制剤、抗凝固薬、抗血小板薬の投与による治療が行われる患者 7) 本研究起点日の1ヶ月前から本研究終了(18ヶ月間)までの期間に治療部位に対する放射線照射および本研究以外の手術による治療が行われる患者 8) 重篤な合併疾患(心疾患、肺疾患、肝疾患、腎疾患、膠原病、コントロール不能な糖尿病、薬剤アレルギーなど)があり、医師が本研究に不適格と判断した患者 9) 妊娠中または授乳中の患者(自己申告) 10) 喫煙者および本研究起点日の1ヶ月前から本研究終了(18ヶ月間)までの期間の禁煙が不可能な患者 11) 全身麻酔がかけられないまたは同意が得られない患者 12) 本研究で指定した治療や検査、通院、入院に協力できない患者 13) その他、医師が本研究に不適格と判断した患者 |
Patients who meet any of the following conditions: 1) Not enough adipose tissue collection 2) Not controlled infectious diseases 3) Evidence of infection in treatment target area and adipose tissue collection site 4) History of breast augmentation in affected side 5) Presence of any other known malignancy or metastasis 6) Use of anticancer, immunosuppressant, anticoagulant or antiplatelet agents during this research, from first adipose tissue collection to 18-month follow-up 7) Surgery or radiation therapy in treatment target area and adipose tissue collection site during this research, from first adipose tissue collection to 18-month follow-up 8) Considered by investigator due to any other severe condition such as cardiac, lung, liver, kidney, auto-immune, not-controlled diabetes, or drug allergy 9) Pregnant or breast-feeding 10) Smoker or unavailable to quit smoking during this research, from first adipose tissue collection to 18-month follow-up 11) Not appropriate or not consent obtained for general anesthesia 12) Lack of cooperation with the procedures designated for this research 13) Considered as inappropriate for this research for any reason by investigators |
||
| 20歳 以上 | 20age old over | ||
| 上限なし | No limit | ||
| 女性 | Female | ||
| 臨床研究の終了 目標症例数が登録され、全ての症例についての評価が終了したことをもって臨床研究終了とする。 臨床研究の中止 臨床研究の中止とは、以下のいずれかの理由により予定より早く中止されることをいう。 (1) 個々の患者における中止 ① 登録後に適格基準等の参加条件を満たさなくなった場合 ② 他疾患で入院し、治療介入継続が不可能と医師が判断した場合 ③ 転居などの理由により、患者が来院できない等の事情で研究が完了できなくなった場合 ④ 患者から研究継続の中止の申し出があった場合 ⑤ 臨床研究が継続不可能と医師が判断した場合 (2) 研究全体の中止 ① 重篤な有害事象の発生により、CRBや病院の関連する委員会より中止勧告があった場合 ② 症例登録の遅延やプロトコール逸脱の頻発により、CRBや病院の関連する委員会より研究の完遂が困難と判断された場合 ③ 実施責任者が研究の中止を必要と認めた場合 臨床研究全体の中止決定後は、実施責任者は可及的速やかに研究中の対象患者に対する対応方法を決定し、CRBや病院の関連する委員会に中止とその理由を報告し、対象患者に対して適切な対応をとる。情報・試料は1年間保管の後に廃棄する。なお、中止時検査は特段実施しないものとする。 |
|||
| 乳房温存療法(乳房部分切除+術後放射線照射)後の乳房変形 | Breast deformity after breast-conserving surgery followed by radiation therapy | ||
| 有 | |||
| 1)脂肪組織採取のための切開及び脂肪組織吸引 2)自己脂肪組織由来間葉系幹細胞、及び培養細胞を混合した脂肪組織の投与 |
1) Adipose tissue collection with inhalation technique 2) Administration of autologous adipose-derived stem cells and adipose tissue with cultured cells |
||
| 因果関係のある有害事象 全ての評価終了時までに本臨床研究との因果関係があると判定された疾病等の数、およびGrade (CTCAE v5.0-JCOG)を主要評価項目とする。 |
Number and Grade (CTCAR v5.0-JCOG) of adverse events related to this research from day 0 to 18 months follow-up | ||
| ・柔らかさ/伸展性 超音波エラストグラフィ検査により治療部位と健側の対称部位で各々評価、計測を行い、起点から18ヶ月後までの変化率を評価する。 ・乳房の厚さ・容積 超音波検査と乳房MRIを用いて計測した、皮下組織の厚さと乳房の容積の起点から18ヶ月後までの変化率を評価する。 ・患者満足度 患者自己記入式アンケートBreast Qを用い、PROを評価する。 |
- Comparison of affected and unaffected breasts in percent change of elasticity measured by ultrasonic elastography - Change in breast subcutaneous tissue thickness and breast volume measured by ultrasonography and breast MRI - Patient reported outcome on health related quality of life evaluated with Breast Q |
||
| 細胞の採取の方法: 帝京大学医学部附属病院形成外科外来手術室において、脂肪採取部位の皮膚消毒後、1%キシロカインE注皮下注射し、メスで約5mmの皮膚切開を入れる。プロテクターを挿入固定し、テュメセント液(1%キシロカインE注20mL+生理食塩水100mL+7%メイロン注2mL)を脂肪採取範囲の皮下組織内に注入する。その後、外径3mmのカニューレを用いて陰圧法で脂肪吸引を行い、必要量(1回30mL以上)を採取する。終了後、採取孔は真皮埋没縫合にて閉鎖し、採取範囲の圧迫固定を行う。採取後、脂肪組織は搬送時まで2-8℃で保管し、専門の検体搬送業者にて特定細胞加工物製造事業者である株式会社ロートセルファクトリー東京に搬送する。 細胞を得るための脂肪組織は、初回採取から3か月後に再度採取され、計2回実施される。 製造及び品質管理の方法の概要: 1回の製造につき、対象患者から採取した30mL以上の脂肪組織から細胞を単離し、培養を開始する。P0培養で約7日間、P1培養で約7日間培養後、回収した細胞を-80℃以下で保管する。同様に合計2回製造する。 患者の治療スケジュールに合わせて細胞を計4回解凍(P2)し、それぞれP2培養7日後に回収する。回収した細胞を搬送液にサスペンドし、バイアル瓶に分注し、搬送時まで2-8℃で保管する。 工程内管理試験としては受入時の目視検査及び脂肪組織量検査、培養中の細胞生存率検査、生菌数迅速試験、細胞回収時の生細胞数検査、フローサイトメトリー検査を実施する。完成品検査として、細胞数検査、生存率検査、フローサイトメトリー検査、マイコプラズマ否定試験、無菌試験、エンドトキシン試験を実施する。 特定細胞加工物の投与の方法: ①細胞のみを注入する場合(1回目、2回目投与) 特定細胞加工物製造事業者から発送されたASCをロック式シリンジに充填し準備する。帝京大学医学部附属病院形成外科外来手術室において、患者は立位で乳房変形を認める注入予定範囲をマーキングしたのちに仰臥位とし、皮膚消毒後、予定範囲の皮下及び軟部組織内にASCを全量注入する。 ②脂肪組織と細胞を混合して投与する場合(3回目、4回目投与) 採取した脂肪組織を遠心機700×g, 3分間で遠心分離し、液層とオイル層を除去して脂肪組織を濃縮する。脂肪組織40mLにASC 2×10^7 cells/20mLを混合する。あらかじめ立位でマーキングした乳房変形を認める注入予定範囲の皮下および軟部組織内に、皮膚に18G針であけた注入孔から注入用カニューレで蜂巣状に注入する。必要であれば脂肪組織のみを追加注入する。 再生医療等の内容をできる限り平易な表現を用いて記載したもの 別添の通り |
|||
2 人員及び構造設備その他の施設等
2 人員及び構造設備その他の施設等
(1)人員及び構造設備その他の施設に関する事項
(1)人員及び構造設備その他の施設に関する事項
| 医師 | |||||
| 小室 裕造 | Komuro Yuzou | ||||
| 帝京大学医学部 | Teikyo University School of Medicine | ||||
| 形成・口腔顎顔面外科学講座 | |||||
| 173-8606 | |||||
| 東京都板橋区加賀2丁目11−1 | 2-11-1 Kaga Itabashi-ku Tokyo 173-8606 | ||||
| 03-3964-1211 | |||||
| ykomuro@med.teikyo-u.ac.jp | |||||
| 自施設 | |||||
| 救急関連特殊病床数 救命センター専用病床数 30床、 ICU 10床、HCU 25床、CCU 12床、救命病棟 6床 救命センター設備概要 大動脈バルーンパンピング、心肺補助装置、頭蓋内圧測定装置、小児蘇生用マット(脊髄針)、水治療室、血漿交換用装置、急速輸血装置、圧迫止血用装置、血液透析装置、血漿交換用装置、血液ろ過透析装置 | |||||
(2)その他研究の実施体制に関する事項
(2)その他研究の実施体制に関する事項
| 宇野 希世子 | Uno Kiyoko | ||||
| 帝京大学医学部 | Teikyo University School of Medicine | ||||
| 帝京大学臨床研究センター | |||||
| 173-8606 | |||||
| 東京都板橋区加賀2丁目11−1 | 2-11-1 Kaga Itabashi-ku Tokyo 173-8606 | ||||
| 03-3964-1211 | |||||
| kiyoko.uno@med.teikyo-u.ac.jp | |||||
| 医師 | ||
| 小室 裕造 | ||
| 帝京大学医学部 | ||
| 形成・口腔顎顔面外科学講座 |
| 医師 | ||
| 堂後 京子 | ||
| 帝京大学医学部 | ||
| 形成・口腔顎顔面外科学講座 |
| 医師 | ||
| 山門 希実 | ||
| 帝京大学大学院 | ||
| 医学研究科 |
| 医師 | ||
| 大河内 真之 | ||
| 帝京大学医学部 | ||
| 形成・口腔顎顔面外科学講座 |
| 医師 | ||
| 山岡 尚世 | ||
| 帝京大学医学部 | ||
| 形成・口腔顎顔面外科学講座 |
| 医師 | ||
| 藤井 麻紀 | ||
| 帝京大学医学部 | ||
| 形成・口腔顎顔面外科学講座 |
| 医師 | ||
| 笹島 ゆう子 | ||
| 帝京大学医学部 | ||
| 病院病理部 |
| 帝京大学臨床研究センター | ||
| 西谷 藍 | ||
| 帝京大学 | ||
| 臨床研究センター | ||
| 帝京大学臨床研究センター | ||
| 西谷 藍 | ||
| 帝京大学 | ||
| 臨床研究センター | ||
| 帝京大学医学部附属病院 | ||
| 西谷 政昭 | ||
| 帝京大学医学部附属病院 | ||
| 臨床試験・治験統括センター | ||
| 帝京大学臨床研究センター | ||
| 宮田 敏 | ||
| 帝京大学 | ||
| 臨床研究センター・大学院公衆衛生学研究科 | ||
| 帝京大学臨床研究センター | ||
| 宇野 希世子 | ||
| 帝京大学 | ||
| 臨床研究センター | ||
| 帝京大学臨床研究センター | ||
| 宇野 希世子 | ||
| 帝京大学 | ||
| 臨床研究センター | ||
(3)多施設共同研究に関する事項
(3)多施設共同研究に関する事項
| 無 |
3 再生医療等に用いる細胞の入手の方法並びに特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法等
3 再生医療等に用いる細胞の入手の方法並びに特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法等
(1)再生医療等に用いる細胞の入手の方法(特定細胞加工物を用いる場合のみ記載)
(1)再生医療等に用いる細胞の入手の方法(特定細胞加工物を用いる場合のみ記載)
| 脂肪組織由来間葉系幹細胞(Adipose-derived Stem Cell:ASC) | |
| 再生医療等の提供を行う医療機関と同じ。 | |
| ① 細胞提供者の健康状態 患者自身の細胞を用いるため、細胞提供者の選定方法における健康状態についての排除基準は再生医療等を受けようとする者と同じである。 ② 細胞提供者の年齢 20歳以上 |
|
| ・登録前の観察項目 ①問診 患者背景確認(生年月日、性別、臨床診断名、併存疾患、アレルギー歴、既往歴(過去5年)) 併用薬・併用療法 妊娠有無 ②症状(原疾患とその治療に関連する症状の有無、重症度) ③一般的身体所見 身長、体重、体温、血圧 ④血液検査 血算、白血球像、網赤血球 糖、HbA1c、Na・K・Cl、総蛋白、アルブミン、T-Bil、AST、ALT、LDH、ALP CK、尿素窒素、クレアチニン、CRP、γ-GTP、T-CHO、尿酸、カルシウム TG、HDL-CHO、LDL-CHO ⑤感染症検査 梅毒検査(STS)、B型肝炎検査(HBsAg)、C型肝炎検査(HCVAb) なお当該臨床研究においては再生医療等を受ける者の細胞を用いるため、ウインドウピリオドについては勘案しない。 ⑥ マンモグラフィ検査 ・登録時 ①問診 併用薬・併用療法(原疾患に関連のあるもののみ) 妊娠有無 ②症状(原疾患とその治療に関連する症状) ③一般的身体所見 体温、血圧、視触診 |
|
| 帝京大学医学部附属病院形成外科外来手術室において、脂肪採取部位の皮膚消毒後、1%キシロカインE注皮下注射し、メスで約5mmの皮膚切開を入れる。プロテクターを挿入固定し、テュメセント液(1%キシロカインE注20mL+生理食塩水100mL+7%メイロン注2mL)を脂肪採取範囲の皮下組織内に注入する。その後、外径3mmのカニューレを用いて陰圧法で脂肪吸引を行い、必要量(1回30mL以上)を採取する。終了後、採取孔は真皮埋没縫合にて閉鎖し、採取範囲の圧迫固定を行う。採取後、脂肪組織は搬送時まで2-8℃で保管し、専門の検体搬送業者にて特定細胞加工物製造事業者である株式会社ロートセルファクトリー東京に搬送する。 細胞を得るための脂肪組織は、初回採取から3か月後に再度採取され、計2回実施される。ただし、1回目の採取で投与4回分に必要十分量のASCが得られたと特定細胞加工物製造事業者が判断した場合、2回目の採取は行わない。 |
(2)特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法(特定細胞加工物等を用いる場合のみ記載)
(2)特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法(特定細胞加工物等を用いる場合のみ記載)
| 吸引法により採取した脂肪組織由来間葉系幹細胞 | ||
| 詳細は「特定細胞加工物概要書」及び「特定細胞加工物標準書」を参照。 1回の製造につき、対象患者から採取した30mL以上の脂肪組織から細胞を単離し、培養を開始する。P0培養で約7日間、P1培養で約7日間培養後、回収した細胞を-80℃以下で保管する。同様に合計2回製造する。ただし、1回目の採取で投与4回分に必要十分量のASCが得られたと特定細胞加工物製造事業者が判断した場合、2回目の製造は行わない。 患者の治療スケジュールに合わせて細胞を計4回解凍(P2)し、それぞれP2培養7日後に回収する。回収した細胞を搬送液にサスペンドし、バイアル瓶に分注し、搬送時まで2-8℃で保管する。 工程内管理試験としては受入時の目視検査及び脂肪組織量検査、培養中の細胞生存率検査、生菌数迅速試験、細胞回収時の生細胞数検査、フローサイトメトリー検査を実施する。完成品検査として、細胞数検査、生存率検査、フローサイトメトリー検査、マイコプラズマ否定試験、無菌試験、エンドトキシン試験を実施する。 |
||
| 皮膚消毒後、予定範囲の皮下及び軟部組織内に、1、2回目はASCのみ、3、4回目は脂肪組織と混合したASCをロック付きシリンジを用いて投与する。必要に応じて1%キシロカイン注の局所麻酔の使用を考慮する。 | ||
| 有 | ||
| 株式会社ロートセルファクトリー東京 | ||
| FA3150002 | ||
| RCFTプロセシングセンター | ||
| 脂肪組織の搬入から提供における当院への輸送までと、特定細胞加工物等の保管における脂肪組織由来間葉系幹細胞の保管及び工程内管理試験、完成品検査を委託する。 | ||
(3)再生医療等製品等に関する事項(再生医療等製品を用いる場合のみ記載)
(3)再生医療等製品等に関する事項(再生医療等製品を用いる場合のみ記載)
(4)再生医療等に用いる未承認又は適応外の医薬品又は医療機器に関する事項(未承認又は適応外の医薬品又は医療機器を用いる場合のみ記載)
(4)再生医療等に用いる未承認又は適応外の医薬品又は医療機器に関する事項(未承認又は適応外の医薬品又は医療機器を用いる場合のみ記載)
4 再生医療等技術の安全性の確保等に関す措置
4 再生医療等技術の安全性の確保等に関す措置
(1)利益相反管理に関する事項
(1)利益相反管理に関する事項
① 再生医療等に対する特定細胞加工物等製造事業者からの研究資金等の提供その他の関与
① 再生医療等に対する特定細胞加工物等製造事業者からの研究資金等の提供その他の関与
| 株式会社ロートセルファクトリー東京 | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
② 再生医療等に対する医療薬品等製造販売業者等からの研究資金等の提供その他の関与
② 再生医療等に対する医療薬品等製造販売業者等からの研究資金等の提供その他の関与
| 無 | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
③ 再生医療等に対する特定細胞加工物等製造事業者又は医療品等製造販売業者等以外からの研究資金
③ 再生医療等に対する特定細胞加工物等製造事業者又は医療品等製造販売業者等以外からの研究資金
| 無 | ||
(2)その他再生医療等技術の安全性の確保等に関する措置
(2)その他再生医療等技術の安全性の確保等に関する措置
| 【非臨床安全性評価に関する情報】 本臨床研究に先立ち、GLP準拠施設にてASCの非臨床による安全性試験を行った。投与する細胞の造腫瘍性を確認する為に軟寒天コロニー試験を、全身の毒性を確認する為に慢性毒性試験を実施した。その結果、造腫瘍性なし、全身慢性毒性なしとの結果であることを確認した。 【ヒトへの使用経験、臨床試験成績に関する報告等】 ① 海外/試験名 Prospective trial of adipose-derived regenerative cell (ADRC)-enriched fat grafting for partial mastectomy defects: the RESTORE-2 trial. 乳房部分欠損に対する脂肪由来再生細胞(ADRC)強化脂肪移植の前向き試験: RESTORE-2試験) 研究デザイン 単群 前向き試験 被験者数 67例 結果の要約:乳房温存療法後150ml以下の欠損による変形がある乳がん患者に対し、脂肪由来再生細胞(ADRC)強化脂肪移植が行われた。吸引脂肪の半量からADRCが抽出され、残りの半量の洗浄脂肪に加えて乳房に注入移植された。治療後12ヶ月で、全体的な乳房変形に関しては患者の75%、研究者の85%が満足していると報告し、MRI画像評価では83%で乳房の輪郭の改善が認められた。手順に関連した重篤な有害事象の発生、がんの局所再発の報告はなかった。注入部位の嚢胞形成10例が有害事象として報告された。これより乳房部分欠損患者に対するADRC強化脂肪移植の安全性と有効性が実証された。(Pérez-Cano R, et al., Eur J Surg Oncol EJSO. 2012; 38: 382–9.) ② 海外/試験名 Enrichment of autologous fat grafts with ex-vivo expanded adipose tissue-derived stem cells for graft survival: A randomised placebo-controlled trial. 培養ASC強化脂肪注入移植の生存率に対する効果:無作為化プラセボ対照試験。 研究デザイン 無作為化プラセボ対照試験(RCT) 被験者数 10例 結果の要約:あらかじめ腹部より採取した吸引脂肪から分離培養されたASC 6.5×10^8個/4mlを混合して強化した吸引脂肪34mlと、強化しない吸引脂肪34mlを参加者の左右の上腕後部に無作為化してボーラスで注入された。注入後121日のASC強化脂肪移植側での残存量23cmˆ3(初期注入量の80.9%)は単純な脂肪移植のコントロール側4.66cm^3(16.3%)と比較して優位に高い結果であった。 重篤な有害事象は認めなかった。(Kølle SF, Fischer-Nielsen A, Mathiasen AB, et al., Lancet. 2013; 382: 1113–1120.) ③ 海外/試験名 Clinical treatment of radiotherapy tissue damage by lipoaspirate transplant: a healing process mediated by adipose-derived adult stem cells. 放射線障害組織に対する吸引脂肪移植による治療:脂肪由来体性幹細胞を介する治癒過程。 研究デザイン 症例シリーズ(臨床パイロット試験) 被験者数 20例 結果の要約:乳がん患者の重度の晩期放射線障害組織(LENS-SOMA grade3,4)に対して脂肪注入による治療が行われた結果、1例を除き、著明な症状改善を認めた。組織学的には、障害されていた皮下組織の脂肪細胞と血管の増成が認められた。注入された吸引脂肪に含有されている脂肪由来幹細胞の作用と考えられた。 (Rigotti G, Marchi A, Galiè M, Baroni G, Benati D, Krampera M, Pasini A, Sbarbati A. Plast Reconstr Surg. 2007; 119(5): 1409-1422.) ④ 海外/試験名 Surgical Outcome and Cosmetic Results of Autologous Fat Grafting After Breast Conserving Surgery and Radiotherapy for Breast Cancer: A Retrospective Cohort Study of 222 Fat Grafting Sessions in 109 Patients. 乳がんに対する乳房温存手術および放射線療法後の自家脂肪移植の手術結果および美容上の結果:109人の患者における222の脂肪移植セッションの後ろ向きコホート研究。 研究デザイン 横断研究 被験者数 109例 結果の要約:乳房温存術および放射線治療後に脂肪移植が行われた連続した109人(114乳房)222回の手術について分析された。整容性として、全体的な外観の評価は術前5.1/10から術後6ヶ月で7.2/10と高くなり、乳房の対称性、ボリューム、形体、傷跡が著明に改善された。抗生剤内服で治癒した局所感染4例、局所麻酔化での切除を要した脂肪壊死1例を生じたが、その他に重篤な合併症は生じなかった。(van Turnhout AA, Fuchs S, Lisabeth-Broné K, Vriens-Nieuwenhuis EJC, van der Sluis WB. Aesthetic Plast Surg. 2017; 41(6): 1334-1341.) ⑤ 海外/試験名 Use of Autologous Adipose-Derived Stromal Vascular Fractions in Revision Rhinoplasty for Severe Contractures in Asian Patients.アジア人患者の重度の鼻拘縮に対する修正鼻形成術における自家脂肪由来間質血管画分(SVF)の使用。 研究デザイン 症例対照研究 被験者数 40例 結果の要約:吸引脂肪由来SVFを抽出後凍結保存し、肋軟骨による整鼻術の前14回、後6回1週間毎に鼻部皮下3点に27G針で注射した(8×10^6cells/0.5ml)。対照には0.9%生理食塩水を同様に注射した。治療後18カ月で、鼻の長さ、鼻尖突出度、鼻唇角の値は対照群と比較して有意に改善された。両者ともに重篤な合併症の発症はなかった。(Ahn TH, Lee W, Kim HM, Cho SB, Yang EJ. Plast Reconstr Surg. 2021; 147(3): 401e-411e.) ⑥ 国内/試験名 Cell-assisted lipotransfer for cosmetic breast augmentation: supportive use of adipose-derived stem/stromal cells. 美容豊胸手術における細胞付加脂肪移植; 脂肪由来幹細胞/間質細胞の支持的な利用。 研究デザイン 症例シリーズ 被験者数 40例 結果の要約:健康な40名の女性の左右の乳房に対し、皮下から採取した吸引脂肪の半分からASC を含む間質血管画分 (SVF)を分離し、残りの半分の吸引脂肪に付加して注入し、豊胸術を行なった。片側で平均270ml脂肪注入し、最終的な乳房容積は100〜200ml増大して2ヶ月以降も変化がなかった。 24ヶ月時に嚢胞形成2名、微小石灰化2名、6ヶ月時に線維性の硬化を1名で認めたが、そのほか重篤な合併症は認めなかった。 (Yoshimura K, Sato A, Aoi N, et al. Aesthet Plast Surg. 2008; 32: 48–55.) <提供しようとする再生医療等との関連性> 吸引脂肪注入あるいは脂肪由来幹細胞の局所注入による臨床治療および臨床試験の結果である。 |
||||||
| 乳がんは、女性のがんの中では最も多いがんである。乳がん罹患数は増加の一途をたどっており、2017年では、日本全国で91,600人、女性の9人に1人が生涯で乳がんに罹患するリスクがあると報告されている1)。乳がんの治療法には主に手術療法、放射線療法、薬物療法があり、これらを組み合わせた集学的治療が行われる。現在の乳がんの標準的な手術の方法は、「乳房温存手術」あるいは「乳房全切除術」があるが、乳房温存療法(乳房部分切除術+術後放射線照射)は、乳房全切除術と同等の治療成績が得られることが示され、乳房温存手術が約60%を占めている2)。 一方で、乳がん術後に生じる乳房変形は、患者のQOLを著しく低下させること(身体的苦痛、衣服の問題、活動の制限、精神的・性的喪失感など)が問題となっており、乳房の再建術や修正術は乳がん治療の一環として求められるようになった2)。 「乳房全切除術」に対する乳房再建術としては、主に自家組織による再建と人工物による再建がある。有茎あるいは遊離自家組織皮弁による乳房再建では、柔らかく自然な乳房の再建が可能となるが、皮弁採取部を含む大きな傷跡と手術侵襲が問題である。2013年に乳房再建用エキスパンダー(組織拡張器)および乳房インプラントが保険収載されてからは人工物による乳房再建が増加したが、人工物は材質や規格の制約、違和感、皮膜拘縮、露出、破損、感染といった特有の問題があり、特に放射線照射後の乳房への使用は合併症発生のリスクが高く推奨されない。また、2019年にはブレストインプラント関連未分化大細胞型リンパ腫(Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma: BIA-ALCL)発生の報告からアラガン社製テクスチャード・インプラントおよびエキスパンダーのリコールが起こり、人工物の使用についての懸念が改めて認識された2,3)。 一方、「乳房温存療法」後の乳房変形に対しては確立された治療法がないのが現状である。「乳房温存療法」では、標準治療として残存乳房に対する術後放射線照射が合わせて行われる。放射線照射された組織は放射線障害による線維化、硬化、萎縮を生じ、柔軟性、伸展性が損なわれる。さらに、組織の虚血、細胞の枯渇を生じ、創傷治癒および再生能が低下しているため、乳房の変形に対して手術による修正を行うことが非常に困難となる。当然、人工物の使用も推奨できない。最近、脂肪注入移植を用いた組織増大法による修正手術が期待されているが4)、一般に注入脂肪の生着率は50%前後と低く治療効果が不安定で5)、一度に注入できる量に制限があることから充分なボリュームを獲得する事が難しい。放射線照射後の脂肪の生着率はさらに低くなるため満足な結果が得られていない2,3)。これに対し、注入脂肪の生着率を改善させる目的に幹細胞を付加した脂肪注入が試みられている6,7)。 脂肪組織由来間葉系幹細胞(Adipose-derived Stem Cell、以下、ASC)とは、脂肪組織中に存在する多分化能を有する幹細胞である。ASCの特徴は、脂肪組織から容易に回収が可能であり、また、細胞の増殖スピードが速いため比較的容易に必要量を確保することが可能となり、高い分化能を有することが挙げられる。再生医療の細胞供給源としては、古くから組織幹細胞である骨髄由来間葉系幹細胞(Mesenchymal stem cell: MSC)が注目されてきたが、骨髄採取は侵襲が大きく、骨髄から得られる幹細胞数は非常に少ない8)。一方、 ASCは研究が進むにつれ骨髄由来MSCと同様の有効性が確認されるようになり、組織採取がより低侵襲かつ幹細胞回収率の高いことから骨髄由来 MSCに代わる再生医療の幹細胞源として期待が高まってきている。 以上のことから、患者自身の脂肪組織から分離したASCを用い、本臨床研究を行う。 1) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(全国がん登録) 2) 乳癌診療ガイドライン2018年版「外科療法」 3) Juhl AA, Redsted S, Damsgaard TE. Autologous fat grafting after breast conserving surgery: Breast imaging changes and patient-reported outcome. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 71:1570-1576, 2018. 4) Krastev TK, Beugels J, Hommes J, Piatkowski A, Mathijssen I, van der Hulst R. Efficacy and Safety of Autologous Fat Transfer in Facial Reconstructive Surgery: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA facial plastic surgery. 20: 351-60, 2018. 5) 形成外科診療ガイドライン1 2021年版 第Ⅳ編 乳房再建診療ガイドライン 6) Matsumoto D, Sato K, Gonda K, Takaki Y, Shigeura T, Sato T, Aiba-Kojima E, Iizuka F, Inoue K, Suga H, Yoshimura K. Cell-assisted lipotransfer: supportive use of human adipose-derived cells for soft tissue augmentation with lipoinjection. Tissue Eng.12: 3375–3382, 2006. 7) Luan A, Duscher D, Whittam AJ, Paik KJ, Zielins ER, Brett EA, et al. Cell-assisted lipotransfer improves volume retention in irradiated recipient sites and rescues radiation-induced skin changes. Stem Cells. 34: 668–73, 2016. 8) Zuk PA, Zhu M, Mizuno H, et al.: Multilineage cells from human adipose tissue: implications for cell-based therapies. Tissue Eng 7: 211-228, 2001. |
||||||
| ① 決定を行う時期 細胞加工施設で製造を開始後、全ての製造工程、及び無菌試験を除く規格試験が終了した時(細胞採取から約1か月後)。ただし無菌試験は判定までに14日かかるため、工程内管理試験である生菌数迅速試験の結果を以って代用する。無菌試験が陽性だった場合、医師は、抗生剤の投与など対処を行う。 ② 決定を行う者 脂肪由来間葉系幹細胞の投与の可否判断の決定は再生医療等を行う医師が行う。 ③ その他 なし |
||||||
| 細胞加工施設は当院からの組織輸送中及び細胞加工施設から当院への試料の輸送中を含め、細胞の安全性に関する疑義が生じた場合、遅滞なく当院に報告を行い、今後の対策(組織の再採取、研究の修正変更、中止等)を検討する。 当院においても組織採取時及び特定細胞加工物投与時において細胞の安全性に疑義が生じる事象を発見した場合、採取または投与を中止し、有害事象として適切な処置を施し、最善の策を講じると共に、Electronic Data Capture(EDCシステム, Viedoc4)に入力する。 |
||||||
| 試料はRCFTプロセシングセンター内の鍵のかかる部屋に設置された冷凍庫に保管する。保存期間は臨床研究終了後より1年とする。 | ||||||
| 保管期間が満了した場合、患者から同意の撤回があった場合、また、試料の取り違えや混入が起きるかそれらが強く疑われる場合、その他廃棄の必要性を認めた場合には、感染性廃棄物として株式会社ロートセルファクトリー東京の規定に基づき廃棄する。 | ||||||
| 本研究では、ASC製造用脂肪組織採取から最終評価終了時までの間に起きた関連のある有害事象について調査記録する。関連の有無に関係なく、有害事象が認められた場合は、適切な処置を施し、最善の策を講じる。本研究との因果関係が疑われる有害事象(疾病等)は、帝京大学医学部附属病院臨床研究モニタリング委員会に報告し、同委員会にて因果関係の有無、疾病等に該当するかを判断する。実施責任者は、臨床研究の実施に起因するものと思われる重篤な疾病等の発生を知った場合には、速やかにその旨を実施医療機関の管理者、及び3営業日以内に特定細胞加工物製造事業者に報告した上で、疾病等発生時の対応に関する手順書に基づき適切に認定再生医療等委員会及び厚生労働大臣に報告する。 重篤な有害事象の報告 重篤と思われる有害事象(疾病等を含む)には、担当医師が本研究実施との因果関係の有無にかかわらず、直ちに(知り得てから24時間以内)に実施責任者に口頭、電話等で連絡する。 |
||||||
| ASCのみ投与1回目を起点として術後18ヶ月後まで調査、観察・検査を行う。経過観察期間中に実施される検査項目は下記の通りである。 1) 併用薬・併用療法 2) 患者背景確認 3) 妊娠の有無確認 4) 有害事象発現確認 5) 一般的身体所見 6) 超音波検査(エラストグラフィ) 7) 乳房MRI検査 8) 乳房写真検査 9) マンモグラフィ 10) 患者満足度確認(Breast Q) 11) 病理組織採取(HE,CD31染色) 当院は再生医療等の提供中止の旨を、その中止の日から10日以内に認定再生医療等委員会に通知するとともに、地方厚生局長に再生医療等提供中止届を提出する。中止届を提出し対象者の措置を終えた後、中止した日又は全ての評価項目に係るデータの収集を行うための期間が終了した日のいずれか遅い日から原則一年以内に総括報告書を提出する。総括報告書の概要を提出し、公表することをもって研究の終了とする。 |
||||||
| 再生医療等の提供に起因するものと疑われる疾病等の発生の場合に当該疾病等の情報を把握できるよう、及び細胞加工物に問題が生じた場合に患者の健康状態等が把握できるよう、あらかじめ患者の同意を得た上で連絡先等の情報を収集し管理する。収集した情報は「臨床研究における記録の保管に関する標準業務手順書」に従い、適切に保管する。 | ||||||
| 有 | ||||||
| 実施計画の公表日 | ||||||
| 研究終了 | Complete | |||||
5 細胞提供者及び再生医療等を受ける者に対する健康被害の補償の方法
5 細胞提供者及び再生医療等を受ける者に対する健康被害の補償の方法
細胞提供者について(特定細胞加工物を用いる場合のみ記載)
細胞提供者について(特定細胞加工物を用いる場合のみ記載)
| 有 |
再生医療等を受ける者について
再生医療等を受ける者について
| 有 |
6 審査等業務を行う認定再生医療等委員会に関する事項
6 審査等業務を行う認定再生医療等委員会に関する事項
| CONCIDE特定認定再生医療等委員会 | CONCIDE Specified Certified Regenerative Medicine Committee | |
| NA8160002 | ||
| 東京都千代田区二番町11番地3相互二番町ビルディング別館7階 | Sougo Nibancho Bld. Annex 7F, 11-3, Nibancho, Chiyoda Ku, Tokyo | |
| 03-5772-7584 | ||
| concide_jimukyoku@concide.or.jp | ||
| 第一種再生医療等又は第二種再生医療等を審査することができる構成 | ||
| 適 | ||
| 2023年03月20日 | ||
7 その他
7 その他
| 本研究の正しい結果を得るために患者個人を特定して実施され、適切な管理のもとに個人情報を利用する。本研究で利用する個人情報は、患者の同定や照会のために最低限のものと考え、登録番号のみとする。患者氏名等そのほかの個人を特定する情報はデータセンターへ知らされることはなく、万が一誤って知らされた場合には、破棄するか、マスキングなど判読不能とする適切な処理を行ったうえで保管する。 本研究における個人情報の利用者は、研究責任医師、研究分担医師、CRCおよび監査担当者とする。 本研究の患者情報は、帝京大学医学部附属病院にてEDCシステムに入力し、データセンターに提出されることによって収集される。電子メールによる問合せのやりとりをする際には登録番号のみを用い、その他の情報を用いない。 (1) 個人情報を加工する方法と対応表の管理 本研究では、登録時に発行される ASCBで始まる患者識別コードを用いて個人を識別する形式に加工する。形成外科外来にて患者識別コード発行時に、研究を担当する医師は登録日、登録番号、カルテID、患者氏名を記入した患者個人対応表を作成する。対応表は下記、情報の保管方法に従い保管する。 (2) 個人情報の保管方法 本研究では、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止のため、情報の保管にあたっては十分な安全管理措置を講ずる。紙媒体の情報は、帝京大学医学部形成・口腔顎顔面外科学講座にて研究室内の鍵で施錠された場所に適切に保管される。電子媒体の情報は、パスワードを設定したファイルに記録し、外付けハードディスクに保存して、さらに、紙媒体と同じキャビネットにて厳重に管理する。これらの研究データには、特定認定再生医療等委員会に承認された研究組織の研究責任医師及び研究分担医師のみがアクセスすることができる。また、データマネジメントを行うデータセンターには、個人情報の加工に用いた対応表は提供せず、担当者は個人を識別できない状態でデータマネジメント業務を行う。なお、データを収集するEDCシステムへのアクセスは申請された者にのみ権限が付与され許可される。EDCシステムに収集されたデータは、アクセス管理されたEDCシステムのサーバー上で管理される。 |
||
| (教育訓練) 提供機関管理者および実施責任者が、医師及び職員に対して以下について定期的に教育及び研修を行い、記録し、保管する。(外部団体の研修含む) 1 医師及び製造管理・品質管理業務に従事する職員に対して製造及び品質管理に関する必要な教育訓練 2 医師及び製造又は検査に従事する職員に対して、特定細胞加工物の製造のために必要な衛生管理、微生物学、医学その他必要な教育訓練 3 清浄度管理区域及び無菌操作等区域等での作業に従事する職員並びに特定細胞加工物の加工等に係る作業に従事する職員に対して、微生物等による汚染を防止するために必要な措置に関する教育訓練 4 必要に応じて、実施責任者からの指示に基づき教育訓練製造及び品質管理に関する必要な教育訓練 5. 医師及び製造管理・品質管理業務に従事する職員に対して被験者保護及び研究倫理に関する必要な教育訓練 (情報の収集) 医師は、専門誌などからの情報収集をはじめ、日本再生医療学会等に出席をして、常に最新の情報の収集につとめる。 |
||
| 苦情及び問合せは下記連絡先に集約し、有害事象への該当性、緊急措置の必要性等を適切に判断し、対応する体制を整備する。 帝京大学医学部附属病院 実施責任者 形成・口腔顎顔面外科学講座 主任教授 小室 裕造 TEL:03-3964-1211(代表) 住所:〒173-8606 東京都板橋区加賀2丁目11−1 |
||
| 非該当 | ||
| なし | none | |
| 無 | ||
| 非該当 | ||
| 非該当 | ||
| 該当 | ||
添付資料
添付資料
| 4 再生医療等を受ける者に対する説明文書及び同意文書の様式 | 04. 同意説明文書ver.2.0 最終.pdf |
|---|