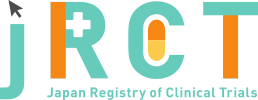臨床研究等提出・公開システム
再生医療等提供計画情報の詳細情報です。
| 第二種 | ||
| 令和7年7月23日 | ||
| 自己脂肪由来間葉系幹細胞を用いた肝硬変に対する治療の安全性を検討する探索的臨床試験 | ||
| 肝硬変に対する脂肪由来間葉系幹細胞療法 | ||
| 医療法人新産健会 LSI札幌クリニック | ||
| 山田 有則 | ||
| 肝硬変の治療として、自己脂肪由来間葉系幹細胞を用いた新しい治療法の安全性を検討する。 | ||
| 1 | ||
| 肝硬変 | ||
| 募集中 | ||
| CONCIDE特定認定再生医療等委員会 | ||
| NA8160002 | ||
1 提供しようとする再生医療等及びその内容
1 提供しようとする再生医療等及びその内容
申請者情報
申請者情報
| 令和7年7月16日 | |||
| jRCTb010250024 | |||
| 医療法人新産健会 LSI札幌クリニック | |||
| 北海道札幌市東区北13条東1丁目2-50 | |||
| 山田 有則 | Yamada Tomonori | ||
(1)再生医療等の名称及び分類
(1)再生医療等の名称及び分類
| 自己脂肪由来間葉系幹細胞を用いた肝硬変に対する治療の安全性を検討する探索的臨床試験 | Exploratory Clinical Trial to Evaluate the Safety of Autologous Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells for Liver Cirrhosis | ||
| 肝硬変に対する脂肪由来間葉系幹細胞療法 | Adipose-derived mesenchymal stem cell therapy for liver cirrhosis | ||
| 第二種 | |||
| 本研究に用いる細胞加工物は、自己の脂肪組織を原料として培養により得られる間葉系幹細胞である。 1.政令の除外技術ではない。 2.人の胚性幹細胞、人工多能性幹細胞及び人工多能性幹細胞様細胞を利用しない。 3.遺伝子を導入する操作を行った細胞を利用しない。 4.動物の細胞を利用しない。 5.投与を受ける者以外の人の細胞を利用しない。 6.幹細胞を利用している。 7.幹細胞の培養を行っている。 以上により、第二種再生医療等技術であると判断した。 | |||
(2)再生医療等の内容
(2)再生医療等の内容
| 肝硬変の治療として、自己脂肪由来間葉系幹細胞を用いた新しい治療法の安全性を検討する。 | |||
| 1 | |||
| 実施計画の公表日 | |||
| 2026年12月31日 | |||
| 3 | |||
| 介入研究 | Interventional | ||
| 単一群 | single arm study | ||
| 非盲検 | open(masking not used) | ||
| 非対照 | uncontrolled control | ||
| 単群比較 | single assignment | ||
| 治療 | treatment purpose | ||
| (1) 同意取得時において満18歳以上、満70歳以下の男女の患者 (2) HBV、HCV又はMAFLDを原因とする肝硬変患者 (3) 肝硬変症例であって、Child-Pughスコア7~9の患者 (4) ECOGのPerformance Statusが0~2の患者 (5) 本研究への参加にあたり十分な説明を受けた後、十分な理解の上、本人の自由意思による文書同意が得られた患者 |
(1) Male and female patients who are at least 18 years old and less than or equal to 70 years old at the time of obtaining consent (2) Patients with cirrhosis caused by hepatitis B virus, hepatitis C virus, or MAFLD (3) Patients with cirrhosis and Child-Pugh score 7 to 9 (4) Patients with an ECOG Performance Status of 2 or less (5) Patients who have been fully informed about their participation in this study and who have given written consent of their own free will based on sufficient understanding. |
||
| (1) 悪性新生物を合併する患者、又は5年以内に悪性腫瘍の既往のある患者 (2) 肝細胞癌の既往のある患者 (3) 静脈血栓症又は肺塞栓の既往のある患者 (4) 過去1年以内の上部消化管内視鏡検査において出血リスクのある食道静脈瘤もしくは胃静脈瘤を有する患者 (5) 高度な心疾患、腎疾患、呼吸器疾患等の合併症を有する患者 (6) 血清クレアチニン値が2mg/dL以上、又はT-Bilが5.0 mg/dL以上の患者 (7) 高乳酸血症の患者 (8) 高マグネシウム血症、甲状腺機能低下症の患者 (9) 献血アルブミンの成分に対しショック又は過敏症の既往歴のある患者 (10) ジメチルスルホキシドに対し過敏症の既往歴のある患者 (11) ヒドロキシエチルデンプンに対し過敏症の既往歴のある患者 (12) ゲンタマイシン並びに他のアミノグリコシド系抗生物質及びバシトラシンに対して過敏症の既往歴のある患者 (13) 本人又はその血族がアミノグリコシド系抗生物質による難聴又はその他の難聴のある患者 (14) エピネフリン含有キシロカインに過敏症の既往歴のある患者 (15) セフェム系抗生物質製剤に対し過敏症の既往歴のある患者 (16) パルボウイルスB19、HTLV-1、HIVに感染した患者 (17) 薬物乱用あるいはアルコール依存症の患者 (18) 臓器移植又は細胞治療を受けた患者 (19) 妊娠中又は妊娠可能な女性の場合は、妊娠検査で陽性の患者 (20) その他、研究責任医師が研究対象者として不適当と判断した患者 |
(1) Patients with malignant neoplasms or with a history of malignancy within 5 years (2) Patients with a history of hepatocellular carcinoma (3) Patients with a history of venous thrombosis or pulmonary embolism (4) Patients with esophageal or gastric varices with risk of bleeding observed during upper gastrointestinal endoscopy within the past 1 year (5) Patients with severe cardiac, renal, or respiratory complications. (6) Patients with serum creatinine level of 2 mg/dL or higher or T-Bil of 5.0 mg/dL or higher (7) Patients with hyperlactatemia (8) Patients with hypermagnesemia or hypothyroidism (9) Patients with a history of hypersensitivity to any component of donated albumin (10) Patients with a history of hypersensitivity to dimethyl sulfoxide (11) Patients with a history of hypersensitivity to hydroxyethyl starch (12) Patients with a history of hypersensitivity to gentamicin, other aminoglycoside antibiotics, or bacitracin (13) Patients or blood relatives with hearing loss or other hearing impairment due to aminoglycoside antibiotics (14) Patients with a history of hypersensitivity to xylocaine containing epinephrine (15) Patient with a history of hypersensitivity to cephem antibiotics (16) Patients infected with parvovirus B19, HTLV-1, or HIV (17) Patients with drug abuse or alcoholism (18) Patients underwent organ transplantation or cell therapy (19) Patients who are pregnant or, in the case of women of childbearing potential, have a positive pregnancy test (20) Other patients deemed inappropriate as research subjects by the investigator |
||
| 18歳 以上 | 18age old over | ||
| 70歳 以下 | 70age old under | ||
| 男性・女性 | Both | ||
| (1) 研究対象者より治療の変更・中止の申し出があった場合 (2) 有害事象が認められ、研究継続が好ましくないと判断された場合 (3) 死亡または死亡につながる恐れのある疾病等が発現した場合 (4) 原疾患の増悪の場合 (5) 研究対象者が妊娠していることが判明した場合 (6) 選択基準から逸脱、又は除外基準に抵触することが判明した場合 (7) 研究対象者が来院しなくなった場合 (8) その他、研究責任医師が不適当と判断した場合 |
|||
| 肝硬変 | Liver cirrhosis | ||
| 有 | |||
| 治療用細胞調製のため、手術による皮下脂肪組織の採取、および研究用各種検査の採血を行う。 3×10^7 cells以下に調製した治療用細胞を4週間隔(ただし、被験者に新型コロナウイルスや流行性感冒などによる一過性の体調不良が被験者に発生した場合に、医師の判断により変更の可能性がある)で計2回点滴静注する。 |
Surgical collection of subcutaneous adipose tissue for manufacturing specified cell products and blood sampling for various laboratory tests. A total of 2 intravenous infusions of up to 3 x 10^7 cells of specified cell products at 4-week intervals. However, the schedule may be modified at the discretion of the physician if the subject experiences temporary health issues such as COVID-19 or seasonal influenza. | ||
| 安全性 輸注毒性に伴う有害事象の種類、程度、発現時期、発現頻度、発現率など |
Safety | ||
| 有効性 Child-Pughスコアの変化量および改善率、線維化マーカーの変化、超音波エラストグラフィの変化 |
Efficacy | ||
| 再生医療等の名称(研究課題名) 自己脂肪由来間葉系幹細胞を用いた肝硬変に対する治療の安全性を検討する探索的臨床試験 研究の目的 肝硬変の治療として、自己脂肪由来間葉系幹細胞を用いた新しい治療法の安全性を検討する。 期待する効果 脂肪由来間葉系幹細胞が産生するサイトカイン等のパラクライン効果による線維化の抑制、肝機能改善 使用する細胞等 自己脂肪組織由来間葉系幹細胞 対象疾患 肝硬変患者 再生医療等を受ける者の基準 【選択基準】 以下のすべての項目を満たす者を対象とする。 1)同意取得時において満18歳以上、満70歳以下の男女の患者 2)HBV、HCV又はMAFLDを原因とする肝硬変患者 3)肝硬変症例であって、Child-Pughスコア7~9の患者 4)ECOGのPSが0~2の患者 5)本研究への参加にあたり十分な説明を受けた後、十分な理解の上、本人の自由意思による文書同意が得られた患者 【除外基準】 以下のいずれかの条件に該当する者は対象としない。 1)悪性新生物を合併する患者、又は5年以内に悪性腫瘍の既往のある患者 2)肝細胞癌の既往のある患者 3)静脈血栓症又は肺塞栓の既往のある患者 4)過去1年以内の上部消化管内視鏡検査において出血リスクのある食道静脈瘤または胃静脈瘤を有する患者 5)高度な心疾患、腎疾患、呼吸器疾患等の合併症を有する患者 6)血清クレアチニン値が2 mg/dL以上、又はT-Bilが5.0 mg/dL以上の患者 7)高乳酸血症の患者 8)高マグネシウム血症、甲状腺機能低下症の患者 9)献血アルブミンの成分に対しショック又は過敏症の既往歴のある患者 10)ジメチルスルホキシドに対し過敏症の既往歴のある患者 11)ヒドロキシエチルデンプンに対し過敏症の既往歴のある患者 12)ゲンタマイシン並びに他のアミノグリコシド系抗生物質及びバシトラシンに対し過敏症の既往歴のある患者 13)本人又はその血族がアミノグリコシド系抗生物質による難聴又はその他の難聴のある患者 14)エピネフリン含有キシロカインに過敏症の既往歴のある患者 15)セフェム系抗生物質製剤に対し過敏症の既往歴のある患者 16)パルボウイルスB19、HTLV-1、HIVに感染した患者 17)薬物乱用あるいはアルコール依存症の患者 18)移植又は細胞治療を受けた患者 19)妊娠中又は妊娠可能な女性の場合は、妊娠検査で陽性の患者 20)その他、研究責任医師が研究対象者として不適当と判断した患者 目標症例数 3例 原料となる脂肪組織の採取方法 患者本人より採取した皮下脂肪を用いる。局所麻酔下において、患者下腹部の皮下脂肪組織を外科的処置により採取する。採取した脂肪組織は、抗生剤入りの脂肪組織輸送容器に入れて、輸送業者を通じて細胞培養加工施設に輸送する。 細胞提供者の選定方法 研究対象者本人の脂肪組織及び脂肪組織から取り出した細胞を用いるため、再生医療等を受ける者の基準満たす者を対象とする。 細胞提供者の適格性の確認方法 研究対象者本人の脂肪組織及び脂肪組織から取り出した細胞を用いるため、ドナースクリーニングは行わないが、再生医療等を受ける者の基準満たす者を対象とする。 細胞の提供を受けた後に再検査を行う場合はその方法 研究対象者本人の脂肪組織及び脂肪組織から取り出した細胞を用いるため、脂肪組織の提供を受けた後にドナーのウインドウピリオドを勘案した感染症に係る再検査は行わない。 細胞の提供を受ける際の微生物等による汚染を防ぐための措置 脂肪採取時には皮膚の十分な消毒を行い、消毒部位は手で触れない。また、滅菌された手術器具を用いる。 特定細胞加工物の製造方法 細胞培養加工施設において、約3〜4週間かけて治療用細胞の培養・調製を行う。 (1)細胞の加工の方法 患者脂肪組織から脂肪由来間葉系幹細胞を含む細胞群を取り出し、組織培養用フラスコにて脂肪由来間葉系幹細胞を拡大培養する。培養した脂肪由来間葉系幹細胞は、回収後に培地成分等を除去・洗浄し、細胞保管投与液に懸濁し、凍結する。 (2)特定細胞加工物の保管方法 出荷から細胞投与前までは、-70℃以下で保管する。 (3)品質管理の方法 1)原料の受入検査: 原料の包装状態に異常がないか外観試験を実施する。 2)工程管理試験: 製造工程内の適切な時期に細胞数および生細胞率の測定、無菌試験を実施する。 3)最終特定細胞加工物の品質試験: 細胞数および生細胞率の測定、細胞表現型試験、マイコプラズマ否定試験、エンドトキシン試験、無菌試験を実施する。 特定細胞加工物の輸送方法 -70℃以下の条件で、輸送業者を通じて実施医療機関に輸送する。 特定細胞加工物の投与方法 治療用細胞懸濁液を急速解凍し、ラクトリンゲル液で希釈し、開口径が210μm以下のフィルターを通しながら30 分以上かけて静脈内へ投与する。 投与スケジュール 4週間間隔、全2回 評価項目 主要評価項目:安全性 副次評価項目:有効性 再生医療等の内容をできる限り平易な表現を用いて記載したもの 別添の通り |
|||
2 人員及び構造設備その他の施設等
2 人員及び構造設備その他の施設等
(1)人員及び構造設備その他の施設に関する事項
(1)人員及び構造設備その他の施設に関する事項
| 医師 | |||||
| 大西 俊介 | Ohnishi Shunsuke | ||||
| 10443475 | |||||
| 医療法人新産健会 LSI札幌クリニック | LSI Sapporo clinic | ||||
| 免疫診療部 | |||||
| 065-0013 | |||||
| 北海道札幌市東区北13条東1丁目2-50 | 1-2-50 Kita 13 Jo higashi, Higashi-ku, Sapporo, Hokkaido | ||||
| 011-731-6669 | |||||
| sonishi@pop.med.hokudai.ac.jp | |||||
| 他の医療機関 | |||||
| 医療機関の名称:北海道大学病院 病床数:総病床数 902床、うちICU 8床、HCU 5床 設備の内容:CT、MRI、血液ガス分析機、X線撮影、透視検査装置、超音波検査装置(心臓、腹部)等の当該研究で必要な救急体制が整備されている。 なお、当院では心電図モニタ(生体情報モニタ)、AED、救急カート、医療用酸素を設置し、病院へ搬送するまでの間の応急処置を行う。 | |||||
(2)その他研究の実施体制に関する事項
(2)その他研究の実施体制に関する事項
| 瀧本 理修 | Takimoto Rishu | ||||
| 医療法人新産健会 LSI札幌クリニック | LSI Sapporo clinic | ||||
| 免疫診療部 | |||||
| 065-0013 | |||||
| 北海道札幌市東区北13条東1丁目2-50 | 1-2-50 Kita 13 Jo higashi, Higashi-ku, Sapporo, Hokkaido | ||||
| 011-731-6669 | |||||
| 011-711-1337 | |||||
| takimoto@lsi-sapporo.jp | |||||
| 医師 | ||
| 大西 俊介 | ||
| 10443475 | ||
| 医療法人新産健会 LSI札幌クリニック | ||
| 免疫診療部 |
| 医師 | ||
| 清野 研一郎 | ||
| 医療法人新産健会 LSI札幌クリニック | ||
| 免疫診療部 |
| 医師 | ||
| 瀧本 理修 | ||
| 10336399 | ||
| 医療法人新産健会 LSI札幌クリニック | ||
| 免疫診療部 |
| 瀧本 理修 | ||
| 10336399 | ||
| 医療法人新産健会 LSI札幌クリニック | ||
| 免疫診療部 | ||
| 島野 千佳子 | ||
| 医療法人新産健会 LSI札幌クリニック | ||
| 大西 俊介 | ||
| 10443475 | ||
| 医療法人新産健会 LSI札幌クリニック | ||
| 免疫診療部 | ||
| 瀧本 理修 | ||
| 10336399 | ||
| 医療法人新産健会 LSI札幌クリニック | ||
| 免疫診療部 | ||
| 瀧本 理修 | Takimoto Rishu | ||
| 10336399 | |||
| 医療法人新産健会 LSI札幌クリニック | LSI Sapporo clinic | ||
| 免疫診療部 | |||
| 非該当 | |||
(3)多施設共同研究に関する事項
(3)多施設共同研究に関する事項
| 無 |
3 再生医療等に用いる細胞の入手の方法並びに特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法等
3 再生医療等に用いる細胞の入手の方法並びに特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法等
(1)再生医療等に用いる細胞の入手の方法(特定細胞加工物を用いる場合のみ記載)
(1)再生医療等に用いる細胞の入手の方法(特定細胞加工物を用いる場合のみ記載)
| ヒト脂肪由来間葉系幹細胞 | |
| 医療法人新産健会 LSI札幌クリニック | |
| 再生医療等を受ける者の自己細胞を用いるため、細胞提供者と再生医療等を受ける者は同一。 再生医療を行う医師が【再生医療等を受ける者の適格基準】に照らし合わせて、当該再生医療を希望する者の背景、治療歴、健康状態等を確認し、細胞提供者(治療対象者)の選定を行う。 |
|
| 再生医療等を受ける者の自己細胞を用いるため、細胞提供者と再生医療等を受ける者は同一。 再生医療等を行う医師が診察時に既往歴等の確認を行い、当該再生医療を実施するために必要な検査を実施する。 |
|
| 実施医療機関の処置室において、再生医療等を行う医師が、患者下腹部の皮下脂肪組織より局所麻酔下において、約2 cmの小切開を加えて、脂肪組織約3〜5gを切除により採取する。採取した脂肪組織は、抗生剤入りの脂肪組織輸送容器に入れて、細胞培養加工施設に輸送する。保管、輸送は2~8℃で行い、採取日から起算して2日以内に細胞加工を開始する。 |
(2)特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法(特定細胞加工物等を用いる場合のみ記載)
(2)特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法(特定細胞加工物等を用いる場合のみ記載)
| 自己脂肪由来間葉系幹細胞 | ||
| 1)採取した細胞の加工の方法の概要 患者から得た脂肪組織を洗浄、細断する。細断した脂肪からコラゲナーゼを用いてSVFを抽出し、全量を組織培養用フラスコに播種する。播種した細胞を37 ℃、CO2 5%で静置培養する。付着性の細胞が培養容器に付着した後、培地を交換する。 細胞がセミコンフルエント~コンフルエントになったタイミングで剥離し、拡大培養するための培養容器に移し替え、37 ℃、CO2 5%で静置培養する。必要に応じ、培地交換する。継代は複数回繰り返す。 必要な細胞が得られる状態となったら、細胞を回収し、培地成分試薬、デブリ、ECMを除去・洗浄する。回収・洗浄した細胞を細胞保管投与液に懸濁し、凍結保存用チューブに分け凍結保管する。 2)特定細胞加工物等の保管方法の概要 凍結した細胞は、細胞培養加工施設において、-70℃以下で保管する。 3)品質管理の方法の概要 (1)原料の受入検査 外観試験により、原料の包装状態に異常がないか、原料が患者由来のものであるかを確認する。また、細胞加工に必要な情報が提供されているかを確認する。 (2)工程管理試験 原料に対する無菌試験を実施する。 回収したSVF、継代時の細胞数および生細胞率を測定する。 (3)最終特定細胞加工物の試験 細胞数および生細胞率:トリパンブルーで染色し、血球計算盤により計測する。 細胞表現型試験:フローサイトメトリー法により実施する。 マイコプラズマ否定試験:核酸増幅法により実施する。 エンドトキシン試験:比濁法により実施する。 無菌試験:平板法により実施する。 |
||
| 細胞培養加工施設から輸送された細胞懸濁液を200mLのラクトリンゲル液で希釈し、フィルターを通しながら30分以上かけて腕の静脈内へ投与する。 詳細は別添の通り。 | ||
| 有 | ||
| 株式会社メディネット | ||
| FA3150001 | ||
| 株式会社メディネット 品川細胞培養加工施設 | ||
| 1) 原料の受領・検査・保管並びにそれに係る文書及び記録等の保管 2) 脂肪組織輸送容器の製造、特定細胞加工物の製造・検査・保管並びにそれに係る文書及び記録等の保管 3) 再生医療等を受ける者が感染症を発症した場合等の原因究明のための原料及び特定細胞加工物の試料の保管 4) 原料及び特定細胞加工物の輸送及び管理 5) 特定細胞加工物を製造するにあたり、必要な材料、試薬、消耗品等の購入・保管及びその管理 |
||
(3)再生医療等製品等に関する事項(再生医療等製品を用いる場合のみ記載)
(3)再生医療等製品等に関する事項(再生医療等製品を用いる場合のみ記載)
(4)再生医療等に用いる未承認又は適応外の医薬品又は医療機器に関する事項(未承認又は適応外の医薬品又は医療機器を用いる場合のみ記載)
(4)再生医療等に用いる未承認又は適応外の医薬品又は医療機器に関する事項(未承認又は適応外の医薬品又は医療機器を用いる場合のみ記載)
4 再生医療等技術の安全性の確保等に関す措置
4 再生医療等技術の安全性の確保等に関す措置
(1)利益相反管理に関する事項
(1)利益相反管理に関する事項
① 再生医療等に対する特定細胞加工物等製造事業者からの研究資金等の提供その他の関与
① 再生医療等に対する特定細胞加工物等製造事業者からの研究資金等の提供その他の関与
| 株式会社メディネット | ||
| 有 | ||
| 株式会社メディネット | MEDINET Co., Ltd. | |
| 非該当 | ||
| 有 | ||
| 2025年03月27日 | ||
| 有 | ||
| 特定細胞加工物等 | ||
| 有 | ||
| ・再生医療等提供計画にかかわる文書作成支援 ・認定再生医療等委員会への申請支援 |
||
② 再生医療等に対する医療薬品等製造販売業者等からの研究資金等の提供その他の関与
② 再生医療等に対する医療薬品等製造販売業者等からの研究資金等の提供その他の関与
| 無 | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
③ 再生医療等に対する特定細胞加工物等製造事業者又は医療品等製造販売業者等以外からの研究資金
③ 再生医療等に対する特定細胞加工物等製造事業者又は医療品等製造販売業者等以外からの研究資金
| 無 | ||
(2)その他再生医療等技術の安全性の確保等に関する措置
(2)その他再生医療等技術の安全性の確保等に関する措置
| 本研究で投与する脂肪由来間葉系幹細胞は患者の自己細胞である。細胞加工工程において、動物に由来する原料等を使用しないことから、動物由来感染症およびアレルギー反応のリスクは極めて低いと考えられる。また、培養および細胞加工物にはヒト血液に由来する原料等を使用するが、いずれも医薬品もしくは再生医療等製品材料適格性確認書を有する原料等である。 本研究で用いる治療用細胞の急性毒性を評価するため、NOGマウスを用いた反復投与毒性試験を実施した。hASCを0(対照)、2.5 × 10^6、7.5 × 10^6、1.3 × 10^7及び2.0 × 10^7 cells/kgの用量で、静脈内に4週間間隔で2回投与し、投与直後~投与後約1時間に一般状態の観察を行い、急性毒性を評価した。 hASCを1.3 × 10^7及び2.0 × 10^7 cells/kgで投与した群において、肺塞栓様症状を示した例を認め、一部は投与後3分以内に死亡した。 以上のことから、今回の試験条件下において、hASCの無毒性用量を7.5 × 10^6 cells/kgと判断した(詳細は添付資料【再生医療等に用いる細胞に関連する研究を記載した書類】に記載)。本研究における投与細胞数は、さらに安全性を考慮し、無毒性用量の1/10とした。また、被験者の体重により、1投与あたりの細胞数が7.5 × 10^5 cells/kgを超えることがないよう、体重40 kgのヒトへ投与する場合を仮定して、1投与あたり3 × 10^7 cells以下とした。 肝硬変治療に対し、ヒト脂肪由来間葉系幹細胞を肝内投与した研究が報告されている(Huang KC, Cell Transplant. 2019 28(1 Suppl): 100S)。この中で胃腸障害、感染症、皮膚及び皮下組織障害等の重篤な有害事象が発生したが、いずれもヒト脂肪由来間葉系幹細胞の投与との関連は認められなかった。ヒト脂肪由来間葉系幹細胞を静脈投与した例は、自己免疫疾患で報告されている(Ra JC, J Transl Med. 2011 21;9:181、Álvaro-Gracia JM, Ann Rheum Dis. 2017 76(1):196)。この中でグレード3の有害事象として、脳梗塞(ラクナ梗塞)が報告されている。ただし、細胞投与後8日目に発生しており、病態生理は不明であると共に、用量依存的ではなかった。また、静脈血栓症や肺塞栓症の兆候は認めなかった。その他、糖尿病や脊髄損傷など少数例の報告があり、いずれも重篤な有害事象は確認されていない(Le PTB, Biomed Res Ther. 2016 3(12):1034、Ra JC, Stem Cells Dev. 2011 20(8):1297)。 以上、実験結果や科学的文献その他の関連する情報により、当該細胞加工物の安全性についてその時点での科学的水準に基づき可能な範囲で検討した結果、十分な安全性があると考えられた。 |
||||||
| 肝硬変治療に対する、間葉系幹細胞を用いた研究の報告例として、骨髄由来間葉系幹細胞または臍帯由来間葉系幹細胞を静脈内投与した研究が報告されている(Mohamadnejad M, Arch Iran Med 2007;10:459、Zhang Z, J Gastroenterol Hepatol 2012;27 Suppl 2:112、Kantarcıoğlu M, Turk J Gastroenterol 2015;26:244、Shi M, Stem Cells Transl Med, 2012;1:725)。当該研究における投与細胞数は1~6×10^7 cellsに設定されており、一部肝機能(MELDスコアや血液生化学的スコア)の改善がみられている。 脂肪由来間葉系幹細胞は骨髄由来間葉系幹細胞に比較して原料の採取が容易であり、患者の負担も少ないことから、肝硬変に対する新しい治療法となり得る。 以上、実験結果や科学的文献その他の関連する情報により、当該細胞加工物を用いる妥当性について検討した結果、当該再生医療等の提供により予測される利益は不利益を十分上回るものと考えられた。 |
||||||
| 再生医療等を行う医師は、毎投与時に品質検査結果等が記載された報告書を確認し、また再生医療等を受ける者の容態を慎重に確認した上で投与可否を判断し、投与可と判断した場合のみ投与を実施する。 | ||||||
| 本研究に起因した感染症が発生した場合等、細胞の安全性に関する疑義が生じた場合は、保管試料を用いてその原因究明にあたる。 | ||||||
| 治療終了より5年間 | ||||||
| 本再生医療等で得た試料は原則として、不活性化処理を行った上で適切な方法で破棄する。 | ||||||
| (1)有害事象発生時の研究対象者への対応 研究責任医師または研究分担医師は、有害事象を認めたときは、救急医療に必要な設備をもつ医療機関と連携して直ちに適切な処置・治療を行う。当該有害事象名、発現日・転帰日、重篤度、重症度(軽度、中等度、高度)、転帰、本研究との因果関係(関連あり、関連なし)及び経過などを記録する。また、特定細胞加工物の投与を中止した場合や、有害事象に対する治療が必要となった場合には、研究対象者にその旨を伝える。 (2)重篤な疾病等発生時の対応 研究分担医師は、重篤な疾病等を知った場合は、速やかに研究責任医師に報告する。研究責任医師は、速やかにその旨を実施医療機関の管理者に報告し、患者の状態を把握し、必要に応じて救急医療に必要な設備をもつ医療機関に患者を搬送する。また、速やかに当該研究の実施に携わる研究分担医師等に対して、当該有害事象の発生に係る情報を共有する。 管理者は「再生医療等安全性確保法」に準じ、特定認定再生医療等委員会及び厚生労働大臣へ、法律等に従い期限内に適切に報告を行う。 (3)非重篤な疾病等発生時の報告 研究分担医師は、再生医療等の提供に起因するものと疑われる非重篤な疾病等が発生した場合には、研究責任医師に報告する。研究責任医師は実施医療機関の管理者に報告し、管理者は「再生医療等安全性確保法」に準じ、適切に特定認定再生医療等委員会へ報告する。 |
||||||
| 再生医療等を受けた患者の疾病等の安全性や効果についての検証をするため、定期的に診察し、経過観察を行う。具体的な定期検査やフォローアップを行う期間や方法等は以下のとおりである。 (1)定期検査やフォローアップを行う時期 ・投与当日および翌日 ・投与2週間後 ・2回目投与4週間後 (2)安全性の評価項目 ・SpO2モニタ、心電図モニタ、及び血栓症マーカーであるFDP、Dダイマーの上昇、呼吸機能の低下の有無、がん化の評価 (3)科学的妥当性の評価項目 ・Child-Pughスコア変化量、Child-Pughスコア改善率、線維化マーカーの変化、超音波エラストグラフィの変化、炎症性マーカー |
||||||
| 患者の健康状態等を把握するため、後観察終了後も健在確認等は、1年間を目処に可能な限り追跡調査等を実施する。 | ||||||
| 無 | ||||||
| 実施計画の公表日 | ||||||
| 募集中 | Recruiting | |||||
5 細胞提供者及び再生医療等を受ける者に対する健康被害の補償の方法
5 細胞提供者及び再生医療等を受ける者に対する健康被害の補償の方法
細胞提供者について(特定細胞加工物を用いる場合のみ記載)
細胞提供者について(特定細胞加工物を用いる場合のみ記載)
| 有 |
再生医療等を受ける者について
再生医療等を受ける者について
| 有 |
6 審査等業務を行う認定再生医療等委員会に関する事項
6 審査等業務を行う認定再生医療等委員会に関する事項
| CONCIDE特定認定再生医療等委員会 | CONCIDE Specified Certified Regenerative Medicine Committee | |
| NA8160002 | ||
| 東京都千代田区二番町11番地3相互二番町ビルディング別館7階 | Sougo Nibancho Bld. Annex 7F, 11-3, Nibancho, Chiyoda Ku, Tokyo | |
| 03-5772-7584 | ||
| concide_jimukyoku@concide.or.jp | ||
| 第一種再生医療等又は第二種再生医療等を審査することができる構成 | ||
| 適 | ||
| 2025年04月01日 | ||
7 その他
7 その他
| 本研究に従事する者は、研究対象者の個人情報等の保護について適用される「個人情報の保護に関する法律」および関連通知を遵守する。本研究の実施により得られた研究対象者に関する情報は、研究に従事する者が登録時に新たに付与する固有の番号(研究対象者識別コード)によって識別することとし、その際特定の個人の識別に繋がる情報を用いない。 研究責任医師は、研究対象者の氏名と研究対象者識別コードの対応表を作成し、実施医療機関内の施錠可能な場所で適切に保管する。 |
||
| 無 | No | |
| 研究責任医師はこれまでも臨床研究および治験の実施経験があり、研究倫理に関する教育研修および日本再生医療学会認定再生医療等委員会教育研修を修了している。 本臨床研究の研究責任医師および分担医師、その他の研究実施にかかわる関係者は、研究開始前にICR臨床研究入門「臨床研究の基礎知識講座」の中から研究責任医師が指定する講座の受講を修了する。 管理者または研究責任医師は、再生医療等を適切に実施するため、本研究の担当医師及び本研究に従事する者に対して、日本再生医療学会や関連学会、セミナー等への参加など教育又は研修の機会を確保する。 また、研究責任医師は本研究を適切に実施するため、研究開始前に本研究の担当医師及び本研究に従事する者に対し、それぞれの業務に応じて本研究に関する十分な教育の機会を確保する。 |
||
| (1) 対応窓口 電話番号:011-731-6669 受付時間:月~金 9:00~16:00 (2)対応手順 対応窓口の担当者が本人や家族からの苦情や問い合わせを受け付け、一次対応を行う。苦情、問い合わせの内容により担当者が対応困難である場合は、研究責任医師または研究分担医師が対応する。 |
||
| 非該当 | ||
| なし | none | |
| 無 | ||
| 非該当 | ||
| 非該当 | ||
| 非該当 | ||
添付資料
添付資料
| 4 再生医療等を受ける者に対する説明文書及び同意文書の様式 | 05_説明文書及び同意文書の様式_v1.4【マスキングあり】.pdf |
|---|