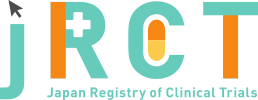臨床研究等提出・公開システム
再生医療等提供計画情報の詳細情報です。
| 第一種 | ||
| 令和2年3月5日 | ||
| 令和4年3月31日 | ||
| 令和3年7月8日 | ||
| 令和3年7月8日 | ||
| 重症低血糖発作を伴うインスリン依存性糖尿病に対する脳死ドナーまたは心停止ドナーからの膵島移植 | ||
| インスリン依存性糖尿病に対する膵島移植 | ||
| 長崎大学病院 | ||
| 病院長 中尾 一彦 | ||
| 本医療の目的は、日本組織移植学会が定めるガイドラインに則り、脳死または心停止後に提供された膵臓から分離された膵島組織をインスリン依存状態糖尿病患者に移植する膵島移植療法によって、インスリン依存性からの離脱あるいは血糖コントロールの改善、重症低血糖発作の予防を図るものである。これまで日本における膵島移植は心停止後に提供された膵臓を使用し施行されてきたが、臨床効果は低いものであった。しかし、2013年より脳死ドナーからの膵島移植が可能となった。また近年、免疫抑制剤の発達により一部の海外施設からは良好な成績の報告がされている。本研究では脳死・心停止ドナーからの膵島移植成績及び安全性の評価を行う。 | ||
| 2 | ||
| 重症低血糖発作を伴うインスリン依存性糖尿病 | ||
| 研究終了 | ||
| 抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン、バシリキシマブ、エタネルセプト、タクロリムス、タクロリムス水和物徐放性カプセル、シクロスポリン、ミコフェノール酸モフェチル | ||
| サイモグロブリン、シムレクト、エンブレル、プログラフ、グラセプター、ネオーラル、セルセプト | ||
| 京都大学特定認定再生医療等委員会 | ||
| NA8150004 | ||
総括報告書の概要
総括報告書の概要
臨床研究の名称等
臨床研究の名称等
| 第一種 | |||
| 令和4年1月20日 | |||
| jRCTa071190048 | |||
| 提供しようとする再生医療等の名称 | 重症低血糖発作を伴うインスリン依存性糖尿病に対する脳死ドナーまたは心停止ドナーからの膵島移植 | ||
| 認定再生医療等委員会の名称(認定番号) | 京都大学特定認定再生医療等委員会 (NA8150004) | ||
| 2021年07月08日 | |||
| 0 | |||
| / | なし | none | |
| / | なし | none | |
| / | なし | none | |
| / | なし | none | |
| / | なし | none | |
| 2022年03月31日 | |||
| none | |||
IPDシェアリング
IPDシェアリング
| / | 無 | No | |
|---|---|---|---|
| / | なし | none | |
1 提供しようとする再生医療等及びその内容
1 提供しようとする再生医療等及びその内容
申請者情報
申請者情報
| 令和4年1月20日 | |||
| jRCTa071190048 | |||
| 長崎大学病院 | |||
| 長崎県長崎市坂本1-7-1 | |||
| 病院長 中尾 一彦 | Kazuhiko Nakao | ||
(1)再生医療等の名称及び分類
(1)再生医療等の名称及び分類
| 重症低血糖発作を伴うインスリン依存性糖尿病に対する脳死ドナーまたは心停止ドナーからの膵島移植 | Islet transplantation using brain-dead donors and donors after cardiac death for patients with insulin-dependent diabetes mellitus suffering from complicating hypoglycemia unawareness( Islet transplantation for insulin-dependent diabetes mellitus ) | ||
| インスリン依存性糖尿病に対する膵島移植 | Islet transplantation using brain-dead donors and donors after cardiac death for patients with insulin-dependent diabetes mellitus suffering from complicating hypoglycemia unawareness( Islet transplantation for insulin-dependent diabetes mellitus ) | ||
| 第一種 | |||
| 投与を受ける者以外の人に由来する細胞加工物を用いた再生医療等技術の範囲であると判断されるため | |||
(2)再生医療等の内容
(2)再生医療等の内容
| 本医療の目的は、日本組織移植学会が定めるガイドラインに則り、脳死または心停止後に提供された膵臓から分離された膵島組織をインスリン依存状態糖尿病患者に移植する膵島移植療法によって、インスリン依存性からの離脱あるいは血糖コントロールの改善、重症低血糖発作の予防を図るものである。これまで日本における膵島移植は心停止後に提供された膵臓を使用し施行されてきたが、臨床効果は低いものであった。しかし、2013年より脳死ドナーからの膵島移植が可能となった。また近年、免疫抑制剤の発達により一部の海外施設からは良好な成績の報告がされている。本研究では脳死・心停止ドナーからの膵島移植成績及び安全性の評価を行う。 | |||
| 2 | |||
| 2016年02月23日 | |||
| 2024年02月22日 | |||
| 10 | |||
| 介入研究 | Interventional | ||
| 単一群 | single arm study | ||
| 非盲検 | open(masking not used) | ||
| 非対照 | uncontrolled control | ||
| 単群比較 | single assignment | ||
| 治療 | treatment purpose | ||
| ①病状:重症低血糖発作を伴うインスリン依存性糖尿病 ②年齢:20歳から65歳まで ③適格基準 1.本人より臨床試験参加に対して文書による同意を得ることができる。 2.当臨床試験でのプロトコールの手順に従うことができる。 3.臨床試験参加時にインスリン依存状態の期間が5年を越えて持続していること。 4.内因性インスリン分泌が枯渇している。 5.糖尿病に対するインスリン強化療法を行っていること。 6.過去12ヶ月間に重症低血糖発作が1回以上発症していること。 7.Clark Score, HYPO Score, Lability Indexについてのデータを持っている。 なお、腎移植後膵島移植の場合には、以下の選択基準を加える。 IAK-1.腎移植後6ヶ月以上経過している。 IAK-2.クレアチニン1.8mg/dl以下で、直近6ヶ月の血清クレアチニンの上昇が0.2mg/dl以下で持続的上昇を認めない。 IAK-3.ステロイド内服量が10mg/day以下。 |
1. Male or female; 20 to 65 years of age. 2. Ability to provide written informed consent. 3. Mentally stable and able to comply with the procedures of the study protocol. 4. Clinical history compatible with type 1 diabetes with insulin dependence for > 5 years at the time of the registration. 5. Absent stimulated C-peptide (< 0.3ng/mL). 6. Involvement in intensive diabetes management defined as the self monitoring of glucose values no less than a mean of three times each day, averaged over each week, and the administration of three or more insulin injections each day or insulin pump therapy. Such management must have been subjected to at least 3 clinical evaluations during the previous 12 months. 7. At least one episode of severe hypoglycemia in the past 12 months defined as an event with symptoms compatible with hypoglycemia in which the subject required the assistance of another person and which was associated with either a blood glucose level < 54 mg/dL (3.0 mmol/L) or prompt recovery after oral carbohydrate, intravenous glucose, or glucagon administration. 8. At least once evaluated glycemic lability status by a Clarke score, a HYPO score and a glycemic lability index (LI) score. |
||
| 以下の条件のどれかに相当した場合、本医療への適応は不適格とする。 1. 体重が80kgを超えている。もしくは、BMIが25kg/m2 を超えている。 2. インスリン必要量が0.8IU/kg/日以上、あるいは 55U/日以上。 3. 過去1年間に複数回測定したHbA1c値(NGSP値)の平均値が10.4%以上。 4. 未治療の増殖性糖尿病網膜症を有している。 5. 血圧:収縮期血圧が160mmHgあるいは拡張期血圧が100mmHg超えている。 6. eGFR 60ml/min/1.73m^2以下(膵島単独移植の場合に限定する)。 7. 現在、尿蛋白が1g/日以上。 8. フローサイトメトリーによるPRA (panel reactive antibody) が20%以上。 9. 妊娠反応陽性例/現在授乳中(いずれも女性)、あるいは本医療後2年間の間に効果的な避妊方法の実施を了承しない。 10. 以下の活動性感染症がある。 B型肝炎、C型肝炎、HIV感染症、HTLV-I感染症あるいは結核を含む抗酸菌症。具体的にはキャリアを含むHBs抗原あるいはHBV-DNAの陽性者、HCV-RNA陽性者注)、HIV抗体陽性者、HTLV-I抗体陽性者。結核を含む抗酸菌症に関しては、クオンティフェロン検査またはT-Spot検査が陽性の場合、あるいは胸部CTにて潜在性結核感染症(Latent tuberculosis infection: LTBI)や非定型抗酸菌症が疑われる場合、抗酸菌症を疑って薬物治療が行われている場合をもって活動性感染症とみなす。ツベルクリン反応は特に参考としない。 注)血漿HCV-RNAの測定は通常HCV抗体陽性者に対して実施される。ステロイドの長期内服時など、抗体産生が抑制されることが予想される場合には、HCV抗体の結果にかかわらず、血漿HCV-RNAを測定する。 11. Epstein-Barr Virus(EBV)に対するIgG抗体陰性。 12. 臨床試験参加前1年間に浸潤性アスペルギルス感染症に罹患したことがある。 13. 癌の既往をもつ。ただし、完全に切除された皮膚の扁平上皮癌あるいは基底細胞癌は除外する。 14. アルコール依存症あるいは薬物依存症を有している。 15. 検査施設での正常下限を下回るヘモグロビン値;リンパ球減少症(<700/μL)、好中球減少症(<1,500/μL)、あるいは血小板減少症(血小板<100,000/μL) (ただし膵島単独移植の場合に限定する)。 16. 第 V 因子欠損の既往がある。 17. 凝固障害があるもの、もしくは移植した後も長期にわたって抗凝固剤(ワーファリンなど)の投与が必要となる医学上の状態を有するもの(低容量のアスピリン治療の場合には許容できる)、またはプロトロンビン時間のINR(International Normalized Ratio)値が1.5を超えているもの。 18. 重度の併存する心疾患を有する場合。以下のいずれかの状態: ①最近(過去6ヶ月以内に)発症した心筋梗塞。 ②過去1年以内に心機能検査において診断された虚血障害。 ③左心室のejection fractionが30%未満。 19. 肝機能検査値が持続的に高値を示すもの。肝機能検査異常とは、SGOT(AST)、SGPT(ALT)、ALPあるいは総ビリルビン値が、正常値上限の1.5倍以上の高値が持続していること。 20. 症候性胆石症を有する。 21. 急性または慢性膵炎を有する。 22. 症候性消化性潰瘍を有する。 23. 重度の頻回な下痢、嘔吐あるいは潜在的に経口薬剤の吸収を障害する可能性のある胃腸障害を有する。 24. 医学的治療に抵抗性の高脂血症(空腹時 LDL コレステロールが 治療されてもされていなくても130mg/dLを超えている場合、かつ、もしくは空腹時の中性脂肪が200mg/dLを超えている場合)を有するもの。 25. 慢性的なステロイド薬の全身投与を必要とする医学的状態に対する治療を受けている。 26. 臨床試験参加の4週間以内に何らかの臨床試験中の薬剤の投与を受けたもの。 27. 臨床試験参加の2ヶ月以内に弱毒生ワクチンの接種を受けている。 28. 必要な検査のための入院、定期的な外来通院が不可能である。 29. 本医療およびその管理期間に問題となる精神的異常を有している。 30. その他、担当医によって受療が不適切と判断されたもの。 |
1. BMI > 25 kg/m2 or weight > 80 kg. 2. Insulin requirement of > 0.8 IU/kg/day or 55 U/day. 3. Mean HbA1c value of several measurements in the previous 12 months >10 %. 4. Untreated proliferative diabetic retinopathy. 5. Blood pressure: SBP > 160 mmHg or DBP > 100 mmHg. 6. Creatinine clearance < 60 mL/min (applied only to islet transplantation alone case). 7. Presence of proteinuria > 1g/day. 8. For female participants: Positive pregnancy test, presently breast-feeding, or unwillingness to use effective contraceptive measures for the duration of the study and 3 months after discontinuation. For male participants: Intent to procreate during the duration of the study or within 3 months after discontinuation or unwillingness to use effective measures of contraception. Oral contraceptives, Norplant, Depo-Provera, and barrier devices with spermicide are acceptable contraceptive methods; condoms used alone are not acceptable. 9. Active infection including hepatitis B, hepatitis C, HIV, or TB as determined by a positive skin test or clinical presentation, or under treatment for suspected TB. Positive tests are acceptable only if associated with a history of previous vaccination in the absence of any sign of active infection. Positive tests are otherwise not acceptable, even in the absence of any active infection at the time of evaluation. 10. Negative screen for Epstein-Barr Virus (EBV) by IgG determination. 11. Difficulty of administration for laboratory and physical tests for evaluation or regular outpatient visits. 12. Mental abnormalities to hinder medical procedure under protocol (Assessment by psychiatrists is required and final decision is made by investigators in charge). 13. Any medical condition that, in the opinion of the investigator, will interfere with the safe completion of the trial. |
||
| 20歳 以上 | 20age old over | ||
| 65歳 以下 | 65age old under | ||
| 男性・女性 | Both | ||
| 1.被験者が同意を撤回した場合 2.登録後に不適格症例であることが判明した場合 3.3回目の移植後、血中C-ペプチド値が連続した2回で0.1ng/ml未満、及びグルカゴン負荷試験での反応がないことを確認した場合(2回目の血中C-ペプチド測定は、1回目測定の約1ヶ月を目処に実施) 4.併用禁止療法で規定されている治療を行った場合 ・当臨床試験に使用している以外の免疫抑制剤の使用 ・全身作用を有するステロイド剤の長期間投与 (過去1ヶ月間におけるステロイドの全身投与量が、プレドニン換算量で0.3mg/kg日以上) 5.医師が中止と判断した場合 |
|||
| 重症低血糖発作を伴うインスリン依存性糖尿病 | Insulin-dependent diabetes mellitus suffering from complicating hypoglycemia unawareness | ||
| インスリン依存性糖尿病 | Insulin-dependent diabetes mellitus | ||
| 有 | |||
| 免疫抑制剤 詳細については別添の研究計画書の通り |
Immunosuppressant | ||
| 初回移植から1年後(365日±14日後)にHbA1c値(NGSP値)<7.4%であり、かつ初回移植後90日から移植後365日にかけて重症低血糖発作が消失した患者の割合。 重症低血糖発作の定義は適切な血糖管理下において、以下のいずれかの項目を満たすものとする:1)自分以外の人(他人)による介助を必要とし、かつその際の血糖が60mg/dL以下である、2)自分以外の人(他人)による介助を必要とし、かつ炭水化物の経口摂取、ブドウ糖の血管内投与、グルカゴン投与によって速やかに回復が認められた。 |
The proportion of subjects with HbA1c < 7.4% and who are free of severe hypoglycemic events (from day 90 to day 365) one years after the first islet cell infusion. | ||
| 1.初回移植から2年後(730±28日後)にHbA1c値(NGSP値)<7.4%でありかつ重症低血糖発作が消失する(初回移植後90±5日から移植後730±28日にかけて)患者の割合。 2.重症低血糖発作が消失する(初回移植後90±5日から移植後730±28日にかけて)患者の割合。 3.初回移植から2年後(730±28日後)にHbA1c値(NGSP値)<7.4%となる患者の割合。 4.初回移植から2年後(730±28日後)にHbA1c値(NGSP値)≦6.9%となる患者の割合。 5.初回移植から2年後(730±28日後)までにインスリン離脱となった患者の割合。 |
1. Proportion of patients with HbA1c (NGSP) < 7.4% and severe hypoglycemic unawareness disappears 2 years after the first transplantation. 2. Proportion of patients with severe hypoglycemic attack unawareness. 3. Proportion of patients with HbA1c value (NGSP) < 7.4% two years after the first transplantation. 4. Proportion of patients with HbA1c value (NGSP) < 6.9% two years after the first transplantation. 5. Percentage of patients with insulin withdrawal by 2 years after the first transplantation. |
||
| 別添のとおり | |||
2 人員及び構造設備その他の施設等
2 人員及び構造設備その他の施設等
(1)人員及び構造設備その他の施設に関する事項
(1)人員及び構造設備その他の施設に関する事項
| 医師 | |||||
| 江口 晋 | Eguchi Susumu | ||||
| 長崎大学病院 | Nagasaki Univercity Hospital | ||||
| 移植・消化器外科 | |||||
| 852-8501 | |||||
| 長崎県長崎市坂本1-7-1 | 1-7-1 Sakamoto, Nagasaki, Nagasaki, Japan | ||||
| 095-819-7316 | |||||
| sueguchi@nagasaki-u.ac.jp | |||||
| 自施設 | |||||
| 救急医療に必要な施設:ICU/CCU/NICU/救急部等 設備内容:X線装置、ヘリカルCT、心電図、輸血・輸液のための設備等 救急のために優先的に使用される病床数:19床 | |||||
(2)その他研究の実施体制に関する事項
(2)その他研究の実施体制に関する事項
| 足立 智彦 | Tomohiko Adachi | ||||
| 長崎大学病院 | Nagasaki University Hospital | ||||
| 移植・消化器外科 | |||||
| 852-8501 | |||||
| 長崎県長崎市坂本1-7-1 | 1-7-1 Sakamoto, Nagasaki, Nagasaki, Japan | ||||
| 095-819-7316 | |||||
| 095-819-7319 | |||||
| adatomo@nagasaki-u.ac.jp | |||||
| 医師 | ||
| 大野 慎一郎 | ||
| 長崎大学病院 | ||
| 移植・消化器外科 |
| 医師 | ||
| 長井 一浩 | ||
| 長崎大学病院 | ||
| 細胞療法部 |
| 医師 | ||
| 阿比留 教生 | ||
| 長崎大学病院 | ||
| 第一内科 |
| 医師 | ||
| 足立 智彦 | ||
| 長崎大学病院 | ||
| 移植・消化器外科 |
| 長崎大学病院 臨床研究センター | ||
| 山本 弘史 | ||
| 長崎大学病院 | ||
| 臨床研究センター | ||
| 長崎大学病院 臨床研究センター | ||
| 山本 弘史 | ||
| 長崎大学病院 | ||
| 臨床研究センター | ||
| 長崎大学病院 臨床研究センター | ||
| 福島 千鶴 | ||
| 長崎大学病院 | ||
| 臨床研究センター | ||
| 長崎大学病院 臨床研究センター | ||
| 佐藤 俊太朗 | ||
| 長崎大学病院 | ||
| 臨床研究センター | ||
| 長崎大学病院 移植・消化器外科 | ||
| 足立 智彦 | ||
| 長崎大学病院 | ||
| 移植・消化器外科 | ||
(3)多施設共同研究に関する事項
(3)多施設共同研究に関する事項
| 無 |
3 再生医療等に用いる細胞の入手の方法並びに特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法等
3 再生医療等に用いる細胞の入手の方法並びに特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法等
(1)再生医療等に用いる細胞の入手の方法(特定細胞加工物を用いる場合のみ記載)
(1)再生医療等に用いる細胞の入手の方法(特定細胞加工物を用いる場合のみ記載)
| 膵島 | |
| 臓器提供が可能な医療機関 | |
| 膵島移植のための膵臓提供は、原則として臓器移植のためのドナーが発生した場合において、提供膵が膵臓移植に用いることが不適と判断された場合に行われる。よって心停止ドナーと、一部の脳死ドナーが選定される。脳死ドナーの場合は、第1回目の法的脳死判定が行われた後、①ドナー年齢が60歳以上、または②肥満度(BMI)が30以上、または③ドナーの原疾患・心肺停止時間・感染症・糖尿病の既往などの因子により臓器移植コーディネーターが斡旋に苦慮する場合に、日本臓器移植ネットワーク(JOT)より膵臓移植メディカルコンサルタントがこれらの条件を確認し、膵臓移植への利用は不適であると判断し、ご家族が膵島移植の説明を希望した場合に、JOTより組織移植ネットワークに連絡いただく。組織移植ネットワークは日本膵・膵島移植研究会の膵島移植班事務局へ連絡をとり、組織移植コーディネーターをドナー発生施設に派遣する。組織移植コーディネーターの不在時には、膵島移植班事務局より情報を受診した膵島移植施設がコーディネーターとしての人材を派遣する。組織移植コーディネーターが膵島提供に関する説明を行い、ご家族より提供の同意が得られた場合に、細胞提供者となる。 細胞提供者の選定基準は以下の通りで、①ドナー年齢は原則70才以下、②温阻血時間は原則として30分以内、③感染症等の除外項目は組織移植学会のガイドラインに基づき、④摘出膵保存はUW液による単純浸漬保存あるいは二層法を用いることが望ましい、⑤糖尿病(HbA1c 6.0%以上)を除外し、その他アルコール依存症・膵炎・膵の機能的・器質的障害を認めるものは除外する。 前述した『ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・利用に関するガイドライン』で定められた細胞提供者の除外項目は以下の通りで、 ・原因不明の死亡 ・敗血症あるいは全身性感染症 ・Creutzfeld-Jakob 病(変異型を含む)とその疑い ・悪性腫瘍(原発性脳腫瘍や固形癌などで治療後5年を経過し、完治したと判断される者では組織採取医の判断に委ねる) ・白血病、悪性リンパ腫などの血液腫瘍 ・重篤な代謝・内分泌疾患、血液疾患や膠原病などの自己免疫疾患 ・梅毒 ・B 型肝炎、HBs 抗原陽性 ・C 型肝炎、HCV 抗原陽性、HCV 抗体陽性、或いはHCV・RNA 定性陽性 ・ヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染症 ・成人T 細胞白血病(ATL)、HTLV-1 抗体(HTLV)陽性 ・パルボウイルスB19 感染症 ・西(ウエスト)ナイルウイルス感染症 ・新型肺炎SARS(重症急性呼吸器症候群)感染症 ・狂犬病 ・その他各組織特有の採取除外条件に合致する者 上記感染症を問診及び検査(血清学的試験や核酸増幅法等)により否定すること。 また、サイトメガロウイルス感染及びEB ウイルス感染については必要に応じて検査により否定すること。 |
|
| 以下のドナー適応基準を満たすことを提供先にて確認する。①ドナー年齢は原則70才以下、②温阻血時間は原則として30分以内、③感染症等の除外項目は組織移植学会のガイドラインに基づき、④摘出膵保存はUW液による単純浸漬保存あるいは二層法を用いることが望ましい、⑤糖尿病(HbA1c 6.0%以上)を除外し、その他アルコール依存症・膵炎・膵の機能的・器質的障害を認めるものは除外する。 また、①適格性の判断時に確認できなかった場合は既往歴の再確認(ア 梅毒他STD、TB、イsepsis、ウ 悪性腫瘍、エ 重篤な内分泌疾患、オ 膠原病・血液病、カ 肝疾患、キ 伝達性海綿状脳症、ク 特定の遺伝性疾患及び当該疾患に係る家族歴)、②次のウイルスの精査(HBV/HCV/HIV/HTLV-1/パルボB19)を施行する。 |
|
| 『採取時の方法』 膵島移植のための膵臓(膵組織)提供に対する協力病院(提供病院)から、脳死または心停止後に膵臓提供の可能性のある患者情報を入手、摘出機材を持参して協力病院を訪問する。感染症の有無、糖尿病の既往の有無など膵島移植ドナーとして適応基準を満たしているかどうかを評価する。コーディネーターによる膵島移植のための膵臓提供に対する承諾をドナー家族より得る。脳死・心停止の発症は不可逆的な事象であり、臓器提供のために行われている治療の方針を変更することはない。提供病院で待機し、膵臓を摘出する。バックテーブルにて摘出膵を処理した後、臓器保存容器にUW液と共に入れ運搬準備を完了する。膵臓摘出に関する記録をつける。提供施設から分離施設へ膵臓を運搬する。 『細胞の加工方法』 膵島分離標準手順書に基づいて膵島分離を行う。提供病院での待機、摘出操作と平行して膵島分離のための準備を開始、完了する。CPC に膵臓を搬入し、膵臓を消毒薬、抗菌剤/抗生剤を用いて、除菌する。続いて、膵臓を低温に保ち、主膵管からコラゲナーゼ溶液を逆向性に圧の調節を行いながら注入し、コラゲナーゼ溶液を膵臓間質内に配置する(膵臓膨化)。コラゲナーゼ溶液にて膨化した膵臓を細切し、チェンバーの中に入れる。チェンバーにはチューブが接続されており流路の一部を形成する。その流路を閉鎖系として循環させ、恒温槽を通すことによって温度を体温近くに上昇させる。それによって組織内に注入されたコラゲナーゼが活性化し膵組織が細かく分解される(膵臓消化)。続いて、膵外分泌腺組織と膵内分泌組織である膵島との比重の違いを利用して比重遠沈法にて消化膵組織から膵外分泌組織を除去し、膵島組織のみを集める(膵島純化)。分離した膵島の膵島量、純度、組織量、Viability、エンドトキシン定量、グラム染色を行う。これらの検査結果が移植基準を満たしている場合、移植用溶液に膵島を懸濁し、移植用バックに充填する。移植膵島を150mL の移植用溶液に混濁し、別にリンス用溶液として100mL の移植用溶液を準備しておく。純化の際に純度が高い移植用膵組織と純度が低い移植用膵組織の2 種類となった場合はそれぞれについて移植用溶液を150mL、リンス用100mL を準備する。膵島調整に関する記録のレビューを行って不備が無いことを確認し膵島の出荷を決定する。 |
(2)特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法(特定細胞加工物等を用いる場合のみ記載)
(2)特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法(特定細胞加工物等を用いる場合のみ記載)
| 膵島 | ||
| 『加工の方法』 膵島分離すなわち膵島の製造工程は、院内の細胞調整室(CPC)内で行う。膵島は提供された膵から分離され、膵β-細胞を含む無菌な組織であり、CPC内で無菌的に製造する。主な工程は膵管への膵島分離酵素の注入、膵臓の消化、消化組織の回収、膵島への純化、及び膵島培養と充填からなる。製造における品質管理は「再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号)第四十四条」に示される厚生労働省令第110号(平成26年9月26日)で定められた「特定細胞加工物製造事業者がその業務に関し遵守するべき事項」を遵守して実施する。膵島製造の品質に関する作業については手順書を定め、それを遵守する。その実施内容を記載した記録書を所定の期間保管する。 『保管の方法』 加工物は投与されるまでCPC内で培養される。培養条件は5%±1%CO2、22℃±1℃とする。保管期間は48時間を超えないこととする。 『試験検査の方法』 以下の項目について膵島分離終了後に検体を採取し各種検査を行い、出荷可能かどうか判定する。1)膵島量 ≧ 5,000IE/kg(患者体重)、2)純度 ≧ 30%、3)組織量 ≦ 10mL、4)Viability ≧ 70%、5)Endotoxin ≦ 5EU/kg (患者体重)、6)グラム染色:陰性 判定は品質管理責任者が行う。 |
||
| 血管造影室にて、局所麻酔を行い、エコーガイド下に門脈を穿刺、経皮経肝的に門脈内にカテーテルを留置する。調整膵島を門脈内へ注入する。 | ||
| 無 | ||
| 長崎大学病院 | ||
| FC7160003 | ||
| 長崎大学病院細胞プロセシングセンター | ||
| 委託しない。 | ||
(3)再生医療等製品等に関する事項(再生医療等製品を用いる場合のみ記載)
(3)再生医療等製品等に関する事項(再生医療等製品を用いる場合のみ記載)
(4)再生医療等に用いる未承認又は適応外の医薬品又は医療機器に関する事項(未承認又は適応外の医薬品又は医療機器を用いる場合のみ記載)
(4)再生医療等に用いる未承認又は適応外の医薬品又は医療機器に関する事項(未承認又は適応外の医薬品又は医療機器を用いる場合のみ記載)
| 医薬品 | |||
| 適応外 | |||
| 抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン | |||
| サイモグロブリン | |||
| 22000AMY00004000 | |||
| サノフィ株式会社 | |||
| 東京都東京都新宿区西新宿三丁目20番号 | |||
| 医薬品 | |||
| 適応外 | |||
| バシリキシマブ | |||
| シムレクト | |||
| 22000AMX01626000 | |||
| ノバルティスファーマ株式会社 | |||
| 東京都東京都港区虎ノ門1-23-1 | |||
| 医薬品 | |||
| 適応外 | |||
| エタネルセプト | |||
| エンブレル | |||
| 22000AMX00942 | |||
| ファイザー株式会社 | |||
| 東京都東京都渋谷区代々木3-22-7 | |||
| 医薬品 | |||
| 適応外 | |||
| タクロリムス | |||
| プログラフ | |||
| 22300AMX00009 | |||
| アステラス製薬株式会社 | |||
| 東京都東京都中央区日本橋本町2丁目5番1号 | |||
| 医薬品 | |||
| 適応外 | |||
| タクロリムス水和物徐放性カプセル | |||
| グラセプター | |||
| 22000AMX01768 | |||
| アステラス製薬株式会社 | |||
| 東京都東京都中央区日本橋本町2丁目5番1号 | |||
| 医薬品 | |||
| 適応外 | |||
| シクロスポリン | |||
| ネオーラル | |||
| 22100AMX01780000 | |||
| ノバルティスファーマ株式会社 | |||
| 東京都東京都港区虎ノ門1-23-1 | |||
| 医薬品 | |||
| 適応外 | |||
| ミコフェノール酸モフェチル | |||
| セルセプト | |||
| 21100AMY00240 | |||
| 中外製薬株式会社 | |||
| 東京都東京都中央区日本橋室町2-1-1 | |||
4 再生医療等技術の安全性の確保等に関す措置
4 再生医療等技術の安全性の確保等に関す措置
(1)利益相反管理に関する事項
(1)利益相反管理に関する事項
① 再生医療等に対する特定細胞加工物等製造事業者からの研究資金等の提供その他の関与
① 再生医療等に対する特定細胞加工物等製造事業者からの研究資金等の提供その他の関与
| 無 | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
② 再生医療等に対する医療薬品等製造販売業者等からの研究資金等の提供その他の関与
② 再生医療等に対する医療薬品等製造販売業者等からの研究資金等の提供その他の関与
| 無 | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
③ 再生医療等に対する特定細胞加工物等製造事業者又は医療品等製造販売業者等以外からの研究資金
③ 再生医療等に対する特定細胞加工物等製造事業者又は医療品等製造販売業者等以外からの研究資金
| 無 | ||
(2)その他再生医療等技術の安全性の確保等に関する措置
(2)その他再生医療等技術の安全性の確保等に関する措置
| 本計画で使用する膵島は、脳死または心停止後に提供を受けた膵臓より、確立された膵島分離標準手順書に則って分離された膵内分泌細胞組織と定義する。また、分離の最終段階で以下の条件を満たすことを確認し移植に使用する(1)。 1)膵島量 ≧ 5,000IE/kg(レシピエント体重)、2)純度 ≧ 30%、3)組織量 ≦ 10ml、4)viability ≧ 70%、5)Endotoxin ≦ 5 U/kg(レシピエント体重)、6)グラム染色陰性 本研究で使用される膵島組織は、他者由来の組織であるため、レシピエントの免疫系を生理的範囲内で賦活化する。この免疫系の賦活化を沈静化するため免疫抑制剤を使用する。免疫抑制剤の投与による副作用については減量や投与の中止により対応可能である。 移植膵島の媒介によりサイトメガロウイルス、EBウイルスなどの感染の可能性がある。これらに関してはドナー、レシピエントともに感染状況を確認している。これまでの国内・海外での実施症例においてはサイトメガロウイルスによる重症感染症あるいはEBウイルスが原因と考えられるPTLDの報告はない。移植手技そのものにともなう死に至るような重篤な合併症は、これまでにわが国で実施された心停止ドナーからの18例の移植、および世界的に300例以上行われている脳死ドナーからの膵島移植も含めて報告されていない。国内実施18例における膵島移植手技に伴う副作用としては肝穿刺に伴う腹腔内出血を1例にみとめた(2)。 外分泌組織を含めて大量に門脈内投与した際に急性肝不全、DICを発症して死亡した症例の報告がある(3)が、総移植量を10ml以下としたエドモントン・プロトコール以降に於いては、このような合併症の報告はない。また、血管内への組織の移植であるため、移植組織による動脈塞栓とそれに続く梗塞の可能性があるが、現在まで脳梗塞、肺梗塞、心筋梗塞などの報告はない。またこれまで実際に移植組織より腫瘍性病変が発生したとの報告もない。以上より、移植膵島の安全性は極めて高いと考えられる。 (1) International trial of the Edmonton protocol for islet transplantation. Shapiro AM, et al. N Engl J Med. 2006 Sep 28;355(13):1318-30. (2) Islet transplantation using donors after cardiac death: report of the Japan Islet Transplantation Registry. Saito T et al, Transplantation. 2010 Oct 15;90(7):740-7. (3) Portal hypertension, hepatic infarction, and liver failure complicating pancreatic islet autotransplantation. Walsh TJ et al. Surgery. 1982 Apr;91(4):485-7. |
||||||
| 膵島移植は、提供された膵臓から特殊な技術を用いて膵島組織を分離し、それを点滴の要領でインスリン依存状態患者の門脈内に輸注する低侵襲治療である。臨床実施は米国ミネソタ大学にて1974年に始まった(1)。International Islet Transplantation Registryからの報告では(2)、1990年から1998年までに267例の同種異系膵島移植が行われ、12.7%の症例において1週間以上の期間インスリン離脱となり、8.2%が1年以上のインスリン離脱が得られている。2000年カナダ・エドモントンにあるアルバータ大学から1型糖尿病に対する膵島移植の臨床試験によって全例(7例)にインスリン離脱を1年以上認めたとの報告がなされた(3)。これがのちにエドモントンプロトコールと言われるもので、次の4項目がその主な特徴である。1)移植の適応を腎機能正常症例に限定し、従来腎移植後に免疫抑制剤として標準的に使用されていたステロイド剤を排除し、移植膵島の機能発現を第一義に考えた免疫抑制療法(導入療法に抗IL-2モノクローナル抗体、維持療法にシロリムス(TOR-I)、少量のタクロリムス(CN-I)を導入)、2)新鮮な状態の膵島を移植に使用、3)比較的短期間の間に複数のドナーから得られた膵島を一人のレシピエントに異時性に移植、4)良質な膵島を充分量分離する膵島分離法の確立。1型糖尿病患者を多く抱える欧米に於いて膵島移植の高い安全性と治療効果を示唆するこの報告以来、膵島移植医療は大きな社会的支援を得て、インスリン依存状態糖尿病に対する治療法として確立されるべく開発が行われている。2002年欧米の9施設が選抜されエドモントンプロトコールを用いた追試が開始され(エドモントンプロトコール マルチセンタートライアル)、施設間での膵島移植成績に差があることが明らかとなった(4)が、十分な膵島分離技術を有する施設に於いては、アルバータ大学での成績の再現は可能であるとの中間報告がなされた(5)。2005年アルバータ大学より膵島移植の長期成績についての報告がなされ(6)、続いて2006年エドモントンプロトコールマルチセンタトライアルの最終報告がなされ(7)、以下のことを結論として挙げている。すなわち、「エドモントンプロトコールを用いた膵島移植は、血糖不安定性をもつ1型糖尿病患者において長期にわたる内因性インスリン産生と血糖安定性を回復することに成功した。しかしながら、インスリン離脱は長期にわたって持続しなかった。持続的な膵島機能によって、インスリンから離脱していなかったとしても重症低血糖は起こらず、また、グリコヘモグロビン(HbA1c)の血中レベルは改善した」。一方、2000年以来世界中でエドモントンプロトコールが採用され、膵島移植が盛んに実施されるようになった。現在まで60以上の施設に於いて600症例以上に膵島移植が行われている。現在、欧米に於いては膵島移植を一般医療として確立するための最終段階であるPhase IIIの治験を行うべく、Clinical Islet Transplantation Consortium(CITC)が組織され、その準備がなされている。その中では、導入療法に抗IL-2モノクローナル抗体にかわり、初回の導入療法としての抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリンと可溶性TNF-alphaレセプター製剤であるエタネルセプトが使用されている。その有効性については、ミネソタ大学からこの導入療法を用いることにより膵島移植を実施した8例全てでインスリン離脱が得られ、インスリン離脱率が向上し、インスリン離脱達成後のインスリン離脱期間の延長が報告されている(8,9)。またブリティッシュコロンビア大学からも、膵島移植の術後免疫抑制剤としてATGを使用しインスリン離脱率64%と報告されている(10)。維持免疫抑制について、前述のミネソタ大学ではミコフェノール酸モフェチル(MMF)、シロリムスまたはタクロリムス、ブリティッシュコロンビア大学ではシロリムスまたはMMF、とタクロリムスの組み合わせとしている。また欧米で進行中のCITプロトコールにおける免疫抑制剤はシロリムスとタクロリムスの組み合わせだが、これらの薬剤のMMFへの変更を認めている。シロリムスはわが国では術後免疫抑制剤としては承認されていないが、MMFは腎移植・肝移植・膵臓移植などで使用されている事実をふまえ、現況本邦の多施設共同研究では導入療法として、抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン(2回目以後はバシリキシマブ)+エタネルセプト、維持免疫抑制剤としてMMFとタクロリムスの組み合わせによる免疫抑制プロトコールによる安全性・有効性の検討がなされている。膵島移植は安全性についての検討内容の項に記載した様に安全性の高い移植医療である。免疫抑制剤による合併症は他の移植と同様にリスクとして考慮する必要があるが、重症低血糖発作からの離脱という利益があり、リスクを利益が上回るものと考える。 (1) Human islet transplantation: a preliminary report. Najarian JS et al. Transplant Proc. 1977 Mar;9(1):233-6. (2) In situ cooling of pancreata from non-heart-beating donors prior to procurement for islet transplantation. Nagata H et al. Transplant Proc. 2005 Oct;37(8):3393-5. (3) Islet transplantation in seven patients with type 1 diabetes mellitus using a glucocorticoid-free immunosuppressive regimen. Shapiro AM et al. N Engl J Med. 2000 Jul 27;343(4):230-8. (4) Lancet. 2003 Jun 14;361(9374):2054. Edmonton's islet success tough to duplicate elsewhere. Ault A. (5) Lancet. 2003 Oct 11;362(9391):1242. Edmonton's islet success has indeed been replicated elsewhere. Shapiro AM et al. (6) Five-year follow-up after clinical islet transplantation. Ryan EA et al. Diabetes. 2005 Jul;54(7):2060-9. (7) N Engl J Med. 2006 Sep 28;355(13):1318-30. International trial of the Edmonton protocol for islet transplantation. Shapiro AM et al. (8) Prolonged insulin independence after islet allotransplants in recipients with type 1 diabetes. Bellin MD et al. Am J Transplant. 2008 Nov;8(11):2463-70. (9) JAMA. 2005 Feb 16;293(7):830-5. Single-donor, marginal-dose islet transplantation in patients with type 1 diabetes. Hering BJ et al. (10) A multi-year analysis of islet transplantation compared with intensive medical therapy on progression of complications in type 1 diabetes. Warnock GL et al. Transplantation. 2008 Dec 27;86 |
||||||
| 研究責任者は研究担当者に対して、特定細胞加工物概要書に従った製造が行われるよう指示する。投与可否決定についても特定細胞加工物概要書に従い、 以下の項目について確認し、基準をみたす細胞加工物、もしくは品質に問題が無いと判定された細胞加工物については使用可能と判定する。 1) 膵島量 ≧ 5,000 IE/kg(レシピエント体重)、2) 純度 ≧ 30%、3) 組織量≦10ml、4) viability ≧ 70%、5) Endotoxin ≦5 U/kg(レシピエント体重)、6) グラム染色陰性 Endotoxinは細胞加工後、グラム染色は細胞加工後及び移植前に施行する。細胞加工後、移植前にグラム染色陽性であれば移植不能と判断。Endotoxinについては細胞加工後、外注業者(SRL)で迅速検査施行。上記基準値外であれば移植不能と判断する。細胞加工後、研究責任者が移植可否の仮決定を行い、最終的な移植可否の決定は研究責任者が移植直前に行う。 |
||||||
| 細胞の安全性に関する疑義が生じた場合の対策の一環として、感染症を発症した場合の原因究明のため、細胞提供者の細胞並びに当該再生医療等に用いた細胞加工物の一部を30年間保管する。 | ||||||
| 本医療の安全性に疑義が生じた際の検討措置として、30年間試料(細胞加工物の一部、加工前膵臓片(CPC内で採取))は保存する。保存はCMRL液にDMSO、Sucrose、Albuminを添加した保存液で細胞および膵臓片を液体窒素で冷凍し行う。具体的には細胞提供者の細胞として、膵島分離作業開始前の膵臓組織を約1~2グラム採取し、-160℃以下で凍結保存する。また、膵島分離後の細胞加工物として、移植予定の膵島を約1,000IE含む膵島混濁液をプログラムフリージングシステムにて-160℃以下で凍結保存する。 | ||||||
| 30年間保管後に破棄する。 | ||||||
| 定期報告や再生医療等の提供に起因するものと疑われる疾病、障害若しくは死亡又は感染症の発生に関する事項について報告を受けた場合、そのほか、再生医療等技術の安全性の確保等、適正な提供のために必要があると認めるとき、当該管理者に対し、その原因の究明及び講ずべき措置について意見が述べられた場合、当該意見を受けて講じた計画の変更やその他の措置について所属する機関の長・日本膵・膵島移植研究会膵島移植班事務局、京都大学特定認定再生医療等委員会、厚生労働大臣に報告する。 特に有害事象の報告手順については下記に記載する。 有害事象の定義 有害事象(AE: Adverse Event)とは、プロトコール治療の開始(第1回目の膵島移植・免疫抑制剤の投与開始)から2年以内に発生する、あらゆる好ましくないあるいは意図しない徴候(臨床検査値の異常を含む)、症状または病気のことであり、当該治療法との因果関係の有無は問わない。有害事象には手術侵襲に関連するものも含まれる。本試験で使用する免疫抑制剤による想定範囲内でのリンパ球減少等は、「好ましくないあるいは意図しない徴候」ではないため有害事象とはしない。 薬物有害反応(ADR: Adverse Drug Reaction)とは、有害事象のうち、当該医薬品の使用との因果関係が否定できないもの(医薬品の使用との因果関係で「否定できない」と判定されたもの)をいう。 重篤な有害事象(SAE: Serious Adverse Event)とは、有害事象のうち以下のものをいう。 1) 死亡、2) 死亡につながる恐れのあるもの、3) 治療のために病院または診療所への入院 または入院期間の延長が必要となるもの、4) 障害、5) 障害につながるおそれのあるもの、 6) その他1)~5)に準じて重篤であるもの、7) 後世代における先天性の疾病または異常 有害事象の評価 プロトコール治療の開始(初回膵島移植・免疫抑制剤の投与開始)から2年間に観察された有害事象は「10.2. 観察・検査・報告項目とスケジュール」で定めたスケジュールに基づき評価する。なお有害事象の転機が確定するまで追跡調査する。 予想される有害事象・合併症 門脈内注入に関する有害事象:組織注入のための経皮経肝的門脈穿刺の操作に関連して生じ得るもので細胞移植によるものではない有害事象・合併症。 1) 腹腔内出血、2) 創感染、3) 局所麻酔に関連する合併症 組織移植に関連する有害事象・合併症 1) 門脈閉塞による肝機能障害・肝不全 移植後の治療に関する有害事象 1) 白血球減少症(バシリキシマブ16.1%、MMF18.5%)、2) 好中球減少症(バシリキシマブ29%)、3) 貧血、4) 血小板減少症、5) 不眠症、6) 頭痛、7) 口腔内潰瘍、8) 下痢、9) 感染症、10) 皮膚異常、11) 浮腫、12) 肝機能異常、13) 腎機能異常、14) 高血圧、15) 高脂血症、16) 卵巣嚢腫、17) 悪性新生物 有害事象の緊急報告と対応 報告義務のある重篤な有害事象は、前記した重篤な有害事象のうち、プロトコール治療中またはプロトコール治療終了後(14日以内)に発生したものとする。 報告手順 上記で定義した有害事象情報については、日本膵・膵島移植研究会膵島移植班事務局、京都大学特定認定再生医療等委員会に報告する。 1) 一次報告(発生を知った時点から72時間以内):報告義務のある有害事象が発生した場合、責任医師/分担医師は、当該治療との因果関係の有無に関わらず、発生を知った時点から72時間以内に所属する機関の長・日本膵・膵島移植研究会膵島移植班事務局に報告する。 2) 二次報告(発生を知った時点から7日以内):責任医師/分担医師は、重篤な有害事象の発生を知った時点から7日以内に直接またはfaxで所属する医療機関の長、日本膵・膵島移植研究会膵島移植班事務局に提出する。 3) 詳細調査報告:主任研究者から二次報告に含まれない詳細な情報の提供を要請された場合、責任医師/分担医師は、その指示に従って必要かつ十分な調査を行い、所属医療機関の長、日本膵・膵島移植研究会膵島移植班事務局に「詳細調査報告書」を提出する。詳細調査報告書の様式については特に定めていない。 4) 最終報告:責任医師/分担医師は、重篤な有害事象の転機が確定した後、二次報告後の経過および転機に関して、「重篤な有害事象に関する報告書(最終報告)」を作成し、所属する医療機関の長、日本膵・膵島移植研究会膵島移植班事務局に提出する。 上記に並行し、京都大学認定再生医療等委員会および厚生労働大臣への報告手順を示す。 再生医療等の提供によるものと疑われる疾病、障害、若しくは死亡または感染症の発生を知った場合には、以下の手順で報告する。 ①再生医療等の提供によるものと疑われる疾病、障害、若しくは死亡または感染症の発生を知った時は、提供機関管理者及び実施責任者に速やかに報告する。 ②報告を受けた提供機関管理者、実施責任者は、当該再生医療等を行う医師に対し、当該再生医療等の中止を命じるとともに、発生した事態が細胞加工物に起因するものであるか、疾病発生の原因の分析と検討等、必要な措置を講じるよう指示をする。 ③疾病の発生の報告を受けた提供機関管理者、実施責任者は、特定細胞加工物製造業者に発生した事態及び講じた措置について速やかに通知する。 ④提供機関管理者は、当該再生医療の提供によるものと疑われれる又は該当再生医療の提供によるものと疑われれる感染症による、死亡、死亡につながるおそれのある症例発生を知ったときは、7日以内に認定再生医療等委員会に報告する。また、当該再生医療の提供によるものと疑われれる又は該再生医療の提供によるものと疑われれる感染症による、治療のために医療機関への入院又は入院期間の延長が必要とされる症例の発生や、障害、障害につながる恐れの症例、重篤な症例、後世代における先天性の疾病又は以上の発生を知ったときは15日以内に認定再生医療等委員会に報告する。 *前述以外の当該再生医療の提供によるものと疑われれる感染症による疾病の発生について、再生医療提供計画を厚生労働大臣に提出した日から起算して60日ごとに当該期間満了 10日以内に認定再生医療等委員会に報告する。 ⑤提供機関管理者は、当該再生医療の提供によるものと疑われれる又は該再生医療の提供によるものと疑われれる感染症による、死亡、死亡につながるおそれのある症例発生を知ったときは7日以内に厚生労働大臣に報告する。また、当該再生医療の提供によるものと疑われれる又は該再生医療の提供によるものと疑われれる感染症による、治療のために医療機関への入院又は入院期間の延長が必要とされる症例の発生や、障害、障害につながる恐れの症例、重篤な症例、後世代における先天性の疾病又は以上の発生を知ったときは15日以内に厚生労働大臣に報告する。 |
||||||
| 移植終了以後は、プロトコールに従って有害事象の確認を行い、重篤な有害事象が発現した場合には、主任研究者・所属する医療機関の長、日本膵・膵島移植研究会膵島移植班事務局、京都大学特定認定再生医療等委員会に報告する。ただしプロトコール中止後に発生した有害事象が膵島移植あるいは治療手順との因果関係が否定される場合には、報告する必要は無い。ただし、臨床研究終了後も安全性及び科学的妥当性の確保の観点から、再生医療等の提供による疾病等の発生について3か月に一度の外来フォローを基本とし、生涯に渡り追跡を行う。また、再生医療等の提供に起因するものと疑われる疾病等の発生の場合に当該疾病等の情報を把握できるよう、及び細胞加工物に問題が生じた場合に再生医療等を受けた者の健康状態等が把握できるよう、生涯に渡り経過観察を行う。そのため、経過観察期間終了後も経過観察を行えるよう再生医療等を受けた者の連絡先を把握しておく。 | ||||||
| 再生医療等の提供による疾病等の発生について3か月に一度の外来フォローを基本とし、生涯に渡り追跡を行う。また、再生医療等の提供に起因するものと疑われる疾病等の発生の場合に当該疾病等の情報を把握できるよう、及び細胞加工物に問題が生じた場合に再生医療等を受けた者の健康状態等が把握できるよう、生涯に渡り経過観察を行う。そのため、経過観察期間終了後も経過観察を行えるよう再生医療等を受けた者の連絡先を把握しておく。 | ||||||
| 有 | ||||||
| 2016年02月23日 | ||||||
| 研究終了 | Complete | |||||
5 細胞提供者及び再生医療等を受ける者に対する健康被害の補償の方法
5 細胞提供者及び再生医療等を受ける者に対する健康被害の補償の方法
細胞提供者について(特定細胞加工物を用いる場合のみ記載)
細胞提供者について(特定細胞加工物を用いる場合のみ記載)
| 無 |
再生医療等を受ける者について
再生医療等を受ける者について
| 有 |
6 審査等業務を行う認定再生医療等委員会に関する事項
6 審査等業務を行う認定再生医療等委員会に関する事項
| 京都大学特定認定再生医療等委員会 | Kyoto University Specially Certified Committee for Regenerative Medicine | |
| NA8150004 | ||
| 京都府京都市左京区吉田近衛町(京都大学大学院医学研究科) | Yoshidakonoe-chou, Sakyo, Kyoto city, Kyoto | |
| 075-753-4680 | ||
| ethcom@kuhp.kyoto-u.ac.jp | ||
| 第一種再生医療等又は第二種再生医療等を審査することができる構成 | ||
| 適 | ||
| 2019年11月11日 | ||
7 その他
7 その他
| 本治療で知り得た個人情報および臨床情報などのプライバシーに関する情報は、個人の人尊重の理念の下、厳重に保護され慎重に扱われるべきものと認識し、プライバシー保護に努める。本療法により得られたデータは、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月)に準拠し、当施設で策定されている個人情報保護規定に則り連結可能匿名化を行い運用する。 | ||
| ①関連学会や勉強会への出席と研修報告を指示する。膵島分離担当者については 1. 製品に関する知識 2. 製造に用いる細胞・組織の安全な取扱いに関する知識及び技術 3. 設備・装置に関する知識及び技術 4. 製造工程の安全性に関する知識及び技術 5. 事故発生時の措置に関する知識及び技術 6. 生命倫理、被験者保護の観点からの教育を実施する。 また、前述内容に加え4か月に1回は大動物(豚)を使用した膵島分離、当院膵臓切除症例に応じて摘出膵からの膵島分離凍結保存(cold run)を行い、手技の習得、維持を行う。 ②膵島移植に関わる全医師は膵島移植を適正に実施するために定期的に院内・院外で開催される再生医療に関する教育又は研修を受け、情報収集に努める。 提供機関管理者又は実施責任者は膵島移植に関わる全ての医師、コメディカルに対して再生医療を適正に実施できる様、教育または研修の機会を設け、医師又その他の膵島移植の提供に係る関係者が適正な教育および研修を受けているかを監督する必要がある。 |
||
| 医療連携・相談室にて精神保健福祉士・医療相談員等が対応する。電話での受け付けも可能とする。 長崎大学大学院 移植・消化器外科 095-819-7316 |
||
| 非該当 | ||
| なし | none | |
| 無 | ||
| 非該当 | ||
| 非該当 | ||
| 非該当 | ||
添付資料
添付資料
| 4 再生医療等を受ける者に対する説明文書及び同意文書の様式 | 4 ドナー膵島 結合版. 2019.10.31.pdf |
|---|